artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
シャルル・フレジェ「YÔKAINOSHÏMA」/「BRETONNES」

会期:2016/02/19~2016/05/15
銀座メゾンエルメスフォーラム/MEM[東京都]
シャルル・フレジェは1975年、フランス・ブールジュ生まれの写真家。特定の民族衣装、ユニフォームなどを着用した社会的集団の構成員を撮影するポートレイトのシリーズで知られている。ヨーロッパの辺境地域の伝統的な儀礼の装束を撮影した「WILDER MANN」のシリーズは、2013年に青幻舎から写真集として刊行されて話題を集めた。それと同じアプローチで、北海道を除く日本各地の祭礼や民間儀礼を撮影したのが、今回銀座メゾンエルメスフォーラムで展示された「YÔKAINOSHÏMA」のシリーズである。
この種の民俗写真の撮影は、日本の写真家たちによっても試みられているが、フレジェの軽やかなカメラワークと弾むような色彩感覚によって、新たな視覚的表現が生まれてきているように感じる。特に日本の神々や鬼たちと、ヨーロッパの「WILDER MANN」の写真を並置した「Winter(冬)」のセクションは、インスタレーションにも工夫が凝らされ、大地に根ざした生命力をヴィヴィッドに感じさせる展示で見応えがあった。
一方、東京・恵比寿のMEMでは、ほぼ同時期に、彼のもう一つの新作である「BRETONNES」シリーズがお披露目されていた。こちらは、フランス・ブルターニュ地方の民俗衣装を身につけた女性たちを、特徴的な白いレースの頭飾り(コワフ)に着目して撮影している。背景をグレートーンでぼかして、被写体となる女性を浮かび上がらせる手法を用いることで、古典的な肖像画を思わせる画面に仕上がっていた。衣装を通じて、それぞれの地域の歴史的な記憶や文化的な背景を浮かび上がらせるフレジェの手法は、さまざまな可能性を孕んでいると思う。比較文化論な視点をもっと強調すれば、よりスケールの大きな作品世界に育っていくのではないだろうか。
「Y KAINOSH MA」2016年2月19日(金)~5月15日(火)銀座メゾンエルメスフォーラム
「BRETONNES」2月10日(水)~3月13日(日)MEM
2016/02/18(木)(飯沢耕太郎)
森永純「WAVE」
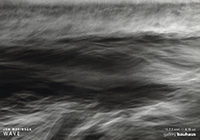
会期:2016/02/03~2016/04/16
gallery bauhaus[東京都]
寄せては返す波をずっと見ていると、次第にトリップ状態に入っていくことがある。単調なように見えて、一つひとつの波の形や変化の仕方には微妙な違いがあり、その表面で起きる出来事はひとつとして同じものはない。波の繰り返しに身を任せていると、自分がどこにいて何をしているのか、目眩とともに足下から揺らいでくるような気分になるのだ。
森永純も「ある年の5月」に、千葉の海岸に撮影行って防波堤に打ち寄せる波を見ているうちに、そんな状態に陥っていったようだ。「太陽熱と心地よい波の揺れのせいで軽い幻覚が起こり、波面が凍結したように見えた」という。この体験をきっかけとして、彼は30年以上にわたって波を撮り続けることになる。それらは2014年に写真集『WAVE~All things change~』(かぜたび舎)にまとめられ、今回はその中から44点(ほかに「河─累影」シリーズから2点)が展示された。
それら、撮影当時にプリントされたというヴィンテージ・プリントを見ると、波という現象が実に魅力的な被写体であることがわかる。撮影の条件によって千変万化するその様相は、それぞれが驚きをともなう奇跡的な瞬間として凝結しており、見飽きるということがないのだ。さらにそれらが繊細で深みのあるモノクロームの印画に置き換えられることで、視覚的な歓びはさらに強まってくる。森永が『WAVE~All things change~』に「「海の波」ほど、私たちの脳でおこる夢に似て、リアリティと幻想の交錯が激しい世界はない」と書いているのは本当だと思う。印画紙に定着された波は、われわれを夢想へと誘う強い力を秘めているのだろう。
2016/02/16(火)(飯沢耕太郎)
イシャイ・ガルバシュ「The long story of the contacts of “the other side”」

会期:2016/01/15~2016/02/28
Baexong Arts Kyoto[京都府]
2016年1月に京都市南区にオープンしたBaexong Arts Kyotoで、イスラエル出身の写真家、イシャイ・ガルバシュの「壁」シリーズが展示された。北アイルランドのピースウォール、韓国の38度線の壁、パレスチナウォール。大判カメラで細部まで捉えられた写真では、ごく普通の住宅街の中に異物のように立つ壁が、鉄条網や「地雷注意」の看板とともに威圧感を与える壁が、写し取られている。北アイルランドのベルファストで撮影された写真では、レンガ作りの住宅のすぐ隣に壁が立ち、その上にフェンスが空高くそびえている。これらの写真は、無人の住宅街や幾何学的な配置が冷たく硬質な印象を与えるが、一方、韓国で撮影された写真では、風景の中に人の気配や痕跡が入り混じり、そのゆるく笑いを誘うような脱力感が、場所の政治性や緊張感を和らげ、あるいは逆説的に増幅させる。軍事境界線の南北に設定されたDMZ(非武装中立地帯)のさらに南側に設定された民間人統制区域内では、防空壕の側に、観光客向けの「撮影スポット」が用意されている。つくりものの鶴とキムチを漬ける壺の背後に描かれた、ペンキの青空。ひなびたハリボテ感と遊園地のような空虚な明るさが、「観光客」向けに用意されたイメージの背後にある政治性を露出させる。一方、北朝鮮との軍事境界線に近い島では、畑の中に場違いな事務イスで「休憩所」がつくられている光景や、過疎化のため打ち捨てられた車の教習所の敷地が唐辛子を干すために無断借用されている光景など、政治的緊張と隣接した中に、日常生活が営まれる場でもあることが示される。そして、道路沿いの草取りしか仕事がない、低所得者の老婦人たちが笑顔で並ぶ写真。国境に近い周縁は、経済的な周縁地域でもある。
境界線を示す「壁」は、物理的な分断、隔離、権力の誇示、攻撃を受けることへの恐怖を体現する。現在の日本には、こうした物理的な「壁」はないが、心理的な境界線はないと言えるだろうか。ここで、展示場所となったBaexong Arts Kyotoの位置する地域が、歴史的にさまざまな差別や抑圧を押し付けられてきたことを考えるならば、本展は、物理的に可視化された「壁」の提示を通して、私たちに内在する見えない「壁」の存在をあぶり出すものであったと言えるだろう。
2016/02/14(日)(高嶋慈)
本城直季「東京」

会期:2016/02/12~2016/03/28
キヤノンギャラリーS[東京都]
本城直季は2006年頃からヘリコプターからの空撮で東京を撮影しはじめる。主に「空気が澄んで遠くまで見通せる」正月の3カ日を選んで撮影を続けたという。それら、使い慣れた4×5インチサイズの大判カメラで撮影された写真群に、高画素のCanon EOS5Dsを使った近作を加えたのが、今回のキヤノンギャラリーSでの展示である。
デジタル一眼レフカメラでの撮影は、本城に大きな解放感をもたらしたようだ。フィルムホルダーを取り替えてセットし直さなければならない大判カメラでは、1回の飛行で撮影できるのは、せいぜい30~40カットほどだ。デジタルカメラなら撮影枚数の制限はなくなる。さらに、ちゃんと写っているのかと心配することなく、安心してのびのびとシャッターを切ることができる。そのことによって、「東京をスナップする」という感覚が強まってきた。
さらに、今回の展示で本城は大きな決断をした。画面の一部にのみピントを合わせて、あとはぼかすことで、ミニチュアのジオラマのような視覚的効果を生じさせる従来の手法の作品と、画面全体にピントが合っている作品とを並置しているのだ。結果的に、つねにうごめきつつ増殖していく巨大都市「東京」の変貌のプロセスを、多面的に定着することができたのではないかと思う。また今回の展示は、あえて東京タワーのようなランドマーク的な建造物を外した作品で構成している。「どこまでも果てしなく続く密集した建造物の景色」に限定することで、「東京」という都市の基本的なエレメントが、くっきりとあぶり出されてきた。120×150センチという大判プリントによる細密描写も含めて、「デジタル化」が彼の作品世界をどう変えていくかが楽しみになってきた。
2016/02/13(土)(飯沢耕太郎)
青木陽「Inverted Spectrum」

会期:2016/02/09~2016/02/26
ガーディアン・ガーデン[東京都]
青木陽の写真の仕事には以前から注目している。2013年に東川町国際写真フェスティバルの一環として開催された「赤レンガ公開ポートフォリオオーディション」でグランプリを受賞し、翌14年に東京・東銀座のArt Gallery M84で展示された「火と土塊」のシリーズでは、濃密なグレートーンのセレニウム調色のプリントに徹底してこだわり、印画紙上に別次元の現実を構築する。ところが第12回写真「1_WALL」展グランプリ受賞者個展として開催された「Inverted Spectrum」では、まったく異なるアプローチを試みていた。
青木が今回の写真制作を通じて見出そうとしているのは、「自分自身の置かれた状況を含む現実の中で発生する出来事の意味」である。1990年代から2000年代にかけて、女性写真家を含む若い世代が、物語性を欠いたごく私的な日常の出来事を、あたかもそのまま撒き散らすような写真を提示し、それらが広く受け入れられた時期があった。写真新世紀や写真「1_WALL」展の前身である写真「ひとつぼ」展などの審査をしていると、たしかにこの種の「日々の泡」のような写真群を大量に目にすることができた。青木の今回の試みは、かつては感覚的、無自覚的におこなわれていたプライヴェートな出来事の写真化を、論理的、自覚的に再検討しようとするものといえる。
会場に展示されているのは「ホームの扉」、「電車のシート」、「コップ」、「台所のタイル」といった「ごく身近な人々、生活の一部、時々の目先の出来事」などの断片的な画像である。だが、青木の手にかかると、それらに奇妙なバイアスがかかっているように見えてくる。手が届くようで届かない、ありそうであり得ない事物や事象──あたかもカフカの小説の中に描写されているオブジェや風景のようでもある。曖昧でありながら明晰でもあるこれらの写真群は、もしかすると「私写真」の伝統を受け継ぎつつ再構築する、新たな写真表現の可能性を孕んでいるのかもしれない。青木が次に何を見せてくれかが楽しみだ。その行方を注視していきたい。
2016/02/10(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)