artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
吉増剛造「盲いた黄金の庭」
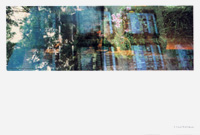
BLD Gallery[東京都]
会期:第1期/6月18日~7月11日、第2期/7月14日~8月8日
最後に銀座2丁目のBLD GALLERYで開催される吉増剛造展のオープニングへ。岩波書店から出版された同名の写真集(20年間の作品からセレクト)の刊行記念展である。吉増剛造は詩作のほかにも、評論、エッセイ、パフォーマンス、映像作品、銅板に言葉を刻むオブジェ作成、そして写真など、多彩な分野で表現者として活動している。だが何をやっても本来的に「詩人」の仕事に見えてくるのがすごい。その存在のあり方が、そのまま「詩人」であるとしかいいようがないのだ。
「写真家」としてのキャリアはかなり長く、1990年代初頭から本格的に写真作品を発表しはじめた。2000年代になると、今回の展示作品のようにパノラマカメラを使った多重露光作品が中心になってくる。多重露光という、何がどのように写り込むのかわからない偶然性を呼び込む手法は、吉増のシャーマン的な体質にぴったりしているのだろう。それに細く芯を尖らせた鉛筆で書き込まれた、繊細な筆致のテキストが付け加えられることで、魔術的な雰囲気がより強まっている。写真と詩をシンクロさせる試みは、これまでもないわけではないが、吉増の積極的な活動に刺激されて、若い世代にその領域を拡張していく試みがあらわれてくるといいと思う。
2010/06/18(金)(飯沢耕太郎)
暗がりのあかり チェコ写真の現在

会期:2010/06/19~2010/08/08
資生堂ギャラリー[東京都]
鑑賞日:2010年6月18日
続いて銀座8丁目の資生堂ギャラリーへ。「チェコ写真」といってもあまりぴんとこない人が多いのではないだろうか。僕もそうだったのだが、本展のカタログに原稿を執筆するため資料に目を通して、あらためてその多様性とクオリティの高さに驚いた。それとともに興味深かったのは、日本の近代写真史との共時性である。1920年代のピクトリアリズムの隆盛、30年代のモダニズムとアヴァンギャルド写真の到来、その後のドキュメンタリーやフォト・ジャーナリズムの高揚といった流れが、ほぼ共通しているのだ。
とはいえ、日本とは異質な要素もある。今回の出品作家はウラジミール・ビルグス、ヴァツラーフ・イラセック、アントニーン・クラトフヴィ─ル、ミハル・マツクー、ディタ・ペペ、イヴァン・ピンカヴァ、ルド・プレコップ、トノ・スタノ、インドジヒ、シュトライト、テレザ・ヴルチェコヴァーの10人で、1946年生まれのシュトライトから83年生まれのヴルチコヴァーまで、世代の幅はかなり広い。にもかかわらず、コントラストの強いモノクローム(黒と白のイメージ)へのこだわり、物質性と身体性を前面に押し出す語り口などが「チェコ写真」の特質として、くっきりと浮かび上がってきているように感じた。被写体に向き合う姿勢と作品の感触が、日本の作家の作品とは違っているのだ。個人的にはまさにカフカ的といえる、モノとモノとが密やかに囁き交わすような思索的な世界を構築するイヴァン・ピンカヴァの作品に強く惹かれるものを感じた。
この展覧会をきっかけとして、今度はチェコで「日本写真の現在」展が開催されるといいと思う。
2010/06/18(金)(飯沢耕太郎)
鷹野隆大「金魚ブルブル」

会期:2010/06/18~2010/07/22
ツァイト・フォト・サロン[東京都]
次に京橋のツァイト・フォト・サロンへ。個展のオープニングの前の時間というのはけっこう狙い目で、作者とゆっくり話をして作品を見ることができる。
鷹野だけではなく、北京で大きな個展を開催したばかりの安齊重男も姿を見せて、世界中のアーティストを撮影する時の興味深い話をうかがうことができた。
鷹野の作品は、「撮りはじめてからまだ2カ月」というまったくの新作で、ロールサイズの大判プリントが3点と全紙サイズのプリントが8点。被写体はすべて全裸、あるいは半裸体の男性である。テーマそのものは鷹野の作品としては決して珍しいものではないが、これまで以上にエロスの強度が増しているように感じる。たとえば、昨年刊行した『男の乗り方』(Akio Nagasawa Publishing)では、やはり男性のエロスを正面から扱っているが、そこではむしろ鷹野と被写体との「距離感」が意識されている。「距離を縮めようとする欲望こそがエロスを生み出す」ということだ。ところが、今回の「金魚ブルブル」では距離がかなり詰められ、「欲望を発生させるポイント」を見つけだすことに狙いが定まっていた。その意図はかなり突き詰められていて、何とも生々しい場面があっけらかんと展開している。『男の乗り方』も「あるようでない」写真集だったが、この「金魚ブルブル」もあまり例を見ないあからさまな直視型の男性ヌードである。その「ぬるり」「ぴちゃぴちゃ」とした肌の感触がなまめかしい。この新作を見ても、鷹野は写真家としての水脈をしっかりと見出しつつあるのではないかと思う。
2010/06/18(金)(飯沢耕太郎)
ウィリアム・エグルストン「パリ─京都」
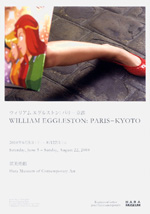
会期:2010/06/05~2010/08/22
原美術館[東京都]
6月18日は何とも大変な一日だった。写真展を梯子して見ることは、それほど珍しいことではないが、この日は回った展覧会がすべて充実した濃い内容の展示で、さすがに相当の疲労感を覚えた。心地よい疲れではあるのだが。
まず、品川の原美術館でウィリアム・エグルストンの新作を見る。エグルストンはいうまでもなく、1976年のニューヨーク近代美術館での伝説的な個展で、「ニューカラー」と称されるカラー写真によるスナップショットの新たな領域を切り拓いた写真家だが、このところがらりとスタイルを変えてしまった。今回の「パリ─京都」のシリーズでは、まるでデジタルカメラで撮影したような(実際には35ミリと6×7のフィルムカメラ)軽やかな浮遊感が漂うイメージが、鮮やかな原色で乱舞していて、その吹っ切れたような自由な撮影ぶりに開放感と昂揚感を覚えた。「ニューカラー」という枠組み自体を、自分で軽々と乗りこえてしまているのだ。写真とドローイングがカップリングされているフレームもあり、このサインペンや色鉛筆でさっと描かれたドローイングがまた、実におしゃれで決まっている。
若い日本の写真家に、僕が「網膜派」と密かに呼んでいる、デジタルカメラを使って被写体の表層的な物質性に徹底してこだわる作風が芽生えつつある(小山泰介、和田裕也、吉田和生など)。ところが、彼らがやろうとしていることを、70歳を越えたエグルストンが先取りして、しかも見事に達成してしまった。これでは彼らの出る幕がないわけで、これはこれで困ったことではないだろうか。
2010/06/18(金)(飯沢耕太郎)
荒木経惟「センチメンタルな旅 春の旅」

会期:2010/06/11~2010/07/18
RAT HOLE GALLERY[東京都]
「センチメンタルな旅 春の旅」というタイトルは、いうまでもなく1991年の写真集『センチメンタルな旅 冬の旅』(新潮社)を踏まえている。愛妻、陽子の死の前後の「写真日記」を中心とした前作に対して、今回は愛猫のチロの最後の日々が描き出されていく。
チロは1989年に4ケ月で荒木家にもらわれてきて、先頃、22歳という長寿を全うして亡くなった。人間の年齢に換算すると105歳という大往生だが、会場に展示されている80枚の写真を辿っていくと、この猫が荒木といかに強い絆で結びついていたのかが伝わってくる。『センチメンタルな旅 冬の旅』を見た時も強く感じたのだが、猫という動物はどこか霊的な兆しを帯びているのではないだろうか。その一挙手一頭足、しなやかで、しかもエロティックですらあるたたずまいが、現実離れした不可思議な気配を漂わせているのだ。今回の連作では、チロがテーブルからベッドへふわりと飛び移る動作をとらえた写真に、魂の震え、揺らぎのようなものを感じた。
そのチロが、いよいよ病み衰えて死の床に横たわる姿に、荒木は何枚も何枚も続けてシャッターを切っている。チロの目が少しずつ潤み、その光が失われ、静かに閉じられていく一連のカットは、これまでも「死者」を撮り続けてきた荒木にしか為しえない、渾身の「魂呼ばい」の儀式といえるのではないだろうか。それに応えるように、最後の一枚の写真ではチロがふたたびバルコニーに姿をあらわすのだ。なお、RAT HOLE GALLERYから900部限定で同名の写真集(デザイン・綿谷修/白谷敏夫)が刊行されている。こちらも素晴らしい出来栄えだ。
2010/06/15(火)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)