artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
川田喜久治「ワールズ・エンド Worlds’s End 2008-2010」
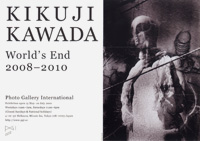
会期:2010/05/13~2010/07/10
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
1933年生まれの川田喜久治は、いまでも週に何日かは「プールで泳いでいる」のだという。70歳代後半だが、気力も体力もまだまだ充実していることが、この新作展からも伝わってきた。
2008年の暮れから2010年3月まで「毎日撮影することを自分に課した」その成果が並んでいる。撮影場所は東京がほとんどだが、あえて今回は、自分が住んでいるこの場所のいまを撮影するというこだわりがあったようだ。前作の「ユリイカ Eureka 全都市」(2005年)、「見えない都市 Invisible City」(2006年)と同様に、デジタルカメラの連写機能やパソコンでの合成や色味の変換を活かした作品が並ぶが、シャドー部の翳りがより強調され、不穏当な気配がさらに大きく迫り出してきているように感じる。全体的に無機的なモノと有機的な生命体とが絡み合うハイブリッドな状況に強く引きつけられるものがあるようだ。その「一瞬のねじれやファルス」を追い求めていくと、どうもフレーム入りの写真が整然と並んでいる、静まりかえった会場の雰囲気とはややそぐわないようにも思えてくる。
これはほんの思いつきだが、逆にノイズがあふれる工事現場のような場所で見たかったような気がする。ノイズ・ミュージックをバックにしたスライドショーのような形も面白いかもしれない。そんなふうに思わせるような、「はみ出していく」エネルギーが、作品に渦巻いているということだろう。
2010/05/21(金)(飯沢耕太郎)
沈昭良 写真展 STAGE

会期:2010/05/12~2010/05/25
銀座ニコンサロン[東京都]
台湾の写真家、沈昭良の個展。「台湾総芸団」をモチーフにした写真作品を発表した。それは歌や踊りなどの演芸を披露しながら台湾の各地を移動していく旅芸人の一座で、移動に使う大型トラックの荷台が演芸の舞台となる。荷台の内部には色とりどりの電飾や照明が仕込まれていて、スイッチひとつで外側に開いていくと煌びやかなステージが完成するという仕掛けだ。写真にはトラックからトランスフォームされたいくつものステージが写されているが、芸人が写りこんでいるわけではないから、旅芸人の演芸を記録した写真というより、むしろ舞台装置を即物的にとらえた写真である。とはいえ、空を赤く染めた夕闇や夜の繁華街のなかに立ち現われたステージは、見えない演芸を想像させる叙情性を強く醸し出している。路上に一時的に生起する非日常的な世界という意味でいえば、これはサーカスや紙芝居に近いのかもしれないし、だとすればこの叙情性は懐古的なニュアンスを多少なりとも含んでいるのかもしれない。けれども、沈昭良は失われた文化を美しくとらえるというより、むしろそうした舞台を内側に含みこんだ都市風景を見せようとしているのではないか。色鮮やかなステージは周囲の街並みを異化しているというより、絶妙に調和しながら溶け合っているからだ。都市と舞台が相対するのではなく、都市そのものが舞台である。そのことを、沈昭良による写真は物語っている。
2010/05/20(木)(福住廉)
侍と私 ポートレートが語る初期写真

会期:2010/05/15~2010/07/25
東京都写真美術館 3階展示室[東京都]
東京都写真美術館が毎年開催している、収蔵品を中心にした企画展。今年は「ポートレート」がテーマとなるが、その第一弾として本展「侍と私」が開催された。以後、夏から秋にかけて「私とヌード」「20世紀の人間像」という展覧会が予定されている。
展示は「プロローグ」「日本」「西欧」「交差」「エピローグ」の各パートに分かれ、幕末のダゲレオタイプ(「島津斉彬像」1857年撮影のレプリカ)や、ガラスネガに黒布で裏打ちしたアンブロタイプの肖像写真から始まって、外人観光客の土産物の「横浜写真」や小川一眞撮影の写真帖『京都大阪今様美人風俗』(1898年)に至る、ほぼ型通りといってよい構成である。何度も展示された写真が多いからというだけではなく、雑然とした並べ方には企画者の狙いがあまりきちんと感じられない。ついジェフリー・バッチェンが構成したIZU PHOTO MUSEUMの「時の宙づり──生・写真・死」展と比較してしまうのだが、企画者のセンスひとつでこれらの写真も見違えるような輝きを放つのではないだろうか。
「西欧」のパートには、ピーター・レリー、イアサント・リゴーらの油彩による肖像画まで展示されている。だが、このようなジャンルの拡張もあまり必然性を感じられない。東京都写真美術館の収蔵品は、いい意味でも悪い意味でも玉石混淆ではあるが、うまく使いこなせば「日本の写真」とは何かという問いかけに面白い答えを出す材料にも使えるのではないだろうか。何かもったいないと感じてしまう企画だった。
2010/05/19(水)(飯沢耕太郎)
古屋誠一「メモワール.」

会期:2010/05/15~2010/07/19
東京都写真美術館 2階展示室[東京都]
古屋誠一の「メモワ─ル」は、二重の意味で不幸な写真シリーズだと思う。このシリーズの主題になっているのは、1985年に東ベルリンで自殺した古屋の妻、クリスティーネとの関係の綾であり、彼女の「記憶」はその不幸な出来事によって枠づけられ、強烈なバイアスがかかっている。そして、われわれもまた、「自殺した妻と残された夫」という情報を抜きにしてはそれらの写真を見ることができないがゆえに、いやおうなしにその不幸に感染してしまう。写真そのものは、衒いなく、柔らかな視線で写しとられた純度の高いスナップショットであり、目を喜ばせ、心を和ませるものも少なくないのだが、彼らの不幸が二重映しに被いかぶさっているので、どうしても身動きの取れない、がんじがらめの気分に追い込まれてしまうのだ。
もちろん、まったくの先入観や予備知識なしに、これらの写真を見ることができたならと、想像してみることはできる。だが、作者の古屋自身が執拗に二人の「記憶」にこだわり続け、瘡蓋をはがすような作業を営々と続けている以上、それは不可能な望みというしかない。要するに、これはある意味写真の宿命とでもいうべきものなのだが、観客はその写真が撮影された状況を写真家とともに分かち持つことを余儀なくされるのだ。しかもそれは、「この不幸な写真を見続けなければならない」という義務感や罪障感にわれわれを強く導く。正直な話、特に古屋とクリスティーネのような重い物語を、これ以上背負わされるのはたまらないという思いが僕には強くあった。会場に足を運んだ時にも、そんな重苦しい気分を引きずっていた。
ところが、会場で写真を見終えたとき、少し違った感触が芽生えてきた。解放感にはまだ遠いが、見慣れた写真の多い「メモワール」のシリーズが、少し違った方向に伸び広がっていこうとしているように感じたのだ。その理由のひとつは、会場構成にある。今回の展覧会の写真は「光明」「円環」「境界」「グラビテーション」「クリスティーネ」「エピファニー」「記憶の復讐」という小さな章に区分されながらつながっていく。もちろん「東ベルリン 1985」から年代をさかのぼって「グラーツ 1978」に至るポートレートを中心とした「クリスティーネ」や、彼女の死の前後のカットを含むコンタクトプリントで構成された「記憶の復讐」の章など、「メモワール」シリーズの中心部分は変わっていない。だがそれらの拘束力の強いイメージを取り囲むように、息子の光明クラウスの成長を追う「光明」や、彼女の死の事後の作品を多く含む「エピファニー」の章が配置されることで、見る者を不幸に感染させていくような力がだいぶ薄まり、弱まっているのだ。そのことによって、「メモワール」の作家ということに限定されがちだった写真家・古屋誠一が本来備えている、のびやかな画面の構成力、被写体をしなやかにつかみ取っていく視線の動きなどが、よりくっきりと見えるようになっていた。
しかも、展覧会のタイトルが「メモワール.」になっていることに注目すべきだろう。このタイトルの末尾に付されたピリオドが意味するのは、本展を「最後のメモワールにしたい」という古屋の意志である。つまり、1989年に刊行された『Mémoires』(Edition Camera Austria and Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum)以来、ずっと続けられてきた「記憶」の検証作業に終止符を撃つという宣言なのだ。これは古屋にとっても、彼の写真を見続けてきた僕のような観客にとっても、よいことだと心から思う。単純に「安心したい」「安らぎを得たい」ということではない。また発表しないことで、あの「記憶」が幸福なものに変わると思っているわけでもない。だが「メモワール」を編み続ける過程で、古屋が苦闘しつつ見出そうとしてきた何ものかは、この断念によって失われるどころか、より豊饒な輝きを増し、「発酵」していくのではないか。そんなふうに信じたいと思うのだ。
2010/05/19(水)(飯沢耕太郎)
春木麻衣子「possibility in portraiture」

会期:2010/05/14~2010/06/12
TARO NASU[東京都]
春木麻衣子は画面の大部分が黒、あるいは白の地で覆い尽くされた作品を発表してきた写真家。その闇や光を透過して、身を捩るようにして見えてくるイメージに独特の緊張感がある。これまでは純粋な風景作品だったのだが、2008年頃から画面に「人」の影が登場するようになり、今回の個展ではポートレートの領域にさらににじり寄ってきている。それでも、ロンドンの大英博物館の階段を昇り降りする観客の姿を捉えた「outer portrait」(白)、ニューヨークの街頭をスポットライトのように照らし出したシリーズと、窓の隙間から見えるチュニジアの石壁と通行人を撮影したシリーズから成る「whom? whose?」(黒)の両作品とも、これまでの彼女の取組みから大きく隔たっているわけではない。だが、着実に表現の幅を広げ、新たな方向に進んでいこうという意欲が強く感じられる展示だった。
僕はポートレート、つまり他者の存在と向き合うことは、春木にとってとても重要なテーマになっていくのではないかと思う。これまでどちらかといえば「inner」な領域にこだわり続けてきた彼女が、「outer」に自分を開いていくきっかけになっていくのではないだろうか。いまのところ、まだ舞台のような場所を設定して、そこに「通行人」を呼び込むようにして撮影されているのだが、さらにこの試みを進めていけば、もっと身近な「顔の見える」他者が出現してくるかもしれない。そんな予感も感じられる展示だ。
2010/05/14(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)