artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
眠り展:アートと生きること ゴヤ、ルーベンスから塩田千春まで

会期:2020/11/25~2021/02/23
東京国立近代美術館[東京都]
写真は現実世界を描写するメディアだから、眠りや夢とはあまりかかわりのないように思える。だが、東京・竹橋の東京国立近代美術館で開催された「眠り展」には、かなり多くの写真作品が出品されていた。第一章「夢かうつつか」のパートに、マン・レイ「醒めて見る夢の会」(1924)、瑛九「眠りの理由」(1936)、楢橋朝子「half awake and half asleep in the water」(2004)が、第4章「目覚めを待つ」のパートにダヤニータ・シン「ファイル・ルーム」(2011−13)、大辻清司のオブジェをテーマにした連作(「ここにこんなモノがあったのかと、いろいろ発見した写真」ほか、1975)が並ぶ。それ以外にも、塩田千春、森村泰昌の映像作品も出品されていた。
眠りや夢は日常や現実の対立概念ではないことが、写真や映像の展示作品を見ているとよくわかる。むしろどこからどこまでが幻影なのか、現実なのかという境界は曖昧なものであり、写真はその両者を結びつけ、リアリティを与えるのに大きな役目を果たしているということではないだろうか。シュルレアリスムの作り手や批評家たちは、写真が現実を克明に描写すればするほど、神秘性、非現実性が増すことを指摘した。そのことが、本展ではくっきりと浮かび上がってきていた。逆に写真作品に絞り込んだ「眠り展」の企画も充分に考えられるのではないだろうか。
なお、本展は独立行政法人国立美術館に属する東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館、国立映画アーカイブの6館の共同企画「国立美術館による合同展」の枠で開催された。これまで「陰翳礼讃」展(国立新美術館、2010)、「No Museum, No Life?−これからの美術館事典」展(東京国立近代美術館、2015)が開催され、今回の「眠り展」が3回目になる。国立美術館の収蔵作品の総数は4万4千点に及ぶという。それらを活用した、より大胆かつ新鮮な企画を期待したい。
2020/12/05(土)(飯沢耕太郎)
岩間玄『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』

雪山で樹木が伐採される場面から映画は始まる。写真家・森山大道には似つかわしくない風景だ。2018年の秋に開かれる世界最大級の写真フェア「パリ・フォト」に向けて、半世紀前の森山のデビュー作『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968/フォトミュゼ・新潮社、1995/講談社、2011)を復刊(月曜社、2018)させるプロジェクトがスタートした。その写真集の完成までと、森山自身の日々の活動を追ったドキュメンタリー映画。
「街を徘徊しながらポケットカメラでスナップショットする森山、復刊プロジェクトの編集部で森山にインタビューする編集者と造本家、随所に挟まれる通称「三沢の犬」をはじめとする写真、伐採された木などの映像が入れ替わりながら進んでいく。そのなかで何度も出てくる名前が盟友だった写真家、中平卓馬だ。その中平の『なぜ、植物図鑑か』(晶文社、1973)をかつて読んだとき、もの派と同じではないかと思ったものだが、そのもの派の理論的支柱である李禹煥が中平だとすれば、それを実践し続けている菅木志雄が森山に重なるかもしれない。2人とも50年間ブレることなく活動してきたし、スタイリッシュだし、内外でますます再評価の機運が高まっていることも共通している。
森山はこの映画が撮られたとき、すでに80歳。にもかかわらず、Tシャツにジーンズで背筋をピンと伸ばし、ややガニ股気味にうろつきまわり、ときに片手でシャッターを切り、なにごともなかったかのように歩き去る。シャツの背中には「On the Road」のロゴ。こんなジジーになりてえよ、と思わせる映画だ。いや、そーゆー映画じゃないんだけど。ところで冒頭に伐採された木材は、その後、洗浄されてパルプになり、紙になって写真集に化けるという映画の流れの進行役を務めていたのだ。
公式サイト:https://daido-documentary2020.com/
2020/12/01(火)(村田真)
瀬戸正人 記憶の地図

会期:2020/12/01~2021/01/24
東京都写真美術館2階展示室[東京都]
瀬戸正人はユニークな出自の持ち主である。1953年、タイ・東北部のウドーンタニに、残留日本人兵士だった父とベトナム人の母との間に生まれ、8歳の時に父の故郷の福島県に移り住んだ。日本人とベトナム系タイ人という複眼を持ったまま育ったわけで、そのことが、東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)卒業後、1981年からフリーの写真家として活動するようになってからも、彼の写真に大きく影を落としている。今回の東京都写真美術館の回顧展では、その瀬戸の代表作を展示していた。
デビュー写真集としてアイピーシーから1989年に刊行された「Bangkok, Hanoi」(1982−1987)のシリーズは、20年ぶりにタイ・バンコクに帰った時のスナップショットと、母とともに訪ねた親族の住むハノイの写真をカップリングしたシリーズである。忘れかけていたタイ人としての視点を再び取り戻していくプロセスが刻み込まれている。東京在住のアジア人と地方出身者のリビングルームを撮影した「Living Room, Tokyo」(1989−1994)、公園で休日を過ごすカップルにカメラを向けた「Picnic」(1995−2003)、台湾の国道沿いに点在するガラス張りの「ビンラン・スタンド」の女性たちを浮かび上がらせた「Binran」(2004−2007)、東日本大震災後に福島を撮影した「Fukushima」(1973−2016)にも、それぞれアジア人と日本人の間を行き来する、瀬戸の眼差しの振れ幅を感じとることができた。
やや戸惑ったのが、会場の最初のパートに展示されていた近作の「Silent Mode 2020」(2019−2020)である。室内で、「数秒程度」の露光時間で、至近距離から撮影された女性ポートレート群は、彼女たちが「自己の内面へと降りていくプロセス」を写しとろうとしたものだという。だがその意図にもかかわらず、写真から見えてくるのは、ある固定した位相に封じ込められた、意外なほどに均質な「(若く美しい)女性像」の集合である。そこには、さまざまな解釈の余地を残す、あの複眼の視点を感じることができない。だが、もしかするとこのシリーズから、瀬戸の写真の次の展開が始まるのかもしれないとも思う。いまは判断を保留しておきたい。
2020/11/30(月)(飯沢耕太郎)
小平雅尋『同じ時間に同じ場所で度々彼を見かけた/I OFTEN SAW HIM AT THE SAME TIME IN THE SAME PLACE』
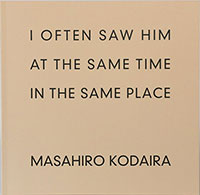
発行所:シンメトリー
発行日:2020/10/19
とても奇妙な、複雑かつ微妙な味わいを残す写真集である。場所はどうやら東京・六本木のようだ。いつもきっかり同時刻に、交差点を小走りに渡っていく若者がいる。やや小太りの体型、大抵チェック柄のシャツを身につけ、チノパンを穿いている。小平雅尋は彼の姿を目に止め、おそらく何気なくシャッターを切った。そのうちに、彼が必ず同時刻に現われることに気がつき、意識的にその後ろ姿を撮影するようになった。写真集にはそうやって撮り溜められた、2019年2月23日から2020年3月5日までの約1年間の写真、56枚が淡々とレイアウトされて並んでいる。
小平は、彼が何者であり、何を目的として、どこに行こうとしているのか、という謎解きをしようとしているわけではない。そのことは、やや距離を置いて後ろ姿だけを写した写真を選んで、顔のような彼の特定に繋がる部位を注意深く避けていることからもわかる。とはいえ、56枚の写真を見ているうちに、この男が写真家にとって、また写真を見るわれわれにとっても、何かしら特別な意味を持つ存在として、じわじわと浮上してくるように感じる。どこかしら、フランツ・カフカの短編小説を読む時のような、細部は明晰であるにもかかわらず、全体としてみるとあやふやで不条理な世界に誘い込まれるような気分になってくるのだ。
小平雅尋はこれまで、写真集『ローレンツ氏の蝶』(シンメトリー、2011)や写真展「他なるもの」(タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム、2015)などで、写真表現の本質的な要素を、抽象度の高いモノクローム写真で追求していくような作品を発表してきた。一転して本作では、曖昧な日常に潜む陥穽を明るみに出すような作品にシフトしている。とても興味深い作風が生まれつつある。
2020/11/21(土)(飯沢耕太郎)
ときたま写真展「たね」

会期:2020/11/19~2020/11/29
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
ときたま(1954年、東京生まれ)は、これまで葉書に「コトバ」を印刷して不特定多数に送る「ときのコトバ」、ドローイングした「プラ板」で立体作品を作る「ぷらたま」、トートバッグに「コトバ」の1文字をドローイングした「ことバッグ」といった、日常の事物を介したコミュニケーションをテーマとするアート活動を展開してきた。2016年に携帯電話をiPhoneに変えたことをきっかけとして、日々写真を撮影し始める。それら数万点に及ぶスナップ写真から約5000枚をポストカード大にプリントし、そこから391点を選んで写真集『たね』(トキヲ)を刊行した。今回のコミュニケーションギャラリーふげん社での展覧会は、そのお披露目を兼ねた企画である。
「ときのコトバ」や「ぷらたま」と同様に、写真でも彼女の基本的な姿勢に変わりはない。日々の出来事を、全方位型のアンテナで捕捉して定着させ、短い断片を撒き散らすように提示していく。「日々は、いつもと面白いとたまたまの「たね」でできている」という認識、それらを再編集し、新たな世界を構築していく歓びが、写真集からも写真展示からもいきいきと伝わってきた。「たね」の写真群には「コロナの日々」に撮影されたものも含まれている。本来は今年6月頃に写真集を出版する予定で、写真選びやレイアウトも終わっていたが、「そのままだとコロナ以前の写真集になってしまう」ということで、急遽予定を変え、自粛期間中に撮影した写真も加えた。そのことで、日常と非日常とが交錯した2020年現在の東京のあり方が、よりヴィヴィッドに浮かび上がってきた。
ときたまの写真行為は、「スマホとSNSの時代」における写真表現のひとつの方向性を示しているのではないかと思う。インスタグラムやフェイスブックでは、垂れ流されるだけで拡散してしまいがちな写真群を、写真集や写真展のような長年の蓄積のある媒体を使って再組織化し、ソリッドな形式に落とし込んで観客に伝達していく。そこに思いがけない新たな可能性が生まれてきそうだ。
2020/11/20(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)