フォーカス
バックナンバー
【ヤンゴン】開国のあとで──揺れ動くミャンマー現代美術家たち
[2020年04月15日号(清恵子)]
中国とインドの中間に位置し、経済成長著しいタイやベトナムに隣接するミャンマー。イギリスからの独立、第二次大戦中の占領時代の歴史のなかで日本とは深い関係があり、現在は日本企業も多く進出している。また、最近はロヒンギャ難民問題が注目されているが...
よりよく生きるための選択──孤立から救済する技術
[2020年04月01日号(青木彬)]
日本型アートプロジェクトの盛行やソーシャリー・エンゲイジド・アートの潮流とさまざまな共同体の実践を比較しながら、「生きること」と「アート」の繋がりを考えようと、筆者は以前 「アートプロジェクトにおける臨床的価値とはなにか」 という試論を寄稿...
【イルクーツク】初心の起爆力を守り抜く──マクシム・ウシャコフ追悼に寄せて
[2020年03月15日号(多田麻美)]
昨年末、あるアニメーション作家が亡くなった。その名はマクシム・ウシャコフ。溢れるような創作の意欲で、アニメーション、ドローイング、俳優業などのさまざまな分野において活躍した。晩年は資金不足に悩むなか、新たな可能性に賭けようとしたものの、夢を...
【台北】「部外者」はいない──カタストロフから顕われる「想像の共同体」
[2020年03月01日号(栖来ひかり)]
もっとも近い隣国台湾は、地震も台風も多い。日本で開催された災害とアートをテーマにした展覧会にインスパイアされた現代美術展が台北市で開催されたという。同市在住の栖来ひかり氏にレポートしていただく。(artscape編集部)
絵が生まれる場所──サンパウロ、ストリートから考えるまちとデザイン
[2020年02月15日号(阿部航太)]
近年、アートと公共について捉え直す展覧会やトークイベントが増えてきている。今号では、デザイナー/ブラジルのストリートカルチャーの研究という二つの異なる視点から「公共」を考える阿部航太氏にご寄稿いただいた。美術館やアートセンターのような専門に...
【シンガポール】「History」への抵抗──バイセンテニアル・イヤーとアーカイヴの実践
[2020年02月01日号(堀川理沙)]
東南アジア全域にわたる膨大な近現代美術のコレクションを誇るナショナル・ギャラリー・シンガポール。作品だけでなく、作家や美術運動のさまざまな資料も収集されている。2019年10月、あらたに図書アーカイヴとしてそれらが公開された。ディレクション...
記憶と忘却の境界に「民話」は潜む
[2020年01月15日号(畑中章宏)]
ドキュメンタリーは事実がそのまま記録されるわけではない。撮影や編集の段階で、演出が行なわれ、編まれ、フィクションが介入していくものである。それは人の記憶と語りそのものに無意識のうちにフィクションが介入しているのと近しい。そのフィクションと事...
作品をつくる場所を集まってつくる──京都・アーティストスタジオ特集
[2019年12月15日号(artscape編集部)]
若いアーティストにとって、制作スペースをどう確保するかは重要な課題である。数人のアーティストが集まって共同で制作スタジオをもつことは珍しくはない。都心では高い家賃という問題を数人でシェアすることで解決できるし、地方なら広い空き物件でも人数が...
【ミュンヘン】印象派の歴史が語らずにきたもの──「カナダと印象派:新たな地平」展
[2019年12月15日号(かないみき)]
カナダの「印象派」をご存知だろうか? 1860年代後半から、カナダの意欲あふれる芸術家たちは海を渡り、パリのアカデミーで学んだ。ヨーロッパを旅しながら、当時スキャンダルを巻き起こして「印象派」と呼ばれた画家たちと交流し、制作を共にしながら、...












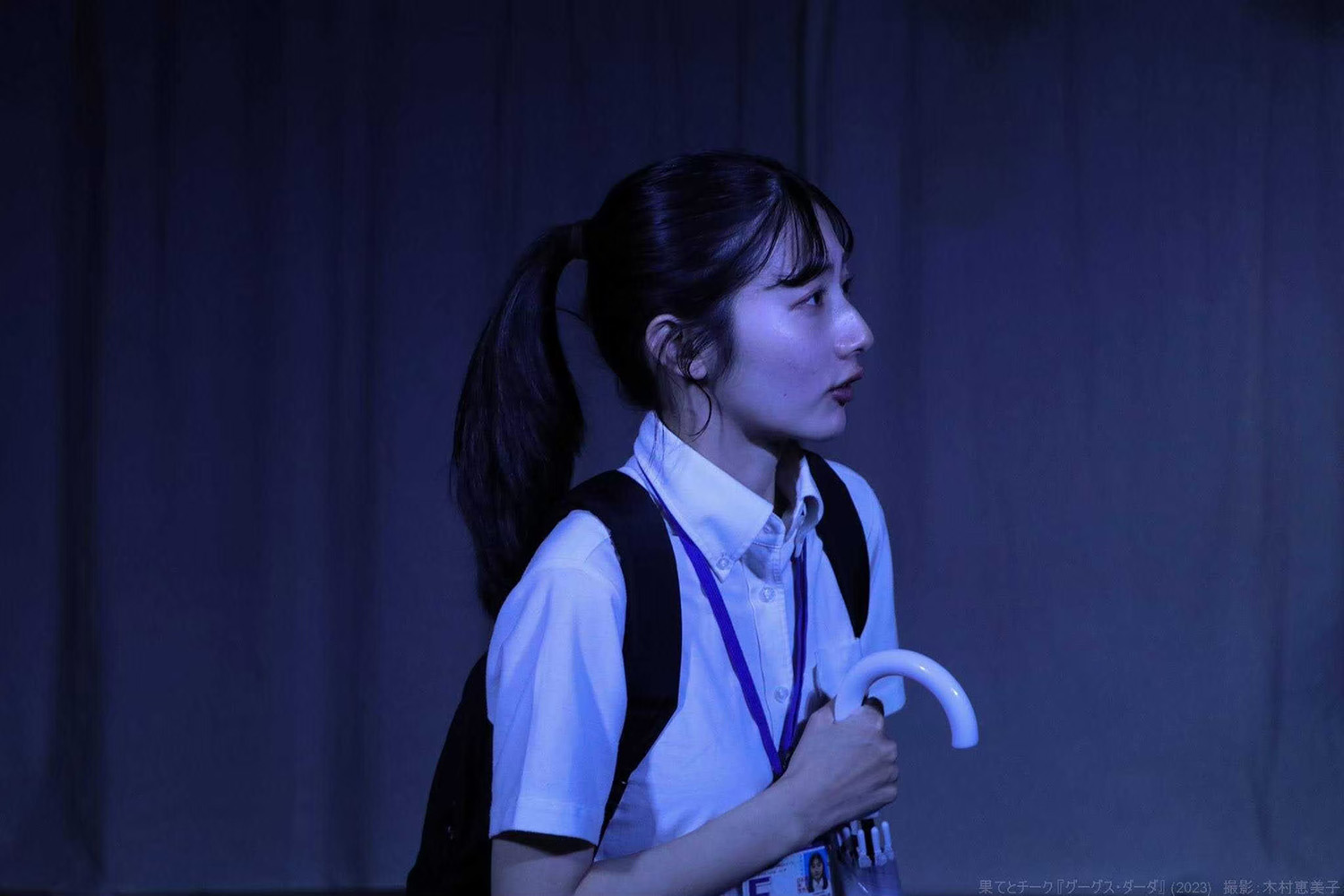


![カタログ&ブックス | 2024年2月1日号[テーマ:みちのくを旅する/暮らす人と、祈りのメディアに思いを馳せる5冊]](/report/review/image/240201_bk_main.jpg)
![[PR]メディアとしてのミュージアムグッズ──文化と経営を媒介する](/report/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/11/30/231201_topics_02_top.jpg)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)