artscapeレビュー
イスラエル・ガルバン+YCAM新作ダンス公演『Israel & イスラエル』
2019年02月15日号
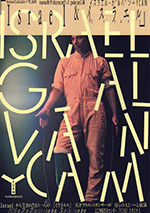
会期:2019/02/02~2019/02/03
山口情報芸術センター[YCAM][山口県]
卓越した技術を誇るフラメンコダンサー、振付家のイスラエル・ガルバンと、彼の神髄と言えるサパテアード(足の裏全体、かかと、爪先などでリズムを刻むテクニック)を機械学習したAIが共演するという、異色のダンス公演。ガルバンとYCAMは約2年間かけて共同制作を行なった。まず、観客に手渡すデバイスの振動を通じてサパテアードを触覚的に伝えたり、照明や音響の変化へと拡張する試み。また、ガルバンの全身の動きをモーションキャプチャーで記録し、そのデータを元に「新たな生命体」が踊る映像も制作された。さらに、徳井直生を中心とするクリエイティブスタジオ「Qosmo」が参加。フラメンコシューズに組み込んだセンサーで足の部位やステップの強さを解析し、AIに学習させてサパテアードの生成モデルを作成し、開発したソレノイド(電磁力によって機械的な運動をするデバイス)が床を叩くことで、ガルバンのサパテアードを「再現」した。
冒頭、現われたガルバンは、小石が敷き詰められたスクエアのなかで、複雑かつ高速の華麗なステップを次々と披露していく。足さばきとともに飛び散る小石の音と軌跡が、水面に広がる波紋や水しぶきのように、彼のサパテアードを聴覚的、視覚的に増幅させる。身体の運動のみをシンプルに提示した導入部の後、サパテアードは、会場全体を体感的に包むような重低音や、照明の色やパターンの変化へと拡張される。中盤では、AIが学習したサパテアードをソレノイドが床を叩いて表現し、「分身」あるいは「もうひとりのダンサー」としてガルバンとの「かけ合い」を見せた。終盤、ガルバンは姿を消すが、「無人」となった舞台上では、蠢く細胞の分裂のような映像をバックに、ソレノイドの刻むリズム、その音響的増幅、そしてめくるめく照明の変化が音と光の饗宴を見せる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
単体で踊る身体の提示から、テクノロジーとの共演を経て、もはや生身の身体が存在しない世界でどこまで「ダンス」を感じられるか。ストーリーは明快で、もちろんガルバンの驚異的な技術も堪能できる。だが、本公演を見る限り、「ガルバンのサパテアード」を「リズム」という音楽的な要素に還元し、音響と光の饗宴として増幅し、スペクタクルとして拡張しただけの印象は拭えない。学習したAIは、人間のダンサーが生み出すパターンよりも複雑かつ多彩なステップを生成できるのか? 模倣を通した学習は「オリジナル」を越えていくのか? AIに「即興」という概念は理解できるのか? 「肉体的疲労や衰え、死」の概念のないAIに「ダンス」の創出は可能なのか? こうした問いの触発には至らず、身体表現とテクノロジーをめぐる問いの深化には繋がらなかった点が惜しまれる。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
むしろ興味深かったのは、上演中/上演後のポストトークにおける、「(女性)通訳者」の置かれた位相(とその反転)である。中盤、YCAMスタッフの大脇理智が登場し、自己紹介を語るシーンがある。エンジニアとしてデバイス開発に携わったこと、ダンサーとしての活動も個人的に行なっていること、ガルバンの舞台を見た印象などだ。彼の言葉は、傍らに立つ通訳者により、英語とスペイン語に変換される。だがその声は、ガルバンが刻むサパテアード(及びその機械的増幅)と、「通訳」を遮って話し続ける大脇の声によって二重、三重にかき消されてしまう(この「自己紹介」は何度も執拗に繰り返される)。

[撮影:守屋友樹 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
一方、ポストトークで彼女は、ガルバンの話すスペイン語を日本語に通訳する。ここでやや珍しく興味深いのは、女性通訳者がガルバンの言葉を伝える際、「私」ではなく「僕」という一人称を用いていたことだ(言い慣れなさの印象と相まったこの奇妙さは、通訳者が男性の場合は特に意識されないだろう)。性差と主体を撹乱させるような一人称の使用は、彼女を、単に他者の言葉を媒介する通訳者としての副次的な立場から、演劇性を帯びた存在へと接近させる。「サブ音声」として文字通り抑圧された状況から、「演劇的なプレーヤー」への接近。ガルバンと対話相手の狭間で、彼女だけがただ一人、別の異なる位相で「発話」しているように見えた。彼女はその一人称の(確信犯的な)使用を通して、他者の言葉のただ中に身を置きながら、その内部において、自らの置かれた位相の転換を密かに図っていたのではないか。公演の本題とは離れたメタな位相で、「通訳、媒介、言語の所有者、一人称とジェンダー、その逸脱的使用と演劇性」についての問いを触発される機会だった。
2019/02/03(日)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)