artscapeレビュー
高嶋慈のレビュー/プレビュー
プレビュー:猿とモルターレ アーカイブ・プロジェクトin大阪
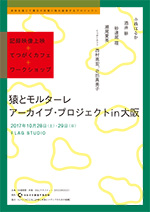
会期:2017/10/28~2017/10/29
FLAG STUDIO[大阪府]
『猿とモルターレ』(演出・振付:砂連尾理)は、「身体を通じて震災の記憶に触れ、継承するプロジェクト」として、公演場所ごとに市民とのワークショップを通じて制作されるパフォーマンス作品。2013年の北九州、2015年の仙台公演を経て、2017年3月に大阪で上演された(大阪公演の詳細は、下記の関連レビューをご覧いただきたい。メタファーを随所に散りばめつつ、声と身体を駆使した圧倒的なパフォーマンスと反復の密度をたたえた、優れた舞台だった)。この大阪公演では、震災後の東北で記録と継承の活動に取り組む映画監督の酒井耕とアーティスト・ユニットの小森はるか+瀬尾夏美が参加し、朗読テクストの提供や記録撮影を手がけた。
今回の「アーカイブ・プロジェクトin大阪」は2日間に渡って行なわれる。1日目は、映像作家の小森による上演の記録上映会と、記録映像と「継承」のあり方について考える「てつがくカフェ」が開催される。2日目には、瀬尾のテクストの朗読ワークショップと、酒井による映像ワークショップを開催。それぞれのワークショップでは砂連尾も講師として加わり、「身体を使ってテクストを読む」「声や身体による出来事の継承」や、「カメラに撮られる身体の変容」「記録メディアによる出来事の編成の危うさとその可能性」について考えるという。
本プロジェクトは、「震災の記憶の継承」という問題に加えて、「舞台芸術の一回性や身体性をどう記録するか」というパフォーミングアーツにおける「記録」やアーカイブの問題についても考える好機となるだろう。また、単なる記録映像ではなく、映像作家や映画監督すなわち表現者としての視点や問題意識をどう取り入れるか、という点にも注目したい。なお本プロジェクトは、来年3月10日~11日にせんだいメディアテークにおいても開催が予定されている。
 撮影:松見拓也
撮影:松見拓也
関連レビュー
砂連尾理『猿とモルターレ』|高嶋慈:artscape レビュー
2017/08/31(木)(高嶋慈)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017
会期:2017/10/14~2017/11/05
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール “アルティ”、京都府立文化芸術会館、ほか[京都府]
8回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下「KEX」)。公式プログラムでは、12組のアーティストによる計12の公演や展示を予定。
今回の大きな特徴は2点あり、1点目は「東アジア文化都市2017京都」コア期間事業の舞台部門として、中国と韓国のアーティストが初紹介される。スン・シャオシンは、ネットやサブカルチャーに浸る中国現代社会の若者を描く作品を発表。また、パク・ミンヒは、韓国の無形文化財である伝統的唱和法「ガゴク(歌曲)」を習得した歌い手。宮廷音楽として確立され、親密な閉鎖的空間で歌われた「ガゴク」の鑑賞形態も取り入れ、パフォーマーと観客が1対1で向き合う上演形式も注目される。ネットやサブカルへの耽溺といったグローバルな現象と、伝統文化の再考。こうした文化的アイデンティティをめぐる考察は、村川拓也、神里雄大、ダレル・ジョーンズ、マルセロ・エヴェリンの作品へと繋がっていく。ドキュメンタリーやフィールドワークの手法を演劇に取り入れる村川拓也は、中国と韓国でのリサーチに基づく新作を発表する。ペルー生まれ、川崎育ちという自らのアイデンティティから、移民や他者とのコミュニケーションを主題化してきた神里雄大は、ブエノスアイレスでの滞在経験に加え、近年訪れたオセアニア、小笠原など各地での取材を基にした新作を予定。現地で出演者を見出し、スペイン語での上演を行なうという。また、アメリカの振付家、ダンサーのダレル・ジョーンズは、ゲイ・クラブで広まったヴォーギングからインスパイアされたダンスを通して、ステレオタイプなセクシャリティや抑圧への抵抗を身体表現化している。日本で滞在制作した新作を発表する予定。ブラジルの振付家、パフォーマーのマルセロ・エヴェリンは、過去2回のKEXで衝撃的な作品を観客に突きつけてきた。今回は、舞踏を生んだ土方巽の著作『病める舞姫』を手掛かりとした作品が上演される。極限的な肉体や暴力性を提示してきたエヴェリンが、土方の思想とどう対峙するのかが注目される。

左:スン・シャオシン『Here Is the Message You Asked For... Don't Tell Anyone Else ;-)』 Photo by Chen Jingnian
右:パク・ミンヒ『歌曲(ガゴク)失格:部屋5 ↻』© Festival Bo:m
また、2点目の特徴として、上記のパク・ミンヒに加え、ハイナー・ゲッベルスの音楽劇や池田亮司による「完全アコースティックなコンサート」など、「音楽」との関連性がある。他領域との横断、総合芸術としてのパフォーミングアーツという点では、光と影が巨大な幻想世界をつくり出す田中奈緒子のインスタレーション・パフォーマンスや、美術作家の金氏徹平の映像作品『Tower』をライブ・パフォーマンスとして演劇化する新作がある。また、今年3月に逝去したトリシャ・ブラウンのダンスカンパニーは、「霧の彫刻」で知られる中谷芙二子とのコラボレーション作品のほか、劇場用に制作された作品群を上演する。

左:ハイナー・ゲッベルス×アンサンブル・モデルン『Black on White』 © Christian Schafferer
右:2人『TOWER (theater) 』2017 Photo by Hideto Maezawa
8回目の開催ともなれば、2度、3度と登場する「常連」的な顔ぶれも見受けられる(村川拓也、マルセロ・エヴェリン、池田亮司、金氏徹平、トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー、そしてリサーチプロジェクトとして参加するresearchlight)。そうしたフェスティバルの「基底」に厚みが加わっていくと同時に、新たなアーティストや方向性が加わることで、より太く展開していくフェスティバルの幕開けに期待がふくらむ。
公式サイト: https://kyoto-ex.jp
*ダレル・ジョーンズ『クラッチ』は事情により上演が中止になりました。(2017年9月22日編集部追記)
2017/08/31(木)(高嶋慈)
時差『隣り』

会期:2017/08/30~2017/09/03
green & garden[京都府]
「時差」は、特定の演出家や劇作家によるカンパニーではなく、複数のアーティストが同じコンセプトを共有しながら、それぞれの新作公演をプロデュースする企画団体。第1回目の企画「動詞としての時間」では、精神科医の木村敏の著作を読み、「臨床哲学」の言葉を手がかりに、演劇、ダンス、映画作品の制作を企画している。
今回上映された映画『隣り』(監督:城間典子)は、城間の幼馴染であり、高校3年の時に統合失調症と診断された女性との共同制作による。本作の特徴は多層構造にあり、過去/4年後の「現在」、再演/ドキュメンタリー、当事者の語り/第3者による証言、といった異なる位相や視点から構成される。映画は大きく2つのパートから構成され、1)幼馴染の女性が心のバランスを大きく崩した時期を、彼女自身が「劇映画」として再現するパートと、2)その4年後に城間が再び彼女を訪ね、編集された映画を見てコメントする様子や、現在の生活を淡々と記録したパートが交互に映し出される。その合間に、高校時代の複数の友人の語りが(おそらく当時のスナップ写真を背景に)挿入され、彼女が演劇部に所属していたこと、演技に情熱を持っていたこと、しかしある時期から様子がおかしくなり、通学も演劇も続けられなくなったことなどが語られる。
本作は一見すると、断片的でとりとめのない印象を受ける。雑多なものが散乱した自宅で、両親や城間と交わす他愛のない会話。弛緩的な日常風景の中に、時折入れ子状に挿入される「劇映画」にも、明確なストーリー性がある訳ではない。彼女自身がノートに綴った「ト書きと絵コンテ」が映し出され、「臭い、死ね」といった「幻聴の声」をアフレコする友人らに「監督」としてダメ出しするシーンも挿入され、これが「再現」すなわちフィクションであることをあからさまに示す。またこの「劇映画」は旧式のビデオカメラで撮影されたため、画質の粗さや縦横比の違いによって「ドキュメンタリー」パートとは明確に区別される。そうした何重ものメタ的な自己言及性に加え、複数の友人による証言が並置される構造は、黒澤明の『羅生門』を想起させ、「当事者による語り、再現」を相対化していく。それは、「物語映画」への構造的な批評であるとともに、彼女とその病についての一義的で安易な「理解」を拒むように働きかけ、「精神病患者」「障害者」としてカテゴリー化して描写せず、他者として一方的に簒奪しないための倫理的な身振りでもある。
2017/08/30(水)(高嶋慈)
キュレトリアル・スタディズ12:泉/Fountain1917 2017 Case 3:「誰が《泉》を捨てたのか Flying Fountain(s)」

会期:2017/08/09~2017/10/22
男性用便器を用いたマルセル・デュシャンによるレディメイド《泉》(1917)の100周年を記念した、コレクション企画展。再制作版(1964)を1年間展示しながら、計5名のゲスト・キュレーターによる展示がリレー形式で展開される。「Case 3: 誰が《泉》を捨てたのか Flying Fountain(s)」は、京都国立近代美術館の元学芸課長、河本信治の企画。タイトルの「Fountain(s)」の複数形が示唆的だ。《泉》のオリジナルはアンデパンダン展で出品拒否された上、現存しないが、アルフレッド・スティーグリッツが撮影した《泉》の写真は広く流通し、後年には複数のバージョンのレプリカが再制作されている。本展では、複製イメージと複数バージョンのレプリカ(もしくはそれに近似した市販品)を用いて、「オリジナル」及びレプリカが提示された各状況がパラレルに「再現」された。
それぞれの「再現」に用いられたアイテムと状況は以下の4ケースである。1)オリジナルを撮影した唯一の写真と言われる、スティーグリッツ撮影の写真。《泉》擁護の記事とともに、雑誌『ザ・ブラインドマン 第2号』に掲載された。本展示では、所蔵品である雑誌そのものではなく、あえて複写した「コピー」を壁に掲示。画像としての拡散性や流通性を強調した。2)デュシャン研究者で画商のアルトゥーロ・シュヴァルツが、1964年に再制作したレプリカ。デュシャンの監修の下、スティーグリッツの写真に基づき図面を作成し、「オリジナルに最も近い」と言われる。このシュヴァルツ版を用いて、「オリジナルがアンデパンダン展会期中、仮設壁の後ろに隠されていた」状況が再現された(展示室のガラス壁面の前を仮設壁で覆い、「バックヤード」を模した空間にひっそりと展示)。3)ニューヨークの画商であったシドニー・ジャニスの勧めで、1950年に再制作されたレプリカ。ジャニスがパリの蚤の市で購入した小便器に、デュシャンが署名し認定した。このジャニス版は、スティーグリッツの写真とは明らかに形態が異なる。所蔵先は他美術館であるため、今回の展示では、近似した市販の小便器を代替品に用い、ジャニス版が出品された1953年の展覧会「Dada, 1916-1923」の記録写真を参照して、展示状況を再現した。台座の上に彫刻的に設置するのではなく、展示室の入り口上部に90度傾けて設置されている。4)もう一台購入した同型の市販製品を代替品として用い、1917年頃に撮影されたデュシャンのスタジオの写真を参考に、彼がレディメイドをどのように提示していたかを再現する。《泉》の他に数点のレディメイドが天井から吊られ、壁に影が投影されている。
このように本展では、1枚の写真と3点のレプリカ(及びその代替品)を用いて、《泉》が提示された複数の状態──展示拒否/雑誌への写真掲載=イメージの固定化と画像としての再生産/再制作としての反復とオリジナルからの逸脱/スタジオでの様態というもう一つの可能態──を同一空間にパラレルに共存させている。それは、資料や記録写真に基づいて状況を検証するという実証的な手続きを取りつつ、複写や再制作という反復の身振りそれ自体を繰り返し、それぞれの個別性と差異を際立たせることで、物理的同一性に基づく「オリジナル」神話の解体、ひいてはそれを制度的に保証する美術館という枠組みに揺さぶりをかけていた。あるいは、《泉》を単一の起源に還元するのではなく、さまざまな歴史的段階における複数の現われとして捉え、それら相互の差分を計測すること。そうした脱中心化に、本展のキュレトリアルな意義がある。

会場風景
2017/08/26(土)(高嶋慈)
笹川治子「リコレクション─ベニヤの魚」

会期:2017/08/25~2017/09/17
Yoshimi Arts[大阪府]
笹川治子は、祖父が陸軍の特攻隊に送られた時の証言や資料をもとに、彼が目撃したというベニヤ板製の人間魚雷を制作している。ツギハギだらけで今にも壊れそうなベニヤ製魚雷の周囲の壁には、取り巻くように海辺や島の写真が(上下反転して)貼られている。これらの写真は、広島県の似島、江田島幸ノ浦、香川県の豊浜、小豆島など、陸軍の訓練施設があったといわれる場所を笹川がめぐって撮影し、祖父が見たであろう風景を収集したもの。人間魚雷の中は空洞になっており、取り付けられた潜望鏡を覗き込むと、(レンズ越しに上下が正しい向きで、だがぼんやりと)海辺の光景の写真が見える。その曖昧にぼやけた像は、祖父の記憶の中のおぼろげな光景とも、過去そのものに触れられないもどかしさともとれる。不鮮明さの印象は、会場内に響くくぐもったノイズ(出撃地点の浜辺で海中の音を採集)や、粗いモザイクのかかった海中の映像(と思われる)によってさらに増幅される。
笹川は以前の作品で、アニメ風の巨大なロボット戦士を透明なビニールでつくり、(空想の)兵器へのロマンや男根的なマッチョイズムを脱力させ、無力化する作品を発表してきた。本展で提示された、脆く弱い素材でハリボテ感の強いベニヤ製魚雷もまた、単に歴史的資料としての再構成に留まらず、そうしたヒロイズムへの批評を内包している。さらに、装備された潜望鏡を通して「過去と現在が折り重なった風景」を見るとき、それは風景への眼差しを再構築する装置であり、風景の中に重層的に沈殿した記憶の中へ潜航するための、想像力を駆動させる乗り物となるのだ。

笹川治子「リコレクション─ベニヤの魚 Recollection: the Plywood Fish」2017 展示風景
© Haruko Sasakawa, courtesy of the artist and Yoshimi Arts, photo by Kiyotoshi Takashima
2017/08/26(土)(高嶋慈)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)