artscapeレビュー
杉江あこのレビュー/プレビュー
石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか

会期:2020/11/14~2021/02/14
東京都現代美術館[東京都]
1966年に発表された資生堂ビューティケイクのサマーキャンペーン・ポスターは、広告業界で長く語り継がれている名作である。「太陽に愛されよう」というキャッチコピーと、ハワイの海辺で撮影された澄んだ青空ときらめく砂浜、そして強い日差しを全身に浴びた健康的な女性が、しっかりとした目力で前を見据える姿は、いつ見ても強いインパクトを残す。これこそ石岡瑛子が世に注目されるきっかけとなった作品であり、また彼女のクリエーティブを物語るうえでの原点とも言える。この健康的で強い女性像は、きっと彼女自身でもあるのだ。そもそも資生堂は、創業者の福原信三が化粧品にも美的価値の必要性を感じて意匠部を設立し、欧州を中心に流行していたアール・ヌーヴォーとアール・デコ様式を積極的に取り入れ、独自の「美」のスタイルを築いてきた企業である。石岡にとって、その伝統さえも時代遅れに感じたのだろう。伝統は革新の連続であるように、以後、資生堂は時代の空気を積極的に取り込んでいくことで、業界ナンバーワンに躍り出る。
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
本展を観て、とにかく石岡のパワーに圧倒された。エントランスに使われたキーカラー、赤のせいもあるかもしれない。資生堂のような大手企業のインハウスデザイナーからスタートし、独立してアートディレクターとして活躍するというのは、言わばグラフィックデザイナーのキャリアの王道であるが、石岡はそこに留まらず、さらに活躍の場を海外に広げた点が圧巻である。しかも演劇、オペラ、映画、コンサート、サーカスなど、エンターテインメント分野までも活動の舞台にしていった点が破格だ。そんなデザイナーは後にも先にも石岡をおいてほかにいないのではないか。なぜならグラフィックと、衣装や舞台はあまりにも違うからだ。彼女の頭のなかはいったいどうなっているんだろう。そんな私の狭い了見に対して軽やかに答えるように、本展のボードには「私は衣装をやっているのではなく、視覚言語をつくっているのだ。」と掲げられていた。なるほど、石岡にすれば、どれもデザインという共通言語でつながっているのか。ところで、観覧中、石岡がデザインについて語るインタビュー音声が会場中に響き渡っており、なんだか彼女に説教を受けているような気分にもなった。
 「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020[Photo: Kenji Morita]
公式サイト:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/eiko-ishioka/
2020/11/21(土)(杉江あこ)
トランスレーションズ展 ―「わかりあえなさ」をわかりあおう

会期:2020/10/16~2021/03/07
21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー1&2[東京都]
恥ずかしながら、数年前から英語学習を再び始めた私としては気になる展覧会だった。コロナ禍で会期が延びたが、本来であれば、本展は東京2020オリンピックに合わせての開催だったのだろう。多くの外国人が日本に大挙して押し寄せる時期に「翻訳」というテーマに挑もうとしたことは理解できる。ただし本展の内容はただ言語を別の言語に変換することだけに留まっていない。視覚や聴覚、身体表現を用いたコミュニケーションや、料理を媒介にした翻訳、現代と古代、未来とのつながり、人と動物、物、さらには微生物とのコミュニケーションにまで風呂敷を広げる。その広げ方は21_21 DESIGN SIGHTらしい。皮肉にも、コロナ禍のいまは人とウィルスとのコミュニケーションが問われているのではないか。そんな風にさえ思えてくる。
本展を観ながら思い出したのが、生まれたときからバイリンガルの家庭環境で育った人に、そもそも頭のなかで何かを考えたり思ったりするときはどちらの言語なのかと尋ねたこと。その答えは意外にも「イメージでしかない」であった。つまり頭のなかでは言語化されていないのだ。日本語しか十分に喋れない私自身も、意識していないが、実はそうなのだろうと気づかされた。つまり我々は思考やイメージを翻訳して言語を発する。だからこそ、時には上手く言い表わせないこともある。そんな翻訳の不思議に迫りつつ、「わかりあえなさ」をわかり合い、また楽しもうというのが本展の狙いのようだ。
 Google Creative Lab + Studio TheGreenEyl +ドミニク・チェン「ファウンド・イン・トランスレーション」[撮影:木奥惠三]
Google Creative Lab + Studio TheGreenEyl +ドミニク・チェン「ファウンド・イン・トランスレーション」[撮影:木奥惠三]
個人的に面白いと感じた作品は、「翻訳できない世界のことば」である。ひと言では言い表わせない、置き換えのできないユニークな世界の言葉をかわいいイラストレーションとともに紹介していた。例えば「PALEGG=パンにのせて食べるもの、何でも全部(ノルウェー語)」、「SAMAR=日が暮れたあと遅くまで夜更かしして、友達と楽しく過ごすこと(アラビア語)」、「SGRIOB=ウイスキーを一口飲む前に、上唇に感じる、妙なムズムズする感じ(ゲール語)」など、これらの言葉からは生活スタイルや人間臭さが透けて見え、とても興味深かった。日本語のなかからも「積ん読」や「木漏れ日」などが取り上げられていて、なるほどと思う。結局、言語はその国や地域の文化を象徴するものである。とすると、翻訳は異なる文化を互いに理解し合うための手段ではないのか。たとえ日本人同士でも、地域や職業、年齢によって使う言葉が微妙に異なることは承知だろう。「わかりあえなさ」をわかり合うことは多様性を認め合うことであり、それはこれからの社会でもっとも問われる姿勢である。わかり合えないからといってイライラするのではなく、むしろ楽しむくらいの余裕を持つ方がいい。そんなことを示唆する展覧会だった。
 エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」[撮影:木奥惠三]
エラ・フランシス・サンダース「翻訳できない世界のことば」[撮影:木奥惠三]
 清水淳子+鈴木悠平「moyamoya room」[撮影:木奥惠三]
清水淳子+鈴木悠平「moyamoya room」[撮影:木奥惠三]
公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/translations/
2020/10/17(土)(杉江あこ)
フィリップ・ワイズベッカーが見た日本 大工道具、たてもの、日常品

会期:2020/10/02~2020/11/20
GALLERY A4(ギャラリー エー クワッド)[東京都]
海外旅行に行くと、街中や宿泊先にあるもの何もかもが珍しく映り、ワクワクする。それは日常的な道具や設備であればあるほどだ。例えば信号機や標識、ポスト……。母国の見慣れたものとは形やサイズ、仕様が違うだけで、その違いがなぜか愛おしく思えてくる。だから、何でもないものをつい写真に収めてしまったという経験はないだろうか。フィリップ・ワイズベッカーの創作の原点もそんな心情にあるのではないかと、本展を観て感じた。もちろん彼の場合、写真ではなく、ドローイングとして残しているのだが。
 展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
ワイズベッカーはフランス政府によるアーティスト・イン・レジデンスの招聘作家として、2004年、京都に4カ月間滞在した経験があるという。また東京2020オリンピックの公式ポスターをはじめ、日本での広告仕事や展覧会も多く、日本との縁は深い。そんな彼が日本滞在中に見たものが本展の主題だ。例えば綿密に描写された畳敷きの和室などは、日本らしい風景としてうなずけるのだが、いかにも和のものばかりではない。小さな工場か倉庫のような素朴な建物、トラックの荷台シート、立ち入り禁止のために道路に置かれたバリア標識、ゴミ箱など、一見、何でもないものを徹底的に観察し、それらにはさまざまな形状があることを知らせる。決して美しいものではないのに、彼の手にかかると、それらはまるで魔法をかけられたように愛おしいものへと変わる。その根底にあるのは、ものへの執着であり愛だ。そう、ワイズベッカーの圧倒的な愛を感じた展覧会だった。
 展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
本展の見どころは、竹中大工道具館の企画ということもあり、日本の大工道具である。鋸(のこぎり)、曲尺(かねじゃく)、墨壺、鉋(かんな)、鑿(のみ)といった伝統的な大工道具やさまざまな木目を写した木片などが、年月を経た古紙に描かれていて圧巻だった。また、パリにあるアトリエをワイズベッカー自らが紹介する映像のなかで、鋸について触れる話も興味深かった。それは「欧米では押して、日本では引いて切るという違いがある。私は絵を描く人間だから、引く方がずっと使いやすい。日本の鋸は私にとって素晴らしい発見だった。そのうえ美しいので気に入っており、しょっちゅう使っている」というのである。そんな視点で日本の鋸が称賛されるとは! 我々も身の回りにある日用品をもう少し自信を持って、いや、愛を持って見直してもいいのかもしれない。
 展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]
公式サイト:http://www.a-quad.jp/
2020/10/17(土)(杉江あこ)
さいたま国際芸術祭2020

会期:2020/10/17~2020/11/15
メインサイト:旧大宮区役所/アネックスサイト:旧大宮図書館/スプラッシュサイト:宇宙劇場、大宮図書館、埼玉会館、鉄道博物館ほか[埼玉県]
2020年3月に開催される予定だった「さいたま国際芸術祭2020」が、コロナ禍のため半年以上のブランクを余儀なくされた後、ようやく公開された。しかし新型コロナウイルス感染拡大が懸念される一部の作品については、展示が中止になるなど、いろいろな苦難を乗り越えての芸術祭である。テーマは「花/flower」であるが、会場を訪れて感じたのは、むしろ「廃墟」という裏テーマのような背景であった。何しろメインサイトは旧大宮区役所、アネックスサイトは旧大宮図書館である。おそらく同芸術祭のディレクターがこうした場を利用することが得意なのだろう。かつて大勢の人々が出入りし活動していた場が、人の気配だけをなくし、そのまま残されている。それが大きな存在感として横たわり、展示作品はそれをいかに生かすか、もしくは共存するかにかかっているようにも感じた。同ディレクターは「花をモチーフとして捉えるのではなく、テーマとして考えること」と語っている。もしかして芽吹き、生長し、咲き、散り、種を落とすといった花の循環を考えるメタファーとして、この廃墟をわざわざ選んだのか。
例えばメインサイトで展示されていた篠田太郎の作品は、もともとあった「支援課」「高齢介護課」などのサインが天井からぶら下がる空間に、いくつもの砂山をつくり、シュールな風景をつくり出していた。シュールではあるが、静謐で、まるで「つわものどもが夢の跡」とでも言わんばかりである。もし地球から人類が急に消えたとしたら、このような風景になるのだろうかと想像してしまう。また、メインサイトの薄暗い地下空間を使ってドラムセットなどを展示した梅田哲也の作品は、一体どこまでが作品で、どこまでが何も手を加えていない廃墟なのか、その境が曖昧で、まるでお化け屋敷を覗くようなドキドキ感をともなった。一方、「花/flower」のテーマを明確に組み込みながら、かつての場の記憶をスパイスとして生かし展示していたのがミヤケマイの作品だ。もともとあった「外国人生活相談室」のサインから始まり、移動を余儀なくされる移民や女性ら弱者への視点、また生物のはかなさや循環などを、工芸的手法で丁寧につくられた作品群を通して問いかけていた。
 展示風景 メインサイト 篠田太郎《ニセンニジュウネン》
展示風景 メインサイト 篠田太郎《ニセンニジュウネン》
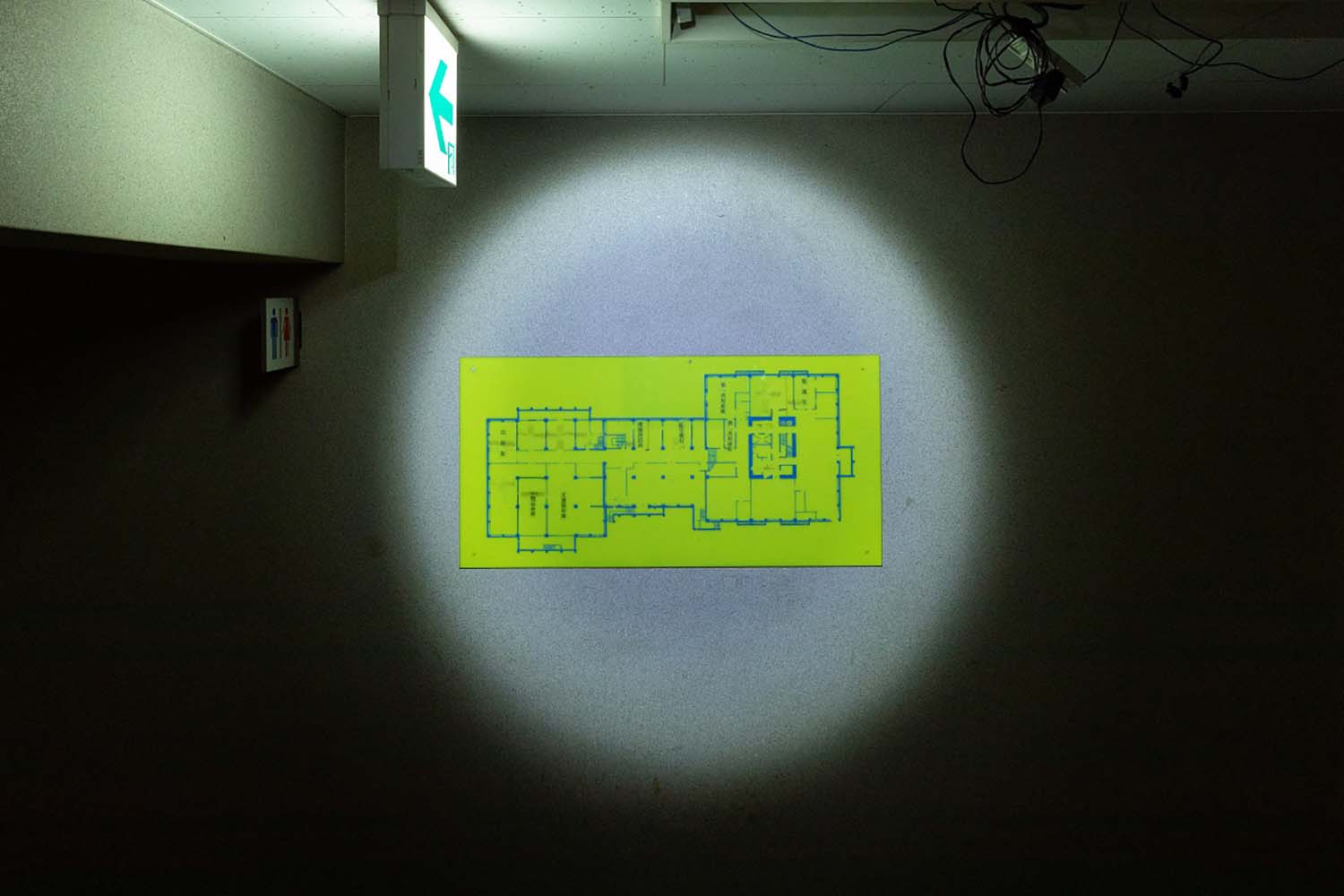 展示風景 メインサイト 梅田哲也《0階》[撮影:丸尾隆一/写真提供:さいたま国際芸術祭実行委員会]
展示風景 メインサイト 梅田哲也《0階》[撮影:丸尾隆一/写真提供:さいたま国際芸術祭実行委員会]
 展示風景 メインサイト ミヤケマイ《胡蝶之夢》
展示風景 メインサイト ミヤケマイ《胡蝶之夢》
コロナ禍を経験したことで、同芸術祭はオンラインとオンサイト(会場)の両方で鑑賞できる体制となった。しかしオンラインではわずかな紹介に過ぎず、やはり会場まで足を運ばなければ作品を真に理解し体験し得なかったことを、最後に付け加えておきたい。
公式サイト:https://art-sightama.jp
2020/10/16(金)(杉江あこ)
いきることば つむぐいのち 永井一正の絵と言葉の世界

会期:2020/10/09~2020/11/21
ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]
照明を落とした薄暗闇の空間に林立する、かわいらしくも、どこか悲しみを帯びた動物たちの絵。その間を縫うようにして言葉が立ち並び、印象的にスポットライトを浴びている。「人と違っているから、生きる意味が生まれる。」「本物の美と出会う。自分が問い直される。」など、どれもシンプルなメッセージでありながら、時々、ハッとさせられてしまう。この絵と言葉の“森”とも言うべき空間に身を置いていると、不思議と心が静かに、安らかになるのを感じた。コロナ禍を経て、ギャラリーは展覧会を通していったい何を発信すべきなのか。そのひとつの答えが本展であるようだ。2020年、我々は多くのことを考えさせられたし、さまざまなものの価値観が変わった。だからこそ「いったん立ち止まって、すべてを考え直す時期にきている。」という言葉が心にグッと響いた。
 展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政]
展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政]
本展は、グラフィックデザイナーの永井一正が上梓した著書『いきることば つむぐいのち』が基となり生まれた企画だ。言うまでもなく、永井は戦後のデザイン創世記を築いた重鎮である。札幌冬季オリンピックをはじめ、JA、三菱UFJフィナンシャル・グループ、アサヒビールなど、誰もが知るロゴマークを数多く手がけてきた。その一方で、ライフワークとして動物の命をモチーフにした「LIFE」シリーズを描き続けている。フリーハンドによる線画や緻密な点描画、そして手の込んだ銅版画まであり、その取り組みには並々ならぬエネルギーを感じる。本展で展示された絵も、すべて「LIFE」シリーズから厳選された作品だ。永井が「LIFE」シリーズを通して訴えるのは、すべての命との「共生」である。この地球上でこれから人間はどう生きるべきか。まさに「いったん立ち止まって、すべてを考え直す時期にきている。」のだ。
冒頭でも述べたが、どれもシンプルなメッセージであるのに、時々、ハッとさせられるのは、おそらく今年91歳を迎えた永井の言葉だからこそだろう。それは100歳前後の人が書いた“アラハン本”が売れるのと同じ構造で、我々は人生の大先輩から生きる術を優しく教えてもらいたいのだ。コロナ禍で心が揺らいでいるいまだからこそ“効いた”展覧会だった。
 展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1階[写真:藤塚光政]
展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリーB1階[写真:藤塚光政]
公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000768
2020/10/09(金)(杉江あこ)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)