artscapeレビュー
杉江あこのレビュー/プレビュー
ポカリスエットCM「ポカリNEO合唱」篇
クライアント:大塚製薬
企画制作:電通・なかよしデザインスプーン
非常事態宣言が発令されてから1カ月以上が経った。長引くコロナ禍で、テレビ放送のあり方も変わった。ニュースやワイドショーなどでは出演者がリモート出演するのが当たり前になり、多くのロケやドラマが撮影中止や延期となったため、過去の番組を再放送する動きが盛んである。では、テレビCMはどうか。海外旅行に行く。家族で行楽地に出かける。友人たちと飲み会を開く。そうしたいままで当たり前にできていたことができない非常事態である。企業はどんな方法で商品やサービスを訴求すればいいのか。いま、新たなコミュニケーションデザインが問われている。
こうした状況下で、ひと際目を引くテレビCMが4月から流れ始めた。大塚製薬「ポカリスエット」のCMである。ひとりの可憐な女子高校生が、自分の部屋でスマホの自撮り画面に向かって歌を歌い始める。が、ひとりではなく、複数人の歌声が重なり合って聞こえてくる。と思った次の瞬間には、やはり自撮りされた複数人の中高校生の顔が画面にタイル状に並び、その数がどんどん増えていく。そして一人ひとりが画面に向かって一所懸命に歌い踊る姿が、小気味良いテンポで、順に大きくフォーカスされていく。同社がこのCMを「ポカリNEO合唱」と名づけたように、これはオンラインを使った新しい合唱なのだ。CMのコンセプト文の冒頭にはこう書かれている。「今はみんなで会えないけれど、歌は歌える」。世の中の空気を鮮やかに読んだ映像表現に、SNSでも高い評価が集まった。
このCMを紹介するネット記事を参照してみると、もともと、同社では「合唱」を軸に昨年秋頃からCMの企画が始まっていたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、大勢の中高校生が一堂に集まって合唱するシーンを撮影することが困難になり、急遽、中高校生にそれぞれの自宅で自撮りしてもらう企画へと変更したのだという。まさにピンチが新しい表現を生んだのだ。自宅で過ごす時間を少しでも楽しんでもらおうと、最近はタレントやミュージシャンらによる歌のコラボやリレーの動画配信が盛んである。「ポカリスエット」のCMはこうした動画も彷彿とさせる。スマホを当たり前に持ついまの中高校生たちは、自撮りで自分を表現することに慣れているという。そのためかわずか30秒の映像のなかで、彼らの情熱がワッと伝わり、見ている方も胸が思わず熱くなった。
公式サイト:https://www.otsuka.co.jp/adv/poc/tvcm202004_02.html
2020/05/04(月)(杉江あこ)
アルベール・カミュ『ペスト』
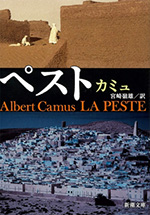
訳者: 宮崎嶺雄
発行所:新潮社
発行日:1969/10/30
フランスの文豪、アルベール・カミュの『ペスト』が、ここ最近、急にベストセラーとなり話題を呼んでいる。4月頭、私も御多分に洩れず新潮文庫を購入し、その奥付を見て驚いた。昭和44年に発行後、平成に一度だけ64刷改刷をするに留まっていたにもかかわらず、令和2年3月30日に87刷である。新型コロナウイルスが猛威を振るうこの非常事態にこそ、疫病を描いた物語を改めて読み、同時体験として共感と教訓を得たいという心理なのか。
通読してみて、やはり想像どおり、物語と現在の状況とがよく似ていて震えた。舞台はカミュの生まれ故郷であるアルジェリアの港町オラン。ひとりの医師の目と、彼の友人が残した手帳の観察記録を通して、物語は淡々と進んでいく。ネズミの死体発見から始まり、ペストが人々を徐々に襲って病や死に至らせると、町がついに封鎖されてしまう。その町の中で、医師と交流のあるさまざま立場の人たちの行動や心理がつぶさに描かれていく。この災禍を「みずからペストの日々を生きた人々の思い出のなかでは、そのすさまじい日々は、炎々と燃え盛る残忍な猛火のようなものとしてではなく、むしろその通り過ぎる道のすべてのものを踏みつぶして行く、はてしない足踏みのようなものとして描かれるのである。」とカミュは描写する。そう、現在、私たちが直面しているこの非常事態宣言下もまるで「足踏み」のようではないか。
本書は「不条理の哲学」と評されている。疫病や戦争、貧困などの不条理な状況下に置かれたとき、結局、人々が取る行動や心理は、昔もいまもあまり変わらないことが切々と伝わる。そもそも本書が発表されたのは1947年。第二次世界大戦直後だったことから、当時のフランス人にはまだ記憶に新しい戦争体験と重なったようだ。しかし当時と現在とでは、大きく異なる点がある。それは現代には進んだテクノロジーがあるということだ。当然ながら医療が進化している一方、世界中の都市がロックダウンしても、我々にはインターネットという強い武器がある。物語のなかでは封鎖された町の人々が引き離された家族や恋人と連絡を取る方法は電報しかなかったが、現代にはビデオ通話がある。学校には通えないが、オンライン授業が試み始められている。会社に通勤せずともリモートワークが実践されている。買い物もネット通販が盛んだ。インターネットだけではない。休業を余儀なくされた企業や人々の間では、新しい仕事への可能性を柔軟に探ろうとする動きがあり、また同時に新しい生活スタイルも築かれつつある。「Withコロナ」や「Afterコロナ」という言葉が生まれているように、このコロナ禍をきっかけとして、いま、社会の大きな価値転倒が起ころうとしているのかもしれない。そう考えると、疫病は人間社会を荒療治するために不意にやって来る“神”のような存在にも思えてくるのだ。疫病神とはよく言ったものである。
2020/04/30(木)(杉江あこ)
白 の中の白 展 白磁と詞という実験。

会期:2020/03/13~2020/07/05(※)
無印良品 銀座 6F ATELIER MUJI GINZA Gallery1[東京都]
※4月11日より臨時休館
本展は小規模ながら、白磁に焦点を当てたユニークな展覧会だ。白磁とは白い磁器。もともとは中国で誕生した青磁と白磁の歴史にもさらりと触れつつ、本展でハイライトとするのはバウハウスで発達したモダンデザインの白磁である。それについて本展では「白無地の価値を『発見する』」と表現している。主な展示品はティーポットとカップ&ソーサーで、白磁の素地と、お茶を淹れて飲むという機能は共通しながら、さまざまな形状や曲線の違いを見ることができた。例えばヴァルター・グロピウスがデザインしたティーポットとカップ&ソーサーには、どことなく建築的な佇まいを感じてしまう。
 カジミール・マレーヴィチ、デザインのティーポット(1923) ©知識たかし
カジミール・マレーヴィチ、デザインのティーポット(1923) ©知識たかし
またロシア・アバンギャルドのひとつと言われる「シュプレマティズム」を宣言した芸術家、カジミール・マレーヴィチがデザインしたティーポットやカップも大変興味深い。代表作《White on White(白の上の白)》を彷彿とさせる形状で、まさに彼の世界観を表現していた。そして日本の白磁として取り上げられたのは柳宗理と森正洋の食器である。彼らは言うまでもなく、日本の食卓に白磁をもたらした代表的デザイナーだろう。本ギャラリーではモダンデザインを軸に企画展を開催していることから、本展でもいわゆる日本の産地に多くある、窯元や作家自身が形を考えてつくる白磁は登場しない。その点にやや物足りなさを覚えてしまうのは私だけか。
したがってモダンデザイン以前の白磁も登場しないのである。そもそも白磁(陶磁器)は6世紀の中国で誕生し、11世紀の宋時代に目覚ましい発展を遂げた。この時代に官窯(中国宮廷の窯)となった景徳鎮窯で染付を盛んに生産したことから、中国磁器=染付のイメージが広まるが、実は青磁を得意とする窯、白磁を得意とする窯などさまざまな窯が誕生した。この中国磁器に大きく影響を受けたのが、日本初の磁器産地となった有田だ。有田でも染付を多く生産し、のちに色絵も誕生するのだが、やはり青磁や白磁も生産していた。一方で15〜16世紀の李氏朝鮮では、染付の原料である呉須が産出されなかったことなどから、生産されたのは主に白磁だった。いわゆる「李朝白磁」である。これが東洋における白磁の大きな流れだ。
とはいえ、白磁に対する解釈はさまざまだ。むしろ本展で白磁を際立たせていたのは、タイトルにもあるとおり「詞」である。展示室の外壁には、日本の前衛詩人、北園克衛が残したコンクリートポエトリー《単調な空間》が印象的に用いられていた。モダンデザインの白磁に対する、この解釈はなかなか新鮮だった。
 展示風景 ATELIER MUJI GINZA Gallery1 ©ATELIER MUJI GINZA 2020
展示風景 ATELIER MUJI GINZA Gallery1 ©ATELIER MUJI GINZA 2020
 北園克衛『煙の直線』(國文社、1959) ©ATELIER MUJI GINZA 2020
北園克衛『煙の直線』(國文社、1959) ©ATELIER MUJI GINZA 2020
公式サイト:https://atelier.muji.com/jp/exhibition/680/
2020/04/06(月)(杉江あこ)
安西洋之『「メイド・イン・イタリー」はなぜ強いのか?──世界を魅了する〈意味〉の戦略的デザイン』

発行所:晶文社
発行日:2020/02/25
本書は、イタリアが得意とするビジネス戦略を解き明かした一冊である。メイド・イン・イタリー、つまりイタリアの製品(主にファッション、食品、インテリアデザイン、自動機械)が、世界市場で存在感を発揮しているという事実に対し、著者は二つのキーワードを提示する。それは「意味のイノベーション」と「アルティジャナーレ」だ。両方とも聞き慣れない言葉かもしれない。前者は「モノやサービスがもたらす意味を変えること」で、必需性や利便性、機能性とは関係なく、言うならばユーザーが熱烈に愛してやまないモノやサービスを開発することである。後者は「職人的」を意味するイタリア語だ。この二つを得意としながら、イタリアの企業は「狭く深い」市場を開拓する。それは大量生産を基本とする米国や中国、ドイツなどの企業や産業とは対極的な手法である。
イタリアの紳士服をはじめ、スパークリングワイン「プロセッコ」、スローフード運動、ショパンピアノコンクールで公式ピアノの一社に採用されたというピアノ、ノートブランド「モレスキン」、イタリア北部の都市レッジョ・エミリアが行なう先進的な幼児教育など、本書で紹介するメイド・イン・イタリーの事例は幅広い。結局、ユーザーが熱烈に愛してやまないモノやサービスをつくるには、その開発者自身がまず欲しいと思うかどうかが問われる。自分が愛せないものを他人が愛せるのかという原点に行き着くわけだ。その点でイタリア人は「好き」「美しい」「おいしい」といった審美眼に長けているだけでなく、それを主張することをいとわないため、意味のイノベーションを実現しやすい。アルティジャナーレを重視する点と合わせ、実に人間的なビジネス戦略だと実感する。日本の企業がもっと積極的に学ぶべき点は、この意味のイノベーションだろう。本書ではその具体的な手法も説き明かされているので参考にしたい。
いま、イタリアと言えば、新型コロナウィルス感染者が世界でもっとも多い国のひとつとしても動向に関心が集まっている。そんなタイミングで出版された本書は、やや不運にも思えるが、一方でこのコロナ禍で見えてきたのは、イタリア人の文化や習慣、人間性だ。例えば三世帯同居率の高さや、身内や親しい人同士でのハグやキスの多さは、真偽のほどはわからないが、感染を広げた原因としても指摘された。しかしどんな苦境に陥っても、窓やバルコニーから身を乗り出して、皆で歌を歌い励まし合う姿を捉えた映像には心を打たれた。いずれもイタリア人の人間性を物語る一面ではないか。本書を読んで驚いたのは、イタリア人経営者のひとりが「ルネサンスの偉大なアーティストたちのDNAを引き継いでいる」と発言していること。どうやらイタリア人の多くにこうした自負があるようだ。この誇り高さにはまいった。
2020/03/27(金)(杉江あこ)
安藤忠雄(原作)/はたこうしろう(絵)『いたずらのすきなけんちくか』

発行所:小学館
発行日:2020/03/03
建築家の安藤忠雄が、大阪・中之島公園内に子ども向け図書館「こども本の森 中之島」を設計し、大阪市に寄贈した(2020年3月1日開館予定だったが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、現在、開館が延期されている)。その開館に合わせて刊行されたのが本書である。なんと安藤が初めて挑んだ絵本ということで興味を惹かれ、手に取ってみた。当然、同図書館の紹介を切り口としながらも、途中から「建築とは何か」という安藤の思想に迫る内容となっていた。
主人公は小学生くらいの兄妹。父に連れられて「こども本の森 中之島」を訪れるが、父とは入り口で別れ、兄妹だけで館内を探検する。3フロア吹き抜けの構造や壁一面に設けられた本棚など、館内を一望する絵がまず大きく描かれる。肝はここからだ。本棚の脇から伸びる細い廊下を発見した兄妹は、「ひみつの においがする」と興味津々で突き進む。すると天井が高い円筒形の空間にたどり着いた。なんとも不思議な空間にワクワクする兄妹の前に、黒い服を着たおじさんが現われる。このおじさんこそ、安藤忠雄らしき人物だ。本物よりやけにスレンダーで若々しいのが気になるが、髪型はそっくりに描かれている。兄妹からおじさんへ素朴な質問が次々と投げかけられ、おじさんは率直に答える。これが実に興味深い。この円筒形の空間のように、よくわからない変な場所は何のためにあるのか。キーワードとして、おじさんは「いたずら」という言葉を使う。頑丈で機能的な建物は便利だけど、それだけではつまらない。「だから ぼくは、たてものに いたずらを しこむんだ」と。
その事例として直島の「ベネッセハウス」や大阪の「光の教会」、「住吉の長屋」など、安藤の代表的な建築作品が登場する。壁一面の十字架も、雨の日に部屋から部屋へ移動するときに傘をさして歩くことも、すべて安藤のいたずらだったのか! 子どもに向けたわかりやすい言葉として選ばれたとはいえ、いたずらという言葉は実に言い得て妙である。これは悪ふざけというよりは、「無駄なもの」という意味に近い。一見、無駄に思えるものこそ、「どんな風に使おうか」と人の想像力をかき立てるから面白いのだ。それが、安藤が建築に求める真髄だった。確かにその通りなのだ。便利なものは人の心にあまり残らないが、面白いものは心にずっと残り続ける。安藤の建築作品が印象的なのは、大人が真剣に考えて設計、施工したいたずらが仕込まれているからなのだ。
2020/03/05(木)(杉江あこ)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)