artscapeレビュー
村田真のレビュー/プレビュー
画廊からの発言「新世代への視点2017」
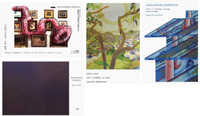
会期:2017/07/24~2017/08/05
ギャラリー58+コバヤシ画廊+ギャラリーQ+ギャラリイK+ギャルリー東京ユマニテ+ギャラリー川船+ギャラリーなつか+ギャルリーソル+藍画廊[東京都]
バブル崩壊後の1993年に始まり、今年で25年目(隔年開催の時期もあるので回数でいうと18回目)を迎えた「新世代への視点」。たしか初年度のサブタイトルは「10画廊からの発言」だったように記憶しているが、参加画廊が少しずつ増減したため「10」を除いたものの、今年は再び10画廊に不時着した模様。振り返ればこの4半世紀に画廊界は大きく変わったが、かろうじて貸し画廊が踏ん張っていられるのは、この「新世代への視点」を開催し続けてきたからではないか。もしこの企画が続いてなければ貸し画廊の存在感はもっと薄くなっていたはず。そう考えるとこの夏、初回から参加していたギャラリー現となびす画廊が相次いで閉廊したのはなんとも寂しい限りだ。
もちろん、いくら展覧会の意義を高く評価したところで、いい作家、いい作品が出ていなければ説得力がない。そこで目に止まった作品をいくつか。まずギャラリー58の水上綾。会場に入ると灰紫色に覆われたモノクロームの抽象画が並んでいる。と思ったら、目を凝らすと白や赤の点が浮かび上がってきて、なんとなく霧のなかに浮かび上がる夜景か、飛行機の上から見た港の風景のようにも見えてくる。白い点はキャンバスをサッと削った跡のようで、なかなかのテクニシャンのようだ。
コバヤシ画廊の幸田千依は清新な水浴の絵で注目を浴びたが、今年のVOCA展では打って変わって木立から遠望した風景画を出品し、VOCA賞を受賞したことは記憶に新しい。今回は水浴図4点と木立から見た風景2点の出品。前者は構図もサイズもバラエティに富んでいるが、後者は縦長と横長の違いはあるものの構図も色彩もほとんど同じで、遠くには小高い山に囲まれた海が見え、瀬戸内海あたりを想起させる。2点とも光(太陽)は画面中央の上から射し、黄色とオレンジ色の光輪を伴っている。水浴図が青、緑を中心としているのに対し、こちらは黄色とオレンジの暖色が支配的。そのせいか、ふと嫌なものを連想してしてしまった。核爆発。まさか作者はそのつもりで描いたんじゃないだろうけど、この白い球は不吉だ。パッと見て瀬戸内海を想起したのも、ひょっとしたらヒロシマを思い出したからかもしれない。考えてみれば太陽はつねに核爆発を起こしているわけだし、あながち的外れな連想でもない。そう思って過去の作品を見直してみると、水浴に気をとられて気づかなかったが、多くの画面の中央に発光源(太陽や火)を据えていたことがわかる。水だけでなく火も主要モチーフだったのだ。
ギャラリーなつかの原汐莉は、具象・抽象を問わずさまざまなかたちに切った板に布を貼り、着色している。色はきれいだが、いまさらシェイプトキャンバスでもあるまいし、と思ったら傍らにドローイングを発見。日付の入ったダイアリーのページにその日に思いついたイメージを描いたもので、ここから図柄をピックアップして拡大し、作品化しているそうだ。そういえば絵画化したものは上下が水平に切れてるものがいくつかあるが、それはダイアリーの罫線によってドローイングをフレーミングしているから。絵画も美しいけど、ドローイングのほうが興味深い。
ギャラリー川船の山本麻世は、壁に掛けた同ギャラリー所蔵の30点ほどの近代絵画に、紅白の工事用テープを絡めている。タイトルは「川底でひるね」というもので、地下にあるこのギャラリー(京橋)はかつて川底に位置していたと想定したインスタレーション。紅白のテープは、川底に隠れていそうなゴカイとかウズムシみたいな細長いグロテスクなかたちに編まれていて、それが絵の周囲をのたうち回り、何点かの絵を飲み込んでさえいる。このバケモノの造形はあまりいただけないが、ギャラリーのコレクションを持ち出して自分の作品に採り込んでいる暴力性は評価したい。ほかにも額縁にカラフルな樹脂製品をはめ込んだり、パレルゴン(作品の付随的な要素)に興味を抱いているようだ。以上4人の作品に共通しているのは、ダブルイメージやダブルミーニングなど多様な見方、多彩な解釈を受け入れる包容力を備えていることだ。
2017/07/29(土)(村田真)
中銀カプセルタワービル
[東京都]
建築・アートの研究者である和田菜穂子さんの案内で、銀座の中銀カプセルタワービルを見学。黒川紀章の設計により1972年に建てられた13階建ての集合住宅で、カプセルを積み上げたユニークな姿は、新陳代謝していく建築・都市を提唱したメタボリズム運動を代表するものとして知られている。「中銀」というのはてっきり中央銀行とかが施主だったから名づけられたんじゃないかと思っていたが、単に中央区銀座にあるからだって初めて知った。丸窓のある直方体のカプセルが積み重なり、外から見ると巨大な鳥の巣か、コインランドリーの洗濯機を縦に並べたよう。個々のカプセルは独立した部屋になっていて、構造的に交換可能なはずだったが、両隣にビルが建ってしまったこともあって一度も交換されたことはないそうだ。
さっそくエレベーターで上階へ。通路や継ぎ目は老朽化が激しいが、部屋のなかに入ると約半世紀前の「未来」が保存されている。室内はオフホワイトで、直線と円で構成されているところがいかにもレトロフューチャーな趣。そう、これが40-50年前の「未来」だった。大阪万博にもこんな未来的なパビリオンが林立してたっけ。独身者用なので1室の広さはビジネスホテルより狭い3畳程度か、でもその後できたカプセルホテルよりずっと広い。ちなみに最初のカプセルホテルを設計したのは黒川紀章とのこと。ユニットバスはついているけどお湯は出ないらしい。ベッドやテーブルは収納式で、テレビや冷蔵庫は備え付け。部屋によってはあれこれ改装しているという。
こういう未来志向の建築は年月を経てほころびが出てくると、見るも無惨な姿をさらすことになる。最新の機器やデザインほど10年もたてば逆に古さが目立つようになるからだ。レトロフューチャーな建築にも二つあって、ひとつは1968年に公開された映画『2001年宇宙の旅』に見られるような、無菌室のごときウルトラモダンなインテリアであり、理想的かつ非現実的な未来像だ。もうひとつは1982年に公開の『ブレードランナー』に代表される薄汚くて猥雑でデッドテックな未来都市で、こちらのほうが現実的。このカプセルタワーは建設当初はウルトラモダンを目指したのだろうけど、年月を経て図らずもデッドテックな味わいを兼ね備えることになってしまった。やはりこれはいろんな意味で永久保存してほしい建築だ。
2017/07/26(水)(村田真)
ベルギー奇想の系譜展 ボスからマグリット、ヤン・ファーブルまで

会期:2017/07/15~2017/09/24
Bunkamuraザ・ミュージアム[東京都]
ボス、ブリューゲルに始まり、アンソール、クノップフ、マグリット、そしてヤン・ファーブルにいたるまで、ベルギーは一風変わった画家を輩出してきた。幻想的というだけでなく、フランスやイタリアのような美術大国の王道から外れ、少しイジケて奇をてらったような奇想の画家たちというべきか。これはおもしろそう。展覧会は15-17世紀と19-21世紀の2つの時代に完全に二分されていて、フランドル─ベルギーの歴史の複雑さ、アイデンティティの危うさに思いを馳せざるをえない。
初めにボス工房の《トゥヌグダルスの幻視》を中心に16世紀の油彩が並ぶ。先日の「ブリューゲル《バベルの塔》展」にも見られた聖クリストフォロス、聖アントニウスを主題とする作品が多く、興味深いことにどの作品も画面の左または右奥が火事で燃えている。これは地獄の業火に由来するらしいが、こうしたネガティブなモチーフもベルギー絵画の特徴のひとつだ。その後ブリューゲルの版画と、息子のヤン・ブリューゲルの油彩小品(これもボスの伝統を受け継ぎ、画面奥がハデに燃えている)、17世紀のルーベンスの版画へと続くが、ルーベンスは絵画の王道を歩んだ巨匠であり、明らかに「奇想の系譜」から浮いている(というより「奇想の系譜」が美術史の王道から浮いているのだが)。中途半端に版画を出すくらいなら最初から選ばないほうがよかったのに。
その隣の壁からいきなりフェリシアン・ロップス、フェルナン・クノップフ、ジャン・デルヴィル、ジェームズ・アンソールら19世紀末を飾った象徴主義が始まり、その落差がいかんともしがたい。300年間なにやってたんだ? だが、時代が離れていてもベルギー美術に通底するのが「死」の影であり、これが20世紀のマグリットやデルヴォー、そして現代のヤン・ファーブル、ウィム・デルヴォワ、ミヒャエル・ボレマンスらの作品にも見え隠れしている。いじわるな見方をすれば、伝統的な死の影を作品に盛り込むのが現代ベルギーのアーティストの世界戦略なのかもしれない。
2017/07/18(火)(村田真)
アブラカダブラ絵画展

会期:2017/06/03~2017/07/30
市原湖畔美術館[東京都]
同展のゲストキュレーター、カトウチカさんから熱心なお誘いを受け、東京駅前から高速バスでアクアラインを通って市原湖畔美術館へ行くハメになった。なんだかんだとここへ来るのも5回目。タイトルの「アブラカダブラ」とはいうまでもなく魔除けの呪文だが、もうひとつ「わけがわからずチンプンカンプン」という意味もあって、ここでは「得体の知れない絵画展」とでも訳すか。カトウの選んだアーティストは、佐藤万絵子、曽谷朝絵、原游、福士朋子、フランシス真悟、水戸部七絵ら12人。いま挙げた6人は、絵画といっても「絵画」の概念を問い直すような境界線上の作品で知られるが(偶然か、うち3人の名前に「絵」が入っている!)、残る6人のうち石田尚志、西原尚、松本力、村田峰紀はそれぞれ映像、音、アニメ、パフォーマンスのアーティストであり、絵画と無縁ではないものの完全に境界線を超えている。ここらへんが「得体の知れない絵画展」たるゆえんだろう。
小規模な美術館の割に出品者数が多いため、ひとり当たりのスペースが限られたせいか、旧作が多いのは残念なところ。監視員や額縁をシートに描いて壁に貼った福士、キャンバスに油彩で同語反復のように服や絨毯を再現する原、超テンコ盛りにした油絵具の重量に耐えきれず斜めに展示する水戸部、回転するドラム缶にスーパーボールを押しつけて意外な音を出す西原など、楽しめる作品も多い。もっとも感銘を受けたのは、正方形の格子天井にボールペンでガリガリと引っ掻き傷をつけた村田の《原初的身体所作図》だ。システィーナ礼拝堂の天井画を描いたミケランジェロのように、実際に上を向いて掻いたのか、それとも天井板を下ろして掻いたのかは知らないが、かつては洋の東西を問わず天井も絵画の支持体であったこと、その天井画は天井を抜けて天上を目指していたことを思い出させてくれる。タイトルの《原初的身体所作図》は、「掻く」という行為が「描く」「書く」の起源であることを示唆している。思考も行為もいよいよ熟してきた。
2017/07/16(日)(村田真)
東京都復興記念館
東京都復興記念館[東京都]
今日はBankARTスクール生と両国界隈の美術館・博物館探訪。最初は復興記念館で待ち合わせたのに、暑いせいか集まりが悪い。ここは関東大震災(1923)の犠牲者を追悼する震災記念堂の附属施設として、震災の惨禍を伝える目的で1931年に建てられたもの。その後、震災記念堂は東京大空襲などの戦災の犠牲者も追悼するため東京都慰霊堂に改称、復興記念館も戦災関連の資料を追加した。設計は伊東忠太+佐野利器。慰霊堂も伊東忠太の設計で、どちらも軒下あたりにガーゴイルみたいなモンスターが装飾されている。入場無料。
まず1階の陳列室に入ると、震災の被害状況を示す写真や地図やデータが展示され、震災後の大火で焼け出された食器、服、眼鏡、硬貨(溶けて塊になっている)などの日用品が並ぶ。広島平和記念資料館の被爆遺品もすさまじいが、破壊力の違いはあれど高温で焼けたり溶けたりした姿は変わりない。2階へ上がると、中央に震災を描いた絵画や復興状況を伝える都市の模型などの陳列室があり、それを囲むように回廊が設けられ、資料やデータが展示されている。絵画は記念碑的な目的で制作されたのだろう、超大作が多い。作者は徳永柳洲のほか有島生馬もいる。ほぼ同時代の聖徳記念絵画館の壁画やこうした震災画が、後の戦争画の原点になっているのかもしれない。模型のほうは復興記念展や博覧会に出されたもので、背景画を組み合わせたジオラマもある。戦前の世相などもしのばれてとてもタメになった。
2017/07/08(土)(村田真)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)