artscapeレビュー
村田真のレビュー/プレビュー
開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会

会期:2023/04/19~2023/09/24
森美術館[東京都]
なんだと? 現代美術を国語、算数、理科、社会などの科目に分けて紹介する? しかも出品作品の約半数が同館のコレクションだと? いよいよ森美術館もネタに尽きて子どもだましの企画に走ったか……と思ったが、実際に見てみたら、確かに取ってつけたようなテーマでまとめたり、総花的に紹介したりするより、このほうが圧倒的におもしろいし、わかりやすい。なんだ、すっかり術中にハマってしまったではないか。
科目は国語算数理科社会に、哲学、音楽、体育、総合を加えた8科目。出品作家は計54組だが、社会だけ19組と飛び抜けて多く、全体の3分の1強を占めている。これは社会的テーマを扱った作品が多いということで、森美術館の志向・嗜好を反映したものだ。興味深いのは、どの作品がどの教科に分類されているかだ。
「国語」は、シャベルを実物、写真、言葉によって表わしたジョセフ・コスースの《1つと3つのシャベル》(1965)や、著名人の原稿を本人の眼鏡越しに撮った米田知子の「見えるものと見えないもののあいだ」シリーズなど、やはり文字や言葉が出てくる作品が多い。でもコスース作品は、ものとイメージと概念について考えさせるという点で「哲学」のほうがふさわしいかも。
「社会」は、社会彫刻を提唱したヨーゼフ・ボイスの《黒板》(1984)から、インドネシアのコレクティブ、ジャカルタ・ウェイステッド・アーティストが集めた商店の看板まで幅広い。そういえば、巨大な黒板にチョークでびっしりメッセージを書き込んだワン・チンソン《フォロー・ミー》(2003)は「国語」なのに、ボイスの《黒板》が「社会」に入っているのは単に文字が少ないからだろうか。おや? と思ったのは、森村泰昌がマネの《オランピア》の登場人物に扮して写真にした《肖像(双子)》(1989)と《モデルヌ・オランピア2018》(2017-2018)の2点があること。前者は白人と黒人の女性をそれぞれ日本人男性が扮することの違和感が焦点だったが、30年近い年月を隔てて制作された後者では、明らかにジェンダー、人種、身分といった社会的な差別問題が強調されているからだと解釈すべきか。
「哲学」も悩ましい。現代美術は基本的に哲学なしに成り立たないから、この科目は入れないほうがよかったかもしれない。豆腐の表面にお経を書いていくツァイ・チャウエイの映像《豆腐にお経》(2005)は、分類するなら「哲学」より「国語」ではないか。1万個のLEDが9から1までカウントする宮島達男の《Innumerable Life/Buddha CCICC-01》(2度目のCCは裏返し)(2018)は、端的にいって「算数」だろう。いちばん首を傾げたのは、目を瞑る少女を描いた奈良美智の《Miss Moonlight》(2020)。確かに少女は沈思黙考しているようだが、「本作の持つ精神性やある種の神聖さはマーク・ロスコの絵画にも通じ、その作品と対峙する体験は、自己の精神との対峙を促すとも言える」との解説は言いすぎだろう。
突っ込んでいけばキリがないが、最後に思ったのは「美術」という科目がないこと。もちろんすべて「美術」だから入れる必要はないだろうけど、でもひょっとしたら、ここには「美術」の名に値する作品がないからだったりして。まさかね。
公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/classroom/02/index.html
2023/04/18(火)(村田真)
戸谷成雄 彫刻

会期:2023/02/25~2023/05/14
埼玉県立近代美術館[埼玉県]
考えてみたら、戸谷さんの仕事はかれこれ40年以上も前から見ているので、作品そのものにはいまさら驚かないが、展覧会の見せ方には感心、いや感服した。これはもう回顧展の鑑、といいたい。まずタイトルが「戸谷成雄 彫刻」のみで、「展」すらつかない。必要にして十分、まさに戸谷成雄の「彫」「刻」を見せるだけ、それ以上でも以下でもない。展示も作品をドン、ドンと置いていくだけで、余計な解説やキャプションはなく、知りたければ入口で配られる作品リスト(必要最小限の文字情報が載っている)を参照すればいい。つべこべいわずに作品を見てくれ、それで判断してくれといわんばかり。よっぽど作品に自信がなければできないことだ。
ぼくが戸谷の作品を見始めた70年代後半は、石膏に鉄の棒をランダムに埋めて固め、それをノミで彫り当てていく「〈彫る〉から」と、角材を直方体に収まるように組んでいく「〈構成〉から」という2つのシリーズを発表していた。それが近代彫刻を成り立たせている「彫る」「構成する」という行為を再確認する仕事であることはわかったが、80年代に入ってひとまわり下のにぎやかなニューウェイブの連中が登場してからも、われ関せずとばかりに相変わらずコツコツと続けている。いったいいつまで続けていくつもりだろうと思っていたら、1983年に浜松の海岸で波打ち際に穴を掘り、石膏を流し込んで「〈構成〉から」のように材木を組み立て、火を放った。埼玉県立近代美術館の建畠館長はこれを「彫刻の火葬ともいうべき儀式」と述べているが、端から見ていたぼくには、これまでのシリーズにひと区切りつけるんだという決意が伝わってきた。
その翌年から始まるのが、現在につながる「森」のシリーズだ。角材の底部をそのまま残し、上部をチェーンソーで無数の切り込みを入れていくもので、それまで抑えていた表現主義的なイメージが立ち現われてきた。そのイメージを戸谷は森に覆われた山に喩えている。山の輪郭は遠くから見れば森の樹冠によってかたちづくられるが、いざ山に入ると地面から樹冠までに大きな空間がある。山に限らず、たとえば肌にもシワがあるように、ものの表面には幅がある。彫刻は立体だが、表面を彫り刻むことで成り立つし、鑑賞者も削られた表面しか見ない。だからチェーンソーで削って凹凸をつけることで表面の幅が表わせるのではないかと。
それからは、石膏を用いた「地下の部屋」シリーズ(1984)を例外として、チェーンソーを使った彫刻のヴァリエーションをさまざま生み出していく。厚めの板に溝を彫って象の肌のようにしたり、反対側まで突き抜けるほど深く切り込みを入れた角材を並べたり、それを小屋のように組み立てて内部に入れるようにしたり、削るときに出たかけらを集めて壁や床に並べたり……。その刺々しく毛羽立つ表面は森のようでも、象の肌のようでも、ゴジラの背中のようでも、水の流れのようでもある。ちょうど無数のイボイボを見たときゾッとするように、あるいはフラクタル図形を見たとき吸い込まれるように、それらは見る者の心をザワつかせる。
出品はドローイングや記録映像なども含めて計40点。学生時代の人体彫刻に始まり、彫刻の原理を問い直した《POMPEII‥79 Part1》(1974/87)を経て、「〈彫る〉から」「〈構成〉から」の連作と続くが、この2シリーズは拍子抜けするほど数が少ない。ていうか、「〈構成〉から」シリーズの《レリーフ》(1982)1点のみ。ぼくにとっては戸谷の原点ともいうべきシリーズだが、実験的な意味合いの強い過渡的作品なので残していないのだろう。
ここまでで11点、彫刻だけだと5点のみ。以後は「森」シリーズ以降の作品に占められている。角材を象の肌のように削って並べた《森の象の窯の死》(1989)、角材の内部をくり抜いて裏側に開いた弾痕のような穴を見せる《地霊Ⅲ-a》(1991)、内面に切り込みを入れた墓室を思わせる小屋状の《《境界》からⅢ》(1995-96)、地下1階のセンター・ホールに置いて内部の凹凸を上から見られるようにした《洞穴体Ⅴ》(2011)など、大作を中心とした展示。出口で「もう終わり?」と思ってしまうほど会場が狭く感じられたのは、1点1点の作品の存在感が大きかったせいか。見終わってこんなに充実した気分になった展覧会は久しぶりだ。
公式サイト:https://pref.spec.ed.jp/momas/2022toya-shigeo
2023/04/16(日)(村田真)
大阪の日本画

会期:2023/04/15~2023/06/11
東京ステーションギャラリー[東京都]
日本画壇といえばなんとなく東京と京都が有名で、大阪にもあったっけ? そういえば大阪中之島美術館の開館記念展で大阪の風俗・風景を描いた日本画を何点か見たなあ、戦前には珍しく女性画家も何人かいたような気がする、程度の知識しかなかった。そもそも東京から見れば京都も大阪もすぐ隣だから区別がつかないし、お互いに文化の違いを強調し合うのが滑稽に思えてしまう。それはともかく。
展覧会は人物画、風俗画、文人画など6章に分かれているが、おもしろかったのは北野恒富の人物画を中心とする第1章、大阪の風俗・催事を描いた第2章、新しい表現と女性画家の作品を集めた第6章あたり。会場に入るといきなり北野の作品が10点ほど続くので、あれ? 北野恒富の回顧展だったっけと勘違いしそうになる。その女性像は、中期・後期になると様式化されてつまらなくなるが、初期の《摘草》はリアリズムに徹していて妖艶。大阪らしさを感じるのは、第2章の菅盾彦の《浪速文人図》や《阪都四つ橋》(1946)、その弟子の生田花朝による《住吉大社御田植》《浪速天神祭》など、近代化により消えゆく大阪庶民の古きよき生活文化を描いた「浪速風俗画」。これらは歴史的にも資料的にも価値があるが、そのローカリティゆえに大阪以外ではほとんど知られることがなかったようだ。
興味深い作品が固まっているのは最終章の「新しい表現の探究と女性画家の飛躍」だ。まず目が止まったのは、上島鳳山の《緑陰美人遊興之図》(1909)。古代風の女性がブランコ遊びに興じる、ある意味ロココ風のチグハグな主題で、色白の肌に怪しい流し目が妙にリアルで困っちゃう。第3回文展に落選したというが、審査員も困っちゃっただろう。同じ作者による神武天皇を描いた《皇祖尊影》は撮影禁止。禁止されているのはこの作品だけなので、主題ゆえか、それとも所有者(個人)の意向か。
日本画では珍しく空間表現で目を引く作品もあった。山口草平の《人形の楽屋》と幸松春浦の《魚游》だ。《人形の楽屋》は文字どおり文楽人形が置かれた楽屋を描いた屏風絵だが、右隻には上り階段、左隻には下り階段が配され、しかも2曲一双のため現実に折り曲げて展示されているので、まるでエッシャーの位相空間を思わせる。そのうえ色彩はほとんどモノクロームで全体に薄暗く、人形は衣裳をつけたまま吊るされているため、首吊り現場のような不気味さが漂う。《魚游》のほうは、石の川底の上を数匹の小魚が弧を描くように泳ぐ姿をほぼ真上から捉えた作品。日本画に描かれる魚はたいてい陸に上がって横から見た姿か、せいぜい池を泳ぐ鯉の姿くらいで、このように深度がわかるくらい川底まで透視した日本画は珍しい。よっぽど魚を見るのが好きなんだろう。
最後に紹介されるのが島成園や木谷千種ら女性画家たち。大阪では江戸時代から女性画家が活躍し、また富裕層は子女に絵を学ばせる習慣があったため多くの女性画家を輩出したのだという。ただそれでもモチーフは女性と子供に限られ、男性が描かれているのは唯一、木谷の《浄瑠璃船》の登場人物8人中2人だけ。なんでも自由に描ける時代ではなかったのだろう。ちなみに今年は「女性画家たちの大阪」展も開かれるので、そちらにまとめて出されるはず。
ところで、日本画は油絵に比べて画材が脆弱なので、展示するにも油絵より制約が多くなる。今回は作品保護のため出品作品の半数くらいは陳列ケースに入れてあるので、ガラス越しに見なければならなかった。最近は油絵も大半が額縁にガラスが嵌め込まれているが、ガラスや照明の精度が上がったためほとんど気にならない。しかし日本画の場合、掛け軸や屏風などはガラスケースに入れなければならず、どうしても作品との距離が遠くなってしまうのだ。もうひとつの制約は、作品の入れ替え制。日本画や古美術の場合、長時間光に晒すのを避けるため、展覧会を前期と後期に分けて作品を入れ替えることが多い。今回は総点数155点にも及ぶが、内覧会で見られたのは半分強の88点だけなので、すべての作品を見るには2回行かなければならないのだ。もちろん入館料は2回払わなければならず、せめて前期を見た人は後期を半額にしてもらいたい。
公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202304_oosaka.html
2023/04/14(金)(村田真)
フローラとファウナ 動植物誌の東西交流
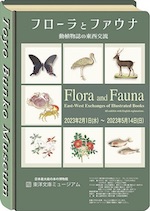
会期:2023/02/01~2023/05/14
東洋文庫ミュージアム[東京都]
初めて訪れる東洋文庫。西洋の古書と違って東洋の古書にはそれほど惹かれないが、同ミュージアムで東西の動植物図譜を展示していると聞いて行ってみた。エントランスから2階へ上ると、三方の本棚を埋め尽くす数万冊のモリソン文庫が現われる。これは1917年にオーストラリア人のモリソン博士からまとめて購入した書籍という。中身は東アジアに関するものだが、西洋で出版された本なので形式は洋書。革装の背表紙に浮き上がる背バンドの凹凸がたまらない。企画展はその奥の部屋から始まる。
「フローラとファウナ」は、長崎のオランダ商館に勤めながら、日本の動植物図譜を出版したドイツ人の医師シーボルトの来日200年を記念するもの。ちなみにフローラとは植物相、ファウナとは動物相を意味する。いま町田市立国際版画美術館でも西洋の博物図譜を集めた「自然という書物 15~19世紀のナチュラルヒストリー&アート」展が開かれているが、東洋文庫では西洋だけでなく東洋の動植物図譜も含めて紹介し、相互の交流をたどろうという企画だ。
東洋には、自然界のあらゆるものを集めて分類・研究しようという「博物学」はなく、主に薬になる植物などの研究とその利用方法、効能に関する学問「本草学」が中国で生まれ、日本にも伝わってきた。東洋のほうが実用的だったのだ。古いものでは、1~2世紀ごろ成立したとされる中国最古の薬草学書『神農本草経』や、中国の本草書に載っていた薬の名を10世紀に醍醐天皇が和訳させた『本草和名』など、古代・中世に書かれた原著を江戸時代に復元・出版した古書がある。これらは文字情報(漢文)だけで図版がないのが残念。それを補うつもりなのか、各キャプションの上に「健康への飽くなき探求心」とか「千年前の動植物の呼び名がわかります」といった軽いキャッチコピーが踊っている。確かにわかりやすいが、余計なお世話という気がしないでもない。
図版のあるものでは、日本の博物学を代表する本草学者の貝原益軒『大和本草』(1709-1715)から、薬品会(物産会)の出品物をまとめた平賀国倫(源内)編『物類品隲』(1763)、ワニやモルモットなど外国の動物をカラーで描いた『異魚奇獣譜』(江戸時代)、精密な植物図鑑の草分けである牧野富太郎『日本植物志図篇』(1888-1891)まである。でもやはり(牧野の本は別にして)描写の精密さ、質感のリアルさ、色彩の美しさでは西洋の博物誌にはかなわない。
洋書で圧倒的に多いのは、西洋人が著した東洋の動植物図譜。その中心になるのが、来日200年のフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトによる『日本動物誌』(1833-50)と、『日本植物誌』(1835-1870)だ。町田でも展示されていたこの2冊は、日本の生物相を西洋に知らしめる役割を果たした。ほかに、シーボルト以前に長崎に来たエンゲルベルト・ケンペル『廻国奇観』(1712)、分類学の父ともいわれるカール・フォン・リンネ『セイロン植物誌』(1748)など、著者の名前は知ってるけど初めて見る書物も少なくない。美しいものでは、鳥類学者にして剥製師のジョン・グールド『アジアの鳥』(1850-1883)、極東まで来て昆虫採集したジョン・ヘンリー・リーチ『中国・日本・朝鮮の蝶類』(1892-1894)などもある。後者のキャッチコピーは「チョウきれい !!」。ダジャレかい。

チョウきれい !![筆者撮影]
公式サイト:http://www.toyo-bunko.or.jp/museum/floraandfauna-detail.pdf
関連レビュー
自然という書物 15~19世紀のナチュラルヒストリー&アート|村田真:artscapeレビュー(2023年04月01日号)
2023/03/31(金)(村田真)
VOCA展2023 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─

会期:2023/03/16~2023/03/30
上野の森美術館[東京都]
1994年に始まったVOCA展が今年30回目を迎えるのを記念して、『VOCA 30 YEARS STORY 30周年記念記録1994-2023』を出した。これを見ると、第1回には大竹伸朗、岡﨑乾二郎、福田美蘭、村上隆、吉澤美香といった錚々たる画家たちが名を連ねていたことがわかる。でもこのなかで受賞したのはVOCA賞の福田だけ(受賞者は計5人)だと知ると、審査員の目は節穴だったのかと思いたくもなるが、そうではなく、おそらく彼らの作品に対する評価がまだ定まっていなかったのだ。まさに隔世の感あり。
VOCA展は、推薦委員によって選ばれた40歳以下の美術家による平面作品という「縛り」があるため、作品傾向が大きく変わったりバラツキが出たりすることはない。それでも初期のころの絵画中心の展示から次第に写真が増え、厚さ20センチ以内の半立体やインスタレーションが登場し、液晶ディスプレイの普及により映像作品も珍しくなくなってきた。絵画が中心であることに変わりはないが、時代を反映して少しずつ変化が見られるのも事実。新しい世代の絵画の動向を観察できるだけでなく、「平面」の枠内でどれだけ冒険しているかを見る楽しみもあるのだ。
今回目についたのは、布地に桃太郎の物語の1シーンを糸で抽象的に縫いつけて棒から吊るした金藤みなみ《桃太郎の母》、9組の兄弟姉妹のそれぞれの服を重ねて縫い合わせた黒山真央《SIBLINGS》(VOCA佳作賞)、日本各地を歩くなかから生み出された陶板、ドローイング、テキストを壁に配置したエレナ・トゥタッチコワ《手のひらの距離とポケットの土》(VOCA奨励賞)、黒い箱に7つのステンドグラスをはめ込み裏から光を当てた中村愛子《Loin de…》、石膏を塗った合板を削って波が押し寄せる海岸のような風景を現出させた七搦綾乃《Paradise Ⅳ》(VOCA奨励賞+大原美術館賞)など、絵画から外れた表現。挙げてみて気づいたが、全員が女性だ。出品者の男女比はほぼ半々なので、女性のほうが「絵画」とか「写真」といった形式にはまらない傾向が強いのかもしれない。
男性で変わり種をひとつ挙げれば、都築崇広の《OSB・森・風》だ。木材の破片を固めたOSB合板を支持体に、植物イメージをコラージュして森を表わした作品。それだけでは珍しくもないが、彼は同時期に開かれている「岡本太郎現代芸術賞展」にも入選していて、そちらには合板に都市の風景を焼きつけた《構造用合板都市図》を出しているのだ。絵画中心のVOCA展と、ドハデなインスタレーションが売りの岡本太郎現代芸術賞展という、二つのコンペをまたいで対照的な作品を出品し、両者でひとつの世界観を示そうとしたってわけ。特にVOCA展は公募ではなく推薦制だから、狙ってできるものではない。これは見事。
公式サイト:https://www.ueno-mori.org/exhibitions/voca/2023/
2023/03/30(木)(村田真)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)