artscapeレビュー
五十嵐太郎のレビュー/プレビュー
金峯神社、沢田マンション
高知で2つのセルフビルド建築を訪れた。ひとつは高知工科大学で教鞭をとる建築家の渡辺菊眞さんの分割造替・金峯神社、もうひとつは有名な沢田マンションである。
前者は地方の過疎化と高齢化する山間地において長い間、補修する費用がなく、ほとんど崩れかけていた神社を復活させるプロジェクトだ。興味深いのは、「分割造替」と命名したように、その際、拝殿と本殿に分割し、前者を地域住民が集まりやすい低い場所に移動させ、おかげで途絶えていた祭りが再開されたことである。一方、後者は江戸時代にさかのぼる小さい本殿だけを残し、老朽化していた覆屋は解体し、もとの敷地の隣に再建した。
そして驚くべきなのは、いずれも単管やポリカーボネートなどを用いた超ローコストのセルフビルドであること。したがって、見たことがない造形であり、簡素なデザインだ。一般的に寺院は建築家による新しいデザインが登場しやすいが、保守的な神社ではそれが難しい。だがここは、厳しい状況ゆえにラディカルな新しい神社モデルが成立した。もっとも、日本各地の限界集落の神社では、おそらく似たような状況を迎えているはずである。

金峯神社の拝殿

金峯神社の本殿に続く、壊れた鳥居と階段

金峯神社の本殿
念願の沢田マンションは、大きなショッピングセンターの近くにたつ。これは1971年から夫婦がセルフビルドで建設した5階建て集合住宅である(本来はもっと高い階数をめざしていたらしいが)。よくここまで許されたと思う凄まじいプロジェクトであり、世知辛くなってしまった現代日本ではもうできないだろう。
興味深いのは、シュヴァルの理想宮のように、この手の建築は装飾的になりがちだが、沢田マンションはそれがなく(住人が後から加えたと思われる装飾はあるが)、基本的にはコンクリートのヴォリュームが強調されたモダニズム系の造形だ。もっとも、合理的なプランというよりも、コンクリートの迷宮のような空間体験を味わう。また広い通路(植栽などが置かれ、コミュニティ・スペースになっている)、両サイドを貫通するヴォイド、多様な間取りなど、いかにも現代の建築家がやりそうなデザインも散見されて興味深い。

沢田マンションの外観

沢田マンションのスロープと階段

沢田マンションの通路

沢田マンションの屋上庭園
2019/10/30(水)(五十嵐太郎)
ART PROJECT KOBE 2019: TRANS-、「タトアーキテクツ」展
兵庫県神戸市、新開地地区、兵庫港地区、新長田地区(TRANS-)
ギャラリー島田(タトアーキテクツ展)[兵庫県]
アートプロジェクト神戸2019のTRANS-は、これまでのジャンル混淆+非現代アート的な神戸ビエンナーレの祝祭とはまったく違う、むしろ岡山芸術交流に近い尖った企画だった。ディレクターは林寿美である。思い切ったのは、参加アーティストをわずか2名に絞っていること。もっともそのうちのひとり、神戸出身でもあるやなぎみわは3日間のパフォーミング・アーツの参加だから、実質的にはグレゴール・シュナイダーの個展を街に散りばめながら開催したというべきだろう。
彼の作品《美術館の終焉―12の道行き》はいずれも建築的であり、TRANS-のテーマにふさわしく、神戸の街の日常の隣に異世界を忍び込ませている。作品を順番にたどる旅を通じて、知らなかった神戸の顔に触れていく。遠隔地の空間におけるふるまいが同期する作品。旧研究所の廃墟の真っ白な空間。地下街で反復される同じ浴室。ツアーで訪れる2つの私邸の個室で展開されるアートやパフォーマンス。かつて労働者の宿泊所だった施設の室内が真っ黒に塗られ、暗闇で小さなライトを持ってさまよう体験。地下道のドアの向こうに出現する収容キャンプの個室群。そして拡張現実によって見える古い市場をさまようデジタル世界の高齢者たち。

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。廃墟となった旧研究所の内部は真っ白な空間にされている

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。廃墟となった旧研究所の中

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。かつて労働者の宿泊所だった施設。室内は真っ黒に塗られていた

グレゴール・シュナイダー《12の道行き》より。拡張現実で見ることができる、デジタル世界の古い市場をさまよう高齢者たち
また、このTRANS-のタイミングにあわせて企画された島田陽「タトアーキテクツ」展(ギャラリー島田)も訪れた。実は島田は、今回のTRANS-の建築的な側面をバックアップした建築家でもある。さて、同展の1階は家型を中心にひたすら模型を並べる、いわゆる建築展の体裁だったが、一方で地階は偏光フィルムによる空間インスタレーションを展開していた。島田による偏光フィルムの作品は、神戸ビエンナーレ2011の元町高架下アートプロジェクトでも見ていたが、今回は特に吊るされた 2枚のフィルムで構成されるモノリスのような虚のヴォリューム群が、鑑賞者が移動する視差によって、驚くほど多様に色彩と表情を変えてゆく。個人的にはミース・ファン・デル・ローエのバルセロナ・パヴィリオンで体験した、めくるめくガラスのリフレクト現象を想起させた。あのとき自分はそれを幽霊のような建築だと思ったのだが、今回の展示室に構築された虚のヴォリューム群も、偏光フィルムによってそれに近い効果を生みだしていた。

島田陽「タトアーキテクツ」展より。家型を中心にした模型群の展示風景

島田陽「タトアーキテクツ」展より。偏光フィルムによる空間インスタレーション
公式サイト:
ART PROJECT KOBE 2019: TRANS- http://trans-kobe.jp/
タトアーキテクツ展 http://gallery-shimada.com/?p=6443
2019/10/22(火)(五十嵐太郎)
「Under 35 Architects exhibition」展覧会とシンポジウム

会期:2019/10/18~2019/10/28
うめきたSHIPホール[大阪府]
大阪における秋の恒例となったU35(「Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会2019」)の展覧会とシンポジウムに今年も参加した。昨年のゴールド・メダルに選ばれた中川エリカはシード枠を使わず、不参加となったが、セレクションに公募だけでなく、推薦制度を導入したこともあり、いつもより個性的な若手建築家が揃った。それぞれの出展者を紹介しよう。
今年のゴールド・メダルに選ばれた秋吉浩気のプロジェクトは、デジタル・ファブリケーションの時代において、ハウスメーカーとは違う、新しい建築生産を視野に入れたもの。かつてFOBが挑戦した試みの現代ヴァージョンのようにも感じた。

秋吉浩気の出展作
伊藤維の作品は、フォルマリズム的な手法をベースとしているが、コンテクストを読みながら、それを崩していく住宅である。展示に用いた模型のための什器は家具としてリサイクルされるのも興味深い。

伊藤維の出展作
パーシモン・ヒルズ・アーキテクツ(柿木佑介+廣岡周平)は、埼玉の観音堂において片方の側面を開くデザインを試みた。なるほど、これは空間が奥に向かって展開する宗教建築において、新しい手法である。

パーシモン・ヒルズ・アーキテクツの出展作
佐藤研吾は、インドや福島でワークショップを展開しつつ、モノの工作のレベルから建築を捉えなおそうと企てる。その方向性は、全体性や構成に向かうよりも、スカルパ的なリノベーションに相性がいいのではないかと思われた。

佐藤研吾の出展作
高田一正+八木祐理子は、コペンハーゲンの運河の水上に建築的なパヴィリオンを浮かせるプロジェクトを展開している。来年、世界運河会議が名古屋で開催されるので、日本の場合、類似した試みはどこまで可能なのかに興味をもった。

高田一正+八木祐理子の出展作
津川恵理は、公共空間の実験や神戸のコンペの最優秀賞案などに対し、新しいノーテーションを構想している。おそらく、これが設計にどのようなフィードバックをもたらし得るかが今後の鍵だろう。

津川恵理の出展作
百枝優は、Agri Chapelから続く、樹木状の天井の架構によって、葬祭場でも空間の特性を獲得している。この手法を冠婚葬祭以外のプロジェクトで採用する場合、どのような展開になるかが期待される。

百枝優の出展作
なお、今年のゴールド・メダルの討議では、完全には説明しきれない謎や魅力を残す試みの伸びしろが注目され(しばしば審査の場面で起こることだが)、明快に設計されたことで限界もわかってしまう実作組が割りをくらう展開だった。
Under 35 Architects exhibition 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会2019 公式サイト: http://u35.aaf.ac/
2019/10/19(土)(五十嵐太郎)
岡山芸術交流2019 IF THE SNAKE もし蛇が

会期:2019/09/27~2019/11/24
旧内山下小学校、岡山県天神山文化プラザ、岡山市立オリエント美術館、岡山城、林原美術館ほか[岡山県]
岡山芸術交流2019は、岡山城などの会場が増えたとはいえ、前回と同様それほど広域に作品が点在せず、コンパクトなエリアに集中しているために、半日もあれば十分にまわることができるのがありがたい。また、日本の作家がほとんどいないため、ドメスティックな感じがせず、ヨーロッパの国際展を訪れているような雰囲気を維持しており、よい意味で日本の芸術祭っぽくない。そして今回はピエール・ユイグがディレクターなだけに、全体的に作品も暗く、変態的である。
しかもメインの会場となった都心の旧内山下小学校は、朝イチで足を踏み入れたにもかかわらず、ファビアン・ジロー&ラファエル・シボーニによって、かつての教室群が不気味な空間に変容しているほか、マシュー・バーニーらの奇妙な実験があり、もしも日が暮れる時間帯だったとすると、相当怖い体験になるのではないかと想像した。体育館の巨大な空間を用いたタレク・アトウィによるさまざまなサウンド・インスタレーションも印象的である。

ファビアン・ジロー&ラファエル・シボーニ《非ずの形式(幼年期)、無人、シーズン3》

マシュー・バーニー&ピエール・ユイグ《タイトル未定》

タレク・アトウィ《ワイルドなシンセ》展示風景
屋外では、パメラ・ローゼンクランツの作品《皮膜のプール》やティノ・セーガルによる運動場の盛り土があまりにも不穏だった。越後妻有アートトリエンナーレでも、いろいろな小学校がアートの展示に用いられていたが、岡山芸術交流2019のような暗さやわかりにくさは抱えていない。

パメラ・ローゼンクランツ《皮膜のプール(オロモム)》

ティノ・セーガルによる運動場の盛り土
前川國男が設計した林原美術館には、ユイグによる少女アニメの映像の横からリアルな少女がとび出してパフォーマンスを行なう作品があるのだが、朝早かったので、あやうくひとりで鑑賞しそうになった。人が少ないと緊張する作品である。また、シネマ・クレールで上映されたジロー&シボーニの作品にはまったく言葉がなく、ひたすら奇怪なイメージが続く。
また今回は岡山市立オリエント美術館も会場に加わり、常設展示のエリアに3点の現代アートがまぎれ込む。そのおかげで岡田新一がデザインした空間を再び体験することになったが、目新しさはないものの、逆に現代の建築には失われた重厚さが心地よい。なお、岡山芸術交流では建築系のプロジェクトがしており、先行して完成していた青木淳に加えて、マウントフジアーキテクツスタジオと長谷川豪がそれぞれ海外のアーティストとコラボレートした宿泊棟が誕生したことも特筆できる。

青木淳+フィリップ・パレーノのコラボレートによる宿泊施設「A&A TUBE」
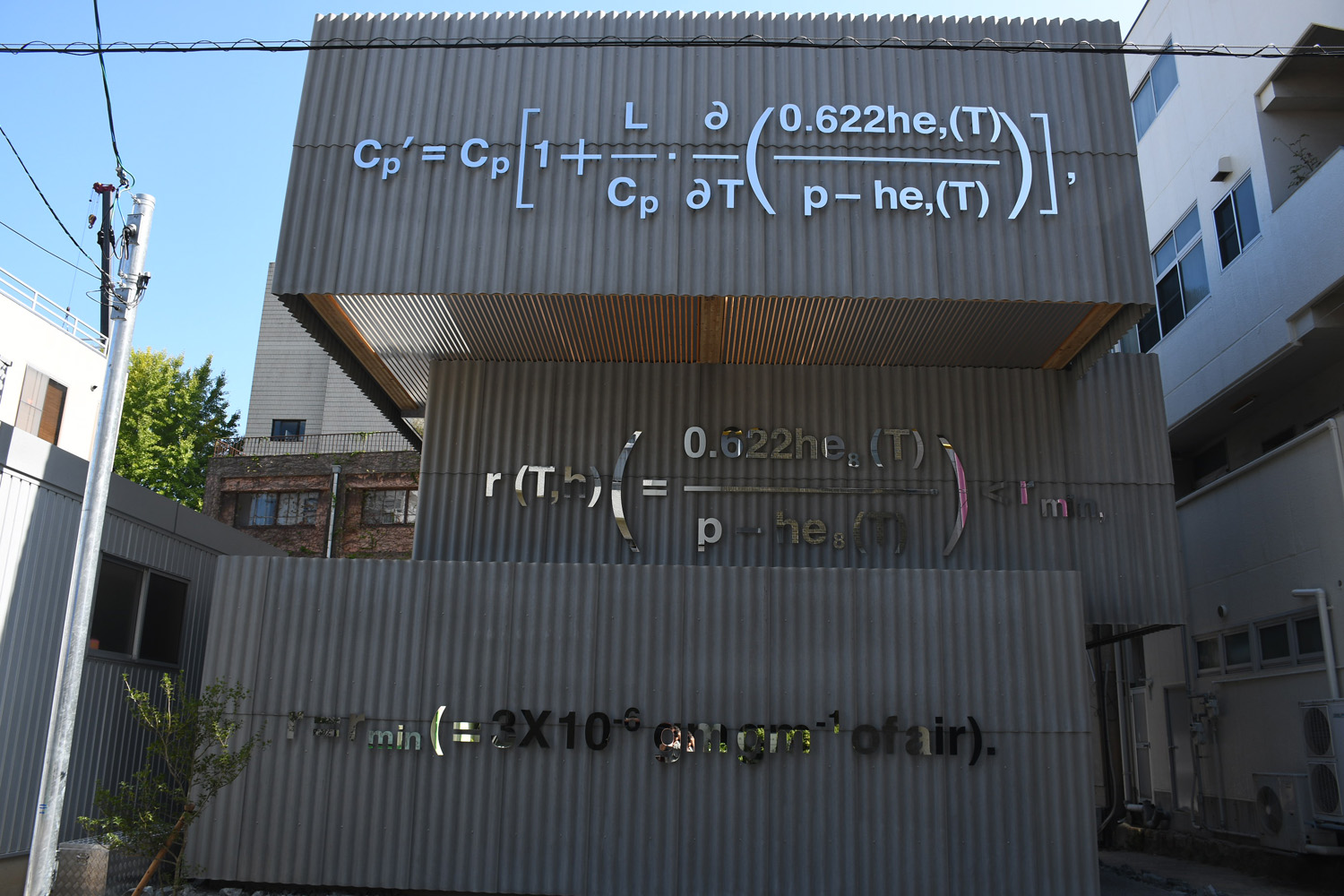
マウントフジアーキテクツスタジオ+リアム・ギリックのコラボレーションによる宿泊施設「リアムフジ」
岡山芸術交流2019 公式サイト:岡山芸術交流2019
2019/10/14(月)(五十嵐太郎)
あいちトリエンナーレ2019 情の時代(6回目)

会期:2019/08/01~2019/10/14
愛知県芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市芸術創造センター[愛知県]
6回目のあいちトリエンナーレ2019である。名古屋市美術館では、復活したモニカ・メイヤーの《The Clothesline》の展示も、開幕当時に比べると、ものすごい書き込みの量が増え、迫力を増していた。そして長かった展示閉鎖時の状況も一部残されていた。
また映画『ジョーカー』を観た後で、愛知県芸術文化センターにおけるウーゴ・ロンディーネの《孤独のボキャブラリー》を再訪すると、なんだか怖い。ともあれ、いったん閉鎖された作品の再開をすベて確認することができた。一方で閉鎖時に寄せられた来場者のメッセージも残されている。最後の訪問は情報系の作品を中心にじっくり見てまわったが、改めて今回のあいちトリエンナーレ2019は同時代的なコンセプトに沿った作品が粒ぞろいだったと思う。なお愛知県芸術文化センターの周辺では、街宣車が「河村市長の言うとおり!」と絶賛していた。彼の言動がそうした状況を導いたわけだが、右翼に擁護される市長というのは驚きである。

モニカ・メイヤー《The Clothesline》展示風景。展示再開を告知する用紙も吊り下げられていた

モニカ・メイヤー《The Clothesline》より。展示閉鎖時の状況も一部残されていた
まとめてパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞した。劇団アルテミスの『ものがたりのものがたり』(名古屋市芸術創造センター)は、先住民、抽象的なオブジェ、ファミリー、劇場にやってくる「ものがたり」という4つのばらばらのレイヤーが同時進行しつつ、観客も安心して鑑賞できないような物語を解体する演劇だった。トランプ/ビヨンセ/ロナウドによる家族(!)の巨大な肖像がそれぞれ動き、唾を吐き、逆立ちする演出は、バカバカしさとともに鮮烈な印象を残した。
続いて参加した、ドミニク・チェンのレクチャー・パフォーマンス『共在言語をつくるために』(愛知県芸術文化センター)は、膨大なスライドを用意され、気合いの入ったプレゼンテーションだった。彼の個人史に重ねつつ、メディア・アート、ドゥルーズ、ベイトソン、マクルーハンと、ガチの講義スタイルで語っていた。そして初めて観た市原佐都子の作品『バッコスの信女─ホルスタインの雌』(愛知県芸術文化センター)は冒頭からフルスロットルで飛ばしていた。とある住宅のリビングで主婦が性/生をあからさまに語った後、同性愛、牛の人工授精、異種交配のテーマが同じリビングでめくるめく展開し、「種」も「性」も「家族」も解体されていく。またミュージカルのごとく、途中でさまざまなタイプの歌をはさみ込む。女性のみの役者陣の、振り切った演技にも刮目した。
観劇が遅くまでかかり、高山明/Port B『パブリックスピーチ・プロジェクト』のライヴ・パーティは、後からニコ生で視聴することになった。当初の予定だったアジアの複数の都市を中継する企画は実現できなかったが、それだけ今回のトリエンナーレの激動に巻き込まれ、代わりの抵抗の方法として、コールセンターの立ち上げに高山の時間が割かれたと察する。それでも、3名のラッパーによるアジアの解釈に、音楽と詞の可能性を十分に感じることができた。
あいちトリエンナーレ2019 情の時代 公式サイト:https://aichitriennale.jp/
2019/10/13(日)(五十嵐太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)