artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
野口里佳「海底」

会期:2017/09/09~2017/10/07
タカ・イシイギャラリー 東京[東京都]
昨年、12年間在住したベルリンから、沖縄に移って制作活動を再開した野口里佳の新作展である。水中で撮影された「海底」のシリーズを見て、野口が1996年に第5回写真新世紀展でグランプリを受賞した「潜ル人」を思い出した。潜水夫をテーマとするこの作品で、彼女は重力のくびきから離れた「異世界」の光景を出現させたのだが、その初心が今回のシリーズにもずっと継続していることが興味深い。野口にとって、写真とは現実世界のあり方を変換させる装置であり続けてきたということだ。太陽の届かない「海底」をライトで照らしながら作業するダイバーの姿は、あたかも宇宙人のようであり、その変換の振幅は相当大きなものになっていた。
ところが、同じ会場に展示されていた2枚組の「Cucumber」や「Mallorca」では、その変換の幅はかなり小さい。「Cucumber」では「21 August 2017」と「22 August 2017」、つまり1日のあいだに伸びたキュウリの蔓を撮影しており、「Mallorca」では海面の微妙な光の変化を捉えている。それでも、2枚の写真のわずかな違いに、野口が奇跡的な「不思議な力」を見出していることがはっきりと伝わってくる。宇宙大の遥かな距離から、日常の微妙な差異まで、彼女の写真の世界は、マクロコスモスとミクロコスモスのあいだを往還する自由さを手に入れつつある。沖縄での次の成果がとても楽しみだ。
Noguchi Rika“At the Bottom of the Sea #3”, 2017 C-print 90 x 135 cm
© Noguchi Rika
2017/09/21(木)(飯沢耕太郎)
黑田菜月「わたしの腕を掴む人」

会期:2017/09/20~2017/09/26
銀座ニコンサロン[東京都]
黑田菜月は1988年、神奈川県生まれ。2001年に中央大学総合政策部を卒業後、写真家としての活動を開始し、2012年に第8回写真「1_WALL」展でグランプリを受賞した。そのころの彼女の写真は、自分の周囲に潜む「けはい」を繊細な感覚でキャッチした、センスのいい日常スナップだったが、まだひ弱さも感じさせた。だが、その後順調にキャリアを伸ばし、確信を持って自分のスタイルを打ち出していくことができるようになってきている。
今回の「わたしの腕を掴む人」は、中国の北京と上海で老人施設を取材した写真群をまとめたものだ。大きく引き伸ばされた老人たちのポートレートが中心だが、室内の情景、庭などの写真もある。認知症を含む老いの進行を注意深く観察し、撮影しているのだが、それをこれ見よがしに露呈していくような姿勢は注意深く回避され、全体的に受容的な眼差しが貫かれている。注目すべきなのは、むしろ写真と写真の間に置かれたテキストだろう。そこに記された内容も、直接的に彼らの状況を指し示すものではない。電車の中で何度も「富士山が見える」と話しかけてくる老女、「船が迎えに来た」と言って息を引き取った老人、日本に来て介護を学んでいる中国人との対話などが、淡々と綴られている。それらの言葉と写真との間合いが絶妙であり、観客を自問自答に誘うようにしっかりと組み上げられていた。
妄想と現実とのあいだを行き来するような構造を、写真とテキストでどのようにつくり上げていくかは、今後も 黑田の大きな課題になっていくのではないだろうか。次作も大いに期待できそうだ。なお、本展は10月19日~10月25日に大阪ニコンサロンに巡回する。
2017/09/21(木)(飯沢耕太郎)
野村佐紀子「愛について あてのない旅 佇む光」

会期:2017/09/09~2017/10/22
九州産業大学美術館[福岡県]
九州産業大学美術館が企画する「卒業生─プロの世界」の第7回目として、野村佐紀子の個展が開催された。1967年、山口県下関市出身の野村は、1990年に九州産業大学芸術学部写真学科卒業後、荒木経惟に師事し、1993年ごろから写真家としての個人活動を開始する。1994年に最初の写真集『裸の部屋』を自費出版で刊行。以後20冊近い写真集を出版し、数々の展覧会を開催してきた。本展では、その野村の20年以上にわたる写真家としての軌跡を、約170点の作品で辿っている。
展示は3部構成だが、第2部の「あてのない旅」は8点のみの「間奏曲」とでもいうべきパートであり、その大部分は第1部の「愛について」と第3部の「佇む光」で占められている。基本的には既刊の写真集の流れに沿って過去の作品を見せる「愛について」と、「2013年以降の新作」を展示した「佇む光」ということになるが、作風的にそれほど大きな違いがあるようには見えない。闇の粒子を身に纏ったような男性の裸体写真を中心に、ごく近い距離感で撮られた室内の光景が配置されている。カメラが外に出る時にも、視覚よりも触感を強く感じさせる被写体の捉え方は共通している。近年はモノクロームだけでなく、カラー写真も多くなってきたが、それでも画面の質感にほとんど変わりがない。老人施設で撮影された異色のポートレートのシリーズ『TAMANO』(リブロアルテ、2014)や、珍しく女性のイメージを中心に構成された『Ango』(bookshop M、2017)などが外されているということもあるが、どちらかといえば野村の作品世界の均質性、一貫性が強調されていた。それほど大きな会場ではないので、その狙いは的を射ている。だが、次はもう少し大きな会場で、より広がりのある構成の展示を見てみたいとも思った。
2017/09/16(土)(飯沢耕太郎)
松本美枝子「ここがどこだか、知っている。」
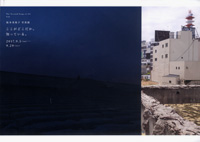
会期:2017/09/05~2017/09/29
ガーディアン・ガーデン[東京都]
松本美枝子は1974年、茨城県生まれ。1998年に実践女子大学文学部卒業後、写真家として活動し始める。写真集『生あたたかい言葉で』(新風舎、2005)、谷川俊太郎との共著『生きる』(ナナロク社、2008)など、日常を細やかに観察しつつ、思いがけない角度から描き出していくスタイルを確立していった。
今回のガーディアン・ガーデンでの個展でも、いかにも松本らしい思考と実践とを一体化した写真の展示を見ることができた。日付け入りの家族写真を再提示した「手のひらからこぼれる砂のように」(2017)、「古生代ゴンドワナ超大陸の海底あるいは高鈴山」、「震災による地盤沈下で消滅した砂浜あるいは河原子海水浴場」の2部から成る「海は移動する」(2017)、東海JCOの臨界事故をテーマにした「想起する」(2017)、日々のスナップ写真をアトランダムに上映する「このやり方なら、知っている。/ここがどこだか、知っている。」(2011~2016)、鳥取藝住祭で滞在制作した「船と船の間を歩く」(2014)、2面マルチのスライドショー「考えながら歩く」(2017)といった作品群は、一見バラバラだが、「時間と、それが流れる場所と、その中に生じる事象について、できるだけ考え続け観察する」という松本の一貫した姿勢を感じられるものになっていた。
特に興味深かったのは、会場の3分の1ほどのスペースを使ったスライドショー、「考えながら歩く」で、天気予報や歌などの日常の音と映像とが少しずつズレたりシンクロしたりしながら進行することで、観客の意識に揺さぶりをかけるつくりになっていた。われわれが「絶えず揺れ動く世界の際」にいることが、一見穏やかだが、微妙な裂け目を孕んだ映像の集積によって提示されている。展示を見ながら、そろそろ次の写真集もまとめてほしいと強く思った。
2017/09/13(水)(飯沢耕太郎)
平敷兼七「沖縄、愛しき人よ、時よ」

会期:2017/09/04~2017/10/29
写大ギャラリー[東京都]
平敷兼七(へしき・けんしち)は1948年、沖縄県今帰仁村運天の生まれ。沖縄工業高校デザイン科卒業後、1967年に上京して東京写真大学(現・東京工芸大学)に入学するが、2年で中退する。東京綜合写真専門学校に入り直して、同校を72年に卒業している。その後、沖縄とそこに生きる人々を柔らかな温かみのある眼差しで撮り続けたが、その仕事がようやく評価されるようになるのは、亡くなる2年前、2008年に銀座ニコンサロンで個展「山羊の肺 沖縄1968─2005年」を開催し、第33回伊奈信男賞を受賞してからだった。だが、没後も展覧会や写真集の刊行が相次ぎ、あらためてその独自の作品世界に注目が集まっている。今回の写大ギャラリーの展覧会には、代表作の「山羊の肺」のシリーズから78点、ほかに沖縄出身者が入寮する東京都狛江市の南灯寮での日々をスナップした写真群から63点が展示されていた。
平敷の写真は一見、目の前にある被写体に何気なくカメラを向けた自然体のスナップショットに見える。だが、「山羊の肺」の「『職業婦人』たち」のパートにおさめられた写真の「前借金をいつ返せるか毎日計算する」、「客に灰皿をもって行く子ども」といったキャプションを読むと、彼が沖縄の現実と人々の生の条件を深く考察し、時には辛辣とさえ思える批評的な眼差しでシャッターを切っていることが見えてくる。亡くなる2日前の日記には「人生の結論は身近にあり、身近の人物達、身近の物達、それらを感じることができるかが問題なのだ」という記述があるという。あくまでも「身近」な被写体にこだわり続けながら、「感じる」ことを全身全霊で哲学的な省察にまで昇華させようとした写真家の軌跡を、もう一度きちんと辿り直してみたい。
2017/09/08(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)