artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
野村佐紀子「Ango」

会期:2017/08/15~2017/09/17
PETIC SCAPE[東京都]
町口覚が新たに編集・造本した『Sakiko Nomura: Ango』(bookshop M)は、1946年に発表された坂口安吾の短編小説『戦争と一人の女』に、野村佐紀子の写真をフィーチャーした“書物”(日本語版、英語版、ドイツ語版を刊行)である。まさに町口の渾身の力作と言うべき写真集で、そのグラフィック・デザインのセンスが隅々まで発揮されている。ページが少しずつずれるように製本されているので、写真そのものも台形にレイアウトされており、ページをめくっているとなんとも不安定な気分になるのだが、それはむろん計算済みだ。文字のレイアウトにも工夫が凝らされており、薄いグレーのインクで印刷されているのは「女は戦争が好きであった」など、GHQによる検閲で削除された部分だという。森山大道と組んだ『Terayama』や『Odasaku』などで練り上げてきた町口のデザイナーとしての力量が、全面開花しつつあることがよくわかった。
野村の写真、それにPETIC SCAPEの柿島貴志による会場構成も、それぞれの代表作と言いたくなるほどの出来栄えだった。野村の写真シリーズで、女性を中心的に描かれるのはかなり珍しいことだが、今回は戦時下をしたたかに、「肉慾も食慾も同じような状態」で体を張って生き抜いていく「一人の女」を取り上げた安吾の小説にふさわしい内容になっている。デスパレートな雰囲気を漂わせる風景写真との組み合わせもうまくいっていた。柿島の会場構成は、写真集の台形のレイアウトを活かしてフレーミングしたゼラチンシルバープリントと、文字を配した大きめのインクジェットプリントを巧みに組み合わせ、観客を作品の世界へと引き込んでいく。町口も野村も柿島もむろん戦後生まれだが、それぞれの「戦争」に対する身構え方がきちんと打ち出されていて、気持ちのいい作品に仕上がっていた。
2017/08/18(金)(飯沢耕太郎)
兼子裕代「APPEARANCE──歌う人」

会期:2017/08/09~2017/08/15
銀座ニコンサロン[東京都]
気持ちのよい波動が伝わってくるいい作品だった。兼子裕代は1963年、青森県生まれ。明治学院大学フランス文学科卒業後、2002年に渡米し、サンフランシスコ・アート・インスティテュートで写真を学んだ。現在はカリフォルニア州オークランドに在住している。
今回発表された「APPEARANCE──歌う人」は2010年から撮影が開始されたシリーズである。タイトルの通りに「歌う人」を近い距離から撮影している。撮影時間はほぼ20分。そのあいだに「目の前で刻々と変化する感情の発露」の様子を観察し、シャッターを切る。モデルは彼女が住むオークランドやサンフランシスコ近辺の老若男女で、彼らが歌っている曲の題名以外はそのバックグラウンドは明示されていない。にもかかわらず、一人一人の出自や、背負っているものが少しずつ見えてくるような気がするのは、「歌う」ことに集中することによって彼らが普段身につけている厚い殻を脱ぎ捨て、無防備になっているからだろう。展示のコメントに、兼子自身が「外国人として疎外と受容とを繰り返してきた私にとって、その道のりを体現するようなプロジェクト」になったと記しているが、それはモデルになっている一人一人にもいえると思う。
プロジェクトの内容自体も微妙に変化してきている。被写体が「子供から大人へ」、カメラのフォーマットが「正方形から長方形へ」になった。おそらくそれは、兼子の視野が以前より大きく広がってきたことのあらわれなのではないだろうか。もう少し続けていくと、さらなる展開が期待できそうだ。なお、本展は9月7日~13日に大阪ニコンサロンに巡回した。
2017/08/11(金)(飯沢耕太郎)
森山大道「Pretty Woman」

会期:2017/06/13~2017/09/17
このところの荒木経惟の大爆発も驚きだが、森山大道も負けてはいない。いまや「後期高齢者」になった彼らのエネルギーの高揚ぶりを見ていると、単なる世代論では割り切れない、特別の力が働いているようにも思えてくる。
森山は2000年代以降、写真集だけでなく展示にも力を注ぐようになってきているが、今回のAkio Nagasawa Galleryでのインスタレーションは、予想以上に大変なことになっていた。壁だけでなく、柱にもコラージュ状にプリントが貼り巡らされ、その上にフレーム入りの作品が掛けられている。カラーとモノクロームが混じり合った作品は、すべて「この一年」に撮影されたという新作であり、そこから「Pretty Woman」というテーマに沿って選択されたものだ。こうしてみると、森山にとってのWomanのイメージの許容範囲が相当に広いことに気がつく。文字通りの「Pretty Woman」の写真もないわけではないが、そこからかけ離れて見えるものも多い。さまざまな物体、ポスターや看板などの二次的な画像、さらには男性すら、強引にWomanの範疇に組み入れられている。それはそのまま、森山が現実世界に対して向ける眼差しの幅の広さを示しているのだが、それでもどの写真も、森山の世界観をそのまま体現しているように見えてくる。信じられないような力業を軽々とやってのけていることに逆に凄みを感じる。
展覧会に合わせて、Akio Nagasawa Publishingから同名の写真集が刊行された。ど派手なデザインの表紙やレイアウトが、写真集の内容にうまく対応している(造本は中島浩)。
2017/08/11(金)(飯沢耕太郎)
ますたにゆたか「さんぽのとちう」

会期:2017/08/01~2017/08/26
ふげん社[東京都]
1967年、東京生まれのますたにゆたかは、やや特異な出自の持ち主である。本人はあまり触れられたくないのかもしれないが、祖父は植田正治で、彼はその長女の和子さんの子息になる。いまは植田正治写真事務所の責任者として、展覧会や写真集出版の企画にもかかわっている。中学生のころ、「オリンパスOM-2nを祖父からもらい」、撮影・プリントした写真を見せて「褒められてまた、少しいい気に」なったという思い出を持つ彼は、しばらく写真からは離れていたが、2011年ごろから「モノクロ写真を再開」した。今回は昨年に続く2度目の個展で、フランス各地を「思い向くまま、気の向くまま」に撮影したモノクロームのスナップショット、23点展示されていた。
彼が植田正治の孫だと知っていると、どうしてもお互いの作品を比較したくなってしまう。特に今回はフランスで撮影された写真が並んでいるので、植田正治が1972、73年のヨーロッパ旅行の成果をまとめた名作写真集『植田正治小旅行写真帖 音のない記憶』(日本カメラ社)がすぐに頭に浮かぶ。たしかに、ますたにと植田正治の写真はよく似ている。端正な造形感覚、的確なフレーミング、巧みな間の取り方、犬、猫、看板、オブジェなど街の片隅の「小さな」存在に向ける視線のあり方など、祖父から孫へと受け継がれたものは多い。何よりも被写体をネガティブに突き放すことなく、柔らかに受け止め、品よく画面におさめていくあり方は、ほぼ同質といってよい。ただ、そのことをあまり強く意識しすぎないほうがいいだろう。独自性を性急に求めると、彼本来ののびやかな撮り方ができなくなってしまうからだ。「植田正治らしさ」をうまく取り込みながら、楽しみつつ自分の写真の世界をつくっていけばいいのではないだろうか。その片鱗は、DMに使われた、列車の窓に顔を寄せた少女のクローズアップにすでにあらわれてきている。ちょっとミステリアスな気配を感じさせる、そんな写真をもう少し見てみたい。
2017/08/02(水)(飯沢耕太郎)
富谷昌子「帰途」
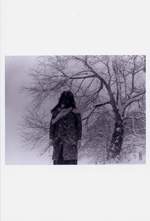
会期:2017/07/25~2017/08/13
POST[東京都]
富谷昌子の最初の個展「みちくさ」(ツァイト・フォト・サロン)が開催されたのは2010年だった。それから何度かの個展を開催し、写真集『津軽』(HAKKODA、2013)を刊行するなど、順調に歩みを進めている。今回の東京・恵比寿のPOSTでの個展(15点)は、フランスのChose Commune社から同名の写真集が刊行されたのにあわせたものだ。
2014年から撮り始められた「帰途」は、青森の家族(母、妹、その子供)を中心に、彼らの周辺の光景を取り込んで構成されている。「わたしとは何か、この世界とは何か」と問いかけ、写真を撮影し、シリーズとしてまとめることで、「時間も意味もわたしも超えて『わたし』を見つめた物語」を編み上げていくという彼女の意図はきわめて真っ当であり、写真も衒いなくきっちりと写し込まれている。とはいえ、モノクロームの柔らかな調子のプリントには、被写体だけでなく、それらを取り巻く気配のようなものも映り込んでおり、見る者の想像力を大きく膨らませていく。あまりにも正統派の「家族写真」、「故郷写真」といえなくもないが、逆にこのような地に足がついた仕事を積み重ねていくことで、さらにひと回り大きな写真作家としての成長が期待できそうだ。
特筆すべきは写真集の出来栄えである。版元のChose Commune社からは、昨年、植田正治の写真集も刊行されており、日本の写真家たちを丁寧にフォローしていこうという姿勢がはっきりと見える。今回の『帰途』も、淡い色遣いの水彩画を使った表紙、端正な造本やレイアウト、暗部に気配りした印刷など、クオリティの高い写真集に仕上がっていた。
2017/07/26(水)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)