artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
吉野英理香「WINDOWS OF THE WORLD」

会期:2022/11/12~2022/12/10
amanaTIGP[東京都]
吉野英理香がamanaTIGPの前身であるタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムで個展「MARBLE」を開催したのは2018年だから、ひさびさの展覧会ということになる。だが、五官を柔らかに刺激しつつ、現実と幻影の間に像を結ぶような彼女の作品世界のあり方は健在で、しかもその洗練の度を増しているように感じられた。
吉野は1990年代半ばにモノクロームの路上スナップ写真の撮り手として登場した。だが、2010年代にカラー写真の制作を開始してからは、むしろ身近な日常の断片にじっと目を凝らし、その微かな身じろぎを画面に刻みつけていくような作風を育てあげていった。被写体に過度の感情移入をすることを注意深く避け、むしろ吉野自身の眼差しに収束することのない、普遍的とさえいえるような視覚世界を探求し続けてきたのだ。今回の「WINDOWS OF THE WORLD」でも、水面の反映、ガラス窓の映り込み、階段の表面の反射、鳥の影など、純粋な視覚的表象へと関心が集中しているように見える。
ただ、バート・バカラックの曲名をタイトルにしていることからもわかるように、その視覚世界は単純に純粋化、抽象化されているのではなく、聴覚、触覚、嗅覚などとも連動するように組み上げられている。一見、外国で撮影されているように見えて、すべて彼女の住む北関東の街の周辺にカメラを向けていることも含めて、現実世界の様相を、そのリアリティを保ちつつ、微妙にずらしていく手際はより鮮やかなものになりつつある。なお展覧会に合わせて、図版51点をおさめた同名の写真集がPAISLEYから刊行されている。
公式サイト:https://www.takaishiigallery.com/jp/archives/27841/
2022/11/16(水)(飯沢耕太郎)
片岡利恵「あわせ鏡」

会期:2022/11/14~2022/11/20
Place M[東京都]
ありきたりの、美しい花の写真ではない。また、花々の生命力=エロスは充分に感じられるのだが、それを手放しで礼賛しているわけでもない。その儚さもまたしっかりと捉えきっている。何よりも花を通して、まさに「あわせ鏡」のように自分自身の存在を照らし出そうとしている姿勢が、切実感をともなって伝わってきた。
片岡利恵は7年ほど前から写真を本格的に撮影するようになり、その時点で花をテーマに定めた。花を選んだのは、彼女の本業が看護師であることから来ているのではないだろうか。いうまでもなく、生と死の境目の状況に常に直面しなければならない職業であり、そのなかで花々に接することに特別な思いを抱くようになっていったのではないかと想像できる。花の勁さ、脆さ、美しさ、猛々しさ、さらに生から死へそして再生へと移り動いていくあり方に、共感と感動を覚えつつシャッターを切っていることが、展示された写真群から伝わってきた。
会場構成にも工夫が凝らされていた。部屋の真ん中には、さまざまな古書が積み上がっており、そのページの合間に花の写真のプリントが挟み込まれている。小高い山のような本の群れは、花たちにとっての「腐葉土」を表現したかったのだという。壁面に並ぶ写真にも、3面のマルチ画面になっていたり、16枚の写真がモザイク状に組み合わされていたりと、写真の視覚的な情報を増幅しようとする試みがみられた。それらのすべてがうまくいっていたわけではない。だが、写真展のインスタレーションからも、やはり、ありきたりの花の写真で終わりたくないという思いを、強く感じとることができた。
公式サイト:https://www.placem.com/schedule/2022/main/20221114/exhibition.php
2022/11/15(火)(飯沢耕太郎)
水越武「アイヌモシㇼ──オオカミが見た北海道──」

会期:2022/11/10~2022/11/27
コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]
水越武は、1988年に長野県御代田町から屈斜路湖畔の北海道弟子屈町に写真撮影の拠点を移した。以来、30年以上にわたって、北海道の自然・風土にカメラを向け続けてきた。今回、北海道新聞社からそれらの写真を集成した新刊写真集『アイヌモシㇼ──オオカミが見た北海道──』が刊行されるのを記念して開催された本展では、数ある写真群から選りすぐった33点を展示していた。
タイトルの「アイヌモシㇼ」というのは、アイヌ語で「人間の大地」を意味する言葉だという。山、海、森、川、湿原などが織りなす北海道の大自然は、この言葉とは裏腹に、人間の営みを寄せつけない厳しさを孕んでいる。それは、もはや絶滅したとされるエゾオオカミが100年以上前に目にしていた風景ともいえる。水越は人工物を一切画面に入れずに、まさに「オオカミが見た北海道」の姿を撮り続けてきたのである。
地を這うように北海道の大地を移動し、時には天空から鳥の眼で地上を見降ろしつつ撮影された写真群は、見方によっては美しい絵のようでもある。DMなどにも使われた、満月の夜に草を食む鹿たちを撮影した写真はその典型だろう。だが、一見日本画のようなこの写真が、実際の場面を撮影したものであることに、むしろ凄みを感じる。北海道の風景は人を寄せつけない厳しさを持ちながらも、崇高な美しさをも感じさせるのだ。水越にとっては北海道とのかかわりの総決算とでもいうべき、記念碑的な写真展、写真集になったのではないだろうか。
公式サイト:https://fugensha.jp/events/221110mizukoshi/
2022/11/10(木)(飯沢耕太郎)
山岸剛「Tokyo ru(i)ns」

会期:2022/11/01~2022/11/14
ニコンサロン[東京都]
山岸剛は2021年に『東京パンデミック──カメラがとらえた都市盛衰』(早稲田大学出版部)と題する著書を上梓している。新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下の東京の様相を、写真とテキストで批評的に浮かび上がらせた意欲作だが、新書版という制約もあり、掲載されたモノクロームの写真図版の解像度、大きさが不足していて、その意図がうまく伝わり切れていないもどかしさも感じた。今回のニコンサロンでの個展に出品された23点は、同書におさめられたものが中心だが、カラー写真でプリントされ、大きく引き伸ばされているので、面目を一新する作品展示になっていた。
山岸は、展覧会に合わせて刊行した小冊子『Tokyo ru(i)ns』で、2019年6月から開始された横長、あるいは縦長のパノラマ画面で東京の各地を撮影したシリーズについて、こんなふうに書いている。
「東京を廃墟に見立て、遺跡として眺める、東京を、かつて華やかなりし都の跡を望むように、ある距離をとって、遠みから観察する。未来に破局が起こってわれわれの文明が滅び去った、その残骸の只中で、異郷からの客として見知らぬ遺跡の発掘現場に初めて立ち会っている、そんなふうに眺める」
この意図は、今回の展示作品でほぼ過不足なく実現しているのではないだろうか。「ある距離をとって、遠みから観察する」という視点を貫くことで、東京湾岸地域を中心としたパンデミック下の東京のうごめきが、異様なほどにありありと浮かび上がってきていた。パノラマ画面の写真による視覚的な情報量の拡張が、とてもうまく活かされたシリーズといえる。
もう一つ印象に残ったのは、東京の写真群の前(展覧会の始まりのパート)に一枚だけ、「2011年5月1日、岩手県宮古市田老野原」の写真が展示されていたことである。山岸には『Tohoku Lost, Left, Found』(LIXIL出版、2019)という著書もあり、東日本大震災以後の東北地方・太平洋沿岸の建造物を、克明に記録してきた。「Tokyo ru(i)ns」の撮影を開始したバックグラウンドに、東日本大震災があり、その経験が「東京を廃墟に見立て、遺跡として眺める」という発想につながっていったことがよくわかる展示構成だった。
公式サイト:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2022/20221101_ns.html
2022/11/07(月)(飯沢耕太郎)
エバレット・ケネディ・ブラウン『Umui』
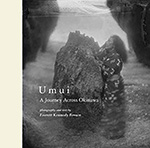
発行所:サローネ フォンタナ
発行日:2022/10/30
1959年、アメリカ・ワシントンD.C.生まれの写真家、日本文化史研究家のエバレット・ケネディ・ブラウンは、このところ初期の写真技法である湿版写真(Wet collodion process)で日本各地の風景、人物、祭事などを撮影している。沖縄県立芸術大学客員研究員(歯科医師、わらべ唄研究家)の高江洲義寛が監修した本作では、沖縄各地を湿版写真で撮影した。
ブラウンが写真撮影を通じて見出そうとしたのは、沖縄人の魂の表出というべき「 UMUI=ウムイ」の在処である。「UMUI」は「思い」と表記されることが多いが、ブラウンによれば「心の中に湧き上がる祈りや感情」であり「生命の叫び」でもある。沖縄の人々、大地、植物、遺跡などに漂う「UMUI」はむろん目に見えたり、手で触ったりできるものではない。だが、あえて露光時間が長くかかり、暗室用のテントで、撮影後すぐに現像・定着をしなければならない湿版写真で撮影することで、被写体をオーラのように取り巻く「UMUI」を捉えようと試みている。そこにはたしかに、沖縄の地霊を思わせる何ものかが、おぼろげに形をとりつつあるように見えてくる。
もう一つ興味深かったのは、そこに写っている沖縄の人たちのたたずまいが、太平洋のより南方の地域に住む人々と共通しているように見えることである。これには理由があって、ガラスのネガを使う湿版写真は、赤に対する感度が低いので、肌や唇の色がやや黒っぽく写ってしまうのだ。だが、そのことによって、沖縄の精神文化がむしろ南方の環太平洋地域に出自をもつものであることが、問わず語りに浮かび上がってくる。日英のテキストと写真とを交互に見せる写真集の構成(デザイン=白谷敏夫)もとてもうまくいっていた。
2022/11/05(土)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)