artscapeレビュー
SYNKのレビュー/プレビュー
よみがえる画家──板倉鼎・須美子展

会期:2017/04/08~2017/06/04
目黒区美術館[東京都]
2015年に松戸市教育委員会が主催して「よみがえる画家──板倉鼎・須美子展」というタイトルの展覧会が開催された(松戸市立博物館、2015/10/10~11/29)。筆者は二人の名前も作品も知らなかったのだが、チラシに掲載された作品と二人のプロフィールがとても気になっていた。残念なことにそのときは足を運ぶことができずに会期が終わってしまってのだが、今回、目黒区美術館で同じ監修者により同名の展覧会が開催されるとのことで、さっそく出かけた。展覧会タイトルや図録はそのときの展覧会と共通だが、目黒区美術館が所蔵する同時代の作品を加えて再構成されている。昭和の初めに夭折した二人の画家の仕事を伝える、とても印象的な展覧会だ。
夫である板倉鼎は明治34年(1901)に埼玉県の医者の家に生まれた。大正8年(1919)に東京美術学校西洋画科に入学し、岡田三郎助、田辺至に指導を受け、大正13年(1924)に卒業した。在学中の大正10年(1921)には第3回帝展に入選を果たしている。美校卒業の翌年大正14年(1925)に昇須美子と結婚し、大正15年(1926)2月に海外留学に出発。ハワイ、アメリカを経由して同年7月にパリに到着した。パリではアカデミー・ランソンで画家ロジェ・ビシエールの指導を受け、それまでの写実的な描法を捨て、キュビズムの影響が見られるモダンでシンプル、華やかな色彩の作品を生み出していった。サロン・ドートンヌに入選したり、日本に送った作品で帝展に入選するなど将来を嘱望されていたが、昭和4年(1929)9月、歯の治療中に敗血症となり、28歳でパリに客死した。
妻 須美子はロシア文学者昇曙夢の長女として明治41年(1908)に東京に生まれた。創立したばかりの文化学院で音楽とフランス語を学んでいたが、大正14年(1925)に中退し、17歳で鼎と結婚した。パリに渡った後、昭和2年(1927)に夫の手ほどきで絵画制作を始めた。ハワイでの思い出を素朴な筆致で描いた作品は、同年サロン・ドートンヌに初入選。鼎が亡くなり帰国するまでに3回連続で入選しているという。帰国後は有島生馬に絵の指導を受けるなどしていたが、昭和9年(1934)、25歳で亡くなった。
突然の死によってスタイルが未完のままに終わってしまったがゆえ、二人の作品はその人となりを抜きにして見ることは難しい。そして生涯と言うにはあまりに短いその人生という点では、鼎以上に須美子に同情する。17歳で結婚し、18歳でパリへ。19歳で長女を生み、21歳で生まれたばかりの次女を亡くし、その3ヶ月後には夫を亡くし、帰国。22歳で長女を亡くし、自身も結核のために25歳で亡くなった。夫や長女と写ったパリでの幸せそうな写真や映像から、どうしてその後に彼らを待ち受けていた過酷な運命を想像できようか。
作品と同様に重要なのは、鼎と須美子の没後、鼎の妹 板倉久子氏によって大切に保管されていた二人の作品、資料類だろう。松戸市に寄贈された資料には、500通にのぼる書簡が含まれ、それらはパリでの展覧会や日本人画家、交友のあった文学者たちの動静を知る手がかりとしても重要なものだという。現在、刊行を目指して準備を進めているとのことで、今後の美術史研究に資することが期待される。[新川徳彦]

左:板倉鼎《黒椅子による女》 1928 松戸市教育委員会蔵
右:板倉須美子《午後 ベル・ホノルル 12》 1927-28 松戸市教育委員会蔵
 会場風景
会場風景
2017/04/07(金)(SYNK)
クラーナハ展──500年後の誘惑

会期:2017/01/28~2017/04/16
国立国際美術館[大阪府]
ドイツ・ルネサンスを代表する画家として知られる、ルカス・クラーナハ(父:1472-1553)の日本初の展覧会。「宮廷画家」、「肖像画家」、「版画家」として、工房での量産体制を築きビジネスに長けていたクラーナハの各画業に加え、独特の「裸体表現」が後世に与えた影響、男性を誘惑する「女性」のイメージ、マルティン・ルターの宗教改革に深く関わりながら生み出された作品群、という6つの多様な切り口から91点の作品を展覧する。見どころはなんといっても、ウィーン美術史美術館所蔵の《ホロフェルネスの首を持つユディト》(1525/30頃)。同作にみる、ユディトの肌の輝くような質感、女性イメージの持つ力、豪華な衣服とジュエリーの素材感までも写し取る写実的描写は、修復に3年かかったという見事な復元技術の賜物。単に大回顧展として終わらせない本展の工夫は、近代日本におけるクラーナハの受容に始まり、西洋20世紀におけるピカソやデュシャン、さらには現代の川田喜久治と森村泰昌に渡るオマージュの系譜も示しているところ。それにしても、出展作《ヴィーナス》(1532)に代表されるような、クラーナハ作品のビジュアル・イメージは強烈で何とも忘れ難く、絵画作品を見る歓びを教えてくれる。[竹内有子]
2017/04/06(木)(SYNK)
おとろえぬ情熱、走る筆。ピエール・アレシンスキー展

会期:2017/01/28~2017/04/09
国立国際美術館[大阪府]
90歳を迎え現役で活躍するベルギーの画家、ピエール・アレシンスキー(1927年ブリュッセル生まれ)の足跡をたどる回顧展。1940年代から現在までの作品、約80点が展示された。アレシンスキーは、1948 年に結成された前衛的な芸術家集団コブラ(CoBrA:コペンハーゲン、ブリュッセル、アムステルダムの頭の文字をとって命名)に参加後、本格的に活動を始める。その後、日本の前衛書家 森田子龍と交流して、床に置いた紙に墨で力強く自由なストロークで書くスタイルに影響を受けた。本展では、墨、唐紙、拓本といった東洋の素材と技法を用いつつ、自由奔放な筆による即興的な線描表現を見ることができる。さらには、コミックの影響を受けてコマ割りにした画面の物語性ある表現、版画技法を活用しつつ新しい技法をも併用して駆使する妙、アクリル絵の具を採用することで生まれる軽快さと鮮やかな色彩性(油彩とは異なる)など、魅力がいっぱい。底流にあるのは紛れもなく西洋のエッセンスなのだが、東洋のそれも昇華・融合した彼の作品群は、もはやなんらの枠や境界に捉われないなにものかを獲得している。齢を重ねて成長し続ける芸術家の旺盛な好奇心としなやかな感受性に魅了された。[竹内有子]
2017/04/06(木)(SYNK)
ヨーロピアン・モード
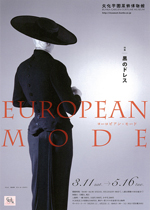
会期:2017/03/11~2017/05/16
文化学園服飾博物館[東京都]
宮廷が流行を生み出した18世紀後半、ロココの時代から若者や大衆が流行の担い手となった20世紀末まで、約250年に及ぶ欧米発信の女性モードの歴史をコレクションで概観する毎年恒例の展覧会。スタイルの変遷と、それらを取り巻く社会的背景も解説され、ファッション、デザインを学ぶ者にとってよい入門展示となっている。そして今年の特集は「黒のドレス」。19世紀後期以降、黒いドレスは喪服としてのみならず、流行として受け入れられるようになった。展示解説によればその理由は、1861年に英国ヴィクトリア女王の夫君アルバート公が亡くなり、女王が長い服喪期間に黒いドレスを着続けていたことと、同時期に黒色の合成染料アニリンブラックが発見され色落ちしにくい黒が安価に染められるようになったためだという。ドレスのほか、扇子やバッグ、帽子などの小物類、ジェットなどを使った黒いアクセサリーも展示されている。黒色に限らず、化学産業の発展による合成染料の普及、機械化の進展が、モードに与えた影響が見て取れる。例年であれば特集展示は本展示と別に独立したコーナーが設けられているが、今回の黒いドレスはモード史の文脈のなかで紹介されている。西洋モードの歴史はスタイルの変遷で語られることが一般的だと思うが、技術的視点から色彩を見るのも興味深い。[新川徳彦]

会場風景
2017/04/06(木)(SYNK)
「今様」─昔と今をつなぐ

会期:2017/04/05~2017/05/21
渋谷区立松濤美術館[東京都]
美術、彫刻、工芸において、日本の伝統的な技法によって制作を行なっている現代美術作家の作品と、それらの技法、イメージソースとなった「本歌」である古美術を組み合わせて見せるという展示。ハワイ大学マノア校日本美術史准教授のジョン・ショスタック氏の企画監修により、ハワイ大学およびホノルル美術館を会場に開催された展覧会の日本展だ。「今様(いまよう)」は、「当世風」「現代的スタイル」という意味を持つ古い言葉。ここに出品されているのは、そうした古さと新しさという矛盾した要素を制作に取り入れている作家の作品ということになる。さらに言えば、日本の現代美術を、アメリカ人の日本美術史研究者の視点で読み解くという、時間軸的にも空間的にも非常に複雑な構造の企画なのだ。参加作家は、染谷聡(漆工)、棚田康司(木彫)、山本太郎(日本画)、木村了子(日本画/陶芸)、石井亨(染色)、満田晴穂(金工)の6名。日本人としては見知った伝統技法と、これまた別の文脈で既知の現代的モチーフとの組み合わせに現われたズレには、しばしばユーモアを見て取ることができる。なかでも山本太郎の「ニッポン画」や、木村了子のイケメンを主題にした屏風は、古典のパロディと見ることもできるかもしれない。しかしながら、いずれの作品も「本歌」に用いられている技法、素材に真剣に取り組んでいるところが、様式やモチーフの表面的な引用にとどまるパロディとは一線を画していると言えよう。
建築家 白井晟一による松濤美術館の空間に、作家たち自らが手がけたという展示がとても印象的だ。日本の現代美術における伝統主義を考察するショスタック氏のテキストも興味深い。[新川徳彦]
2017/04/04(火)(SYNK)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)