artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
Tokyo Rumando(東京るまん℃)「S」

会期:2018/03/02~2018/03/31
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
Tokyo Rumandoの「S」は意欲的な新作である。「S」という謎めいた文字が何を意味するかについては、いろいろな解釈が可能だろう。一番わかりやすいのは、「ストリップティーズ」の「S」ということだ。展示されている作品には、ストリップ劇場の看板や楽屋を撮影したものが多い。実際にその舞台で作者本人がストリップティーズを演じている場面もある。もうひとつ、「ストーリーズ」の「S」という解釈も成り立つ。これまでも、Tokyo Rumandoの作品には物語性が組み込まれていることが多かったのだが、今回はそれがより強く打ち出されてきている。一枚一枚の写真に、いわくありげなバックグラウンドがあるように見えるし、セーター服、網タイツ、能面のような仮面など小道具もそれぞれが自己主張しているのだ。さらに、ワックスペーパーに焼き付けた写真に、透過光を当てて再複写したという、ざらついた、白黒のコントラストの強いプリントも、ミステリアスな雰囲気を醸し出すために効果的に使われていた。
だからこそ、その物語性をもっとくっきりと浮かび上がらせる仕掛けが必要だったではないかとも思ってしまう。写真の並びだけでそれを実現するのはやや難しいので、テキスト(言葉)もあったほうがよかった。《DISCO Red Dress》(2017)と題する映像作品も、静止画像の作品ともっとうまく組み合わせれば、面白いインスタレーションとして成立しそうだ。全体的にまだ未完成な印象だが、ブラッシュアップしていくと、さらにインパクトが強まるのではないだろうか。
なお展覧会に合わせて、ZEN FOTO GALLERYから、同名のスタイリッシュな造本の写真集が刊行されている。
2018/03/08(木)(飯沢耕太郎)
今道子「Recent Works 2018」

会期:2018/03/07~2018/04/28
PGI[東京都]
今道子は2016年に初めてメキシコを訪れ、すっかり気に入ってしまった。それはそうだろう。彼女の魚や野菜や果物を使ってあり得ないオブジェをつくり上げて撮影する作品は、元々ラテン・アメリカの「魔術的リアリズム」の風土ととても相性がいいからだ。その後の2回の滞在を経て、メキシコで受けたインスピレーションを形にした作品が、今回の展示の中核部分を占めている。実際に「死者の日」に撮影したという「Self portrait in Mexico」(2016)は、顔の半分にドクロのメーキャップを施し、メキシコの人形、聖母像、布などを配した作品だが、あまりの違和感のなさに思わず笑いがこみ上げてきた。
今回、もうひとつ気になったのは、昆虫を被写体にした作品が目につくことである。特に蚕蛾の生育キットをモチーフにした「蚕観察」(2018)のシリーズが興味深い。《目の見えない蚕》、《飛べない蚕蛾》、《口がない蚕蛾》、《蚕蛾と生きているアワビ》とそれぞれ題された作品には、今道子にはやや珍しく、苦いアイロニーが感じられる。ほかの作品も、それぞれ思考の深まりと技術的な洗練とが見事に合体しており、見応えのあるものが多かった。メキシコ滞在をひとつのきっかけとして、また別の世界が拓けてきつつあるのではないかと思う。今回で、PGI(フォト・ギャラリー・インターナショナル)では6回目の個展になるそうだが、さらなる飛躍が期待できそうだ。
2018/03/07(水)(飯沢耕太郎)
渡邊耕一「Moving Plants」
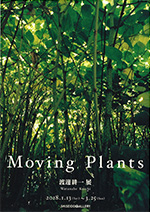
会期:2018/01/13~2018/03/25
資生堂ギャラリー[東京都]
スケールの大きな思考と実践の成果である。渡邊耕一は「15、6年前」に北海道を撮影している時に目にした、巨大なオオイタドリの群生に興味を惹かれ、その来歴をリサーチし始める。その結果、驚くべきことがわかってきた。イタドリ種の植物は日本では普通に見られるが、ヨーロッパやアメリカでは外来種であり、江戸時代に来日したフォン・シーボルトによって種子が持ち込まれ、「侵略性植物種」として各地にはびこることになったのだ。渡邊はこの「名も無き雑草」の200年以上にわたる遥かな旅の足跡を辿り、イギリス、オランダ、ポーランド、アメリカなどで、イタドリが生えている風景を撮影し続けた。本展はその成果をまとめて大阪のThe Third Gallery Ayaで2015年に開催された同名の個展の拡大版である。
渡邊の撮影のやり方は、正統なドキュメンタリー写真のそれだが、写真だけではなく、標本や古文書などの原資料、テキスト、スライド・プロジェクションなども加えたインスタレーションはとても現代的に洗練されている。発想の鮮やかさはもちろんだが、それを粘り強い調査を積み重ねて丹念に編み上げていくことで、展覧会としてもよくまとまったものになっていた。イタドリのある見慣れた眺めが、この写真展を見たあとでは、まったく違ったふうに目に映るのではないだろうか。写真による新たな世界認識のあり方を提示しようとする意欲的な試みといえる。なお、2015年の展覧会に合わせて、青幻社から同名の写真集も刊行されている。
2018/03/06(火)(飯沢耕太郎)
『光画』と新興写真 モダニズムの日本

会期:2018/03/06~2018/05/06
東京都写真美術館[東京都]
1932~33年に全18冊刊行された写真雑誌『光画』のバックナンバー一揃いを、古書店から購入したのは1987年頃だったと思う。それらを原資料として『写真に帰れ──「光画」の時代』(平凡社)を書き上げ、出版したのは1988年だった。それから30年が過ぎ、その『光画』の写真家たちの作品を中心とした大規模展が、ようやく東京都写真美術館で開催されることになった。そう考えると、感慨深いものがある。
今回の展示は「同時代の海外の動き」、「新興写真」、「新興写真のその後」の3部構成、147点で、野島康三、中山岩太、木村伊兵衛という『光画』の同人たちはもちろんだが、飯田幸次郎、堀野正雄、ハナヤ勘兵衛、花和銀吾、安井仲治、小石清などの名作がずらりと並んでいる。プリントが残っていない写真については、『光画』の図版ページを切り離し、そのまま額装して展示しているのだが、その差はほとんど気にならない。『光画』の網目銅版の印刷のレベルの高さがよくわかった。
もうひとつ重要なのは、『光画』の前後の時代状況をきちんとフォローしていることである。1930年の木村専一らによる新興写真研究会の結成に端を発した、カメラやレンズの「機械性」を強調する「新興写真」の運動が、どのように展開し、ピークを迎え、終息していったのかが、立体的に浮かび上がってきた。特になかなか参照することができない新興写真研究会の機関誌『新興写真研究』(1930~31)全3冊を完全復刻して、カタログに掲載しているのはとてもありがたい。『光画』と「新興写真」の面白さが、若い世代にもしっかりと伝わることで、1930年代の日本写真史がさらに広く、深く検証されていくきっかけになることを期待したいものだ。
2018/03/05(月)(飯沢耕太郎)
写真発祥地の原風景 長崎

会期:2018/03/06~2018/05/06
東京都写真美術館[東京都]
2017年に開催された「夜明けまえ 知られざる日本写真開拓史」展で、東京都写真美術館の「初期写真」へのアプローチはひとつの区切りを迎えた。本展は、それ以後の展望を含めて新たな連続展として企画され、長崎という地域に限定することで、より厚みのある展示・構成が実現していた。この「写真発祥地の原風景」シリーズは、今後「北海道編」、「東京編」と続く予定である。
「江戸期の長崎」、「長崎と写真技術」、「長崎鳥瞰」、「クローズアップ長崎」の4部構成、306点による展示には、写真だけではなく版画、古地図、旅行記、カメラ等の機材も組み込まれており、まさにパノラマ的に長崎の「原風景」を浮かび上がらせていた。特に圧巻なのは国内所蔵の最古のパノラマ写真、プロイセン東アジア遠征団写真班による《長崎パノラマ》(1861)をはじめとする、写真をつなぎ合わせて長崎の湾内の眺めを一望した風景写真群である。それらを見ていると、長崎を訪れた外国人写真家や、彼らから技術を習得した上野彦馬らの日本人写真家が、写真という新たな視覚様式を、驚きと歓びを持って使いこなしていたことがよくわかる、山、海、市街地がモザイク状に連なる長崎の眺めは、彼らの表現意欲を大いに刺激するものだったのではないだろうか。
なお、本展は長崎を撮影した古写真のデータベースを立ち上げてから20周年を迎えるという長崎大学と共同開催された。今後も、各地の写真データベースとリンクしていく展覧会企画を、ぜひ実現していってもらいたいものだ。
2018/03/05(月)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)