artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
友人作家が集う──石原悦郎追悼展“Le bal” Part1-maestoso

会期:2016/09/03~2016/10/05
ツァイト・フォト・サロン[東京都]
オーナーの石原悦郎(1941~2016)の逝去にともなって、1978年にオープンした写真プリント販売ギャラリーの草分け、ツァイト・フォト・サロンが幕を下ろすことになった。その最後の展示として、12月まで3期にわたって「“Le bal”」展が開催される。これまでツァイト・フォトが開催した展覧会は400近く、かかわった写真家(美術家)は100名以上にのぼる。今回の「Part1-maestoso」展には64名の写真家たちが出品しているのだが、その顔ぶれを見ているだけで、このギャラリーが日本現代写真の展開に果たしてきた役割の大きさがわかる。出品作家は以下の面々である。
1ロベール・ドアノー、2築地仁、3丹野章、4畠山直哉、5小野祐次、6林隆喜、7ベルナール・フォコン、8中川政昭、9小石清、10クッチオーニ、11細江賢治、12服部冬樹、13アキ・ルミ、14ウィリアム・クライン、15荒木経惟、16ジョック・スタージェス、17ハナブサリュウ、18杉浦邦恵、19沈学皙、20北井一夫、21渡辺兼人、22富谷昌子、23杉本博司、24アドルフ・ブラウン、25吉川富三、26ルイジ・ギッリ、27ウジェーヌ・アジェ、28ゲイリー・ウィノグランド、29青木野枝、30ロバート・メイプルソープ、31小林秀雄、32木村伊兵衛、33モーリス・タバール、34市川美幸、35鈴木涼子、36屋代敏博、37柴田敏雄、38廣瀬忠司、39松江泰治、40尾仲浩二、41荒井浩之、42木之下晃、43安斎重男、44橋本照嵩、45山崎博、46先間康博、47佐藤時啓、48小瀧達郎、49アンドレ・ケルテス、50小林のりお、51金村修、52筑紫拓也、53松本路子、54楢橋朝子、55オノデラユキ、56佐野陽一、57浦上有紀、58藤部明子、59須田一政、60蔵真墨、61渡辺眸、62鷹野隆大、63ロバート・フランク、64神蔵美子。
これらの写真家たちの作品がアトランダムに壁に並ぶ様は壮観であり、それぞれの個展のシーンがよみがえってくる。ツァイト・フォトの閉廊の痛手は、むしろこれから先にじわじわと広がっていくのではないだろうか。なお「“Le bal”」展の「Part2-scherzo」は10月11日~11月12日に、「Part3-adagio cantabile」は11月18日~12月22日に同会場で開催される。
2016/09/03(土)(飯沢耕太郎)
あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術
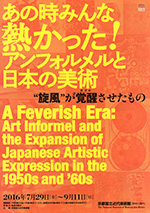
会期:2016/07/29~2016/09/11
京都国立近代美術館[京都府]
1950年代初頭、欧米で同時多発的に登場した熱く激しい抽象表現美術に対して、「アンフォルメル」(未定形なるもの)と名付けたフランス人美術評論家、ミシェル・タピエ。この動向は、展覧会やタピエの評論の翻訳を通じて50年代後半に日本に紹介され、特に56年に開催された「世界・今日の美術展」は大反響を呼び、「アンフォルメル旋風」を引き起こした。57年にはタピエが来日し、「世界・現代芸術展」を企画。デュビュッフェ、デ・クーニング、フォートリエ、フォンタナ、マチュー、ポロックなど自身が推す欧米作家に加えて、吉原治良、白髪一雄、嶋本昭三、田中敦子ら具体美術協会の作家や勅使河原蒼風、福島秀子、今井俊満、堂本尚郎といった日本人作家を組み入れて展示した。美術ジャーナリズム上では58年に終息する「旋風」だが、本展は、その影響力の射程を60年代前半まで広げ、約100点の作品を通して考察している。
本展の構成は、タピエが推した欧米作家12人の作品を展示した第1章と、「身体・アクション」「原始・生命」「反復・集合」「マチエール・物質」といったキーワードから日本での受容と展開を考察する第2~5章からなる。本展のポイントは、1)油彩画だけでなく、日本画、染織、陶芸、生け花といったジャンル横断的な影響の検証、2)爆発的な流行を受け入れた下地として、各キーワード毎に、「前衛書道との親和性」、「岡本太郎による縄文土器の『発見』(1951)や『メキシコ美術展』(東京国立博物館、1955)の反響に見られる、原始的な生命力への希求」、「日本画の画面構造の非中心性や平板な空間」、「物質の素材感に対する日本人独自の感受性」を挙げ、複数の要因を指摘している点である。
ここで問題提起をしているのは、2)の指摘である。タピエの言説と展覧会企画によって強力に推進された「アンフォルメル」が、「熱い」抽象表現をめぐる戦後の美術の主導権争いであった以上、ここには、「(欧米発信・主導の)国際的な美術動向の受容とローカリティ」という問題が横たわっている。確かに、森田子龍や井上有一らの前衛書家と、戦後の抽象絵画の方向性を模索する美術家との交流は、50年代初頭からあった。また、本展の展示の見どころの一つに、16mの長さに及ぶ篠原有司男の《ボクシング・ペインティング》と前衛書道の並置がある。墨を全身全霊で叩きつけた篠原の作品と並置されることで、前衛書道における生々しい身体性やエネルギーの過剰さが浮上し、紙面からはみ出した太い線は、漢字としての意味を失って抽象化へと接近している。しかし、ここで注意したいのは、「書道」も、「縄文土器やメキシコ美術」も、「日本画」も、還元すれば「非西欧、前近代」のモメントへと折り返されるということだ。それは対内的には、「起源」を反復するトートロジーであり、「伝統や土着の文化との親和性・連続性」を担保することで受容を推進する一方、対外的にはエキゾティシズムを発動させ、商品として差異化する記号として働くだろう。美術の国際的な基準への参入に際して、対内的にも対外的にも、ローカリティが価値づけを保証するものとして積極的に召喚される、という構造的な問題がここに露呈している。
また、第5章「マチエール・物質」も複数の問題をはらむ。この最終章では、アンフォルメルの影響力の射程を「旋風」終了の58年を区切りとして切断するのではなく、60年代前半まで射程圏に収め、絵具の物質性を強調したスタイルから、石、砂、麻袋、木片、陶片、アスファルトなどの「物質」を貼り込んだ絵画を紹介している。さらに、57年結成の「九州派」や荒川修作、工藤哲巳、高松次郎など、「読売アンデパンダン展」を中心に展開した「反芸術」も連続性のうちに捉えている。ここでの疑問は3点挙げられる。1)「農耕民族としての土との親和性や、素材感への感受性」をアンフォルメル受容の一要因と見なす姿勢に対する疑問。「超時代的な民族性」といったものが、はたして自明な存在としてあるのか? 2)素材が喚起する、脱ニュートラルな意味性。例えば、九州派がよく用いた「アスファルト」や「麻袋」という素材は、単に物質性の強調という審美的な側面を超え、近代化・工業化と労働、さらには炭鉱と労働争議、左翼的な政治性といった同時代の社会性への示唆を含む。こうした素材の使用は、その触覚性と脱ニュートラルな意味性において、「視覚性だけで完結する」とするモダニズム美学への批評として考えられるべきではないか。3)「絵具の物質性の強調」から「生の物質そのものの露呈」がはらむ射程の範囲について。この最終章では、絡まり合った紐を貼り付け、画面を黒い円形に塗った高松次郎の《点(No.16)》(1961-62)も含むことから、概念芸術への射程も示唆されている。では、高松を経由して、行きつく先は「もの派」まで射程圏を広げることはできるのか? この問いへの答えは提示されないまま宙吊りに終わっていた点が惜しまれる。
2016/09/03(土)(高嶋慈)
燃える東京・多摩 画家・新海覚雄の軌跡

会期:2016/07/16~2016/09/11
府中市美術館[東京都]
府中来訪の目的はこれ。1904年生まれの新海覚雄は、30年代の不況時から労働者を描き、戦後は日本美術会の創設に参加、砂川闘争をはじめとする平和運動や労働争議をモチーフに「ルポルタージュ絵画」を制作した画家。その後もメーデーのポスターや原水禁の版画を手がけるなど、バリバリの社会派でならした。ただし戦時中、いわゆる作戦記録画は描かなかったけれど、広い意味での戦争画は手がけた。銀行にお金を預ける人々を描いた《貯蓄報国》がそれだが、戦闘図ではなく銃後の生活を描いた穏やかなもの(本展には出ていない)。とはいえ貯蓄を奨励し、軍事費増強のプロパガンダを担った面は否めない。だから悪いというのではなく、もしこれも戦争画と呼ぶなら、社会派絵画とは紙一重かもしれないということだ。例えば1955年の国労の闘争を描いた《構内デモ》は、《貯蓄報国》などよりはるかに戦争画っぽい。いろいろ考えさせられる展覧会だ。しかし同展は「府中市平和都市宣言30周年記念事業」の位置づけで、出品作品約70点と半端でなく、しかもその大半を他館から借りているのに、なぜか常設展示室で行なわれている。また開催前には上から中止を含む再検討を指示されたという。どういうこと? それこそ戦争画の時代が近づいているんじゃないか?
2016/09/02(金)(村田真)
とことん!夏のびじゅつ(じ)かん

会期:2016/07/16~2016/09/11
府中市美術館[東京都]
夏休みの子供向け企画。「美術館で美術の時間を」ということで「びじゅつ(じ)かん」になった模様。幕末生まれの中村不折から山本麻友香までコレクションを使って、クイズや体験装置を通して楽しもうという趣向だ。清水登之のパリで描いた《チャイルド洋食店》、高松次郎の「影」、三田村光土里のサウンド・インスタレーション、富田有紀子の大きな花の絵など、テーマ展では一堂に会すことのない多彩な作品が並んでいた。山田正亮のストライプ絵画などは「いろのじゅんばんをかえてみよう」なんてやられて立つ瀬がない。奥の展示室には、まるでミニチュア模型みたいに航空写真を撮る本城直季と、その写真から本当にミニチュア模型をつくった寺田尚樹の「スモール・ワールド」があって、大人でも楽しめる。
2016/09/02(金)(村田真)
杉本博司 ロスト・ヒューマン

会期:2016/09/03~2016/11/13
東京都写真美術館[東京都]
2年間の休館を経て、東京都写真美術館がリニューアル・オープンした。英語の名称がTokyo Metropolitan Museum of PhotographyからTokyo Photographic Art Museum(TOP MUSEUM)に替わった。エレベーターが2台に増え、展示室も改装され、より快適な環境での作品鑑賞が期待できそうだ。そのこけら落としとして2階展示室、3階展示室で開催されたのが杉本博司の「ロスト・ヒューマン」展(地下1階展示室では「世界報道写真展2016」を開催)。リニューアル・オープン展以外にはまず考えられない予算と時間をかけて、凝りに凝った大規模展を実現した。
3階展示室の「今日 世界は死んだ もしかすると昨日かもしれない」は、2014年にパリのパレ・ド・トーキョーで開催された同名の展覧会をバージョン・アップしたものである。「理想主義者」、「比較宗教学者」、「養蜂家」から「国土交通省都市計画担当官」、「自由主義者」、「コメディアン」に至る、世界の終わりを記述した33のテキストにあわせて、トタン張りの小室をしつらえ、そこにさまざまな収集品、書籍、歴史資料、自作の写真作品などを配置している。質の高いコレクションとよく練り上げられたインスタレーションは圧巻であり、「漁師」のパートに展示された「歌い踊るロブスター」や、マルセル・デュシャンの「遺作」を意識した「ラブドール・アンジェ」の部屋など、絶妙な諧謔味もまぶされている。視覚的なエンターテインメントの展示として、上々の出来映えといえる。
2階展示室の「廃墟劇場」、「仏の海」では、一転して写真のテクニックの極致というべき作品を見せる。「廃墟劇場」は杉本の代表作である上映中の映画館のスクリーンを長時間露光で白く飛ばして撮影した「劇場」シリーズの延長上にある作品である。見捨てられて廃墟になった映画館で撮影するというコンセプトは、3階展示室のインスタレーションと呼応している。「仏の海」は京都・三十三間堂の千手観音像を、早朝の自然光で撮影した写真群で、8×10インチカメラの緻密な描写力で「荘厳の内に西方浄土が顕現する」瞬間を写し止めている。
これらの展示を見て、どうしても考えてしまったのは、写真美術館、そして写真という媒体が、この先どうなっていくのかということだ。リニューアル・オープン展には、今後の写真美術館の方向性が、メッセージとして託されていると考えるのは当然だろう。杉本の「今日 世界は死んだ もしかすると昨日かもしれない」は、もはやコントロール不可能な現実世界(仮想現実も含めて)に撮影という行為を通じてかかわり、そこから新たなヴィジョンを引き出してくる「写真」の営みからは遠く隔たったものだ。それは彼の内なる構想(むしろ「妄想」)を、手際よく組み上げたインスタレーションであり、観客は杉本の掌の上を連れ回され、目の前に繰り広げられる仮想的現実に驚嘆することを強いられる。先に述べたように、展示の出来映えは見事なものだが、それは「写真のこと」ではないだろう。東京都現代美術館や国立国際美術館ではなく、東京都写真美術館がリニューアル展示として開催するのにふさわしい企画であったのかという点については、疑問を呈しておきたい。
2016/09/02(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)