artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
すごいぞ、これは!

会期:2015/09/19~2015/11/03
埼玉県立近代美術館[埼玉県]
「おかしいだろ、これ。」は安保法に対する明快きわまりないコメントだが、「すごいぞ、これは!」は展覧会名としてはどうなんだろ。斬新ともいえるが、投げやりにも聞こえる。ポスターやチラシのデザインも、書体をさまざまに変えた「すごいぞ、これは!」の文字と作品図版で画面を埋め尽くして、まるで落書きみたい。実際、すごい作品もある。紙でデコトラやクレーン車をつくる伊藤輝政は、小さいころ見た映画『トラック野郎』に刺激されてつくり始めたというが、それだけで30年にもわたって800台もつくり続けるか? しろ(30代女性)の描く絵もインパクト大。彼女は他人とコミュニケーションができず、数年前から少年を主人公とする絵を描き始めたというが、その絵は仲間はずれにされたり身体の一部が切られたり仏に包まれたりと、まるで絵に描いたような(事実絵に描いてるが)自閉的なものばかり。いわゆる「ヘタ」ではないが、紙にペンと色鉛筆で描かれた絵は弱々しく、見る者を不安に陥れる。喜舎場盛也はある意味きわめて正統なアウトサイダー・アートで、カラーのドットで紙をびっしり埋めていったり、図鑑の余白に漢字を書き込んでいったり、意味の無意味の意味を追求するかのような「作品」はスゴイとしかいいようがない。とはいえ、それを額装し、整然と壁や陳列台に並べ、同じ大きさのブースで区切って見せるのはいかがなものか。とくに紙片に等間隔にハサミを入れて櫛のようにする藤岡祐機や、スナップ写真を触りまくってボロボロしてしまった杉浦篤の「作品」などは、それ自体とてつもなくインパクトがあるのに、残念ながらそれを生かした展示がなされていない。とりわけ杉浦の作品なんか貧相な現代美術にしか見えない。同展は「平成27年度戦略的芸術文化創造推進事業」として、文化庁の委託を受けた「心揺さぶるアート事業実行委員会」が実施するもの。「戦略的」に「芸術文化」で「心揺さぶ」ろうって魂胆が寒い。
2015/09/30(水)(村田真)
プレビュー:学園前アートウィーク2015
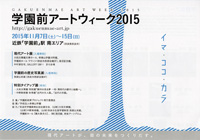
会期:2015/11/07~2015/11/15
大和文華館文華ホール、帝塚山大学18号館、学園前ホール ラウンジ(奈良市西部会館3階)、淺沼記念館、中村家住宅、GALLERY GM-1[奈良県]
関西屈指の高級住宅街と言われる奈良市内の学園前エリアで、初めて開催される地域型アートイベント。奈良といっても寺社や古民家の立ち並ぶ観光地ではなく、郊外型二ュータウンであるが、学園前は特に、教育施設や美術館もある文教地区として知られている。一方で、少子高齢化に伴う空洞化も進行しつつあるという。
ディレクターの野村ヨシノリ氏は、奈良市内のGallery OUT of PLACEのオーナーであり、2008年、奈良における現代美術の振興を目指して「奈良アートプロム(NAP)」を設立。2010年に「第1回奈良アートプロム」を開催後、NAP代表として奈良県委託事業「奈良町家の芸術祭・はならぁと」のアートディレクターを2011年~2013年まで歴任し、奈良県下の地域と密接に関わってきた。本イベントでは、いままでの実績を活かしながら、それらとどう差別化を図り、現代アートと郊外型二ュータウンの共存を目指すのかが期待される。
参加アーティストは、安藤栄作、稲垣智子、大西康明、三瀬夏之介、伊東宣明、鍵豪、狩野宏明、クニト、こだまだいすけ、中島麦、西川茂、マリアーネ、森末由美子、ピン前川の14名。奈良出身や関西在住の作家が多く、期待できる顔ぶれだ。
2015/09/30(水)(高嶋慈)
三上浩+達川清「QUAU in photo」

会期:2015/09/09~2015/10/11
POETIC SCAPE[東京都]
開館したばかりの水戸芸術館現代美術ギャラリーで、1990年に開催された「脱走する写真|11の新しい表現」は懐かしい展覧会だ。森村泰昌、今道子、コンプレッソ・プラスティコ、ソフイ・カル、ダグ&マイク・スターンなど、写真と現代美術の境界領域で活動しはじめていた写真家/アーティストが出品しており、この種の展示の走りというべき企画だった。三上浩+達川清も同展に「QUAU in photo」という作品を出品していたのだが、そのシリーズが、今回25年の時を経て東京・目黒のPOETIC SCAPEで展示された。
「QUAU」というのは「石の音、石の光」を意味する古い漢字「 (コウ)」から来ているという。彫刻家の三上が暗闇の中で石をハンマーで打ち続け、達川が飛び散る火花を写真に定着した。写真には火花によって浮かび上がる石の輪郭(形が変わっていくのでおぼろげに揺らいでいる)と周囲の状況も写し込まれている。単純なパフォーマンスの記録というだけでなく、写真それ自体が光のオブジェとして立ち上がってくる、密度と緊張感のあるいいシリーズだと思う。1980年代から90年代初頭にかけてのこの時期、多くの場所で写真家とさまざまなジャンルのアーティストとの接触、交流の実験が繰り返されていたはずだ。三上浩と達川清のコラボレーションだけでなく、他の写真家/アーティストたちの作品についても、もう一度見直していくべきではないだろうか。
なお1948年生まれの達川清は、1977~80年に三好耕三、広川泰士らと大判写真誌『GRAIN』を刊行し、80年代には『流行通信』などに意欲的なファッション写真を発表していた。技術力と発想力とをあわせ持ついい写真家だと思う。これを機会に、ぜひ新作を発表してほしい。
2015/09/30(水)(飯沢耕太郎)
岡本光博「LIFEjackets」

会期:2015/09/29~2015/10/04
KUNST ARZT[京都府]
現代社会にあふれる企業ロゴや商標、商品パッケージを引用し、「ベタ」なまでのユーモア感覚で言葉遊びを具現化させ、記号を物質へと反転させる作品を制作してきた岡本光博。岡本作品の面白さは、消費資本主義社会への批評、現代アートにおける「登録商標」とも言える既成の表現スタイルの引用など、複数の記号の操作のなかに、毒と笑いの共存というギャグの本質を含ませながら、現代社会を痛烈に批判する点にある。
本個展では、東日本大震災以降に岡本が制作してきた、「LIFE」という言葉を冠した作品のなかから、4着の「ライフジャケット」が展示された。1着は、生命保険会社21社のイメージキャラクターのぬいぐるみ52体を縫い合わせた立体作品。CMでおなじみのかわいいキャラクターたちが、文字通り、救命胴衣のベストを形づくる。「信用」や「安心」「保障」をお金で買うという行為のあやふやさとともに、幼児化する社会への批評が見てとれる。また、別の「ライフジャケット」は、上着に、生命保険会社のロゴが刺繍やプリントでびっしりと施された作品である。スポンサー企業のロゴが貼り付けられたF1レーサーやスポーツ選手のユニフォームのように見えるとともに、護符のような呪術性をも感じさせる。この「ライフジャケット」を実際に着た作家が、原発のある敦賀湾の海に溺死体のように浮かぶ映像作品も合わせて展示された。
一方、最後の1着は、霊能師であった祖父や幼い頃に飼っていたペットなど、作家自身の「守護霊」によって守られた上着の作品である。現世の「守護霊」(物質主義)と霊界の「守護者」(目に見えない存在)。両極端に見える両者はしかし、「その効力を信じるしかない」という一点で共通している。果たして、どちらの力を信じるべきなのだろうか。
2015/09/29(火)(高嶋慈)
八嶋有司「The Dive Methods to trace a city」

会期:2015/09/22~2015/10/03
galerie 16[京都府]
八嶋有司の作品は、断片の収集と身体性、知覚のシステムというキーワードから考えることができる。例えば、筆記具売り場に残された試し書きの筆跡をサンプリングし、アクリルやネオン管へと物質的に変換した《formless works》や、ネコに小型カメラを取り付けて撮影し、屋根の上や路地裏を徘徊するネコの視線を擬似的にトレースした《みるねこ》がある。
本個展で発表された《The Dive》は、作家自身の身体に計6台の小型カメラを取り付けて撮影した映像を、ギャラリーの全方位の空間に投影したビデオ・インスタレーション。前面と後面の頭部2ヵ所、両腕、両足に取り付けたカメラの映像が、部分的に重なり合いつつ、壁、天井、床に投影され、鑑賞者の身体を包み込む。撮影された光景は、ごく日常的な風景だ。自宅の部屋から出る、階段の上り下り、車の運転や電車内、水田の広がる田園風景の中を歩き、野原や林の中へと歩行は続く。正面に投影された映像は平衡を保ち、眼の代替としてのカメラの役割を保っているが、左右の壁面に投影された映像は、左右の腕の振りや動きに合わせてブレ続け、絶え間なく回転し、時に上下反転するほど激しく動き、平衡感覚を撹乱させる。床面にはブレまくった足元の地面と両足の動きが映し出され、後ろを振り返れば、風景は小刻みに上下に揺れながら、どんどん遠ざかっていく。眩暈を誘う一方で、歩行に由来する一定のリズムが陶酔感を与えるようでもある。
ここでは、複数のカメラによる同時撮影によって全方位の視覚が統合されるのではなく、むしろ分裂が積極的にもたらされる。映像の微細な振動や一定の間隔を刻むリズムは、身体各部のバラバラな動きと歩行の身体的リズムを見る者にダイレクトに伝える。《The Dive》では、撮影行為が先行し、外部に存在する被写体を撮るという目的に身体が従属するのではなく、カメラ=眼は身体の運動(歩行、階段の上り下り、車の運転……)に付随させられているという転倒が起きている。その結果、全体の滑らかな統合は放棄され、運動体に由来する固有のリズムと振動を伴った映像の断片の重なり合いが、連続と不連続の内に提示される。ここでは、普段は自明視されている運動と知覚、映像イメージの関係をめぐって、ふたつの問題提起がなされている。ひとつの運動体を複数のカメラを用いて異なる距離やアングルから撮影し、ショットの切り替えなど巧みな編集操作によって、視覚的に再統合させるという映像の文法に対して。そして、全身を映す鏡や写真といった外部の視覚装置によって担保されている、統合された身体という自己イメージに対してである。八嶋の試みは、カメラそれ自体を用いて亀裂を入れることで、それらがいかにあっけなく解体してしまうかを問いただしている。
2015/09/29(火)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)