artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
Aokid『"Blue city"-aokid city vol.3』
会期:2013/08/24
Shibaura house[東京都]
Aokidは現在25歳のダンサー。東京造形大学出身。ヒップホップをベースにしながらも、そこにかわいくて、フレンドリーなアイディアを盛り込み踊る。ぼくはこのダンサーが率直にいって好きだ。好きな理由のひとつは、アニメっぽかったり絵本ぽったりするイメージが、速い動きの最中、花火の炸裂するように散りばめられる、そんなところだ。Aokidのアクロバットは、たんなるテクニックの披露ではなく、まるで気まぐれに紙切れに書かれた漫画のようで、ぼくらが見慣れ過ぎている非人間的な身体イメージと似ていて、リアルだ。もうひとつ好きなのは、彼の優しさ。本作は、昨年12月から始まったAokid Cityという公演の3回目。会場のギャラリースペースに入ると、受付でドリンクが振る舞われ、着席すると、Aokid本人が観客にお菓子を振る舞うのだった。Aokidは忙しく会場を歩き回り、上演の準備の傍ら、観客に話しかけ、場を和ませてゆく。そうした振る舞いは、パフォーマーと観客との境界を曖昧にし、客席と舞台空間との境界を曖昧にする。ストーリーは簡単だ。Aokidが海を泳ぐうちに見知らぬ島に辿り着く。そこで怪獣と遭遇し闘い、犬と知り合いになってまた分かれ、クジラに呑み込まれたかと思えば、再びこの世界(Blue city)を後にする。まるで絵本のようなファンタジー。3歳の息子を連れて行ったのだが、彼は公演の1時間を集中して、ときに爆笑しながら楽しんで見ていた。クジラに呑み込まれた場面では、クジラの胃袋をレストランに見立てると、テーブルが舞台横に登場し、サンドウィッチや飲み物が観客に差し出された。上演が中断し、しばし歓談。「つながり」を楽しむほんわかした時間は、別に批評の対象ではないし、批評性のなさを批判するなんて無粋だ。「好き」なんていっている時点で、批評をぼくは放棄している。Aokidのダンスがもっている質は、今後、ダンスに新しい局面をもたらすかも知れないけれど、そうしたことはまあちょっと置いておこう。優しくてかわいい男の子によるささやかなパーティ、これはこれとして類い希な楽しさに満ちていたのだ。
2013/08/24(土)(木村覚)
プレビュー:六甲ミーツ・アート 芸術散歩2013
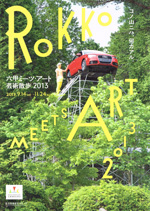
会期:2013/09/14~2013/11/24
六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲山ホテル、六甲ケーブル、六甲ヒルトップギャラリーオテル・ド・摩耶(サテライト会場)[兵庫県]
神戸の六甲山上に点在する、さまざまな施設を会場に行なわれるアートイベント。都市に隣接しながらも豊かな自然環境が残る六甲山の魅力を、ピクニック感覚の山歩きとアート作品を通して再認識できるのが大きな魅力だ。4度目の開催となる今回は、開発好明、國府理、クワクボリョウタ、西山美なコ、袴田京太朗など35組のアーティストによる展示が見られる。また、新たに設置された公演部門で、明和電機、森山開次×ひびのこづえ×川瀬浩介など5組のパフォーマンス公演も行なわれる。年々評価が高まっているイベントだけに、4年目のさらなる飛躍を期待したい。なお、会場が山上ということもあり、気候の変化が大きいのも「六甲ミーツ・アート」の特徴。ご観覧の際は、暑さ、寒さ、雨への対策をお忘れなく。会期後半の紅葉シーズンにもう一度訪れるのもおすすめだ。
2013/08/20(火)(小吹隆文)
プレビュー:奈良・町家の芸術祭 HANARART2013
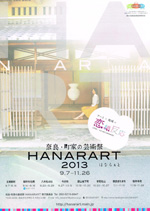
会期:2013/09/07~2013/11/26
会場:五條新町(9/7~16)、御所市名柄(9/14~16、一部作品は9/7~16)、八木札の辻(9/20~29)、今井町(9/27~10/6)、郡山城下町(10/12~20)、宇陀松山(10/20~27)、奈良きたまち(11/1~10)、桜井本町(11/16~26)[奈良県]
奈良県内に数多く残る伝統的な家並みや町家と斬新なアート作品を組み合わせる、まちづくり型現代アートイベント。今年も県内8カ所を会場に少しずつ時期をずらして開催されるが、その内容は昨年とは大きく異なる。まず、キュレーターを公募する企画展「HANARARTこあ」は、郡山城下町1カ所での開催となり、奥中章人、サラスヴァティ、銅金裕司の3組が選出された。ちなみに「こあ」の審査を行なったのは、中井康之(国立国際美術館主任研究員)である。次に、アーティストが自主的に参加し展覧会やイベントを行なう「HANARARTもあ」。こちらは昨年と同様だ。そして3つ目が、アーティストが会場に長期間滞在して制作と展示を行なう「HANARARTえあ」で、国内作家はもちろん、フランス、台湾、タイの作家も参加している。「HANARART」は日程と会場が分散しているため、すべてを見届けるのは難しい。その代わり、どのエリアに出かけてもアートと地域の魅力を体感するだろう。ちなみに筆者自身が注目しているのは、やはり郡山城下町である。
2013/08/20(火)(小吹隆文)
『吾妻橋ダンスクロッシングファイナル!』
会期:2013/08/17
アサヒ・アートスクエア[東京都]
タイトルに「ファイナル」とついた吾妻橋ダンスクロッシング(以下「吾妻橋」)が上演された。前半と後半(「コンピレーション・アルバム」の体裁を模した吾妻橋らしく「DISK 1」「DISK 2」と呼称)でトータル約7時間(!)。とはいえ、18組のパフォーマンスとChim↑Pomによるインスタレーションは、ほぼ10年続いた吾妻橋を総括するというよりも、いまの旬のパフォーマンスをキュレーターの桜井圭介による独特のセレクションで集めており、その意味で相変わらずの吾妻橋だった。桜井は、これまでの10年をまとめ、今後の10年を予感させるつもりで選んだと筆者に話してくれたが、なるほどKATHY、黒田育世、身体表現サークルというチョイスは、「The Very Best of AZUMABASHI」★1が上演された2007年頃を思い起こさせて、懐かしさを感じさせるものだったし、ただそうした観客側の懐古的な思いを打ち消すように、ロロ、ピグマリオン効果、hyslom(ヒスロム)、ダンシーズ(皆木正純+山田歩+唐鎌将仁)のような新しいラインナップも加わわっていた。
今回の吾妻橋にぼくが見た特徴は二つ。
ひとつは、身体という存在の不確かさ・不安を訴えているような作品が目立ったこと。DISK 1のトップバッター、音楽家の安野太郎は、4本のリコーダーをPCの制御のコンプレッサーが奏でるという実演を行なった(タイトルは「ゾンビ音楽」)。空気圧で鳴る音色の非人間的な感触は、パフォーマンスにおいて人間の肉体が不在であることの無気味さを強く印象づけた。ほかにも、かつて大分で遭遇した心霊体験を語り、その際撮影した写真を紹介した捩子ぴじんの上演は、目の前に存在しない(いや、存在するかどうか不確かな)霊的な存在をめぐってのものだった。KATHYは美術家の水野健一郎とともに、普段ぼくたちが知覚せずにいる次元に迫り、見えないものを観客に感知させるパフォーマンスを行なった(タイトルは「確かにみえている」)。ルックスからしてそうであるが、かねてから踊る身体の存在の不確かさ、曖昧さについて自覚的であったKATHYのさらに一歩超常現象へと進んだ表現を見た後では、快快の山崎皓司によるパフォーマンスもいつも以上に、存在の不安に迫っているように見えてしまう。山崎はユニクロとダイソーを愛する中年女性に扮した。自分を見過ごす社会への不満が演じる山崎自身の抱く役者生活への不安と重なる。余剰的存在として役者を提示することは快快の舞台に時折盛り込まれるものだ。昨今の、三次元よりも二次元、現実よりもヴァーチャルを志向する社会の傾向にあって、パフォーマンスする身体の価値はそれほど自明ではなくなっている。そうした状況が滲んで見えたのが、今回の吾妻橋に目立った特徴だった。
もうひとつは、冷笑的な傾向だ。ダンシーズの男3人が野良犬のようにうろうろする舞台、そこに尾崎豊のライブ語りを流したのだが、尾崎の真っ直ぐさを冷やかしているように見えたし、DISK 2のラストで有志の観客100人を斬り続けた悪魔のしるしの危口統之は、観客を愚かな死体と化してその状況を高みから笑っているように見えた。ひたすらくだらないだしゃれを口にし、まとまらない状態を演出したライン京急も、とくに今回は、くだらないことをあえて強調している気がした。舞台を、ダンスや演劇を、あるいは観客を嗤う批評性は、どうしても笑う者の優位と笑われる対象の劣位が際立ってしまい、破壊のダイナミズムに乏しい。その意味では、最近の吾妻橋に頻繁に出演していた遠藤一郎の不在が寂しかった。彼の度はずれた真っ直ぐさこそ、優劣を超えた場を引き出す力となるのではないか。それは吾妻橋が示す倫理的態度でさえあった、そう思っていたから。
★1──木村覚「アメーバ化したぞ『吾妻橋』」(吾妻橋ダンスクロッシング「The Very Best of AZUMABASHI」レビュー、ワンダーランド、2007)
2013/08/17(土)(木村覚)
ままごと「日本の大人」
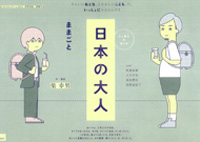
会期:2013/08/10~2013/08/15
愛知県芸術劇場 小ホール[愛知県]
あいちトリエンナーレの委嘱作品、ままごとの「日本の大人」を観劇した。小6のとき、小学26年生と出会った主人公が32歳を迎え、子どもと大人、過去と現在が交錯する物語である。柴幸男らしいリズミカルで心地よいテンポと、時空が切り替わるときのシンコペーションするような演出がよかった。そして笑いがある。「日本の大人」は、大人と子どもが一緒に見ることを想定しているが、それを大成功させた「モーレツ! オトナ帝国の逆襲」も両世代のツボを配しながら、大人になることの拒否をテーマとする。小6という設定は、マッカーサーが日本人の精神年齢は12歳と言ったことを想起させる。小学26年生のくまのさん=日本なのか。あいちトリエンナーレでは異ジャンルが共振するが、日本/女性とアメリカ/男性のオリエンタリズムからアイデンティティの揺らぎを描く「蝶々夫人」と「ゼロアワー」のように、「日本の大人」は映像プログラムの「playback」と比較できるだろう。この映画も突然大人の姿のまま高校時代に戻り、時空が交錯するからだ。
2013/08/12(月)(五十嵐太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)