artscapeレビュー
2013年06月15日号のレビュー/プレビュー
NHKクローズアップ現代「1000年後の命を守るために~どう伝える 震災の教訓~」
NHKの番組「クローズアップ現代」の震災遺構を考える回に出演した。事前に僕の話は取材されているのだが、直前にスタッフと再度打ち合わせを行ない、その場で会話の構成を決めていく。個人的に、東日本大震災から3週間後の女川訪問は忘れ難い。いまは3つの被災建物以外ほとんど消えたが、当時はこれを見つけるのに、30分以上廃墟の街を歩かないとわからないほど、ぐちゃぐちゃの風景だった。が、これに遭遇したとき初めて震災遺構を残すべきであり、ここで見たことを後世に伝える使命を感じたことを思い出す。
2013/05/15(水)(五十嵐太郎)
水田寛 展「日課」

会期:2013/05/07~2013/05/19
ギャラリー恵風[京都府]
水田寛の油彩画とドローイング。わりと小さめの作品が多数展示されていた。鉄棒にぶら下がってスカートもめくれた子どもの姿が映り込む水面、水中で水を蹴って泳ぐ人の足(の裏)、真上から見た自転車のボディなど、多くは身近なものをモチーフにしており色も多彩なのだが、ものの断片や風景が入り混じるような、距離感やスケール感、図と地の境界もはっきりとは判別できない画面構成で、何が描かれているのだろうといちいち凝視してしまう。しかし、そうして画面を注視しているうちに愉快な作品世界に引き込まれていくからニクい。私は水田のドローイングの展示をこんなにまとめて見たのは初めてだったのだが、会場には過去のドローイングをたくさん収納したファイルも置かれていて堪能できた。
2013/05/16(木)(酒井千穂)
松延総司「棚/SHELVES」
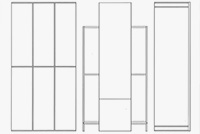
会期:2013/04/25~2013/05/19
LABORATORY[京都府]
松延総司が久しぶりに個展を開催していた。これまでも、ミニマルな表現でモノの機能や存在にアプローチするインスタレーション作品を発表してきた作家だ。今回は「機能を持つものから機能をはぎ取ったとき、その後に何が残るのか」というテーマのもと、“実験的な棚”を展示するとフライヤーに記されていて気になった。綺麗に組み立てられているが、6面とも板で塞がれた箱状の“棚”、しきり板がすべて斜めになっている“棚”、知恵の輪のように組み合わされた“棚”など、会場には数点の木製の“棚”が展示されていた。当然ながらそれらは正確には“棚”ではなく目的を持たないオブジェだと言える。ただそれだけ、といえばそうなのだが、面白いのは松延の視点。今展のステイトメントには「棚になる可能性を持つものは星の数ほどあるかもしれないが、そこにモノが置かれない限りそれは棚ではない」という作家のコメントもあった。私たちは、モノを前にして、その機能を知らずにはその存在にも無関心になることができない。いつもそこにあるモノの存在を当たり前に措定し、無関心でいられるのは、機能を理解しているからこそだ。それは人間の動作、行為の延長上にある知覚だから、逆に言えばモノもまた、その存在に人間的な意味をもっている。その存在だけを抽出した松延の“棚”は、翻って人間の行為や私自身の存在を鏡合わせのように意識させる。連想を掻き立てる表現がスマートだった。
2013/05/16(木)(酒井千穂)
SSD オープンレクチャー 相馬千秋「演劇はなぜ、都市に出るのか?─都市のドラマトゥルギーを引き出す、演劇的想像力の可能性」
会期:2013/05/16
東北大学片平キャンパス都市建築学専攻仮設校舎ギャラリートンチク[宮城県]
今期、せんだいスクール・オブ・デザインのメディア軸は、「演劇/ライブから考える」と題して雑誌制作を行なう。第一回のゲストの相馬千秋は、劇場を飛びだし、都市のドラマトゥルギーを引き出す事例を紹介した。池袋の芸術劇場の前で行なわれたフラッシュ・モブ、フェスティバル・トーキョーにおいて新橋と福島をつなぐ高山明の「光のないII」、移動するトラックが客席となって都市を体験する試みなど、演劇の可能性を開く挑戦だ。
2013/05/16(木)(五十嵐太郎)
日本写真の1968
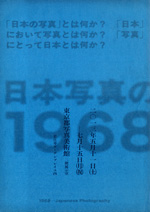
会期:2013/05/11~2013/07/15
東京都写真美術館 2F展示室[東京都]
さまざまな問題提起を含む重要な展覧会である。1968年と言えば、「プラハの春」やパリの「五月革命」に続いて、日本全国で学園闘争の嵐が盛り上がりを見せるなど、第二次世界大戦後の政治・社会体制への「異議申し立て」が相次いだ年だ。日本の写真表現においても、大きな変革への胎動が形をとり始めていた。本展はその1968年を中心にした、1966〜74年の写真家たちの動向を「プロローグ」「写真100年展」「プロヴォーク」「Interlude」「コンポラ写真」「写真の叛乱」「エピローグ」の7部、約250点の写真群で概観しようとする意欲的な企画である。
「プロヴォーク」以下の中間部の写真家たちの動きについては、これまで多くの展覧会や写真集で取り上げられてきたので、それほど新味はない。むしろ見所は、その前後の「写真100年展」と「写真の叛乱」のパートである。1968年6月1日から東京・池袋の西武百貨店でスタートし、同年11月まで全国各地を巡回した「写真100年──日本人による写真表現の歴史展」(日本写真家協会主催)は、画期的な展覧会だった。その成果をまとめて71年に刊行された『日本写真史1840-1945』(平凡社)を含めて、日本の写真表現の展開の見取り図を、この時点で提示できたことの意義はいくら強調してもし過ぎということはない。本展では、実際に会場に展示された大判の木製パネルも並んでいて、その衝撃を追体験できるようになっていた。また同展に出品されていた「北海道開拓写真」や山端庸介の原爆投下直後の長崎の記録写真が、「アノニマスな記録」の意味を再評価しようとした多木浩二、中平卓馬、森山大道ら「プロヴォーク」の同人たちに大きな影響を与えたことが伝わってきた。
さらに興味深いのは、「写真の叛乱」のパートに展示された全日本学生写真連盟とその周辺の写真家たちによる「集団撮影行動」の成果である。大学、高校の写真部のメンバーたちの全国組織である全日本写真連盟(1952年設立)は、一定のテーマを決めて手分けして写真を撮影・発表する「共同制作」を盛んに試みていた。ところが、60年代半ば以後の新左翼と全共闘運動の高揚のなかで、「あらかじめ作られたストーリーを絵解きするのでもない、共通の主題を持ちながら個々人の撮影行動を集約していく」動きが具体的に形をとっていく。この「集団撮影行動」は、写真集『この地上にわれわれの国はない』(全日本学生写真連盟公害キャンペーン実行委員会、1970)や『ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə』(全日本学生写真連盟広島デー実行委員会、1972)に結実し、未刊には終わったが明治以降の近代化の矛盾を問い直す「北海道101」の撮影・発表活動も積極的に展開された。
すでにややセピア色に変色し、生々しい折り目や皺が入ったままの無名の学生たちのプリントが、これだけ大量に展示されたのは初めてだろう。それらはこの時期の日本の写真表現の変革が、若い写真家たちの無償の情熱に火をつけ、厚みのある「集団撮影行動」のうねりを巻き起こしていった様を、まざまざとさし示していた。いわば写真史の「表の顔」だけではなく、このような「裏の顔」(むしろ「地下の顔」といった方がいいかもしれない)を明るみに出そうという作業は、きわめて実り多い、豊かな可能性をはらんでいるのではないかと思う。
2013/05/17(金)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)