artscapeレビュー
2011年01月15日号のレビュー/プレビュー
ヤマザキマザック美術館所蔵作品展

会期:2010/04/23
ヤマザキマザック美術館[愛知県]
2010年4月にオープンした、精密機械の会社のコレクションを展示する施設。日建設計が手がけたスマートなオフィスビル(2010)の4階と5階が美術館になっているが、エレベータを降りて、いきなり視界に入る、アンチ・ホワイトキューブの空間に驚かされた。作品は18世紀のロココから始まり、19世紀のフランス絵画がメインだが、いわゆるヨーロッパ宮殿風の内装である。なるほど、ヤマザキマザックの社長が海外出張のときに見学していた西洋美術は、宮殿に展示されていることが多い。そうした箱の記憶も再現したのだろう。お台場のヴィーナス・フォートと同様、現代的な外観のビルと、ヨーロッパ的なインテリアという分裂症的なデザインの対比が著しい。個人的には、4階の1900年前後の装飾芸術、すなわちアールヌーボーの家具、エミール・ガレの工芸などが楽しめた。とくに前者は家具から食器まで、当時の部屋をまるごと再現している。ともあれ、こういうコレクションがいきなり公開されることに、愛知がもつ底力を感じた。
2010/12/05(日)(五十嵐太郎)
大洲大作写真展「光のシークエンス」
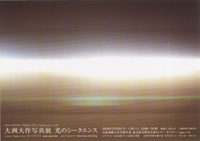
会期:2010/12/06~2010/12/18
大阪成蹊大学芸術学部 総合教育研究支援センター ギャラリー〈space B〉[京都府]
横浜市在住で、近年はベルリンで発表している大洲大作の写真展。はじめて作品を目にした。移動する電車の窓に流れていく景色や、穏やかに変化する海辺の光景。一瞬の光を美しい構図でとらえた写真はこれまで他にも見たことがあるが、ただ奇麗にまとまるというだけで終わらず、大洲の視線や感情の推移がともに重なって写り込んでいるように思える。光をとらえようとレンズ一点に集中するのでも、そのような光景の瞬間を待ち構えるでもなく、まるで流星を見たときの喜びのような雲散霧消の余韻が心地よい展覧会であった。
2010/12/06(月)(酒井千穂)
伊東宣明 回想の遺体

会期:2010/12/07~2010/12/12
立体ギャラリー射手座[京都府]
髪の毛や尿など、自らの身体の一部を用いた作品を制作したり、祖母の死をテーマにした映像作品、同じ場所を異なる時代に描いた絵ハガキを並置する作品などを通して、人間の認識や自己の境界線を探る作品を発表してきた伊東宣明。彼は大学卒業後に葬儀会社に就職し、退職するまでの約1年半の間に多くの“死”と接してきた。本展では、その体験を元にした新作を発表している。会場の床一面には、アンプ、スピーカー、コードが配置されていて、スピーカーからは伊東がメモを読む声が聞こえてくる。メモの内容は、彼が出会った遺体の状態をしたためた文面だ。具体的な内容を聞き取りたいのだが、複数の声が同時に聞こえるので、個々の文章を聞き取るのは至難に近い。それでも断片的な単語は聞こえるので、徐々に自分が不穏な空気の真っただ中にいるような気分になってくる。不穏とは、それ自体が実在するのではなく、人の心がつくり上げる一種の幻影である。それは死の恐怖についても同様だろう。伊東の新作は、そうした感情がどのようにして形成されるのかを明らかにしたものと言える。
2010/12/07(火)(小吹隆文)
下園詠子『きずな』

発行所:東京ビジュアルアーツ/名古屋ビジュアルアーツ/ビジュアルアーツ専門学校・大阪/九州ビジュアルアーツ(発売=青幻舎)
発行日:2010年11月30日
下園詠子は1979年鹿児島県生まれ。九州ビジュアルアーツ卒業後、2001年に個展「現の燈」(コニカプラザ)でデビューし、早くから将来を嘱望されていた。だが2010年度の第8回ビジュアルアーツフォトアワードで大賞を受賞し、この写真集『きずな』の刊行にこぎつけるまではかなり時間がかかった。その10年余りの紆余曲折が決して無駄ではなかったことが、写真集を見るとよくわかる。試行錯誤の積み重ねによって、説得力のある表現に達しつつあるのだ。ビジュアルアーツフォトアワードの審査後に、僕が書いた選評を引用しておこう。
「下園詠子のポートレートを見ていると、被写体からまっすぐに放射される『気』のようなものを強く感じる。ヒトはそれぞれそのヒトに特有の『気』の形を持っているのだが、彼女はそれをまっすぐに受けとめて投げ返す。2001年の最初の個展「現の燈」に展示されたものと近作を比較すると、そのエネルギーのやり取りの精度が高まり、激しさだけでなく柔らかみが生じてきている。彼女の成長の証しだろう」
さらに、彼女が常用している6×6判のカメラの真四角の画面から発する魔力が、より増してきていることも付け加えておきたい。「気」を呼び込むための装置もまた、以前にくらべると自在に使いこなすことができるようになったということだ。
2010/12/08(水)(飯沢耕太郎)
第12回三木淳賞 金川晋吾 写真展「father」

会期:2010/12/07~2011/12/13
ニコンサロンbis新宿[東京都]
三木淳賞は、ニコンが主催する35歳までの若い写真家たちの公募展「Juna21」の出品作から選出される賞。今年の第12回三木淳賞には、2010年2月23日~3月1日に新宿ニコンサロンで開催された金川晋吾の「father」が選ばれた。
金川は1981年生まれ京都生まれで、東京藝術大学先端芸術学科大学院在学中。「蒸発」をくり返す父親にカメラを向けたこのシリーズは、以前からずっと気になっていたものだが、2月~3月の展示を見過ごしていたので、受賞記念展が開催されたのはありがたかった。家族や社会との関係を自ら断ち切り、「何もない人間」になってしまった父親を撮影し続けることによって、かろうじてその存在の痕跡を浮かび上がらせようとする切迫した行為の集積であり、微温的なもたれあいを感じさせる凡百の「家族写真」とは完全に一線を画する。「何もない人間」が発する荒廃の気配が、写真にぬぐい切れずに漂っていて、痛々しく、不気味でさえあるのだ。とはいえ、ぎりぎりの撮影行為を続けることで、なぜかほのかな「希望」のようなものがあらわれてくるように感じるのはなぜだろうか。ここからさらに何かが見えてくる可能性を秘めた、新たなドキュメンタリーの方法論が模索されている。
一緒に展示してあった「2009・4・10~2010・4・09」と表紙に記されたフォトブックも興味深かった。父親本人にカメラを持たせ、毎日セルフポートレートを撮影してもらう。その一年間の写真の集成である。時々抜けている日もあるが、それでもかなりこまめに撮影を続けている。その無表情の集積を見ているうちに、哀しみとも怒りとも虚しさともつかない感情がじわじわとせり上がってくる気がした。
2010/12/08(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)