artscapeレビュー
高嶋慈のレビュー/プレビュー
KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING ショーケース「Forecast」国枝かつらプログラム

会期:2016/03/20~2016/03/21
京都芸術センター フリースペース[京都府]
「KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING」公式プログラムとは異なる視点から舞台表現を紹介することを目的に、外部キュレーターを招聘し、ショーケース形式で新進作家を紹介する「Forecast」。丸亀市猪熊弦一郎現代美術館学芸員、国枝かつらによるプログラムでは、「声と身体」に焦点をあてた作家3名が選出された。
中でも出色だったのが、梅田哲也の「COMPOSITE」。フィリピン山岳地帯の村の子どもたちと2014年に制作した作品が、再構築されて上演された。声と身体という最小限の要素を用いて、ルールの設定に即興を組み込むことで、共鳴と不調和が織り成す豊穣で示唆的な世界をつくり上げている。
6人の男女が輪をつくり、「アレアレウッウッ」という独特の掛け声を発しながら、腕や肩や太ももを叩き、足踏みを鳴らして、一定のリズムを反復する。全員が同じリズムパターンではなく、向き合った2組ごとに三つのパターンが掛け合わされる。リズムが途切れると、輪を左周りに回転させ、少しリズムパターンを変化させて、掛け声や手足を叩く音を繰り返す。原始的な儀式のような光景だ。構成要素はミニマルだが、パターンの選択と順列、声の高低、身体を叩く部位に関する複数のルールがおそらく設定されているのだろう。単純な要素の反復とズレによって多様なパターンが生成され、声と身体の音が折り重なった音楽を立ち上げていく。パフォーマーたちは皆、目をつぶっており、それぞれに課せられたルールを順守しようと内側への集中を高めるとともに、外部の音へと聴覚を研ぎ澄ましているように見える。
しばらくすると、客席から6人の子どもたちが飛び出し、もうひとつの輪をつくって同じような掛け合いを始める。しかしお互いの発するリズムがズレているため、二つの輪は完全には同期せず、不協和音が波紋のように広がっていく。そのうち、別の大人の男女6名が舞台上に加わり、単調な節回しのメロディを歌いながら、一歩ずつ前進と後退を繰り返し始める。第三勢力の登場だ。この第三勢力は、輪をつくっていた二つのグループにはない「能力」を有しており、1)(おそらくルールに従って)一歩ごとに移動できる、2)移動先で接触した相手を同じメロディに吸収することができる。こうして、身体の接触を契機として、集団内で共有されていた「ルールの順守」にほころびが現われ、徐々に崩壊していく。掛け声や足踏みを反復していた輪のパフォーマーたちは、ひとり、またひとりと単調な節回しのメロディを歌い、輪から外れてバラバラな方向へ歩き始める。大人の輪も子どもだけの輪も解体し、混ざり合い、輪郭が溶け合っていく。古いルールの崩壊と新たなルールの浸食、ひとつの共同体の解体と融合のはざまに出現する、カオティックな音響世界。
そして暗転と一瞬の静寂後、灯りに照らされた空間には、全員が同じ単一のメロディを歌う姿が出現した。ノイズは排除され、「美しく」調和した音楽だけがそこにある。ただし目を閉じたまま、お互いがどこにいるかも分からない暗闇の中、バラバラな方向への一進一退を繰り返しながら。それは他者への共鳴や共感が浸透した世界なのか、それとも個々はバラバラに分断されたまま、支配的な単一の旋律が全体に波及し飲み込み覆っていく過程の恐るべき出現なのか。
ショーケース「Forecast」国枝かつらプログラム/梅田哲也「COMPOSITE」
Photo: Tetsuya Hayashiguchi
2016/03/21(月)(高嶋慈)
トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー「Trisha Brown: In Plain Site」
会期:2016/03/19~2016/03/21
京都国立近代美術館 1階ロビー[京都府]
「KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING」公式プログラム観劇6本目。
トリシャ・ブラウンの初期作品群をオムニバス形式で上演する本作。(90年代に発表された1作品を除き)1973年~1983年の約10年間のエッセンスを凝縮したプログラムが、京都国立近代美術館の1階ロビーにて上演された。数分~10分ほどの小作品が計13個、吹き抜けの階段や天上高のあるロビー、10mほどの壁など、開放感ある空間の中で移動しながら上演される。客席はなく、観客もまた移動しながら鑑賞する。
白が基調の空間に、白に統一された衣装のダンサーたちは、ニュートラルで幾何学的に構成された振付を淡々と繰り返す。だが、水平/垂直、直角や斜線、並列の正面性/向き合った左右対称性など身体の向きの変化、フォーメーションの変化、空間との関係性など、さまざまなバリエーションを加算的に加えていくことで、運動の見え方は複雑に変化する。また、幾何学的に分節化された単位の反復がズレをはらむことで、ダンサーの従事する運動そのものは変化しなくても、観客の知覚の方が変容する。ミニマルで抑制の効いた振付と構成の明晰さが、そのことをより際立たせる。一方で、45度に傾けた棒の角度をキープしながら、頭や爪先など支える身体部位を入れ替える、横倒しにしたダンサーの身体を数人で支えながら、壁=90度回転した床であるかのように歩かせるなど、空間を身体で測定していくような試みもなされる。作品はいずれも、数理的な構成や幾何学的な厳格性において徹底しているが、同時にユーモアをたたえ、ボーカル入りの楽曲の使用とあいまって、とても軽やかだ。
(メディウムとしての)身体の即物性、分節化された単位への還元、単位の反復とズレによる知覚の変容など、ミニマル・アートとの共通性。制度的空間であると同時に物理的スケールに規定されたミュージアムの空間、その中で特権的な眼差しとして振る舞いながらも、身体的存在であることから逃れられない私たち観客。そして、通常は「物質的」存在である芸術作品を収集・保存・展示する美術館において、テンポラルでエフェメラルな「舞台芸術」の「再演」を行なうこと。本作の上演は、約30~40年前のブラウンの諸作品の単なる回顧にとどまらず、生成された時空間の限定性から切り離されたかたちで「作品」を収集・提示する「美術館」の制度性を浮き彫りにするとともに、再生装置としての可能性をも示唆する。「美術館」の空間で上演されることの(複数の)意義が、十分に感じられた公演であった。
トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニー「Wall Walk(from Set and Reset, 1983) 」
レンバッハハウス(ミュンヘン)、ダン・フレヴィンギャラリー 2014
(c)
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München
2016/03/20(日)(高嶋慈)
チェルフィッチュ「部屋に流れる時間の旅」

会期:2016/03/17~2016/03/21
ロームシアター京都 ノースホール[京都府]
「KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING」公式プログラム観劇5本目。
花瓶ののったテーブルと2脚の椅子、奥にはカーテン。どこにでもあるリビングを思わせる簡素な空間。だが舞台上手には、水の入ったコップとホース、電球や石を組み合わせた奇妙な装置や、バケツ、プロペラ、丸い金属板のような物体が置かれている。日常的な室内を非日常が静かに侵食していくような舞台空間の中で、「震災直後」と「現在」と「近未来」をめぐる死者と生者の語りが交錯する。
「ねぇ、おぼえてる?」と執拗に夫に語りかける妻。「あの日を境に、私たちは生まれ変わったの。すばらしいと思わない?」と言う妻は、目に映るものすべてが美しく見えること、地震後に世の中が変わると確信した幸福感、隣人への思いやりや助け合いの気持ちが湧いたこと、赤ん坊に未来への希望を感じたことなどを延々と語り続ける。実は、彼女は地震の4日後に喘息の発作で死亡しているのだが、「災害ユートピア」の出現と社会の変化への希望を抱いたまま、円環的に閉じた時間の中に留まり続けている。死者の時間は安定しているが、もはや変化は訪れない。止まったままの死者の時間、その中で繰り返し語られる「希望」や「明るさ」、「幸せ」。「未来」を断たれた死者が「希望」を語り、過去の中にしか「未来への希望」がないという反転は、生者にとっては耐えがたい重荷となり、「ねぇ、おぼえてるでしょ?」という執拗な反復が負荷をかけ続け、生者の身体を硬直させていく。
呪いのような祝福の言葉から逃れるように、夫は新しい恋人を部屋へ迎え入れようとする。「わたしの乗ったバスは渋滞に巻きこまれていて、この部屋への到着が遅れています」「わたしは少しずつ、この人と親密になっていきます」と観客に向かって語りかける新しい恋人。死んだ妻=過去、夫=現在であるならば、この新しい彼女=来るべき未来の擬人化と考えられる。3つの時制の擬人化像を、元妻・夫・新しい彼女という3人の恋愛劇として重ね合わせた本作。死んだ妻は夫にだけ語りかけ、夫はぶっきらぼうな返事を返しつつ、新しい彼女とぎこちない会話を交わし、新しい彼女だけが観客に語りかけるメタな位置にある。あえて一幕の構成にすることで、限定された空間の中に、異なる話者と複数の時制が共存する構造が際立つ。現在において「今」を語ること、「現在時にはいない者」として「これから起こる未来」を語ること、「過去」を忘却しようとすることがかえって「過去」の存在を強く思い出せること。それは、「現在時には定住しえない、不在の者」としての「幽霊」を召喚する。「ねぇ、おぼえてるでしょ?」の執拗な繰り返しと、媚態とも苛立ちともつかない身体の微細な揺らぎ。現在時から疎外された「幽霊」は、絶えず想起されなければ存在できないのだ。
時間の圧縮、並置と共存。過去─現在─未来へと流れる単線的な時間ではなく、むしろ複数の時間軸の混線。伸縮自在に複数の時間を行き来するこの「部屋」とは、劇場空間に他ならない。「たくさんの、ここには聞こえてこない音があります」という新しい恋人の台詞には、社会的現実から切断された非日常的な「劇場空間」への自己批判が込められており、「ねぇ、おぼえてるでしょ?」という執拗な反復の居心地悪い響きは、倫理的要請と矛盾した希望のあり方、それが叶わなかった絶望、その諦めさえ忘却しつつある2016年の現在の後ろめたさを照射する。震災後の日本社会の矛盾を、死者と生者の交錯・対立を通して描き出す点で、本作は、前作の「地面と床」の延長線上に位置づけられる(「地面と床」では、国外への避難を企てる「嫁」を演じた青柳いづみと、ネイティブの土地や国語への愛を語る死者の「母」を演じた安藤真理という2人の女優が、本作では生者と死者の役柄を交換して演じている点も興味深い)。
また、時空の伸縮装置としての劇場空間への言及は、現代美術作家の久門剛史による音響と舞台美術によって増幅されていた。バケツ、ホース、小石、カーテン、電灯……一つひとつは見慣れたものだが、心地よい生活音や水の滴り、不穏なノイズを背景に、反復的な運動と光の明滅が与えられることで、自律的な領域をひとりでに生き始める。あるいは、揺らいだカーテン越しに差し込む光が、僥倖のような一瞬をつかの間出現させる。3人の話者による3つの時制の並置に加えて、もうひとつの時空間を到来させていた。
チェルフィッチュ「部屋に流れる時間の旅」
Photo: Misako Shimizu
2016/03/20(日)(高嶋慈)
PATinKyoto 第2回京都版画トリエンナーレ2016
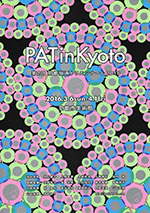
会期:2016/03/06~2016/04/01
京都市美術館[京都府]
2回目を迎える「京都版画トリエンナーレ」。本展の特徴は、コミッショナー20名の推薦方式による若手~中堅作家の積極的な紹介と、「版」概念の拡張にある。
また、狭義の「版画」の枠組みにおいて制作する作家においても、メディウムそのものを問い直す実験性が見られる。例えば、小野耕石は、インクの色を変えて100層以上もシルクスクリーンの版を刷り重ねることで、極小の突起に覆われた表面が、見る角度により玉虫色に生成変化する作品をつくり出す。《Hundred Layers of Colors》と題されたそれは、「インクの物質的な層の堆積」というメディウムの原理を露呈しつつ、光の反射や視点の移動によって、物理的には単一の表面を、現象的な現れの空間として、複数性へと開いていく。また、金光男は、白く不透明な蝋を支持体として、その上に写真を転写し、熱を加えることで、溶けた蝋の上でインクが流動化し、波打つように崩壊したイメージをつくり出す。凝固と流動性のはざまを漂う不穏な緊張感とともに、インクの物質的な層が剥離し、ただれた表面が浮き上がったような錯視を生み出している。そうした錯視効果を出現させるため、「金網のフェンス」「波」「カーペット」など、単位の反復性から構成される被写体を用いているのが特徴だ。さらに、手描きのモチーフではなく写真画像を用いる金の作品は、写真という複製物・「版」性とシルクスクリーンという「版画」技法を組み合わせたハイブリッドな表現でもある。
一方、写真や映像を用いて、間接性と反復性(複製性)という点から、「版」概念へと言及しているのが、山下拓也と林勇気である。山下拓也は、野球チームやオリンピック、万国博のマスコットとして、かつては人気者だったが今は忘れ去られたキャラクターたちを大量に複製し、過剰に増殖させたインスタレーションをつくり出す。どぎつくポップな色彩で彩られ、ペラペラの紙で複製されて「薄さ」を強調されたそれらは、二頭身のキャラクターに内在する「不気味さ」を剥き出しにし、イメージの大量生産と消費が夥しい「亡霊」を生み出していることを突きつける。また、林勇気は、パソコンのハードディスクやネット上に大量に蓄積された写真画像を用いて、1コマずつ切り貼りして緻密に合成し、アニメーションを制作している映像作家である。出品作《すべての終りに》は、これまでにない暴力性を感じさせるものであった。食べ物、車、植物、ペットボトル、家電製品などの夥しい画像が、視認不可能なほどの高速で接合され、伸縮自在に変形し、輪郭が溶解し、暴力的なまでに切り刻まれ、遂には渦まく砂嵐となって画面を覆う。そして、画像の断片が星くずのように瞬きながら暗闇に散らばって集合離散を繰り返すラストは、消滅か、新たな再生の予兆か。夥しい量の画像が、ネットの共有空間上でコピー・複製され、共有され、拡散するとともに撹拌・かき混ぜられてキメラ化し、瞬く間に消費されて消滅していく。その美しくも暴力的な様相を、宇宙の生成と消滅を思わせる映像として可視化していた。
2016/03/19(土)(高嶋慈)
降り落ちるものを 今村遼佑

会期:2016/03/08~2016/03/20
アートスペース虹[京都府]
なんとも詩的なタイトルに、詩的なインスタレーション。「降り落ちるもの」、つまり時間の流れや変容を感じさせる作品が、視覚、音、匂い、手触りを刺激させながら、ゆるやかな連想を描くように配置されている。
白い地に、白や灰色、クリーム色、薄いブルーや黄色の筆致が舞うように散る絵画作品は、雪が雨粒へと変化していく様子を描いたもの。大きな雪片に見える白い塊が落下する絵画は、ハクモクレンの花びらが散る情景を描いている。雪解けと花びらの落下。冬から早春へ。その季節の移り変わりは、沈丁花が植えられた植木鉢と呼応する。白い小さな花が放つ、甘くかぐわしい香り。舞い落ちる雪が感じさせた、張りつめた空気の冷たさが、ゆるやかにほどけていく。
一方、沈丁花の植木鉢には、ミニチュアの街灯が添えられている。街灯の灯る夜の帰宅路、視覚よりもまず匂いで沈丁花に気づいたときの記憶がよみがえる。日常の中で、ふと訪れる情景の変化。別の作品では、ポリバケツの中に置かれたiPhoneの画面に、バケツに張った氷が映っている。突然、小石が投げ込まれ、ひび割れる氷の表面。液晶画面が薄い氷の層と一瞬、重なり合う。もうひとつのiPhoneの画面は、どこかの住宅の窓辺を映し出すが、静止画のように変化しない画面のフレーム外から聴こえる音が、さまざまな情景をかき立てる。車の音、子どもの遊び声、どこかから聴こえる美しいピアノ曲。日常にふと差し込んだ劇的な瞬間は、室内外の生活音にかき消されていく。傍らに吊られたカーテンが、画面の内と外、ギャラリー空間と「ここではないどこか」との境界を、一瞬、曖昧に溶解させる。
季節の変わり目が、肌で感じられながらも明確な境目として区切られないように、今村の作品世界は、部屋の内と外、昼と夜、「いま」と記憶の中の手触り、「ここ」と「どこか」が一瞬混じり合って溶け合うような体験をつくり出す。それは、仕掛けやガジェットを見せながらも、イメージの多重化や現象的なものを扱い、複数の異なる時間の流れをひとつの空間の中に呼び込み、観客の身体と五感をとおして体感させるという点で、人物は不在であっても、ある種の演劇性をたたえていると言えるかもしれない。
2016/03/13(日)(高嶋慈)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)