artscapeレビュー
山﨑健太のレビュー/プレビュー
青年団リンク やしゃご『てくてくと』

会期:2021/04/17~2021/04/27
こまばアゴラ劇場[東京都]
伊藤毅が作・演出を務める青年団リンク やしゃごはその前身である青年団若手自主企画伊藤企画時代から、障害者とその周囲の人々を繰り返し描き続けてきた。最新作のテーマは「発達障害グレーゾーン」だという。
舞台は事務所に工場、直売店が併設された「コグマ製菓」の休憩室。障害者雇用で働く間宮(藤尾勘太郎)はようやく仕事に慣れてきたところだが、本当はパソコンを使った仕事をしたいと思っている。同じく障害者雇用で働く中本(井上みなみ)は小学生の工場見学でなぜか特技のルービックキューブを披露することに。一方、二人のジョブコーチの猿手(とみやまあゆみ)は、自らの仕事のできなさに落ち込む新入社員・八幡(石原朋香)の様子を見て相談に乗れるかもしれないと申し出る。八幡は猿手の勧めに従い発達障害の診断を受けるが結果はグレーゾーンで──。
 [撮影:田中流]
[撮影:田中流]
「発達障害グレーゾーン」は「発達障害の特性があるが、診断基準は満たさない状態を指す通称」。当日パンフレットには「診断基準を満たす場合と比べ困難は少ないと思われがちだが、理解や支援が得られにくいなど、グレーゾーンならではの悩みもある」という解説も付されている。自分は発達障害だからこんなにも仕事ができないのだと折り合いをつけようとしていた八幡はその結果が受け入れられず「こんなに困ってるのに」「私普通なんですか?」「私は発達障害になりたかったんです」と感情を爆発させる。
八幡のあんまりな発言に「中本に失礼ですよ」と怒り出す工場ライン長の犬塚(佐藤滋)。それにもちろん、たとえ発達障害だという診断が下されたところで八幡の抱える困難のすべてが解決するわけではない。上司の綿引(中藤奨)は障害者雇用だと給料が安く、発達障害では障害者年金ももらえないという現実を八幡に突きつける。だから自分はクローズで(=障害のあることを伏せて)就職したのだと。「八幡さんは、出来ると思ってたことが出来なくて、駄々こねてるだけです」。
綿引の怒りの矛先は犬塚にも向かう。犬塚は中本に自らの妹の姿を重ねて見ているらしい。工場見学で中本にルービックキューブを披露させることを提案したのも犬塚だ。何かと中本を構う犬塚に綿引は「中本さんのことどう思ってるんですか?」「かわいそうだと思ってるんでしょ?」「思ってるから、あんな構うんですよ」「どっちが失礼なんだ」と畳みかける。その言葉は中本が猿手との面談で発した「私を助けてくれるから」「言われてる気がする。お前が悪いって」という言葉とも呼応するだろう。
 [撮影:田中流]
[撮影:田中流]
「障害」は個人の性質ではなく周囲の環境との関わりなかに生じるものだという考え方がある。八幡の両親は家業であるケーキ屋を手伝う娘の「できなさ」を本人には「言えなかった」。結果として八幡は外で働くようになってはじめて自分の「できなさ」と向き合うことになる。両親の選択は「正しかった」のか。
一方、事務所で働く牧野(岡野康弘)と直売店で働く小渕(木崎友紀子)の娘は去年から学校に行っていないらしい。「私は別に自由にしたらいいと思うんだけど」「逃げられるんだったら、逃げた方がよくない?」と小渕は言うが、夫の牧野はフリースクールに通うことには前向きではないという。不登校の理由は明かされないのだが、小渕は八幡を「ピッコロ」と中学時代のあだ名で呼ぶ山下(辻響平)に「それって、いじめじゃないの?」「もう呼ぶのやめなね」と厳しい。山下は八幡が「嫌がってた前提じゃないですか」と反発するが、「ピッコロ」が『ドラゴンボール』に登場する全身緑色の宇宙人に由来するあだ名であることを考えれば八幡がそう呼ばれることを嫌がっていた可能性は高いだろう。しかし八幡と同期の小湊(赤刎千久子)は「ぴっころ」を『にこにこぷん』に登場するしっかり者の女の子ペンギンのことだと勘違いし、落ち込んでいた八幡を励まそうとして「ぴっころ」を連呼してしまう。
 [撮影:田中流]
[撮影:田中流]
伊藤の筆は残酷なまでに公正だ。人も行為も出来事も、単純な善悪に振り分けることを許さない。コグマ製菓の人々に工場見学に訪れる小学校の先生・植田(緑川史絵)を加えた11人の登場人物の間に生じるいくつもの小さな出来事を通して、伊藤は観客の感情と思考を揺さぶり続ける。中本は「ちゃんと言ってくれないとわからなくて、すいません」と曖昧な会話の意図を汲み取れないことを詫びるが、翻って犬塚は、山下は、小湊は、あるいは私は、どこまで相手の気持ちを理解できているだろうか。
結局、八幡は「もうちょっと頑張ります」と自分にできることを探しはじめる。工場見学でのルービックキューブの披露は無事に成功し、中本自身も嬉しそうにしていたらしい。犬塚の暴走にも見えた提案は、結果としてはよかったことになる。間宮はひとつ仕事が終わるたびにスタンプカードにシールを貼っている。それは「自分は間違ってない」と安心できるからだ。誰もが正解のない問いに向き合い、誰かに「間違ってない」と言ってもらいたいと思いながらときに間違い、それでも日々を「てくてくと」一歩ずつ進んでいく。そうやって進んでいくことだけは「間違ってない」。エピローグで間宮が八幡と犬塚に差し出すシールはどこまでも優しい。
青年団リンク やしゃご:https://itokikaku.jimdofree.com/
関連レビュー
青年団リンク やしゃご『上空に光る』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年10月15日号)
2021/04/23(金)(山﨑健太)
グループ・野原『自由の国のイフィゲーニエ』

会期:2021/04/03~2021/04/11
こまばアゴラ劇場[東京都]
グループ・野原は演出家の蜂巣もも、舞台美術の渡邉織音、俳優の岩井由紀子と串尾一輝からなる演劇を上演するための集団。2017年にどらま館ショーケースに参加した『愛するとき死ぬとき』(作:フリッツ・カーター)の上演で活動を開始して以降、蜂巣の個人企画であるハチス企画名義での公演と合わせて三好十郎やベケットなど国内外のさまざまな戯曲を上演してきているが、グループ・野原名義での単独公演は今回が初となる。
『自由の国のイフィゲーニエ』は東ドイツ時代、「国家公認の作家でありながら、体制批判者と見なされ」「古典作品のモチーフに当時の事件や流行語を細かく織り交ぜる手法で、国家の検閲を回避し散文や詩を発表してい」(当日パンフレットより)た作家フォルカー・ブラウン(1939-)が87年から91年にかけて、つまりベルリンの壁崩壊と東西ドイツの統一を挟んで執筆し92年に発表した戯曲。四つの場面からなる戯曲はギリシア悲劇を下敷きにして書かれているが、ト書きや役名は一切記されておらず、複数の人物の言葉(と思しきもの)が渾然一体となって台詞を構成している。例えば「1. 鏡のテント」は愛人と共謀して父アガメムノンを殺した母クリタイムネストラへの復讐を計画する姉エレクトラと弟オレスト(オレステス)の対話のように読める。だが、戯曲と作者による注解にそれぞれ登場する「エレクトロレスト」「オレステレクトラ」という名は、姉弟が別個の人格としてではなく、分裂を抱えたひとつの人格として想定されていることを示唆する。「民衆(フォルク)/俺はフォルカーだ」というセリフはさらに、言葉を発する主体としての作者自身の姿をも投影するだろう。四つの場面にはほとんどつながりもなく、ギリシア悲劇に関する知識がなければそこで何が語られているのかを理解することも難しい。グループ・野原の上演では当日パンフレットに各場面のあらすじと登場する人物に関する説明を記載することで観客の理解の助けとしていた。
今回の上演ではしかし、言葉の主体には比較的シンプルなアイデンティティが割り当てられていた。最初の2場では言葉がその主体となる(と思しき)人物ごとに俳優に振り分けられ、「1. 鏡のテント」では岩井がエレクトラを、串尾がオレストを、「2. 自由の国のイフィゲーニエ」では1場と同じく串尾がオレストを、日和下駄がその友人ピュラデースを、岩井がオレストの姉イフィゲーニエを、田中孝史がイフィゲーニエを保護した敵国の王トーアスを演じていたと言って差し支えないだろう。
 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
一方、このような配役によって失われた戯曲の複雑さは空間によって担われていたように思われる。グリーンバック(映像撮影において後から背景を合成するために使用される緑色の背景)のような舞台美術に覆われた空間はアナログとデジタルの入り混じったような質感で、その緑色が果たして地の色なのか照明によるものなのかも判然としない。そこに立つ俳優たちもまた、仮想空間に立つアバターのようにも見えてくる。1場での俳優たちのふるまいがその連想を強化する。エレクトラと対話するオレストの背後には二人の男(日和と田中)が影のように付き従い、エレクトラの言葉に反応するかのような彼らの身体の動きは次第に同調していく。独裁者の言葉に煽動されていく民衆。あるいは、SNS上の炎上に群がる匿名アカウント。同じ世界に生きながら、分断された私たち。
 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
2場では同じグリーンバックの空間が一転してオレストらにとっての敵国であるトロイアはタウリス島となる。仮想空間=演劇的なそのふるまいは、しかし同時に、ひとつの空間をミュケナイとトロイアに引き裂くことでもある。それはミュケナイからトロイア、そして再びミュケナイへと自らの仕える先を変えざるを得なかったイフィゲーニエが背負わされた分裂でもあるだろう。
「強制収容所(大量死)でもあり、スーパーマーケット(大量生産)でもある場所に、死んだ兄をショッピングカートに乗せたアンティゴネーがやってくる」と説明される「3. 野外オリエンテーリング」ではラジコンのトラックが舞台上を走り回り、その荷台から言葉が聞こえてくる。スーパーに物資を運ぶトラックは同時にショッピングカートのようでもあり、その荷台には劇場が載せられている。ならば劇場が発するのは死者の言葉だろうか。ラジコンを操作するのは舞台袖に立つ日和だ。空間はその外部の論理によってコントロールされている。
 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
「4. 古代の広間」にはギリシア悲劇の人物の名は登場しない。舞台に立つ日和は何者でもないようで、発される言葉は誰かの台詞というよりはただの言葉のようにして浮かぶ。ほかの三人の俳優が舞台に現われるとストレッチをはじめ、やがてまた去っていく。それは演劇の終わりであると同時にはじまり、あるいははじまり以前のようでもある。劇場を去る観客に手渡されるポストカードには「古代の広間」の声や音にアクセスできるQRコードが記されている。グループ・野原によって劇場に持ち込まれた言葉は、観客によって再び劇場の外部へと持ち出され、いつか解凍されるときを待つ。
 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
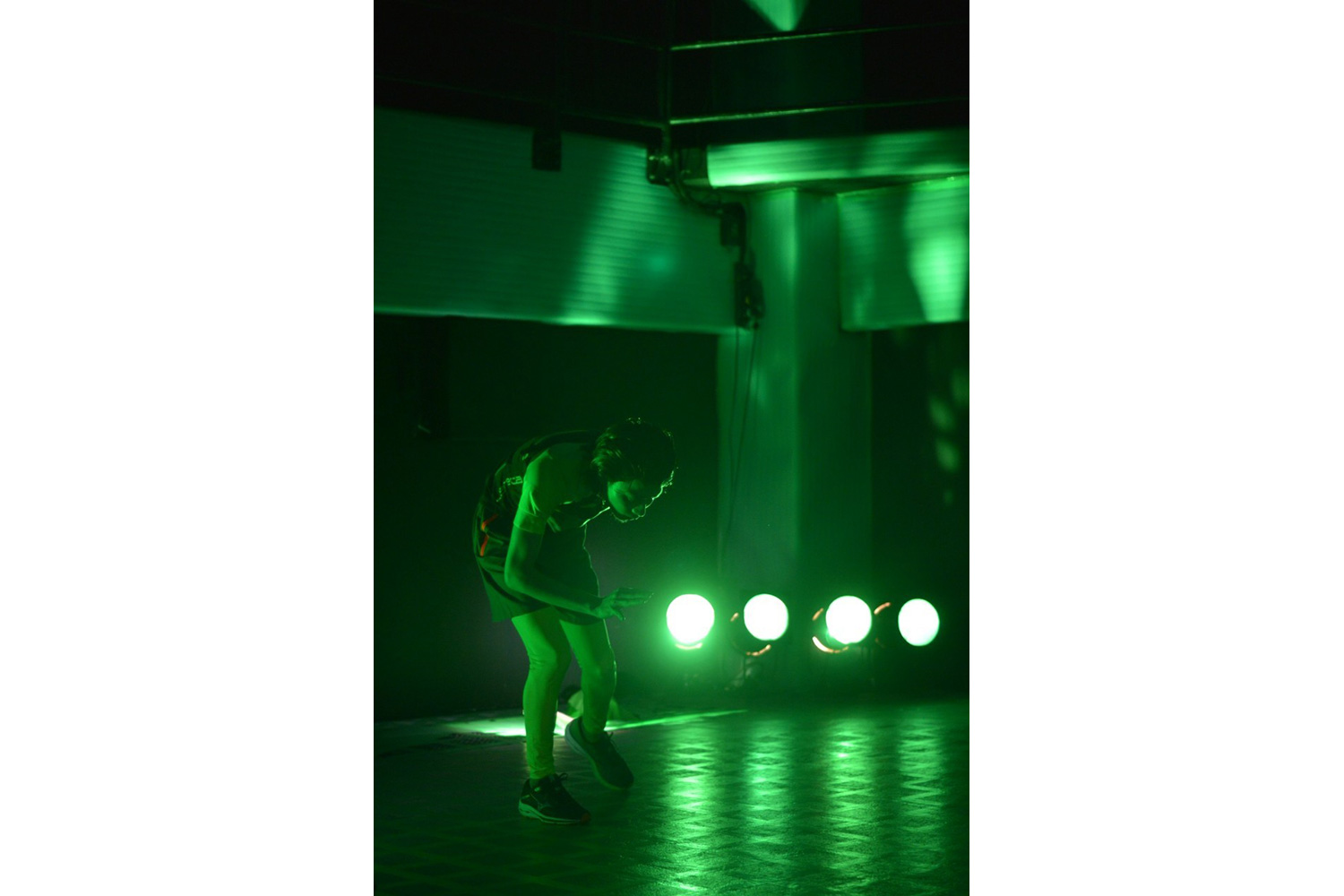 [撮影:渡邉織音]
[撮影:渡邉織音]
グループ・野原:https://groupnohara3.wixsite.com/website
ハチス企画:https://www.hachisu-kikaku.com/
関連レビュー
青年団若手自主企画vol.79 ハチス企画『まさに世界の終わり』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)
2021/04/07(水)(山﨑健太)
劇団ドクトペッパズ『ペノシマ』

会期:2021/03/25
花まる学習会王子小劇場[東京都]
劇団ドクトペッパズの新作人形劇『ペノシマ』が2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル参加公演として上演された。以前「アジア児童青少年舞台芸術フェスティバル2018」で上演された『うしのし』と同様、子ども向けの枠組みでの上演ながら、影絵や映像を組み合わせつつ人形劇というメディアならではの趣向を凝らした舞台は、子どもだけでなく多くの観客に見られるべき完成度となっている。
「ストーリー」として事前に公開されていた情報は次の通り。「遠い海の向こう、ポツンと浮かぶ南の島に、小さな洞穴が一つ。その中を覗くと、バラバラの『骨』が落ちていた。一体これは誰の骨で、なぜこんなところにあるのか? 物語の時間は逆転を始め、骨たちが動き始める…」。舞台は洞窟内部のような設え。スクリーンのようになっている舞台奥の壁面に洞窟内部に分け入っていくような影絵が映し出されたかと思うと二匹の蝶が舞い、Welcomeとピンクのネオンサインが点灯して上演がはじまる。



ブラックライトに照らされ光る骨は舞台上をコミカルに動き回りながら自らのパーツを収集し、ほぼ完全な(しかし一方は片腕の)二人分の骸骨となる。やがて上空を鳥の群れが通過し大量の糞が降り注ぐと、一方の頭蓋骨がパカっと開き、糞の中の種が芽吹くように人間の頭部が現われる。その後、頭上から降り注いだ肉片を組み合わせることで人間の形をなした二人は果実を食べることで言葉と恥の概念を獲得しますます人間らしくなっていくが、自分たちが何者かを思い出すことができない。洞窟内で発見された将棋盤の裏には「花園」と「前野」の名。どうやらこれが自分たちの名前らしい。将棋に負けた前野が食糧の調達に出かけていくが、戻ってきた彼は軍服を着ていて──。

こうして、この作品はどうやら太平洋戦争を背景としたものだということが明らかになる。劇中で明示されるわけではないがタイトルの『ペノシマ』はペリリュー島を指すものだろう。パラオ諸島に位置するペリリュー島では太平洋戦争中の1944年の9月から11月にかけ、日本軍とアメリカ軍との陸上戦があった。洞窟などに潜みつつゲリラ戦を展開した日本軍は2カ月の戦闘の末に敗北。しかし日本軍の生き残りはその後も島内の洞窟に潜伏し続け、1947年になってようやく帰順することになる。
洞窟に残された人骨が自らの来歴を「思い出す」過程とはつまり、戦争によって失われた個人の生を「再生」する過程であり、だが同時に、死に向かう彼らの最期の時を「再生」する過程でもある。自分たちが何者であるかを彼らが思い出すとき、影絵の鳥は反転して戦闘機となり、再生のきっかけとなった鳥の糞は死をもたらす爆撃となる。表裏一体の生と死。
ところで、劇中にはしばしば、Welcomeのネオンサインが点灯するとともに時間が巻き戻り、パラレルワールドのように異なるバリエーションの短いシークエンスが展開される場面が挿入される。それは何とか生き残ろうとする彼らのあがきのようにも見えるが、いずれにせよ死という最終的な結末は変えられない。だが、この作品の上演自体がWelcomeのネオンサインの点灯とともにはじまったことを考えれば、そこに働く想像力は彼らのものではなく私のものだと考えた方がよさそうだ。残された骨は何も語らない。遺品や遺された証言もすべてを語るわけではない。想像は想像でしかない。だがそれでも、欠落を埋めることは決して叶わないと知りながら、なお繰り返し想像しようとしてみること。

『ペノシマ』は今回、フェスティバルの枠組みのなかでの1回のみの上演であり、残念ながら限られた人数の観客しか目撃することができなかった。ドクトペッパズのほかの演目と同じようにレパートリーとして再演されていくことを期待したい。Welcomeのネオンサインが点灯するたび、魂は蝶となって還り彼らは動き出すだろう。
「ペリリューの戦い」については、近年では武田一義が史実を参照したフィクションとして漫画『ペリリュー─楽園のゲルニカ─』を描き2017年度の日本漫画家協会賞優秀賞を受賞、2021年4月の連載終了(最終巻は7月末発売)とともにアニメ化が発表されている。大川史織編著『なぜ戦争をえがくのか』には武田と担当編集者の高村亮のインタビューも収録されており、フィクションを通して戦争に触れることについて考えるためのさまざまな示唆を与えてくれる。
劇団ドクトペッパズ:https://dctpeppers.wixsite.com/mysite
関連レビュー
劇団ドクトペッパズ『うしのし』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年04月01日号)
2021/03/25(木)(山﨑健太)
高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』
会期:2021/03/04~2021/03/11
ニュー新橋ビルおよび新橋駅周辺[東京都]
シアターコモンズ'21で上演された高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』は東日本大震災の翌年、フェスティバル/トーキョー12でPort B『光のないⅡ』として上演された作品の「リクリエーション再演」。10枚組のポストカードとポータブルラジオを手にした観客がひとりずつ新橋の街を巡るというツアーパフォーマンスの形式とそれが辿るおおよそのルートは初演と変わらなかったものの、観客が立ち止まることになるポイントとそこで対峙するものの変化は作品の印象に大きな違いをもたらすことになった。それは同時に、震災から10年という時間が否応なく私にもたらした変化でもあっただろう。
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
10枚組のポストカードにはそれぞれ表面に報道写真が、裏面に次のポイントまでのルートが記されていて、観客はそれを見ながら新橋駅周辺の10のポイントを巡っていく。ポイントに着いた観客はポストカードの裏面に記された周波数にラジオを合わせ、そこから聞こえてくる音声に耳を傾ける。聞こえてくるのはオーストリアの劇作家エルフリーデ・イェリネクが震災と原発事故に応答するかたちで発表した一連の戯曲の一作、『エピローグ?』[光のないⅡ]を読み上げる訥々とした声。クレジットによればそれはいわき総合高校演劇部の生徒の声らしい。
10のポイントで待っているのは潜在する不可視の声だけではない。例えば、福島のものと思われるひび割れた地面を写したポストカードは私を東京電力本社の向かいにある内幸町広場に導く。そこには特別なものは何も置かれていないのだが、広場のタイルは報道写真に写る地面と似た、ひび割れたような文様を描いている。その類似が私のいる新橋と遠く福島とを無理矢理につなげてみせる。あるいは雑居ビルの一室には、報道写真に写るもぬけの殻の布団が敷かれた暗い和室の様子が「再現」されている。ある種のインスタレーションのようなその空間はしかし、報道写真に写る光景を模したものであることは明らかなものの、最初からリアルな再現は目指されていないようなおざなりな作りであり、その「再現できてなさ」が私に自らのいる新橋と福島との距離を、そこにある断絶を突きつける。
しかしこれらは私の記憶に残る初演の話だ。今回の再演では空間の再現はなく、各ポイントにはポストカードに印刷されたものと同じ報道写真、あるいはそこに写し出された場面を含む動画が配置されていた。あるものはショーウインドウの中に、あるものは引き伸ばされて高架下の壁面に、またあるものは駅前のSL広場のディスプレイに。ひとつを除いて公共の空間に配置されたそれらは行き交う人々の注目を集めることもなく街に溶け込み、ラジオを持った観客に「発見」されるのを待っている。
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
異物であるはずの報道写真が街に溶け込んで見える理由のひとつは、そこに写っているマスクをした人々の姿や防護服が、2021年の東京を生きる人々にとっては見慣れたものになってしまったからだろう。たまたまそこを通りがかった人々の目には、それらの写真は単に「現在」を写したものと見えたのではないだろうか。
ツアーパフォーマンスの観客もまた、現在の磁場から逃れることはできない。受付でラジオとポストカードを受け取った私が最初のポイントで出会うのは、防護服を来たジャーナリストと思われる人物が鏡に向き合うかたちで自分を撮影した写真だ。浪江の文字が刻まれた鏡越しには住民が避難した後と思しき民家の光景が見える。写真が置かれたカメラ屋のショーウインドウは奥の壁面が鏡になっていて、写真を見る私は自然と写真の人物と同じように鏡に対峙することになる。そこに映し出されるのは写真の人物と同じようにマスクをした私自身の姿だ。このことは、報道写真に写る光景と2021年現在の私を取り巻く状況との「類似」を強烈に印象づける。ラジオから聞こえる「目に見えない」「触れるのも余計なこと」などの言葉がさらにその印象を強化する。放射能について述べたものであるはずのそれらの言葉を現在の自分を取り巻く状況に引きつけるほどに、福島第一原発事故は遠ざかる。
今回の再演では内幸町広場は立ち止まるポイントに指定されていなかった。第3のポイントに向かう私は最短経路ではなく、マップの指示通りに大回りのルートを通る。かつて大勢の警備員を目撃した東京電力本社前を通り過ぎ、福島の遠さに愕然とした内幸町広場を通り抜ける。そうやって「通り過ぎさせられる」ことで私は、通り過ぎてしまったことすら意識してこなかった場所を、時間を、ものごとを思う。
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
 © シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
© シアターコモンズ ’21[撮影:佐藤駿]
『光のない。─エピローグ?』:https://theatercommons.tokyo/program/akira_takayama/
Port B:http://portb.net/
2021/03/06(土)(山﨑健太)
百瀬文『鍼を打つ』

会期:2021/03/06~2021/03/10
SHIBAURA HOUSE 5F[東京都]
「喉の奥に痛みがある」「頭痛がある」「ため息が多い」「頭の中が雲で覆われているような気分になることがある」「平熱が37.0°C以上である」。問診票の言葉を読む私は一行ごとに「さてどうだろうか」と自分自身の状態を省みる。即答できる項目もあればしばしの検討を要するものもあり、あるいはときにそんなことは考えたこともなかったという予想外の問いが含まれていたりもする。それらは普段は意識していない「自分」の姿を浮かび上がらせる。
百瀬文『鍼を打つ』のメインビジュアルとして使用されていたイラストには、水に浮かんだ裸体のあちこちにピンが刺さっている様子が描かれていた。それはもちろん鍼の施術を思わせるものではあるのだが、水面からのぞく体の部分は同時に海に浮かぶ島のようでもあり、イラストの全体が地図のようにも見えてくる。小さな赤い球体を頭につけたピンは地図上の一点を指し示す印だ。だとすれば鍼の施術は、問診票によって把握された「状態」を人体へとマッピングしていく作業だということになるだろう。問診票の言葉は私の体の任意の点へと変換され(実際には単純な一対一の対応ではないのだろうが)、鍼によってそこには印が刻まれていく。
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
『鍼を打つ』ではまず、6枚の問診票に回答するように言われる。冒頭に記したのはその最初の五つだ。「問い」の多くは体調や生活習慣に関する一般的なものだが、なかには「よく黒い服を好んで着る」「他人に迷惑をかけてはならないと強く思う」など、鍼治療にどのように関わるのかよくわからない問いも含まれている。「過去と未来を行き来している」「時間をかけてようやく思い出す」などに至っては意味も判然としないが、いずれにせよ私は当てはまるものにチェックマークをつけていく。
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
ひと通り回答を終えると施術台に置かれたイヤフォンを装着し、鍼師が来るのを待つ。しばらくするとイヤフォンから声が聞こえてくる。それは先ほど私が記入した問診票の言葉だ。しかし語られる順序は問診票のそれとは違っている。「心臓がドキドキすることがある」「風邪をひきやすい」「咳が止まらなくなることがある」。やがて鍼師がやってきて、横たわるよう促され施術が始まる。声はときに沈黙を挟みながら、施術が終わるまで淡々と続く。
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
問診票では一行ずつ独立していた言葉たちは、異なる順序で語られることでときに物語のようなものを浮かび上がらせる。「視界がぼやける」「かつて海にいたことがある」「耳がつまり、くぐもって聞こえることがある」「ものの輪郭より、色のかたまりがまず先に見える」「国境はなくてもいいと思う」あたりは海中の世界を思わせるし、「地図がないと道がわからない」「点と点のあいだに線を結びたがる」「大地が揺れているように感じる」「歯がぐらぐらする」という言葉の連なりは地図を媒介に大地と私の身体の感覚とを直結させる。
しかしそのような連想はあくまで事後的に生じたものに過ぎない。声に耳を傾けているその瞬間ごとの私にできるのは、「問い」の一つひとつに改めて向き合うことだけだ。私はすでに、いくつかの「問い」に対してどのように答えたかを忘れてしまっていることに気づく。答えた記憶さえない「問い」もある。私は声が語り直す問診票の言葉に導かれ、すでに失われてしまった少し前の私を探しているような気分になる。
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
鍼を初めて体験する私はひどく緊張していて、施術箇所に意識を集中するあまり、気づけばしばしば声の語る言葉を聞き逃している。その都度、意識を声へと向け直すのだが、すると今度は体への意識が疎かになり、いつしか施術箇所は移っている。『鍼を打つ』はそのような、声への意識と体への意識の綱引きの体験として私には感覚された。
ところで、問診票の言葉は厳密には「問い」ではない。誰かによって用意されたその言葉は疑問文ではなく、断定のかたちで書かれていた。問診票はその形式によってそこに記された平叙文に「問い」としての機能を付与する。だが、声によって語られる言葉をそのまま受け取るならば、主語こそ欠落してはいるもののむしろそれゆえに、それは声自身についての言明として解釈されるはずだ。「他人が何を考えているのかわからないことが多い」「青あざができやすい」「特定の職業に対する偏見がある」。自問自答を引き起こす私への問診は、一方で見知らぬ誰かと同調するポイントを探る作業でもある。
誰かによって用意された問診票の言葉は私のすべてを把握するにはまったく十分ではなく、そうして捉えられる私の姿は夜空の星を結ぶことで浮かび上がる星座程度の解像度しかない。だが一方で、それはたしかに私には見えていなかった私自身の一端を示してもいるのだ。「他者がいなければ自分のかたちを決められない」。「上から自分を見下ろしているような気分だ」。声は最後に私を突き放す。「時間をかけてようやく思い出す」。「これは自分の体ではない」。
 [©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
[©シアターコモンズ ’21/撮影:佐藤駿]
『鍼を打つ』:https://theatercommons.tokyo/program/aya_momose/
百瀬文:http://ayamomose.com/
関連レビュー
百瀬文「I.C.A.N.S.E.E.Y.O.U.」|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年02月01日号)
2021/03/06(土)(山﨑健太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)