artscapeレビュー
山﨑健太のレビュー/プレビュー
ロロ『ここは居心地がいいけど、もう行く』
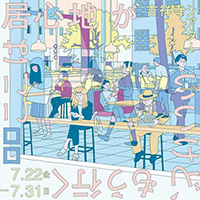
会期:2022/07/22~2022/07/31
吉祥寺シアター[東京都]
学校という空間の時間は螺旋状に流れている。授業や毎年の行事は繰り返しのようでいながら少しずつ違っていて、その担い手となる生徒たちもたとえば3年という定められた期間とともにその場所を通過していく。教師だけが例外だ。
ロロ『ここは居心地がいいけど、もう行く』は2021年に全10話をもって完結したいつ高シリーズのキャラクターが再び登場する新作。吉祥寺シアターでの公演は7月31日で終了したが、8月28日まではアーカイブ配信が視聴できる。以下の文章には重大なネタバレが含まれるので注意されたい。また、いつ高シリーズ未見でも十分に楽しめる作品ではあるが、作中にはシリーズを知っていることでより楽しめる仕掛けもいくつか用意されている。いつ高シリーズの戯曲は多くがWEBで無料公開されているのでそれらを(特にvol.6とvol.2を)読んでから配信を観るのもいいかもしれない。vol.6『グッド・モーニング』については映像も8月28日まで無料公開されている。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
舞台は文化祭当日。旧校舎の屋上に続く階段の踊り場ではダブチ(新名基浩)と机田(大石将弘)が本番の迫ったコントの練習をしている。しかし何やら屋上に出入りする悠(島田桃子)が行き来し、白子先生(大場みなみ)がやってきては茶々を入れとなかなか練習は進まない。悠は旧校舎の屋上から旧々校舎の屋上へとこっそり何かを移動させようとしているらしいが、旧々校舎の屋上に続く踊り場では息子のコントを見に来て校舎を間違えた(逆)おとめ(望月綾乃)と鉢合わせてしまう。物語はダブチと机田のコント、悠の隠し事、そしてかつてこの高校の生徒だった白子と(逆)おとめの再会という三つの筋が絡み合いながら進んでいく。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
高校生が演じることを念頭に、高校生だけが登場する作品として書かれたいつ高シリーズは、高校生のスケールの世界を立ち上げながらその少しだけ外側を指し示すような物語だった。対して、かつて高校生だった大人とこれから大人になる高校生を描いた『ここは居心地がいいけど、もう行く』は、螺旋状の時間の異なる2点を並べることで、自分がいない/いなかった時空間への想像力をより強く喚起する作品になっている。あるいはそれは、この作品とも深い関係のあるいつ高シリーズvol.2『校舎、ナイトクルージング』で描いたものをさらに大きなスケールで描いているのだとも言えるかもしれない。
いつ高シリーズでは高校生だった白子と(逆)おとめは大人になり、片や教師に、片や生徒の親になっている。そこにあるのはシリーズを追ってきた私が知るいつ高でありながら、しかし同時にもはやまったく別の場所だ。ダブチ、机田、悠の向こうには同じ俳優によって演じられたかつてのいつ高の生徒たち(シューマイ、楽/水星、朝)の姿が透けて見えるが、それもまたシリーズを追ってきた私の勝手な感傷でしかない。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
時間の経過は否応なく人を変えていく。かつてはおどおどとして学校にもほとんど通っていなかった(逆)おとめはローカルラジオのディレクターとして働くようになった。一方の白子はあまり変わっていないようにも見えるが、最近は同居する親の視線が気になって家出をし、学校に寝泊まりしているらしい。だが、(逆)おとめと再会した白子は突然、家を買うことを決意する。大きく変わった(逆)おとめと、その変化に触れて変わろうとする白子。生徒たちと同じように大人もまた悩み、変わっていく。
(逆)おとめの存在は生徒たちにも、いや世界にも影響を与えている。(逆)おとめが担当するラジオ番組「グッドモーニングレディオ」のヘビーリスナーである悠は、同じく番組のファンだという「友達」が、20年以上前に(逆)おとめが深夜の校舎に忍び込んで発信していた誰にも届かないかもしれないラジオ番組を好きでずっと探していたのだと言い出す。悠とともに先々週、地球を救った(!)というこの「友達」の正体は実はエイリアンなのだが、遠くから電波の波形を見ていたというエイリアンが20年以上前の(逆)おとめのラジオ番組を探していたということを踏まえれば、エイリアンが地球にやってきたのは(逆)おとめのおかげだということになる。ならば誰にも届かないかもしれなかったラジオが遠く宇宙に届き、時間を超えて地球を救ったのだ。のみならず、エイリアンはダブチと机田のコントにも3人目のメンバーとして参加することになる。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
ここでは学校に通えず中退することになったかつての(逆)おとめが、そして彼女の誰に届かずとも何かを発信しようとする気持ちが強く肯定されている。もちろん、誰にも届かないことは苦しいかもしれない。ダブチと机田のコントの1回目の上演にはひとりの観客も現われず、ダブチはくじけそうになる。だが、ダブチの書いた台本は(不本意ではあるかもしれないが)母親である(逆)おとめに、そしてエイリアンに読まれ演じられることになるだろう。そして2回目の上演には何人かの観客が現われるかもしれない。自分の存在がいつ、誰に、どのように影響を与えるかは誰にもわからない。それでも、発せられた電波の波形は地球を救うかもしれない。そう思ったっていいのだ。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
ロロ:http://loloweb.jp/
いつ高シリーズ:http://lolowebsite.sub.jp/ITUKOU/
いつ高シリーズvol.7『本がまくらじゃ冬眠できない』映像(STAGE BEYOND BORDERS):https://stagebb.jpf.go.jp/stage/itsukou-series-vol-7-i-cant-hibernate-with-books-as-a-pillow/
関連レビュー
ロロ『とぶ』(いつ高シリーズ10作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月01日号)
ロロ『ほつれる水面で縫われたぐるみ』(いつ高シリーズ9作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年09月01日号)
ロロ『心置きなく屋上で』(いつ高シリーズ8作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年10月01日号)
ロロ『本がまくらじゃ冬眠できない』(いつ高シリーズ7作目)|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年12月01日号)
2022/07/25(月)(山﨑健太)
PLAY/GROUND Creation #3『The Pride』

会期:2022/07/23~2022/07/31
赤坂RED/THEATER[東京都]
俳優主体の創作活動のために井上裕朗が立ち上げたPLAY/GROUND Creationの#3として『The Pride』が上演された。2008年にロンドンで初演された『The Pride』は俳優として長く活動したアレクシ・ケイ・キャンベルが劇作家に転身しての第1作。日本では2011年にTPTが小川絵梨子の演出で『プライド』というタイトルのもと初演している。今回は日本初演時にも翻訳を手がけた広田敦郎を翻訳・ドラマターグに迎え、井上の演出での上演となった。なお、公演はダブルキャストとなっており、キャストはA/Bの順で併記している。
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
物語はオリヴァー(井上裕朗/岩男海史)とフィリップ(池田努/池岡亮介)の出会いの場面からはじまる。児童文学作家のオリヴァーは本の挿絵を担当するシルヴィア(陽月華/福田麻由子)の計らいで彼女の夫・フィリップと三人で食事をするために二人の家を訪れる。出迎えたフィリップと挨拶を交わすオリヴァー。初対面ゆえかのぎこちなさもありながら会話は和やかに進み、やがて着替えを終えたシルヴィアも合流する。しばしの歓談の後、予約したレストランへと出かけていくところでこの場面は終わる。
暖色の照明が白々とした明かりへと変わり、次の場面になると舞台の中央でナチスの制服を着た男(鍛治本大樹/山﨑将平)が「お前は何だ」「この変態のメスブタ」とオリヴァーを責め立てている。いまいち乗りきれずプレイを中断したオリヴァーが男と話していると、3日前に別れて家を出ていったフィリップが荷物を取りに戻ってきてしまう。慌てたオリヴァーは男を追い出し自らの行ないを弁明するが、フィリップは再び出ていく。
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
パラレルワールドのような二つの場面は(上演中に明示されることこそないものの)それぞれ1958年と2008年の出来事であり、この作品では同じ名前を持つ三人の人物が生きる二つの時代が交互に描かれていくことになる。
1958年のフィリップはオリヴァーと惹かれ合い関係を持つ。以前からフィリップの苦悩に気づいていたシルヴィアは二人が関係を持ったことを知り、傷つきながらも二人の幸せを気にかける。だが、二人の間にあるものを愛だと言うオリヴァーの説得も虚しくフィリップは同性愛を「倒錯」と退け(それは当時の「常識」である)、「治療」のために医者(鍛治本/山﨑)にかかることを選ぶのだった。
一方、2008年のフィリップはオリヴァーが見知らぬ男と頻繁に関係を持ってしまうこと(本人曰く「中毒」)に耐えられず別れを選択する。フィリップと共通の友人でもあるシルヴィアはオリヴァーを慰め諭すが、イタリア人のマリオという恋人がありながらオリヴァーに振り回される現状に思うところもあるらしい。フィリップとオリヴァーはシルヴィアに誘われたプライドパレードで再び出会い、和解する。それは50年越しの二人の和解でもあった──。
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
二つの時代の三人はそれぞれに異なる人物のはずだがどこか響き合うようでもあり、互いに因果の糸で結ばれているようにも思える。あるいはそこにある差異を、同じ人物が異なる時代に生まれたがゆえに生じてしまった性格や人生の違いと解釈することもできるだろう。その差異と共通性をどう演じるかが俳優の見せどころにもなっている。ダブルキャストによる上演はさらに異なるバージョンの三人への想像を促す。ひとの人生はわずかな環境の違いでも大きく変わってしまう。「正直な人生を生きること」が困難な状況であればなおさらだ。
2008年の三人は1958年のそれと比べれば幸せな関係を築けているように見えるが、それでもなお偏見や困難があることは作品のそこここで示されている。では、2022年の日本はどうだろうか。そのような想像力を喚起する点において、この戯曲は初演よりもむしろそれ以降の上演の方がより一層意義のあるものになっていると言えるかもしれない。三人が「いまここ」に生きていたらどのような人生を送っているかを想像すること。「いまここ」の向こうに2008年を、1958年を、いくつもの時代の人々の人生を透かし見ること。
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
side-Bでは若い俳優陣が傷つきながらも自分が何者かを探し続ける登場人物たちの姿を繊細に立ち上げていた。特に岩男海史のオリヴァーは好演。ただ、登場人物のフラジャイルな懸命さが際立った分、シルヴィアひとりが犠牲になっているようにも見えてしまう点は気になった。ゲイ男性二人が中心の物語だけに、唯一の女性であるシルヴィアの存在をどう見せるかは重要だろう。これは個々の演技ではなく上演全体のバランスの問題だ。一方、side-Bと比べるとやや年上の俳優たちによって演じられたside-Aでは、自身の人生を探求する切実さは抑制された演技によって胸の裡に秘められたものとなったが、その分、自ら立とうとする登場人物たちの強さが感じられる上演となっていたように思う。二つの時代を生きる三人の姿を、そして彼らを演じる二組の俳優陣の姿を通して『The Pride』が描き出したのは、いまなお続く、そして個々人においては一生をかけて向き合わざるを得ない、人間の尊厳をめぐる闘いだった。
 [舞台写真:保坂萌]
[舞台写真:保坂萌]
PLAY/GROUND Creation:https://www.playground-creation.com/
2022/07/24(日)(山﨑健太)
青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』

会期:2022/07/07~2022/07/17
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
東京芸術劇場が若手劇団に上演の機会を提供する提携公演「芸劇eyes」の1本として青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』(作・演出:伊藤毅)が7月17日(日)まで東京芸術劇場シアターイーストで上演されている。2017年にやしゃごの前身である青年団若手自主企画 伊藤企画の名義で初演された戯曲を加筆修正しての上演となった本作で描かれるのは、伊藤が「目に見えないマイノリティ」と呼ぶ「きょうだい児」(=病気や障害を抱える兄弟姉妹を持つ人)の姿だ。
舞台は関東郊外の日本家屋。母亡きあとの高木家には、軽度の知的障がいを持つ長女・雪乃(豊田可奈子)、次女・月遥(とみやまあゆみ)と助教として大学で生物学の研究をする夫の大越(辻響平)、そして三女の花澄(緑川史絵)が暮らしていた。次女夫妻の結婚に伴う引っ越しの日、知らない男性が苦手な雪乃は引っ越し業者の綿引(海老根理)に驚いてパニックを起こしてしまう。なんとか雪乃を落ち着かせ、引っ越しの作業を進めようとする面々だったが、電話の子機が行方不明になったり綿引が腰をやってしまったりとトラブルが続く。そこに雪乃と同じ授産施設に通う正志(岡野康弘)がやってくると、雪乃と二人で「お世話になりました」と家から出て行こうとする。どうやら二人は結婚するつもりらしく──。
 [撮影:石澤知絵子]
[撮影:石澤知絵子]
思いとどまらせようとする妹たちに対する二人の反応は痛切だ。「大人になったら何になりたい? ユキは聞かれませんでした」という雪乃。「お母さんはダメって言います。女の子のこと好きになっちゃダメって」「付き合っちゃダメって」「セックスしちゃダメって」「結婚しちゃダメって言います」という正志。二人を見た引っ越し業者の由香里(清水緑)の「純粋だなあ」という言葉は素朴に過ぎるが、「この二人、普通じゃないから」と言い放つ月遥に大越が返す「なに、普通って」という問いはあまりに重い。
だが、未来の可能性を閉ざされたと感じているのは雪乃だけではない。花澄は母亡きあとの高木家を切り盛りし、そのためにかつて描いていた漫画も描かなくなってしまったのだった。「自分のこと考えていいんだよ」という母(の幻覚)(藤谷みき)に対しても花澄は「もう遅い。見て、私、歳取っちゃった」と答えることしかできない。
本作に限らず、伊藤の戯曲にはそれなりの数の人物が登場し(本作では12人)、濃淡こそあれどほとんどその一人ひとりが抱える「事情」が作中でそれぞれきっちりと描かれる。それらは作品の中心的なテーマに関わり、あるいはそこから派生したものであることもあれば、まったくそれとは関係のない(ように思える)こともある。例えば高木家に頼りにされている授産施設職員の小篠(井上みなみ)は実は雪乃に嫌われていて、給料が安いこの仕事を辞めようかと思っている。花澄の友人で漫画家の幸子(赤刎千久子)は花澄にすべてを任せ家を出ようとする月遥に思うところがある様子。自分の連載もなかなか決まらないらしい。由香里の義理の兄で引っ越し業者の社長でもある康介(佐藤滋)はどうやら由香里に思いを寄せているようだ。大越の助手の笠島(藤尾勘太郎)が生物学の道に進んだのは父親が若年性認知症になったからだという。伊藤の筆は少々律儀に過ぎるようにも思えるが、そのような姿勢自体、かつて自らも「目に見えないマイノリティ」であったという伊藤の倫理を示しているようにも思える。全員の「事情」を詳細に描くことは不可能だが、それでも、それぞれが「事情」を抱えた、つまりは生きた人間であることを示すこと。人はそれぞれに異なる事情を抱え、その事情を抱えたまま、ほかの人の事情に関わることしかできない。
 [撮影:石澤知絵子]
[撮影:石澤知絵子]
上演の終わり近く、花澄が卵を机に落とそうとし、寸前でそれを月遥が止める場面がある。卵が今年で20歳になる年経たニワトリ・ピー助が産んだものだということを考えれば、卵は花澄の未来を象徴するもののように思える。あるいはピー助が大越の手によって恐竜の尻尾を取りつけられた「普通じゃない」ニワトリだということを考えれば、それは雪乃の未来だっただろうか。尻尾という「重荷」が取れた直後にピー助が卵を産んだことを考えれば、それは高木家を去り新しい生活をはじめようとしていた月遥の未来を示すものだったかもしれない。雪乃の結婚はもちろん、大越との関係に問題を抱える月遥の未来も、花澄のこれからの生活も先は見えない。花澄が捨てようとして考え直し、月遥が救おうとしたものはなんだったのか。二人はそこに何を見ていたのか。観客は何を見るのか。彼女たちの人生がこれからも続くことを強く示すかのように、終演のアナウンスの後も舞台の上の芝居は続いていた。
青年団リンク やしゃご:https://itokikaku.jimdofree.com/
関連レビュー
青年団リンク やしゃご『てくてくと』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月01日号)
青年団リンク やしゃご『上空に光る』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年10月15日号)
2022/07/10(日)(山﨑健太)
範宙遊泳『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』
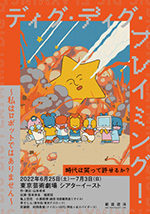
会期:2022/06/25~2022/07/03
東京芸術劇場シアターイースト[東京都]
『バナナの花は食べられる』で第66回岸田國士戯曲賞を受賞した範宙遊泳/山本卓卓の新作『ディグ・ディグ・フレイミング!〜私はロボットではありません〜』が7月15日(金)18:00から8月14日(日)23:59までオンデマンド配信されている。
炎上を意味する「フレイミング」をタイトルに掲げた本作は、インフルエンサー集団「MenBose−男坊主−」のメンバーである藤壺インセクト(埜本幸良)、キング塚村(小濱昭博)、根津バッハロー根津(福原冠)、そしてエキセントリック与太郎(百瀬朔)が謝罪の準備をしているところからはじまる。いや、正確には、謝罪の準備をしていてふと、何を謝らなければならないのかがわからないということに気づくところからはじまる。謝らなければならないのは与太郎が飼っていたスズメが死んでしまい、それを焼き鳥にして食べてしまったことか。動画のネタで「商店街の看板いくつ蹴って倒せるか大会」を開催したことか。あるいはホームレス美大生のアラレ・ビヨンド(李そじん)をゲストに迎えた企画をバラエティ調に撮ってしまったことか。過去の出来事を舞台上に召喚しながら検証は進むが、どれもこれも違っているようで謝らなければならない理由はなかなか見つからない。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
すると突然「オデのせいだ」と言い出す与太郎。どうやら与太郎には「文字が聞こえる」らしく、その文字は与太郎を責め立て「命をもって謝れ」とまで言っているらしい。「心ない声なんて全部ゴミ」と言い放つアラレに対しディスプレイに映し出される文字は「文字の奥に心がある!」と反論し、二人は「心があるならこんなにひとりの人間を追い詰めない。あなたは人間じゃない」「私は人間だ!!!!!」と激しくやり合う。そしてMenBoseのメンバーは炎上する画面の向こう側から文字の本体を引きずり出すが、そこにあったのはかつて企画でコラボしたインフルエンサー・ロクちゃん(亀上空花)のママ(村岡希美)の姿だった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
さて、この物語は一体どこに向かうのだろうか。謝らなければならない理由、つまりは「罪」を探し求めることがこの物語を推進するが、ようやく辿り着いたかのように思われた罪もまた、探していたそれではない。ママはMenBoseとの収録の際に起きた出来事がきっかけでロクちゃんが部屋から出てこなくなってしまったと思っているが、そもそもママとMenBoseとでは「起きた出来事」に対する認識が大幅に食い違っている。部屋を訪れ、引きこもりの理由を直接ロクちゃんに尋ねたママとMenBoseは結局、MenBoseには非がなかったことを知るのであった。だがそれでも文字による糾弾は止まらない。それどころかその苛烈さは増し、やがて画面の向こうから「死」が現われ、オレンジ色の浮き輪のようなオブジェとして登場するその巨大な文字にメンバーは捕らわれていく。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
ある時期以降の範宙遊泳は、プロジェクターで舞台上に文字を投影する演出を取り入れ、その文字をときに登場人物のようにも扱ってきた。『ディグ・ディグ・フレイミング!』もその延長線上にあることは確かだが、決定的に異なっているのは、この作品においては文字が単にディスプレイに映し出される文字として扱われているということだろう。範宙遊泳/山本の視線は文字の向こうにいる人間に向けられている。MenBoseはしょうもなくモラルも低い集団かもしれないが、ディスプレイに映る文字の向こうにいる人間を相手にしようとする点においては誠実だ。与太郎が看板を蹴ってしまったスナックで一日バーテンをやってみたらそこのママに気に入られてしまったように、顔を突き合わせることでよい方向に向かうこともあるだろう。匿名の文字を相手にした格闘はほとんど何も生み出さない。そういえば、『バナナの花は食べられる』もまた、マッチングアプリの客とサクラとして画面越しに出会った二人の男がリアルで顔を合わせるところから物語が動き出すのだった。
 [撮影:鈴木竜一朗]
[撮影:鈴木竜一朗]
スタート地点が間違っているのだから「罪」の追及がどこにも行きつかないのは必然だ。物語はほとんど消化不良のまま唐突な幕切れを迎える。文字によって犯罪歴を含む秘密を暴露され力尽き倒れる登場人物たち。その様子は生配信されていて、舞台上にもその映像が映し出されている。やがて聞こえてくるサイレンの音。どうやら視聴者が通報したらしい。逮捕されると怯える彼らだったがそれはパトカーではなく救急車のサイレンで──。
劇中の言葉の繰り返しにはなるが、最後の最後で罪の追及は傷ついたもののケアへと転じる。そこにあるのは劇作家・山本卓卓が物語に込めたあるべき世界への願いであり、同時に、「そこにいるあなたは物語の結末と世界の行方を委ねるに足る人物のはずだ」という、配信の視聴者=客席の観客に向けられたほとんど攻撃的と言っていいほどの信頼でもあるだろう。世界を、人間を変えるには、まずはそれらを信じるところからはじめなければならない。範宙遊泳はそれを実践してみせたのだ。
範宙遊泳:https://www.hanchuyuei2017.com/
関連レビュー
範宙遊泳『バナナの花』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年09月15日号)
2022/07/03(日)(山﨑健太)
いいへんじ『器』
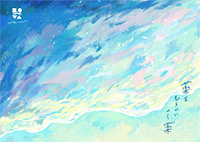
会期:2022/06/08~2022/06/18
こまばアゴラ劇場[東京都]
「死にたみ」とともに生きるとは、あるいは「死にたみ」とともにある人とともに生きるとはどういうことか。いいへんじ『器』(作・演出:中島梓織)は擬人化された「死にたみ」の存在を通して、「死にたみ」とともにあることになんとか折り合いをつけようとする作品だ。なお、公式のウェブショップでは戯曲も販売されている。以下では作品の結末にも触れているので、興味を持たれた方は先に戯曲を読んでいただく方がいいかもしれない。
冒頭、ピエロのような服(衣装:カワグチコウ)を着た人物が「みんなー! おれっちの声、聞こえるー?」と観客に向かって大声で語りかける。すぐさま「聞こえてないよねー? おっけおっけー!」と言う、もうすぐ生まれるところらしいその人物(?)こそがこの作品に登場する「死にたみ」のひとり・メラン(小澤南穂子)だ。

続く場面では就職し二人での新生活をはじめるカズキ(宮地洸成)とカナ(松浦みる)の引っ越しを友人のショウ(藤家矢麻刀)とその兄・ハル(竹内蓮)が手伝っている。ハルには「死にたみ」・ドンク(箕西祥樹)がついているが、ほかの人間には見えていないようだ。また別の場所ではカズキの高校の同級生・サキ(波多野伶奈)が配信をしていて、その側にも「死にたみ」・クラン(飯尾朋花)がいる。再び場面が転換すると新生活がスタートしていてカナコは出勤していくのだが、どうやらカズキは働いていない様子。夕方になって二度寝から目覚めたカズキは頼まれていた買い物のために訪れたスーパーでメランと出会い──。


アニメやゲームなどメディアミックスで展開する『妖怪ウォッチ』という作品がある。『妖怪ウォッチ』では世の中の困った問題や不思議な現象はすべて「妖怪のしわざ」だとされ、主人公たちは妖怪と友達になることでそれらの問題を解決していく。例えば子供がいたずらをするのもその子が悪いのではなく取り憑いた「妖怪のしわざ」なのだというわけだ。「死にたみ」を感じるのも当人に原因があるのではなく取り憑いた「死にたみ」のせいなのだ、という考えはそれ自体、当人や周囲の人間の気持ちを軽くし「問題解決」への第一歩となり得るものだろう。心理療法でいうところの認知療法の実践に近いところもあるかもしれない。
完治が難しいとされるうつ病では、「普通の」生活ができる程度に症状が改善した状態を寛解と呼ぶ。「持病」としてのうつ病とどう付き合っていくか。ドンクの機嫌の取り方を覚え、何とか日々を過ごしているハル。クランの言葉を聞かないふりでやり過ごそうとするサキ。そして何なのかわからないままに生まれたばかりのクランと暮らしはじめるカズキ。「死にたみ」との距離感は付き合いの長さによって三者三様だ。

「死にたみ」が俳優という生身の人間によって演じられるこの作品では、観客にとって「死にたみ」がそこに存在していること、そしてそれが取り憑いている当人とは別個の存在であることは最初から自明のことだ。だが、登場人物にとってはそうではない。メランがカズキのことをずっと見ていたと言うのに対し、カズキはメランの存在に気づいてなお、「それ」がなんなのかわからずメランの言葉を聞き取ることもできない。メランを「見つけた」カズキはなぜか就職活動に精を出しはじめるのだが、その行動はカズキが自らの抱える感情を見極められていないがゆえのものでもあるだろう(その点では、急に就職活動をはじめたカズキを心配するカナの方がまだカズキの状態に敏感であると言えるかもしれない)。状態が悪化し引きこもり、やがて「死にたい」とつぶやくようになってようやく、カズキはメランの言葉を理解できるようになる。それはつまり自分のなかに「死にたみ」があることを認めることだ。時を同じくしてメランは、自分たちが生まれたのは「このままじゃ死んじゃう」ことに「気づいてもらいたかった」からじゃないかという話を先輩であるところのドンクから聞いていた。当然といえば当然だが、カズキとメランの変化は連動しているのだ。そうしてカズキとメランはともに「生きる」ためのスタート地点に立つ。登場人物の微細な心の揺れを丁寧に掬い上げた俳優陣に拍手を送りたい。


ひとりの女性の脳内会議の様子を描いた『つまり』や自分のなかにある他人のイメージを具現化した『夏眠』『過眠』など、いいへんじには演劇的な仕掛けを巧く使って心の動きを視覚化した作品が多い。一方、作品ごとに描きたいことがあまりに明確であるがゆえか、メイン以外の登場人物に作品内で与えられた役割以上の広がりが感じられず、テーマや物語を描くためだけに存在しているように見えてしまうきらいもある。今回『器』と二本立てで上演された『薬をもらいにいく薬』では演劇的な仕掛けが控えめだったこともあり、特にその点が気になった。どの作品でも中心となるテーマや登場人物へのまなざしとそれを扱う手つきは繊細であるだけに「もっといけるはずだ」と思ってしまうのは高望みだろうか。
いいへんじ:https://ii-hen-ji.amebaownd.com/
関連レビュー
いいへんじ『薬をもらいにいく薬(序章)』(芸劇eyes番外編vol.3.『もしもしこちら弱いい派 ─かそけき声を聴くために─』)|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)
いいへんじ『夏眠』/『過眠』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)
2022/06/16(木)(山﨑健太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)