artscapeレビュー
きりとりめでるのレビュー/プレビュー
開館20周年記念展 ワールド・クラスルーム:現代アートの国語・算数・理科・社会

会期:2023/04/19~2023/09/24
森美術館[東京都]
会場に入って最初に遭遇したのは「国語」と半立体で示された大きな文字と、ジョセフ・コスースの《1つと3つのシャベル》(1965)だった。シャベルの実物と、シャベルの写真と、英語の辞書に掲載された「シャベル」の定義が並んでいる。いずれも作家が作成したものではない。シャベルの絵だったら「美術だ」とわかりやすいだろうか。いや、美術とは、ものそのものではなく、何かを表現したものでしかなかったのだろうか。芸術はイメージのみでなく、概念そのものをこそ扱うという作品だ。なぜこれが国語と位置付けられたのか。
コンセプチュアル・アートの金字塔から入って、本展は150点以上の作品が所狭しとひしめいている。映像作品も多く、すべてを余すことなく視聴しようとしたら休憩を挟みながら1日必要なほどだ。しかしながら、その多くが収蔵作品ということもあるからか、キャプションでの作品説明が行き届いているため、例えば、スーザン・ヒラ―による映像作品《ロスト・アンド・ファウンド》(2016)を30分見続けなくてはならない、と思う人はいないはずだ。
この作品は、さまざまな消失した、あるいは失われつつある言語を話す人々の話を収録し、その声とその波形を映像にしたものである。鑑賞体験の99%以上は結果的に英語を基点とした翻訳(日本語での字幕はきっと、英語からの翻訳だろう)で把握可能になるが、キャプションにあったとおり、それは帝国主義や植民地主義が押しつぶしてきた言語の歴史と表裏一体である。こうなってくると、背後にある、いまさっき見たコスースの英語の使用が透明な媒体に思えなくなってくる。だからこの二つは「国語」になくてはならなかったのだろう。
スーザン・ヒラ―の暗室を出てすぐにあるのは、米田知子の「見えるものと見えないもののあいだ」シリーズだ。例えば、フロイトの眼鏡のレンズを通してユングのテキストを見るという構図の写真であるのだが、活字にしても、それが誰にとってどう見えるのかという個人のありようが、無味乾燥な活字に意味を与える。
続くのはミヤギフトシの《オーシャン・ビュー・リゾート》(2013)。沖縄出身のある男はなぜアメリカに渡ったのか、だれをどう恋しく思っているのかを英語のモノローグで綴る。隣のイー・イランはボルネオ島のさまざまな織手と協働制作を行なっており、本展の《ダンシング・クイーン》(2019)は竹でできた巨大なタペストリーだ。そこにはABBAなど世界的な流行曲の歌詞が英語で織り込まれ、キャプションではABBAやレディ・ガガの音楽が「織手の生活へ寄り添ってきた」ものであることが示されていた(2021年のABBAのニューアルバムはマレーシアを含む世界40カ国と地域でiTunes1位を獲得した★)。イランの作品とミヤギの作品、それぞれにとって一定の意味をもつ英語という言語で受容してきた文化のあり方に、四方八方へと心が揺さぶられる。
「国語」というより、コスースならイデア論を引いて「哲学」、ミヤギなら歴史を踏まえて「社会」なのではないかという疑問も確かにありつつ、「国語」とカテゴライズされることで作品が相互に反響し合っている。このように、作品が並ぶことで意味を引き出し合うキュレーションが本展の膨大な作品の並びにおいて、幾度となく現われていた。
すべてに触れることはできないが、収蔵品が多いこともあり、本展の作品の一端は森美術館のウェブサイト「コレクション」で詳細なキャプションと一緒に伺うことができる。アイ・ウェイウェイの《漢時代の壷を落とす》(1995)、ヴァンディー・ラッタナの写真作品「爆弾の池」シリーズなどなど、本展を見る機会が得られなかったという人にも、ぜひ見てほしい。
ただし、本展のなかで取り扱い上、ひとつ浮いていたと思われるのが、笹本晃の《パフォーマンス記録映像 ストレンジアトラクターズ》(2010)ではないだろうか。本作についてはいつか別稿で取り上げたいと思う。
本展は2000円で観覧可能でした。なお、土日祝は2200円だったそうです。
★──ユニバーサル ミュージック合同会社「ABBA、40年ぶりのニュー・アルバム『ヴォヤージ』が日本で42年5か月ぶりのTOP5入り!」(『PR TIMES』2021.11.10)2023.9.25閲覧(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001482.000000664.html)
公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/classroom/02/index.html
2023/07/01(土)(きりとりめでる)
坂口佳奈・二木詩織「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」

会期:2023/06/03~2023/06/25
Gallery PARC | GRANDMARBLE[京都府]
「あと坂口さんはよくウィルキンソンの炭酸を飲んでいて、それよく飲んでますねとはなすと『味ないけど美味しいよー』と言っていました。
(…)すぐに『味ないけど美味しい』ってうちらの展示みたいじゃないって言って二木さんの方をみたら笑ってました」
(会場配布のハンドアウトより)
わたしの住む築30年以上のマンションの入口付近には花壇がある。建物に備え付けられたタイプの花壇で、その縁の幅も高さも、人が座るのにピッタリだからか、昼下がりに誰かしらが3人くらいで集まってひっそりと酒盛りをしている。缶ビール1本にコンビニのちょっとしたおつまみくらいの規模だ。その人たちは花壇や目の前の生垣にその痕跡を残すことがある。
晩ご飯の買い出しから戻ると、ある日はつつじの葉の上に空き缶が、あくる日には枯れた草木の傍らにアイスの棒が3本刺さっていた。マンションの清掃と管理を担う人物が翌朝それを片づける。ゴミは持ち帰ってほしいと思いつつ、わたしはそれを触る気にはならない。とはいえ、その人たちの営みがわたしは羨ましい。と、こんなことを滔々と書いたのは、そのアイスの棒のありさまと、ほどんど同じものを展覧会で目にしたからだ。
 「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]
「そこら中のビュー」会場写真[画像提供:ギャラリー・パルク/撮影:麥生田兵吾]
坂口佳奈と二木詩織による展覧会「そこら中のビュー」にまさに、食べ終わったあとのアイスの棒が刺さったオブジェが床に置かれていた。それは厚みのあるコルクの円形の台座に7本の木製の棒が不規則に刺さっているという小さなものだ。うっかり踏んでしまいそうなほど。会場はひと目で間取りを把握できる程度の広さなのだが、この「棒のオブジェ」みたいなものが壁の上とか、部屋の真ん中、隅とか、至るところに密かに点在している。会場の広さに対してオブジェの大きさと導線がきっちり設定されているから、散らかっているようには思えない。
その個々のものの塊の在り方は、インスタレーションというより、彫刻がたくさんある、ドナルド・ジャッドの「スペシフィック・オブジェクト」のようなミニマリズムが生活の結果で展開されている、というわたしの印象につながった。部屋の隅に、20センチ程度の長さの角材が5個摘み上がっていて、その角材と角材の間には靴下が1個ずつ挟まれている。分厚い年季の入った木製の将棋盤が垂直に建てられて、その上には青い養生テープが5つテープ面を下にして並ぶ。
かと思うと、部屋の真ん中に6枚の写真と4つの石。写真に映るのは、砂浜・河・海・島の沿岸・公園の噴水・車のフロントガラスにこびりつく雪。植生の違いが感じられるため、それぞれ別々の旅先なのだろうか。石もまた、河原の丸石や火成岩といった産出地のバラけが感じられる。写真とともに撮影された土地の石とおぼしきものが置かれると、ロバート・スミッソンがどこかの土地をポータブルなものにした「ノンサイト」が想起されるが、「ノンサイト」で土地の構成要素の一部を持ち運び可能にしたスチールでできた容器やその光景を拡張するための鏡や場所を指し示す地図はここにはない。だが、本展のように石を最低限にすれば箱も鏡も必要ないし、本展で転がった4つの石はそれぞれ指標性を発揮して、あなたの心の中でどこか別の場所を思い起こさせるはずと言わんばかりだ。
でもそうなのだ、地図はない。なんだったら地名の情報もない。いや、間接的な地名はあった。展覧会のプレスリリースに記載されたテキストに、坂口と二木が展覧会やワークショップで招聘されるにつけて発生した旅(兵庫「あまらぶアートラボ A-Lab」での展示、鹿児島「三島硫黄島学園」や長野「木祖村立木祖小学校」でのワークショップなど)を契機に制作していると。ただし、その文章はこう続く。「リアルとフィクションの曖昧なインスタレーション形式として発表しています」。会場に点在する石と写真が指し示す場所に対応関係があるとは限らないということは含意しているだろう。
作品の輸送費といった金銭面での負担をクリアするために、1967年のデュッセルドルフでギャラリストであるコンラート・フィッシャーが各国の作家を招致して、あるいは指示書によっての現地での制作をミニマリズムやコンセプチュアルアートの作家たちへ依頼できたのは、その作品の物質的な基底が重要ではなかったり、鉛板や蛍光灯といった一定の地域で広く入手可能な工業製品で構築されているからだ。坂口と二木がそれぞれの場所から招致を受け、そういった旅を契機としつつ本展をつくり上げるなかで、ジャッドやスミッソンの作品との類似点を得たのは偶然ではない。現代の日本の美術家たちが旅を前提とした(/旅を前提としない)「地域の肖像作家」という要請を引き受けつつ、その場所を離れることも可能にするうえで、ミニマリズムとは持ち運ばずともポータブルであることが可能な作品の形態であり、ノンサイトとはそういったポータブル性をどこかと結びつける手法なのである限り、その両者はフォームとしてとても使えるものなのだから。
次回以降は、「地域の肖像作家」という比喩について検討しつつ、坂口と二木による泥をこねる映像作品を観ていき、「味ないけど美味しい」の意味、あるいは記名して立つという在り方について検討したい。そこからさらに、近年のいくつかの展覧会を踏まえつつ、「凡人(ボンドマン)」による展覧会「BankART Under 35 凡人」を扱い、現在的な土というメディウムについて取り上げられたら。
「そこら中のビュー The Journey Through Everyday View」は無料で観覧可能でした。
公式サイト:https://galleryparc.com/pages/exhibition/ex_2023/2023_0603_saka_futa.html
2023/06/20(火)(きりとりめでる)
The Flavour of Power─紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?

会期:2023/03/11~2023/06/25
山口情報芸術センター[YCAM][山口県]
会場の入口に、目を引くフレーズが書かれている。「飢餓はなくならない」。そしてこう続く。「あなたが気にかけない限り」。
本展は山口情報芸術センター[YCAM]が実施する研究開発プロジェクト「食と倫理リサーチ・プロジェクト」の成果展だ。YCAMはその研究の過程でインドネシアを中心に活動する8名の研究者やアーティストによるユニット「バクダパン・フード・スタディ・グループ」(以下、バクダパン)と調査を実施した。展覧会は、バクダパンが2021年の「アジアン・アート・ビエンナーレ」(台湾・台中)や2023年の「foodculture days」(スイス・ヴォー)で出展してきた、インドネシアの食糧危機をシミュレートしたカードゲーム(今回は日本語版)とミュージックビデオ調の映像作品からなる《ハンガー・テイルズ》を入り口に据え、新作《Along the Archival Grain》(2023)の内容はおのずと日本とインドネシアの接点である太平洋戦争中の日本統治下での出来事にフォーカスされた。
 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
 バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
《Along the Archival Grain》は資料展示のパートと映像インスタレーションのパートで構成されている。「資料展示パート」というのはキャプションに書かれている言い回しでもあるが、作品内でも自己言及されているとおり、そこで読めるのは資料を編纂して示された「物語」である。日本占領下の台湾に派遣された日本人作物育種家の磯栄吉による植民地での「ジャポニカ米」の栽培可能品種の研究、その末の「蓬莱米」の開発とその台湾やインドネシアでの展開を皮切りに、日本が第二次世界大戦後の戦争債務処理を「貧困の撲滅」という英雄的な意識のもとに行なった「奇跡の米」の開発に言及することで幕を閉じる。
この物語は5章立てでウェブサイトにまとめられており、会場にあるタッチパネルで観賞者個々人が閲覧できるようになっている。ひとり掛けの椅子ごとに1台の端末というセットが4組あるので、ほかの鑑賞者に気兼ねすることなく、ゆっくりと読むことが可能だ。読了までは30分ほどの物語で、文末に参考資料のURLやQRコードが付随しており、この物語は各種資料への入り口にもなっているといえるだろう。
 バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
物語の冒頭で、磯栄吉の遺稿が引用されている。
「いかなる農夫も作物に対する限りただ誠あるのみで虚偽は許されない。故に人を道徳的にならしめる。(…)それにより民族の健全性が保たれ『農は国の基』となる」
磯が研究した「蓬莱米」は作地面積ごとの収穫量が増加する一方で、それまでの自前の肥料ではなく化学肥料を必要とするといった、「政府が整備したインフラに依存」せざるを得なくなる。インドネシアに対する日本政府による米の独占的な管理が実施された1942年の「米の引き渡し政策」、1943年の「緊急食糧対策」では「蓬莱米」が導入され、収穫高の管理のために諸種間作は禁止、空地があれば農地となったのだ。この施策は、石炭のための大規模伐採と絡まり合い、それまでのヴァナキュラーな営為や環境の破壊、干ばつ、飢餓、害虫を引き起こした。
磯の言葉や物語中で引用されるプロパガンダ雑誌『ジャワ・バル』が示す通り、日本政府による植民地統治ではつねに「農民」が生産者として称揚される。だがそれは、農業という技術をより善きものと位置付けることによって、農業の収穫高の向上が徳の高さに、搾取的な統治の強化が尊い技術の伝達にすり替えられているのだ。物語の後半では、国際稲研究所(IRRI)が害虫や干ばつといった自然災害に強い品種を開発した「緑の革命」が説明されている。そして、そこに参画した日本が開発する「奇跡の米」もまた化学肥料依存度が高く、「飢餓をなくす」という英雄的意識のもと技術による国家的な搾取構造を繰り返していること、1964年には日本が放射線照射米「黎明」を開発し、そのハイブリット種がマレーシアで継続的に研究されているということが示されて幕を閉じる。いずれも物語というにはあまりにも即物的だが、最後に書かれた問いはこの物語の要旨だろう。
「科学技術的な合理性は植民地主義的な傾向があるため、農業知識を共同化し、そこから脱却するためにはどうすればいいでしょうか?」
 YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
 バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]
映像作品《ハンガーテイルズ》のフレーズ、「ハンガーテイルズ/遺伝子組み換えの食事は美味しいかしら!/ハンガーテイルズ/開発計画で私たちは干からびるのよ!/ハンガーテイルズ」「政府は我慢しろと言うだけ! 我慢しろ! 我慢しろ! 我慢しろ!」。革命を呼びかけるような、抑圧に対する激しい言葉が並ぶが、耳に残る反復的な音楽はどこか気だるげで、映像のメインアイコンは映画『サウンド・オブ・ミュージック』のヒロイン、マリアが満面の笑みでアルプスの山頂で草原を抱くグラフィックの引用だ。
全体的に特権階級に対する市民革命を想起させる言葉だが、そこで選ばれたマリアはナチスドイツ下のオーストリアからスイスへと向かった亡命者だ。ジェームズ・C・スコットの大著『ゾミア― 脱国家の世界史』(みすず書房、2013)は、稲作のような国家的なインフラに依存度が高く、収穫高が管理されやすい作物、すなわち国家運営にとって都合のよい民の在り方とは逆の存在、ゾミアの民について記している。それは「国家」を避けるように山間部を移動しながら焼き畑を行ない根菜を育て、文字を使わず、知識の偏在を回避する生き方である。マリアとトラップ家の人々はスイスでどのように暮らしているのだろうか。あるいは、山間部を移動し続ける生活を行なっているのだろうか。革命ではなく回避のなかに、バクダパンからの問いへの答えはあるのかもしれない。
公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2023/the-flavour-of-power/
2023/06/19(月)(きりとりめでる)
「風景の中の人間像」丸木位里 丸木俊 内田あぐり 柴田智明の絵画について

会期:2023/05/16~2023/05/27
画廊 楽Ⅰ[神奈川県]
本展「風景の中の人間像」は、丸木位里と丸木俊による1947年を中心とした人体デッサンと水墨画、丸木夫妻のドローイングの研究も行なってきた日本画家である内田あぐりの屏風絵、柴田智明による画布やキャンバスが混在した大量の絵画で構成されていた。
会場の大半を占めるのは内田の《緑の思想》(2013)だ。人間はそこにいない。十数羽の黒い鳥が羽を閉じ、一羽を見守っている。例えば黒い鳥の輪郭線は岩絵の具が削り取られることで生じたものと、紙縒で麻紙が縫い付けられたキワで生じたものがあるのだが、これが「鳥だ」と認識させるうえで重要な役割を担う嘴にある輪郭線は寄ってみると案外おぼろげだ。嘴も黒かったらカラスかと思うが、ところどころ白い。白い結果何が起こるかというと、その鳥たちの視線の先が明確になる。湖畔のような緑青に浮かぶ、眼を閉じた一羽に視線が向かっている。明らかな死に顔。しかし、死んだ鳥の丸みがかった嘴はまた一羽のほかの鳥の空白(嘴)から身体へと視線を誘導する。
 内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)
内田あぐり《緑の思想》(2013/筆者撮影)
 内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)
内田あぐり《緑の思想》部分(2013/筆者撮影)
 内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)
内田あぐり《ドローイング》(制作年不明/筆者撮影)
本作の習作と思しきドローイングが数点展示されていた。そこでは黒い鳥というよりも、黒く描かれた人々が緑に光る湖畔に手を伸ばしたり、見下ろしたりする様子が伺える。黒い鳥は当初、人間だったのだろう。丸木位里の人体デッサンや丸木俊の水彩ドローイングが、表情を丹念に描くことで視線の強さを感じさせていることにより、それらに囲まれた《緑の思想》は一層対比的に、感情の抑圧的な象徴化が実行されていることがわかる。
また、この流れを受けて、アメリカのロサンゼルスを拠点に雑踏を凝視し続けてきたという柴田智明のペインティングを見ると、人物の身振りや筆致の雄弁さには反して、その表情は全体的に曖昧だ。どの人格にも眉毛が描き込まれているのだが、下がりも上がりもしていない。むしろ、その眉が激しく動いていたのは柴田が会場に置いた日誌だろう。covid-19が蔓延した時期に柴田は金銭目的での1週間の治験参加を日記にしている。柴田は食事を堪能し、看護師の気を引こうとライオンのおならについて語り、病院の外の世界で何が起きているのかを綴った。生政治が一気に加速した状況下で、人間というよりも物質的な人体として扱われることになる治験に際し、雑踏ではなく個としての自身の状況やストレス感情を見つめ直すことは、作者にとってそれまでとまったく別の仕事だったのだろうか。
柴田に関する作品リストにはプライスは掲載されていたが、作品名や制作年数はわからなかった。そのため憶測でしかないが、無題が無時間に並ぶのだとしたら、そこに差はないのだろう。
 柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)
柴田智明の展示の様子(制作年不明/筆者撮影)
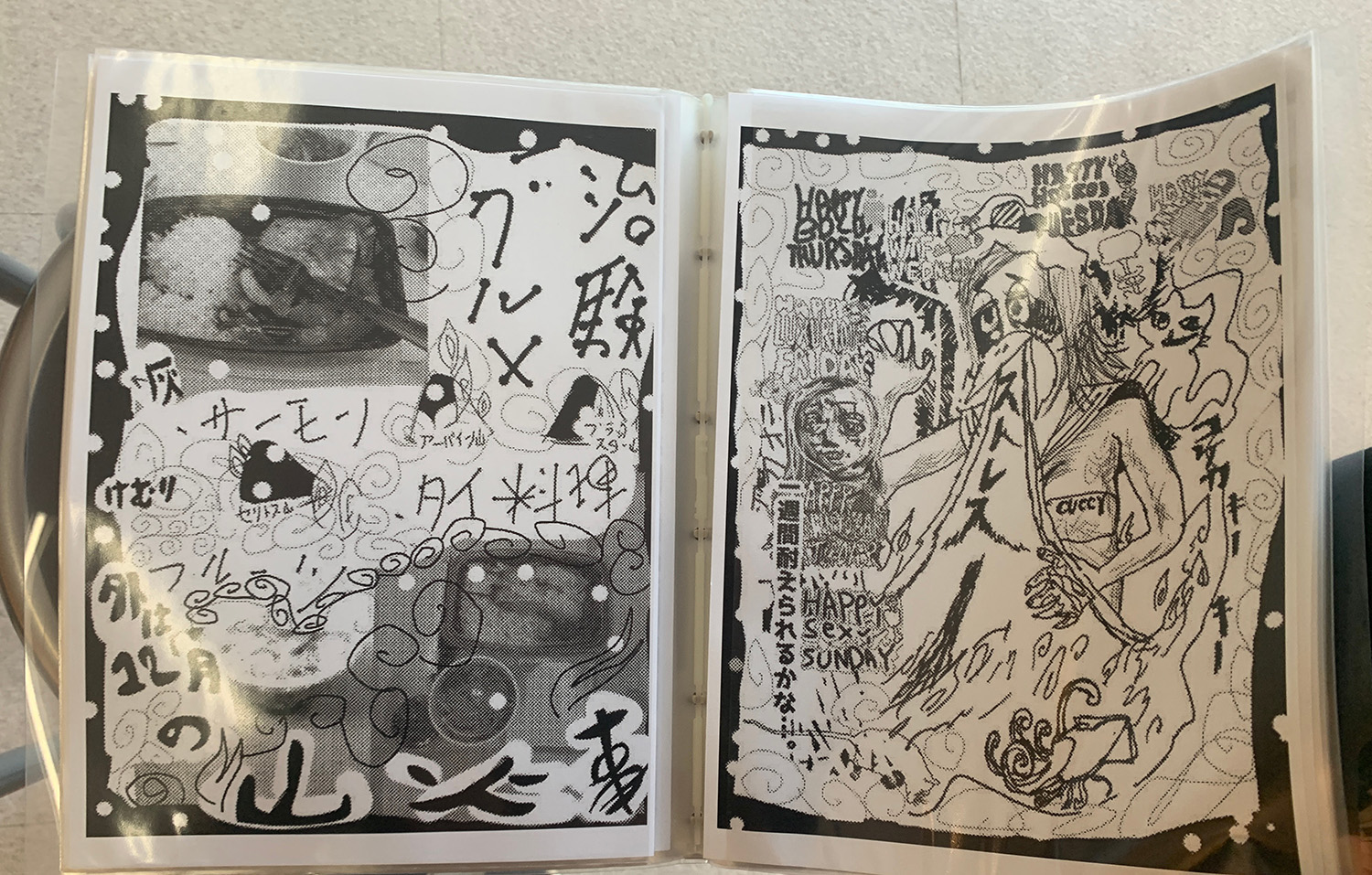 柴田智明のファイル(筆者撮影)
柴田智明のファイル(筆者撮影)
公式展覧会情報(画廊 楽Facebook):https://www.facebook.com/raku.garou/posts/pfbid02jGBHdf2n5aeD94Uyc5GSe8xi6VBEHgwo2fNn43RX8QUoCM1DgCfXYVLSi1SQTkCHl
2023/05/20(土)(きりとりめでる)
第14回 光州ビエンナーレ(フランスパビリオンでの展示、ジネブ・セディラ《꿈은 제목이 없다 Dreams Have No Titles》)

会期:2023/04/07~2023/07/06
楊林美術館(フランスパビリオン)[韓国、光州]
2022年のヴェネツィア・ビエンナーレでもフランスパビリオンで展示されたジネブ・セディラ(Zineb Sedira)の《Dreams Have No Titles》(2022)が光州ビエンナーレでもフランスパビリオンに出展されていた。ジネブが生まれ育ったのはフランス、両親の出身地はアルジェリア、そしていまイギリスに在住している。アルジェリアは1954年から1962年にかけての「アルジェリア戦争」を通してフランス領からの独立を目指し、達成した。本作はアルジェリア独立後のある映画史にジネブが入り込んだものだ。
 Zineb Sedira, Dreams Have No Titles, 2022 Duration: 24 mins, Shot in 16 mm and digital film
Zineb Sedira, Dreams Have No Titles, 2022 Duration: 24 mins, Shot in 16 mm and digital film
Commissioner French Institute, Paris & Production ARTER, Paris. Courtesy the artist and Mennour, Paris. © DACS, London 2023
14th Gwangju Biennale: soft and weak like water, South Korea, April 7 – July 9 2023, 14gwangjubiennale.com
会場はその映画についての映像作品と、その撮影セットが部分的に組まれたインスタレーションで構成されている。特に映像ではジネブ本人がナレーションを務め、『ル・バル』(1983)をはじめとした数々の映画をリメイクしたシーンに自身が登場した。ここでの映画史はとりわけ、フランス、イタリア、アルジェリアにおける1960年代、1970年代、そしてそれ以降に焦点を当てたものだ。そのなかでジネブは時代をつくった諸映画に入り込むのであるが、その所作は1970年代以降のシミュレーショニズム──作者がある既存の作品を参照し、その既存作品の登場人物とはアイデンティティや国籍が異なる自身の身体を提示することによって先行作品の意味を読み替えたり、特定のステレオタイプを再演することである社会や文化を戯画化するといったアプローチ──とは違っている。ジネブ自身はそれを「リメイク」と呼んでいるが、シミュレーショニズム(例えば、シンディ・シャーマンや森村泰昌)とここでのジネブ作品との差分をどこに見出すことができるだろうか。そのリメイクの特徴としては、シミュレーショニズムの多くが映画→写真、絵画→映像、絵画→写真等々メディアを変更している一方で、映像→映像であること(もちろん福田美蘭のように絵画→絵画というものもある)、そして、先行作品を模倣しているシーンがあったかと思えば、リメイク撮影をしている現場が広角のショットで挿入されることが顕著だろう。
参照されている映画はいずれも、アルジェリアとフランスとイタリアの共同制作である。ジネブは2017年に初めてアルジェリア・シネマテックのアーカイブを訪れ、そこで独立後につくられた映画が第三世界の価値観と美学をいかに遵守していたかということに感銘を受けた。そんなジネブのいうところの第三世界で開発された「戦闘的で反植民地的なアプローチ」は、フランスや特にイタリアの監督たちと共振し、1960年代からアルジェリアとの共同制作が行なわれていたのだ。
特に中心的な参照先である『ル・バル』は言葉のない映画だ。第二次世界大戦から1980年代までの変遷を、ダンスフロアでの身振りと音楽だけで描き切ったものになっている。すなわち、いずれの参照映画も三国間での文化的同盟の模索が形になった映画なのだ。しかし、作品の冒頭からオーソン・ウェルズの『F for Fake』を引き合いに、「この映画はトリックについての映画だ」と主張して始まるように、本作では具体的にその協働について分析・描写されることはないが、その参照先のリメイク映画が別のリメイク映画に切り替わるとき、ミザンナビーム(紋中紋=入れ子構造)が幾重にも行なわれている★1。
本作でのミザンナビームは主に、1960年代、70年代、それ以降のラジオやブラウン管テレビといった時代とともにあるメディアの当時の音質や画質を、目下の視聴覚環境(本作はフルハイビジョン、画素数1080p)のなかでの画中画、作中音楽としてシミュレーションし、出現させている。ミザンナビームによって発生する1080p以前の映像の質感の衝突は、映像や音声の解像度の低さへ移り変わり、作中での映画の時代の変遷を示唆するのだ。
この演出が本作にとってどのような意味をもつのかというと、『ル・バル』に現われる時代を代表する音楽や人物や雰囲気といったものではなく、その媒体の質感の変遷に世界的な共感や同期性が現在は見出せるということだろう。いまのダンスホール、文化の結晶はスクリーンの中にあるから。こういった現代性の表出によって、本作はアルジェリアとイタリアとフランスの外にもメッセージを送ることができているとわたしは思う。
シミュレーショニズムの作品の多くが媒体を変更することによって、あるいは、自身の身体を古今東西の名作に入れ込むことによって、当時の時代の在り方を批判的に再考させてきた。しかしジネブはそうではない★2。著名な作品を再考させるためというよりも、フィルムの存在が忘れ去られていた映画『Tronc de figuier』の再発見を出発点に、映画というフィクションのなかに、いまを生きる自身や自身のファミリーヒストリーを挿入することで、1960年代以降の映画での協働を現在に結び直そうとしている。
アルジェリア戦争当時から長きにわたり、フランス政府はアルジェリアの独立に向けた一連の活動を「事変」や「北アフリカにおける秩序維持作戦」と見なしていたが、1990年に正式に「アルジェリア戦争」と呼称を変更した。韓国の軍事政権に対する民主化要求である光州事件(1980)がかつて内乱陰謀と位置づけられていたこととパラフレーズするパビリオンになっているといえるだろう。
光州ビエンナーレではどのキャプションも作家の出自を地域名で記載していた。それは「国家」というものと作家の表現が同一視される狭窄的な受け取り方を是正するためのやり方だ。「soft and weak like water」をメインパビリオンのタイトルとし、実際多くの作品が実直に「水」をモチーフとしていたが、それはあらゆる観賞者が作品に対して一瞥で政治的判断を迫られないようにするという共感可能性の幅を広げるという方法でもあっただろう。西欧との別の方法、知恵の模索といったものが、水をはじめとした「自然とともにある」といった様相を呈しているように見えることはまた別稿で検討したいが、そんななかで、国を代表するパビリオンを並置するということは、パビリオンに向けたビエンナーレ側からの「なお国を代表する作家をどのように選ぶことができるのだろうか」という問いでもある。フランスパビリオンの本展は、光州の人々に向けたメッセージを、国際展を見に来るあらゆる人々へどのようなメッセージをつくるのか、ひとつの明快な解答に見えた。
★1──本作については詳細なプレスキットが出ている。
★2──とはいえ、例えば森村泰昌もシンディ・シャーマンもキャリアを積み重ねた後、「自伝的」な作品が多くなっている。
第14回 光州ビエンナーレ:https://14gwangjubiennale.com/
関連レビュー
第14回 光州ビエンナーレ(Horanggasy Artpolygonでの展示)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年05月15日号)
第14回 光州ビエンナーレ|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)
2023/05/07(日)(きりとりめでる)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)