artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
須田一政『SUDDENLY』
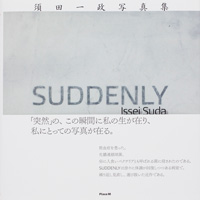
発行所:Place M
発行日:2016年5月16日
須田一政は2015年に敗血症を患っていた。化膿連鎖球菌に侵され、炎症の程度を示すCRP値は最高40に達した(基準値は0.3以下)という。その「いつ心臓が停止しても不思議ではない状態」から帰還したあとに、体調回復のために入院していた病院の病室で、繰り返し写真を見直し、「選び抜いた」近作を集成したのが本書である。
まさに「生死の境」に去来し、うごめきつつ姿を変えていくようなイメージ群が、写真集のページから溢れ出すように並んでいる。このところの須田の仕事ぶりには鬼気迫るものがあるが、この写真集でもそのただならぬ凄みに、絶句してしまうような写真が目白押しだった。特に目につくのは、液晶テレビの画面を写している写真である。須田は洋画が好きなようで、それらの一場面が断片的な映像として写しとられている。ほかにも、看板やポスターの一部を切り取った写真も多い。須田は写真集のあとがきで、スタンリー・キューブリックの「妄想や実現しなかった夢を現実と同じくらい重要なものとして扱おうとした」という言葉を引用している。このような、映像(まさに「妄想や実現しなかった夢」)を現実と等価のものとして扱う姿勢は、初期の頃からあったのだが、それがより研ぎ澄まされ、融通無碍なものになりつつある。
同年齢の(76歳)の荒木経惟もそうなのだが、須田の近作を見ていると、老いをネガティブにとらえるのではなく、むしろ何かを呼び覚ましていく契機としてとらえ直していこうとしているように見える。幽冥の世界を自由に行き来する表現が、輪郭をとりつつある。
2016/08/10(飯沢耕太郎)
サイ・トゥオンブリーの写真 ─変奏のリリシズム─
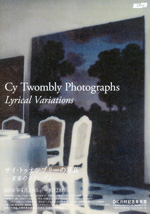
会期:2016/04/23~2016/08/28
DIC川村記念美術館[千葉県]
会期終了間際になって、ようやくサイ・トゥオンブリー展に足を運ぶことができた。これまでにも彼の写真作品は断片的には展示されたことがあるものの、これだけの規模の展示を見ることができるのは、まさに嬉しい驚きといえる。DIC川村記念美術館の会場には、初期から最晩年に至る写真作品100点のほか、絵画、彫刻、ドローイング、版画の代表作も並んでいた。
トゥオンブリーが写真作品を制作し始めたのは、1951年にノースカロライナ州のブラック・マウンテン・カレッジで、写真家のヘイゼル・フリーダ・ラーセンのピンホールカメラの授業を受けたことがきっかけだったようだ。つまり、絵画やドローイングとともに、ごく初期から視覚的な探求のメディアとして写真を意識しており、その後も断続的に作品制作は続けられていた。だが、それがまとまったかたちで展開されていくのは、1980年にポラロイド写真を使い始めてからである。今回の展示の中心になっているのは、ポラロイドで撮影したプリントを、複写機で2.5倍ほどの大きさに拡大し、さらにそれらをフレッソン・プリントやカラー・ドライプリントで、ややざらついた手触り感のある画面に仕上げた写真群だ。花、野菜、自作の絵画や彫刻などのクローズアップのほか、墓地や海辺の光景なども被写体になっている。どうやら、何を写すかよりも、そこにある事物が、写真、複写、プリントなどの操作を経ることで、どのように変容していくかに強い関心を抱いていたようだ。ここにも、トゥオンブリーの絵画やドローイング作品とも相通じる、「ものの流転」(things in flux)へのこだわりがあらわれている。写真をもうひとつの視覚として使いこなしていくことへの歓びが伝わってくるいい展示だった。
個人的には、以前から見たかった版画集『博物誌1 きのこ』の全作品が出品されていたのが嬉しかった。作品そのものに内在する偶発性、魔術性、多様性から見て、トゥオンブリーがきのこに強い親近感を抱いているのは間違いない。そういえば、彼の写真作品も、どことなく増殖するきのこの群れのように見えなくもない。
2016/08/06(飯沢耕太郎)
ナムジュン・パイク没後10年 2020年笑っているのは誰?+?=??(前半)
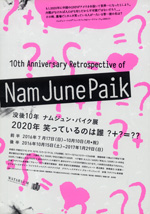
会期:2016/07/17~2016/10/10
ワタリウム美術館[東京都]
ナムジュン・パイク(1932~2006)の仕事は相当に面白い。ビデオアートの創始者という肩書きでのみ語られることの多い彼だが、今回ワタリウム美術館で開催された「没後10年」の展示を見て、あらためてあらゆるヒト、モノ、コトを結びつけては変質させる、その強力な「触媒」としての可能性に着目した。
会期の前半は、現代音楽からスタートして、前衛美術作家としての志向を強めていく1950~80年代の作品を中心に展示している。この時期、パイクはジョン・ケージ、ジョージ・マチューナス、マース・カニンガム、ヨーゼフ・ボイスらとの出会いを軸に「ブラウン管がキャンバスにとってかわる」時代の新たな表現様式を模索していた。《ジョン・ケージに捧ぐ》(1973)、《ガダルカナル鎮魂歌》(1976)、《TVフィッシュ》(1975)といったビデオアート作品は、今見ても充分に刺激的、挑発的だし、「来るべき21世紀を見据えて、新たな形の分配について考えていく」というクリアーな思考が貫かれている。
映像メディアを通じて、出会いをグローバルに拡張していこうという彼の志向が頂点に達するのが、「サテライト・アート」として制作された《グッド・モーニング、ミスター・オーウェル》(1984)である。ニューヨークのテレビスタジオとパリのポンピドゥセンターで収録した番組を、放送衛星を使って同時中継するという試みが、視覚的、聴覚的なエンターテインメントとしても高度な段階に達していたことを、今回はじめて確認することができた。むろん、インターネットを使えば、いまは同じアイディアをもっと簡単に実現できるわけだが、問題はパイクほどのスケールの大きな構想力を備えたプロデューサーがいるかどうかだろう。そう考えると、やや悲観的にならざるを得ない。
世界各地で大プロジェクトを実現するとともに、ワタリウム美術館とのつながりも深まってくる1990年代以降の作品をフィーチャーした、会期後半(2016年10月15日~2017年1月29日)の展示も楽しみだ。
2016/08/05(飯沢耕太郎)
羽永光利アーカイブ展

会期:2016/07/23~2016/08/20
AOYAMA|MEGURO[東京都]
羽永光利(1933~1999)は東京・大塚生まれ。文化学院美術科卒業後、フォトグラムやデカルコマニー作品を発表していたが、1962年からフリーランスの写真家として活動し始めた。以後、雑誌等で仕事をしながら、現代美術、舞踏、演劇などの現場に密着して取材・撮影を続けた。1981~83年には、創刊されたばかりの「フォーカス」(新潮社)の企画・取材にかかわったこともあった。
アーティストたちのエネルギーが交錯しつつ、高揚していく時代の貴重な記録として、このところ、羽永の写真は国内外で大きな注目を集めつつある。昨年の「羽永光利による前衛芸術の"現場" 1964-1973」展に続いて東京・上目黒のAOYAMA|MEGUROで開催された今回の個展では、10万カットに及ぶという遺作から約450点が展示されていた。会場は「演劇」、「舞踏」、「世相」、「前衛芸術」の4部構成で、それぞれ1960~80年代撮影の写真がアトランダムに並んでいる。ハイレッドセンターやゼロ次元のパフォーマンスのドキュメントを含む「前衛美術」のパートや、土方巽、寺山修司、唐十郎などのビッグネームの姿が見える「演劇」、「舞踏」のパートもむろん面白いのだが、むしろこれまであまり発表されたことのないという「世相」のパートに注目した。「前衛芸術」の担い手たちの活動は、突然変異的に出現してきたわけではなく、それぞれの時代状況をベースにしてかたちを取ってきたことがよくわかるからだ。逆に1960~80年代の大衆社会の成立がもたらした解放感、エネルギーの噴出こそが、「前衛芸術」の活況を支えていたともいえるだろう。写真に引きつけていえば、中平卓馬、森山大道、荒木経惟、深瀬昌久らの「ラディカル」な表現のあり方は、羽永の写真に見事に写り込んでいる「世相」のエスカレートぶりと響きあっているようにも思えるのだ。
なお、羽永のアーカイブが所蔵する写真1000枚を収録した文庫版写真集『羽永光利 一○〇〇』(編集・構成、松本弦人)の刊行が決定したという。内容と装丁とがぴったり合っているので、出来映えが楽しみだ。
2016/08/04(飯沢耕太郎)
三田村陽「hiroshima element」

会期:2016/07/29~2016/08/11
三田村陽は1973年、京都生まれ。1997年に大阪芸術大学写真学科を卒業後、京都造形芸術大学大学院メディアアート専攻に進み、1999年に同大学院を修了した。ここ10年余り、広島に月1度ほどのペースで通い続け、撮りためた写真を2015年12月に写真集『hiroshima element』(ブレーンセンター)にまとめた。今回のphotographers' galleryでの展示は、そのシリーズの東京でのお披露目展ということになる。
6×7判のカラーで撮影・プリントされた写真は、のびやかで屈託のないスナップショットである。三田村本人は「広島で写真のよろこびを表明する」ことに、ある種のうしろめたさを感じているようだが、実際に展示されている写真には、そのような翳りはまったく感じられない。むろん、原爆ドームや慰霊碑などは画面に映り込んでいるし、デモ隊や右翼の姿も見える。だが広島を取り巻く政治的な状況については、ことさらに言及することなく、むしろさまざまな都市的な要素に、目立たないように埋め込んでいくことがもくろまれている。その狙いはかなり成功しているのではないだろうか。
とはいえ、広島はやはり特別な都市であり、三田村の写真を見る者は否応なしに「見える街と見えない街」の二重性を意識せざるをえなくなる。そこから、どのようにして広島に特有の社会・文化の構造をあぶり出していくかが大きな課題なのだが、それはまだ緒に就いたばかりのようだ。この中間報告を踏まえて、さらなる「hiroshima element」の抽出が必要になってくるだろう。それがうまくいくかどうかは、次の発表ではっきりと見えてくるはずだ。
2016/08/03(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)