artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
増田友也の世界─アーカイブズにみる思索の軌跡

会期:2021/10/27~2021/12/12
京都大学総合博物館[京都府]
「モダン建築の京都」展(京都市京セラ美術館)の第7セクション「モダン建築の京都」において、山田守の《京都タワー》(1964)や前川國男の《京都会館》(1960、現・ロームシアター京都)は年表のみの記載だが、厳選された最後の作品として、《京都大学総合体育館》(1972)が登場する。設計者は京都大学で長く教鞭をとった増田友也(1914-1981)であり、同校の関係者から分かる人には分かる凄い人といった風に、カリスマ的に語られていたため、正直近づきがたい印象があり、展覧会の扱いはやや唐突にも思えた。

「モダン建築の京都」展の京都大学総合体育館模型

京都大学総合体育館
世代としては1913年生まれの丹下健三と同世代だから、東大と京大をそれぞれ代表するモダニズムの建築家と言えるだろう。ちょうど同時期に、《京都大学総合体育館》と道路を挟んで向かいの京都大学総合博物館において増田の建築展が開催された。彼の作品と活動をていねいに紹介しており、ようやくその重要性を理解することができた。特に興味深いのは、増田の建築が数多く建設され、ほとんど残っている鳴門市が共催し、映像や家具、過去の記録写真なども展示していること。そこでは建築論をきわめた哲人としてではなく、使用者の立場から、市民がいかに彼の建築を愛し、使っていたかをとりあげている。

京都大学総合博物館の展覧会案内パネル

鳴門市民会館の椅子

鳴門市民会館の椅子
今回の企画は、脱神格化しつつ、増田展を実現したことに加え、建築アーカイブズをどう扱うかというもうひとつの重要なテーマをもつ。実は2015年にも生誕100周年記念建築作品展が京都工芸繊維大学の美術工芸資料館で開催されており、そのときに制作された模型は「増田友也の世界」展でも活用されている。が、増田が残した膨大な資料、すなわち各種の図面、スケッチ、写真、メモ、研究ノート、手稿、領収書、手帳、チラシなどを、京都大学の田路貴浩、博物館の齋藤歩らが整理する京都大学研究資源アーカイブ事業の成果を反映したものなのだ★。どういうことか。例えば、完成した建築の図面よりも、途中のプロセスで描かれた図面を優先している。また大きな図面によってそれぞれの建築を紹介しつつ、手前では同時期に彼が考えたことを伝える、さまざまなタイプの資料が並ぶ。おそらく、見せることを主眼とする展覧会ならば、細々とした手前の資料は省くか、もっと点数を絞るだろう。しかし、今回は建築アーカイブズとは何か、またどのように整理するか(キャプションでは、「Ar MIXED 2017/2/S1/062」など、詳細な資料情報を記載)を知ってもらう試みでもある。その結果、京都大学総合博物館の企画展としては、通常よりもかなり広い面積をとって開催された。もちろん、国立近現代建築資料館でもアーカイブズを紹介しているが、本展はかなり意識的にアーカイブズとは何かに焦点をあて、今後の建築界が大いに参考にすべき試みとなっている。
★──京都大学研究資源アーカイブ「増田友也建築設計関係資料, 1938–1984(主年代1950–1981)」https://www.rra.museum.kyoto-u.ac.jp/archives/1666/

増田友也の世界」展会場
2021/12/05(日)(五十嵐太郎)
クリスチャン・マークレー 「トランスレーティング[翻訳する]」

会期:2021/11/20~2022/2/23
東京都現代美術館[東京都]
映像作品はたいてい長い割に退屈なのが多く、時間の無駄なのでチラ見しかしないが、クリスチャン・マークレーの映像は長いくせにずっと見ていて飽きることがない。今回は出品されていないが、ヴェネツィア・ビエンナーレで金獅子賞を受賞した《The Clock》は、映画の断片をつなぎ合わせて24時間を表現した文字通り24時間の長尺。ぼくは一部しか見ていないけど、時間が許せばすべて見たいと思っている。
出品作の《ビデオ・カルテット》は、《The Clock》に先行する作品。4面スクリーンにそれぞれ映画の登場人物が楽器を鳴らしたり、歌ったり、叫んだりするシーンの断片が次々と映し出されるのだが、それらの音がつながってひとつの「曲」を構成しているのだ。いわば映画のリミックスだが、原理がわかっても「はいおしまい」にはならず、繰り返し見ても飽きるどころか、見れば見るほど新しい発見があっておもしろさは増していく。それは映画の選択と構成の巧みさによるものだろう。
マークレーはもともと音楽シーンから出発し、レコードジャケットやコミックを使ったコラージュやペインティングを制作するなど、音楽と現代美術をつなぐ活動を展開してきた。例えば最初の部屋の《リサイクル工場のためのプロジェクト》は、奥行きのある旧式のパソコンのモニターを円形に並べ、工場でパソコンを解体する流れ作業を画面に映し出すインスタレーション。これから自分の身に降りかかるであろう運命を予知するかのような解体現場の映像を、モニター自身が流しているのだ。ユーモアと残酷さの入り混じった自己言及的な作品といえる。 《アブストラクト・ミュージック》は、ジャズなどのレコードジャケットに抽象絵画が使われることに目をつけ、タイトルやアーティスト名を絵具で消して原画の抽象絵画を復元させたもの。よくある遊びではあるが、カンディンスキーがシェーンベルクに触発されて抽象を始めたいきさつとか、ポロックがジャズ好きだったエピソードとかを思い出させる。こうした視覚と聴覚に関わる作品で笑えるのが、「アクションズ」のシリーズ。荒々しく絵具が飛び散るアクション・ペインティングの上に、コミックの「SPLOOSH」とか「THWUMP」といったオノマトペをシルクスクリーンで刷った絵画作品だ。絵具をぶちまけるアクションとオノマトペが見事に合致しているだけでなく、抽象表現主義にポップアートをレイヤーとして重ねることで、両者の差異と相似を示唆しているかのようにも見える。
「叫び」や「フェイス」のシリーズも、コミックから顔の部分をコラージュしたものだが、その選択と構成の巧みさといったら、どんなグラフィックデザイナーも顔負けだ。もう天性のヴィジュアルセンスとしかいいようがない。言い方は悪いが、他人のフンドシで相撲をとる大横綱だ。比べるのも酷だが、同時開催していたユージーン・スタジオが吹っ飛んでしまう。
2021/12/03(金)(村田真)
村越としや「息を止めると言葉はとけるように消えていく」

会期:2021/11/20~2021/12/18
amana TIGP[東京都]
会場に入ると7点の作品が展示されていた。イメージサイズは60×190cm。マットの余白とフレームがあるのでさらに大きく感じる。写っているのは横長の海の景色で、水平線がちょうど画面の中央に来ている。2012年から21年にかけて、福島第一原子力発電所近くの、ほぼ同一の場所から、6×17cmサイズのパノラマカメラで撮影されたものだ。雨、あるいは霧がかかっているのだろう、湿り気を帯びたグレートーンが、画面全体を覆いつくしているものが多い。
この「息を止めると言葉はとけるように消えていく」と題されたシリーズを見て、杉本博司の作品を連想する人は多いだろう。むろん、発想もプロセスもかなり違っているのだが、見かけ上は杉本の「Seascapes」と同工異曲に思える。人によっては、村越がずっと撮り続けてきた、実感のこもった福島の風景とは違った方向に進みつつあるのではないかと感じるかもしれない。彼もそのことを充分に承知の上で、あえてこの隙のない画面構成と、モノクローム・プリントの極致というべき表現スタイルを選択しているのではないかと思う。個人的には、その方向転換をポジティブに捉えたい。村越のなかにもともと強くあったミニマルな美学的アプローチを、むしろ徹底して打ち出そうとしているように思えるからだ。不完全燃焼に終わるよりは、より先に進んだ方がいいのではないだろうか。DMの小さな画像ではよくわからなかった、彼の全身感覚的な被写体の受け止め方が、大判プリントの前に立つことでしっかりと伝わってきた。
関連レビュー
村越としや「沈黙の中身はすべて言葉だった」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年03月15日号)
2021/11/30(火)(飯沢耕太郎)
遥かなる都市展
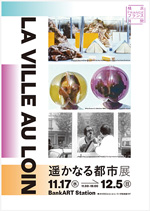
会期:2021/11/17~2021/12/05
BankART Station[神奈川県]
会場には映像を投影する9面のスクリーンのみ(そのうち4面は、2つの壁の表裏=両面を使用)。都市への批評的な提案をテーマとしながら、立体的な表現がないので、物足りないのではないかと思ったが、杞憂に終わった。1960年代や70年代に撮影された、興味深い作品がいくつか含まれており、しかも全体を鑑賞できるような各作品が適度な長さの映像だったのもありがたい。なお、この展示は「横浜フランス月間2021」のイベントとして開催されたものだが、前半は特にイタリア人が多く、後半もオーストリアやアメリカの建築家やアーティストを含み、むしろフランス人は少数派である。さて、建築の観点からは、いずれも「アーキラボ:建築・都市・アートの新たな実験展 1950-2005」 (森美術館、2004-2005)などでオブジェとしては見たことがあったが、アーキズームの《ノーストップ・シティ》(1971)やスーパースタジオの「基本的な行為:人生《スーパーサーフェス》(1972)の映像を初めて実見したのが大きな収穫だった。後者は地球の表面を均質なスーパー・グリッドで覆う《コンティニュアス・モニュメント》のプロモーション・ビデオといった趣である。
同時代のラディカルな建築家集団、アーキグラムが映像を制作していたことは、日本でDVD化されたことで知っていたが、アーキズームやスーパースタジオも試みていたわけである。かつてル・コルビュジエはその建築・都市論を映像化し、山本理顕は修士論文のためにアニメーションを制作していた。フィルムの時代における建築家による映像の系譜はまだ全容がわからないので、今後のテーマとなりうるだろう。さて、同展では、ハウス・ルッカー・コーの《イエローハート》(1968)と、フィレンツェ中心部の運動をとりあげたUFOの《都市現象no.6》(1968)が、改めて1968年の文化革命と空気膜のオブジェの強いつながりを示していた。ウーゴ・ラ・ピエトラ《街を取り戻す》(1977)は、ミラノ周辺に生成したセルフビルド的な家屋群を紹介している。またアント・ファームの《メディア・バーン》(1975)は、アメリカのアイコンである自動車とテレビを衝突させるパフォーマンスだった。なるほど、これらの作品は、やはり映像でしか伝えられないものだろう。
2021/11/27(土)(五十嵐太郎)
遥かなる都市展
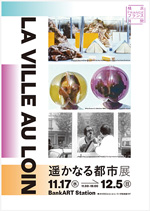
会期:2021/11/17~2021/12/05
BankART Station[神奈川県]
アーティストによる都市への介入や、建築家集団による都市のアート化の試みを記録した映像作品が公開された。アーキズームやスーパースタジオといった伝説的な建築家集団など、映像は全部で13本。うち60-70年代が7本と過半数を占め、90年代が1本で、2001年以降が5本と年代が偏っている。80-90年代が少ないのは、ポストモダニズムにかまけて建築もアートも前衛が後退し、保守化したせいだろうか。全部見たわけじゃないけど、チラッと見ておもしろかったのが、チャールズ・シモンズの《小さな家、冬》と、ジョルディ・コロメールの《アナーキテクトン、バルセロナ》の2本。
チャールズ・シモンズは、崩れかけた建物の一画に極小の手製レンガを積み上げて廃墟のような構築物をつくるアーティスト。映像は1974年のもので、ニューヨークやベルリンでの活動が記録されている。彼の作品は写真か、完成品しか見たことがなかったが、それがビルの廃墟に勝手に積み上げていくストリートアートだったと初めて知った。当時、路上で破壊活動をしたりデモンストレーションしたりするアーティストはいても、このように路上で勝手に作品をつくるアーティストはまだほとんどいなかった時代だから、彼こそ「ストリートアート」の先駆者といってもいいかもしれない。現在でも知ってか知らずか、ビルの隙間にミニチュアの廃墟みたいなものを組み立てるストリートアーティストがいるが、そういう若いアーティストにもぜひ見てほしいドキュメントだ。
ジョルディ・コロメールはバルセロナをはじめ、大阪、ブカレスト、ブラジリアなど世界各都市で「アナーキテクトン」なるプロジェクトを展開してきたアーティスト。アナーキテクトンとはアナーキーとアーキテクトン(ギリシャ語で「都市建築家」)の合成語だという。映像は2002年にバルセロナで撮られたもので、ビルの模型を棒の先に取り付けて実際のビルの前でデモンストレーションするというもの。コマ落としの映像なので、本物のビルと模型がほぼ同じ大きさで近づいたり、重なったりするシーンは思わず笑ってしまう。さっき見た松江泰治の「マキエタCC」を思い出す。
2021/11/26(金)(村田真)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)