artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
清里フォトアートミュージアム収蔵作品展 原点を、永遠に。─2018─

会期:2018/03/24~2018/05/13
東京都写真美術館[東京都]
1995年に山梨県清里に開館した清里フォトアートミュージアム(K★MoPA )は、これまでさまざまな活動を展開してきたが、特に35歳以下の若手写真家たちを対象に、公募で写真作品を収集する「ヤング・ポートフォリオ」は注目すべき企画である。今回の「収蔵作品展」では、海外および日本の著名な写真家たち66人が、35歳以前に撮影した作品に加えて、「ヤング・ポートフォリオ」のなかから29人の作品が選ばれて展示されていた。
全部で95人、409点という大規模展は、前期と後期に分けられている。前期の「歴史篇」は「1886~2016年の作品を撮影年代順に展示」したものだが、後期の「作家篇」は「作家名をほぼアルファベット順に展示」するという、よりラジカルな構成になっていた。つまり、展示の最初のパートで言えば、ベレニス・アボット、アンセル・アダムス、マヌエル・アルバレス・ブラボ、G.M.B.アカシュ、荒木経惟、有元伸也という具合に作品が並ぶ。このような、時代も、出身国も、作風もまったくバラバラな作品を、ごった煮状態で見せることは、一見混乱を招くように思える。だが、実際に展示を見ると、逆に隣り合った写真が乱反射して目に飛び込んでくることが、スリリングで刺激的な視覚的経験を呼び起こすことにつながっていた。
こうしてみると「ヤング・ポートフォリオ」にはじつに多彩な作品が選ばれていて、それ自体が現代写真のショーウィンドーとしての役割を果たしていることがわかる。ポーランド、ギリシャ、ロシア、中国、韓国、バングラデシュなど、写真家たちの国籍を見ているだけでも、多様な表現が花開いている。日本の写真家に限っても、本城直季、北野謙、亀山亮、林典子、東京るまん℃、下薗詠子など、次世代の写真家たちを育てるのに、大きな役目を果たしてきた。「35歳以下」という応募条件が、これから先も有効性を持つかどうかはやや疑問だが、続けていってほしい企画である。
2018/04/22(日)(飯沢耕太郎)
《障害の家》プロジェクト
京島長屋[東京都]
東京スカイツリーがどこからでもよく見える墨田区の一角を訪れ、大崎晴地による《障害の家》プロジェクトを見学した。2015年のアサヒアートスクエアの展示において、建築家とともに提唱していたものである。今回の展示では、関東大震災後につくられた老朽化した長屋が並ぶ街区において、2つの会場が用意された。いずれも解体予定の2階建ての建物だが、外観は手を加えず、その内部を徹底的に改造した。ひとつは水平の梁を残したまま、複層の斜めの床を新しく挿入し、上下の移動ができるように丸い穴があけられた。梯子や階段はない。斜めの床が接近する箇所の穴ゆえに、自らの腕の力を使い、身体能力を駆使して移動する。また下から見上げると、各層の円がすべて揃う視点も設けられている。
もうひとつは二軒長屋を仕切る中央の壁を抜くことで可視化される平面の対称性を生かしつつ、1階の天井(と2階の床)を外し、代わりにそれよりも低い天井と、以前の2階よりも高い床をつくり、3層の空間に変容させた。1階の天井と2階の床の間の本来、人が入らない空間が膨らんだとも言えるだろう。したがって、1階は立つことが不可能であり、はいつくばって動くしかない。また通常は隠された押し入れはむき出しとなり、両側の家を行き来するための空間となる。そして片側の新しい3階の床は瓦を敷き、その上部の屋根はスケルトンになっていた。
いわば既存の家屋に手を加えるリノベーションだが、建築と決定的に違うのは、役立つ機能に奉仕していないことだ。むろん、かつてバーナード・チュミは、プログラム論の文脈において不条理なリノベーションを提唱している。が、それはミスマッチであろうとも、何かの役割を想定していた。一方、《障害の家》は、使い方というよりも、訪問者の身体性に直接的に働きかけ、覚醒させることに賭けている。すなわち、バリアフリーではなく、バリアフルな家。荒川修作の建築的なプロジェクトを想起させるが、大崎はかつて彼をサポートしていたという。が、荒川がまっさらな新築をめざしていたのに対し、これは増改築である。それゆえ、日常的な空間の異化効果が加わっている。
 第一会場
第一会場
 第一会場、二軒長屋を仕切る壁が抜かれて、対称性が可視化される
第一会場、二軒長屋を仕切る壁が抜かれて、対称性が可視化される

第一会場、上下の移動ができるようにあけられた穴
 第二会場の1.5階
第二会場の1.5階
2018/04/22(日)(五十嵐太郎)
開館45周年記念展 絵画と想像力 ベルナール・ビュフェと丸木位里・俊

会期:2018/03/17~2018/06/12
ビュフェ美術館が開館45周年だという。ベルナール・ビュフェといえば戦後まもない時期に10代でデビューし、早熟の天才画家と騒がれたものだ。戦後の荒廃した時代気分を映し出すかのような鋭い線描は、贅肉をそぎ落としたジャコメッティの彫刻とともに実存主義にも結びつけられ、人気を博した。だが、こうした厳しい時代背景の下に生み出された芸術というのは、衝撃力はあるけど往々にして長続きしない。社会的にも個人的にも平穏な時代が訪れると次第にマンネリに陥り、また抽象芸術の全盛期には時代遅れと見なされていく。
まあ日本では地理的にも文化的にも時差があるので、この美術館が建った70年代前半にはまだビュフェの威光は輝いていた。今回初めてビュフェの作品をまとめて見て、いったいこの画家はモダンアートの文脈のなかでどのように位置づけられるのか、首をひねった。とくに60年代以降どんどんマンガチックになっていき、芸者を描いた《日本女性》や関取を描いた《相撲:睨み合い》などはご愛嬌としても、1988年の超大作「ドン・キホーテ」シリーズなど笑いをとろうとしたとしか思えないほど。
だが、最後に大展示室に掛かっていた作品を見て、少し見方が変わった。そこには丸木伊里・俊の《原爆の図第三部 水》と、ビュフェの「キリストの受難」シリーズ2点が比較できるように展示されていた。どちらも「受難」をテーマに同時期に描かれたほぼモノクロームの大作で、「原爆の図」は180×720センチ、「キリストの受難」は1点が280×500センチある。こうして比べてみると、「原爆の図」が水墨画ベースのため線が薄くて細く、意外にも黒い輪郭線でかたちづくったビュッフェの人物が力強く感じられたのだ。もちろんテーマも違うし、ビュフェはまだ若く勢いがあったころの作品だから、比較してもあまり意味はないかもしれないが、それにしてもビュフェの人物像に力強さを感じるとは、予想外の発見だった。
2018/04/22(村田真)
須田悦弘 ミテクレマチス
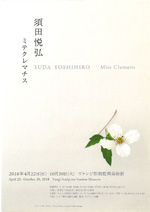
会期:2018/04/22~2018/10/30
クレマチスの丘 ヴァンジ彫刻庭園美術館[静岡県]
BankARTスクールの生徒たちと三島駅で待ち合わせ、無料シャトルバスでクレマチスの丘へ……と思ったら、日曜日の発着時間は40分もズレていたのでタクシーで行くことに。まずはヴァンジ彫刻庭園美術館へ。タイトルの「ミテクレマチス」はもちろんダジャレだが、クレマチスの花をテーマにしていることは予想できる。しかし須田のことだからどこに作品があるかわからないので気をつけなければ、と階段を下りながら作品リストを見ると、さっそく1点エントランスホールの「花」を見逃していた!
注意深く見ていくと、コンクリート壁の上下(決して目線の高さには置かない)に次々と花を発見。どれも一輪ずつポッと咲いている。作品名の《テッセン》《白万重》《ミケリテ》《モンタナ》は、いずれもクレマチス属の一種だそうだ。最後は円形の池に睡蓮を浮かべたもので、これが今回最大の作品だ。作品リストを確認すると1点見逃している。戻って探したら、壁にスリットが空いているではないか。のぞいてみると、床の隙間から雑草が生えているのが見えた。計7点すべてが、ジュリアーノ・ヴァンジの彫刻が置かれたメインギャラリーではなく、隅っこの階段やロビー空間に展示しているのが須田らしい。ひょっとしたらリストには載せてないけど、ヴァンジの彫刻にポソッと取り付けた作品があるんじゃないかと妄想が膨らむ(いちおう確認したけどなかったみたい)。
2018/04/22(村田真)
KG+ 2018 三宅章介「切妻屋根の痕跡のための類型学」

会期:2018/04/10~2018/04/25
Lumen gallery[京都府]
空き地に面した壁に、かつてそこに隣接していた家屋の痕跡が、屋根のシルエットや壁面の色の濃淡差として残されている。三宅章介は、そうした壁の痕跡をタイポロジーとして撮り集める。特徴的なのは、その「プリント」方法だ。撮影画像をモノクロネガに変換し、ギャラリーの壁面いっぱいに貼られた2×3mのモノクロ印画紙に、会期中1日6時間×3日間=18時間、プロジェクターで画像を投影して焼き付けていく。1枚目の画像の3日間の露光が終了すると、順次、2枚目、3枚目も同様の手法で進めていく(15日間の会期で計5枚の露光を行なった)。従って、会期が進むにつれ、既に露光が終了したもの/現在進行形で露光中のもの/ブラックシートで覆われた未現像のもの、という3様態が併存することになる。
プロジェクターからモノクロネガの画像を投影すると、光を強く受けた部分が感光し、徐々にポジ画像が浮かび上がる。 ただ、露光後も薬品の定着処理を行なわないので、時間の経過に伴い、室内光の影響を受けて全面に感光が進むため、やがて画面全体が黒化して画像が消失するのではないか。三宅は当初、そのように考えていたという。しかし、実際に行なってみると、6時間の露光を終えたあたりから、ソラリゼーション効果(一定量以上の光を受けると感光層のなかの銀粒子が破壊される)のためか、強く光があたって黒化すべき部分が逆に明るくなる反転現象が起きた。
三宅の試みは、やがて「壁」自体も解体され、物理的痕跡としても人々の記憶としても消滅していく存在を、時間的な有限性のなかで変化し、定着を拒むイメージとして差し出すものとして、まずは素朴に理解される。ここで考察をさらに進めよう。(フィルム)写真は、「かつてそこにあった存在」の視覚的痕跡を印画紙という物質に定着させる。「かつて隣接していた家屋の痕跡を宿した壁」は、すぐれて写真の謂いである。三宅の試みは、一種のメタ写真としての「隣家の痕跡を残した壁の写真」を、プロジェクターから投影される自身の「光」そのものによって焼き付け、現像/反転/変容させていくことで、幾重にもはらんだ自己言及性とともに、自己破壊のアイロニーをも含み込んで屹立する。

左:1枚目を18時間露光した後、さらに3日経過した状態。ほぼ完全に反転している。
右:2枚目を12時間露光した状態。ソラリゼーション状態が見られる。
2018/04/19(木)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)