artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
アートと考古学展

会期:2016/07/23~2016/09/11
京都文化博物館[京都府]
考古学のオリンピックと呼ばれる「世界考古学会議」が京都で行なわれることを記念した企画展。考古遺物を展示するほか、アーティストと考古遺物がコラボレーションした作品も展示され、芸術と考古学の共同作業とその可能性が紹介された。参加アーティストは、安芸早穂子、日下部一司、清水志郎、伊達伸明、松井利夫、八木良太の6名。アーティストが考古学をイメージソースとするケースはままあるだろうが、考古学は芸術を必要とするのだろうか。そんな疑念を抱きつつ展覧会を見たが、これがめっぽう面白かった。例えば、純粋に記録のために描かれた遺跡の図面に、ある種の芸術性を認める、陶磁器の断片が見立てひとつで作品に生まれ変わるといった事例が、そこかしこで展開されているのだ。考古学者とアーティストが互いに専門外の領域から刺激を受け、自分のフィールドを広げていく。これこそまさにクリエイティブではないだろうか。
2016/08/09(火)(小吹隆文)
古代ギリシャ─時空を超えた旅─
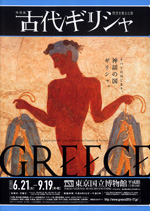
会期:2016/06/21~2016/09/19
東京国立博物館 平成館[東京都]
なぜいまギリシャなのか? と思ったのだが、展示に古代の競技のセクションがあったように、ちょうどオリンピックが開催されているからのようだ。われわれがよく知っている「美しい」古典の造形に到達する、はるか昔の紀元前6,500年頃までさかのぼり、ミノス、幾何学様式を経て、洗練の過程をたどることができる内容はとても勉強になった。
2016/08/07(日)(五十嵐太郎)
VvK Programm 16「赤い車が走り抜ける」

会期:2016/07/30~2016/08/07
KUNST ARZT[京都府]
VvK(アーティストキュレーション)の16回目は、中山和也のキュレーションによる企画。「ギャラリーの内部空間には一切作品を置かず、通りに面したギャラリーの窓から見える景色が作品鑑賞の場となる」というシンプルなルールだけが出品作家に課せられている。普段はモノと視線で充満した空間が空白化され、ギャラリーの窓は「外の景色を見る」という機能を取り戻すとともに、内と外、ギャラリー内部と路上、美術と日常の公共空間を媒介する装置となる。「ギャラリーの中に作品を置いてはいけない」というルールに素直に反応すれば、窓が切り取る景色のどこかに作品を仕込まねばならないからだ。あるいはこのルール自体をどう読み替え、逸脱するかが作品成否のカギとなる。
出品作品は、3つの軸に大別することができる。1)「窓」という物理的装置への介入、2)「窓」を介した視線の反転、3)現実空間とそこに内在する社会的ルールへの介入。まず、1)「窓」という装置への介入については、藤本由起夫の《there》とインテクストの《red car》が挙げられる。藤本の《there》は、玄関ドアのドアスコープに使われる魚眼レンズを窓辺に吊るして覗かせることで、中山によって決められた「窓というフレーム」の中に、もうひとつの眼差しのフレームを介入させるというもの。また、外山央、真下武久、見増勇介によるグループ・インテクストは、それぞれがデザイナーやプログラマーとして活動するなかで共有する興味や問題を取り上げ、文字、印刷、コミュニケーションについて考察する作品制作を行なっている。出品作《red car》は、窓ガラスに赤い文字で「CAR」と刻印することで、窓を開け閉めするたびに「赤い車が走り抜ける」という、ささやかだが詩的な想像力に満ちたものだ。
2)「窓」を介した視線の反転については、井上祐希《パラオからギャラリー監視》と小宮太郎《垂直で水平な風景(を撮る)》が挙げられる。井上の作品は、日本の真南に位置するパラオにギャラリーの椅子を持ち込み、会期中の開廊時間、その椅子に座って、海の彼方にある日本の方角を見つめ続けるというパフォーマンス。パラオは太平洋戦争の激戦地のひとつだが、戦後はリゾート地として「楽園」のイメージを付与されてきた。パラオから日本を「見つめ返す」井上のパフォーマンスは、占領地/楽園のリゾートという日本からの一方的な眼差しを反転させると同時に、「作品を見る」観客が「見られている」という眼差しの主客の反転を引き起こす。一方、小宮の作品は、ギャラリーの窓枠や壁、床、展示台、クーラーや電源コンセントにいたるまで、実寸大の模型をつくってさまざまな場所に設置し、「(フェイクの)ギャラリーの窓が切り取った風景」とともに写真に収めている。一見リアルなギャラリーの窓の向こうに突如出現する、住宅街、美大の制作室、松林と湖。よく見ると、展示台や壁には、その時々に「展示中」だった作品の複製が掛けられ、フェイクとリアルが奇妙に同居する。
3)現実空間とそこに内在する社会的ルールへの介入を行なったのが、中山和也《ピンクの川》と中本結《the vending machine is singing on the street》。中山の作品は、対面したビルのベランダや、建物どうしの隙間の細い路地に「ピンク色の柄のモップ」を3本立てかけたもの。無断の設置だが、会期中、モップは撤去されず、ずっと立てかけられたままだったという。「グレーゾーン」である空間や悪意のない清掃用具という絶妙なチョイスによって、建物の所有者と賃貸住人、隣人どうしの間で空間の所有権をめぐる暗黙の了解を浮かび上がらせる。一方、中本の作品は、街頭の自販機のジュースを、左右対称や交互など「美的な」ルールで並び替えたもの。こちらは業者に協力を依頼し、共犯関係に基づくが、商品の陳列という消費社会のルールに介入し、一時的な書き換えを行なっている。
このように本展は、展示空間から物理的な作品を消去することで、物理的な実体のみがアートの本質ではなく、むしろ作品を触媒に引き起こされた思考や想像力で充満する場であることを浮き彫りにしている。同時にそこでは、ギャラリーの「窓」という物理的/制度的なフレームが、「見ること」を批判的に問い直すとともに、外部の社会や公共空間と接続し、接触を引き起こす比喩的な「通路」としても機能していた。
2016/08/07(高嶋慈)
─画廊からの発言─ 新世代への視点2016

会期:2016/07/25~2016/08/06
ギャラリー58、なびす画廊、GALERIE SOL、藍画廊、ギャラリーなつか、ギャラリー川船、ギャルリー東京ユマニテ、ギャラリイK、ギャラリーQ、ギャラリー現、コバヤシ画廊[東京都]
毎年そうだが、今年も炎天下、銀座・京橋の11画廊を見て回る。40歳以下を対象とした企画展で、出品作家はぼくが見た11人中9人が女性。このなかでは最年長の佐藤万絵子(なびす画廊)はキャリアも15年に及び、もはやベテランの域だが、作品は相変わらずゴミタメのように新鮮だ。寺井絢香(ギャラリーなつか)はバナナの束を描いてるのかと思ったら、角棒の先に丸いものがついたマッチ棒みたいなものの集合体らしい。これは変! 村上早(コバヤシ画廊)と日比野絵美(藍画廊)はどちらもモノクロの銅版画だが、日比野の抽象形態に対して村上は具象、しかも村上はこってり個人的な物語を詰め込んでいる。繪畑彩子(ギャルリー東京ユマニテ)は映像と小品の展示。映像は水槽にカメや魚が泳ぐというもので、その顔や手足は人間のもの。ほとんどモノクロで、ちょっと懐かしいシュルレアリスムのコラージュを思い出させる。こういうクセの強い作品に比べれば、鉄による花の彫刻を置いた内山翔二郎(ギャラリイK)と、マユのような壷型の彫刻を出品した松見知明(ギャラリー58)のふたりの男性陣は、きわめて真っ当に見える。
2016/08/06(土)(村田真)
サイ・トゥオンブリーの写真 ─変奏のリリシズム─
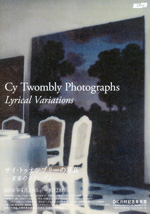
会期:2016/04/23~2016/08/28
DIC川村記念美術館[千葉県]
会期終了間際になって、ようやくサイ・トゥオンブリー展に足を運ぶことができた。これまでにも彼の写真作品は断片的には展示されたことがあるものの、これだけの規模の展示を見ることができるのは、まさに嬉しい驚きといえる。DIC川村記念美術館の会場には、初期から最晩年に至る写真作品100点のほか、絵画、彫刻、ドローイング、版画の代表作も並んでいた。
トゥオンブリーが写真作品を制作し始めたのは、1951年にノースカロライナ州のブラック・マウンテン・カレッジで、写真家のヘイゼル・フリーダ・ラーセンのピンホールカメラの授業を受けたことがきっかけだったようだ。つまり、絵画やドローイングとともに、ごく初期から視覚的な探求のメディアとして写真を意識しており、その後も断続的に作品制作は続けられていた。だが、それがまとまったかたちで展開されていくのは、1980年にポラロイド写真を使い始めてからである。今回の展示の中心になっているのは、ポラロイドで撮影したプリントを、複写機で2.5倍ほどの大きさに拡大し、さらにそれらをフレッソン・プリントやカラー・ドライプリントで、ややざらついた手触り感のある画面に仕上げた写真群だ。花、野菜、自作の絵画や彫刻などのクローズアップのほか、墓地や海辺の光景なども被写体になっている。どうやら、何を写すかよりも、そこにある事物が、写真、複写、プリントなどの操作を経ることで、どのように変容していくかに強い関心を抱いていたようだ。ここにも、トゥオンブリーの絵画やドローイング作品とも相通じる、「ものの流転」(things in flux)へのこだわりがあらわれている。写真をもうひとつの視覚として使いこなしていくことへの歓びが伝わってくるいい展示だった。
個人的には、以前から見たかった版画集『博物誌1 きのこ』の全作品が出品されていたのが嬉しかった。作品そのものに内在する偶発性、魔術性、多様性から見て、トゥオンブリーがきのこに強い親近感を抱いているのは間違いない。そういえば、彼の写真作品も、どことなく増殖するきのこの群れのように見えなくもない。
2016/08/06(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)