artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
片岡球子 展
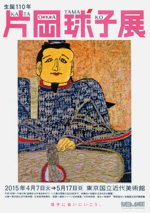
会期:2015/04/07~2015/05/17
東京国立近代美術館[東京都]
片岡球子(1905〜2008)と言えば、日本画の由緒正しい画題である富士山を、まるでヘタウマのイラストレーションのように大胆きわまるタッチで描いた日本画家という印象だった。しかし今回の回顧展で彼女の画業を通覧すると、そうした理解がいかに皮相であったかを存分に思い知らされた。
展示されたのは、昭和初期の作品から代表作「面構」のシリーズ、そして晩年の裸婦を描いた作品まで、資料を含めて100点あまり。何よりも印象深いのは、その卓越した描写力。一見すると、大胆不埒な画面のようだが、それはあくまでも全体の構図に由来するのであって、細部に目を凝らすと、とてつもない執着心で絵の具を塗り重ねていることがわかる。とりわけ着物の柄やレースの靴下などは尋常ではないほど緻密に再現しており、これはもはやフェティシズムと言ってもいいほどだ(だからこそ晩年の裸体画は着物の装飾性を自ら封印したがゆえに、筆先が上滑りしているように見えて仕方がない)。そのようにして徹底して細部に拘泥する一方で、全体としては豪放な印象を与える二重性に、片岡球子の真骨頂がある。
かつて片岡球子の絵を見た小林古径が「自分で自分の絵にゲロが出るほど描き続けなさい」と激励したという逸話がある。それが「ゲテモノ(下手物)」と評されることの多かった彼女の絵に対する、文字どおりの激励なのか、はたまた皮肉に満ちた逆説なのか、その真意はわからない。しかし、いずれにせよ、そのゲテモノ性を突き詰めたからこそ、小林古径のような優美な線と色によって構成された上手物の日本画には到底望めない、片岡球子ならではの画境を切り開いたことは間違いあるまい。日本画に限らずとも、師匠や先達の乗り越え方を鮮やかに示している点で、学ぶところは大きいはずだ。
2015/05/14(木)(福住廉)
林明輝『空飛ぶ写真機』

発行所:平凡社
発行日:2015年5月12日
『水のほとり』(愛育社、2001年)、『森の瞬間』(小学館、2004年)など、クオリティの高い風景写真集を刊行してきた林明輝は、近頃何かと話題になっているドローン(マルチコプター)にカメラを搭載して、2013年から全国各地を撮影しはじめた。ヘリコプターやセスナからの航空写真では、150メートル以下の高度での撮影はできない。だが、ドローンならかなり低い高度からでも撮影可能なので、カメラアングルや構図を自由に選択できる。まさに「鳥の目線だけでなく、時には昆虫の目線で」見た眺めを定着できるということだ。撮影機材が軽量化したことも大きかった、2400万~3600万画素という高画質であるにもかかわらず、重さは1キログラム程度のミラーレス一眼レフカメラの出現で、飛行時間が数分から20分に伸びたという。
結果として、「撮り尽くされたと思われる有名な景勝地であっても、新鮮な風景」が見えてくることになった。たしかに北海道から沖縄まで、四季とりどりの風景写真をおさめた写真集のページを繰ると、地上からの眺めとしては見慣れたものであっても、上方から思いがけない角度で見下ろした風景は、浮遊感を生み出す思いがけないものになっている。ただ、今のところはまだ「有名な景勝地」のネームバリューに頼っている写真も目につく。氷の穴の中に水が落ち込む「石川県/百四丈滝」の滝壺の写真のように、無名の景観に新たなピクチャレスクを再発見していくことが、さらに求められていくのではないだろうか。
なお、写真集の刊行にあわせてソニーイメージングギャラリー銀座で同名の写真展が開催された(前期5月1日~14日、後期5月15日~28日)。同展は来年4月まで山形、横浜、大田(島根県)、広島、東川(北海道)、富山などに巡回する予定である。
2015/05/13(水)(飯沢耕太郎)
遠藤一郎 個展「吉祥寺に潜伏しているというカッパ師匠の部屋」

会期:2015/05/06~2015/05/17
Art Center Ongoing[東京都]
遠藤一郎の個展。これまで「未来美術家」として全国のさまざまな現場で活躍してきた遠藤の、ある種のターニングポイントとなる重要な個展だった。
展示されたのは、積み上げられた大量のスピーカーとアンプなどを背に、ちゃぶ台の前で佇む遠藤自身。ただし、その姿は、顔面はもちろん手足の先までを緑色に塗りあげ、甲羅を背負ったもの。カッパ師匠が来場者にお茶を振る舞うパフォーマンス作品である。とはいえ、カッパ師匠は何かしらの演芸的なパフォーマンスを披露するわけではない。カッパの姿のまま会場に自然と佇み、来場者と雑談を交わすにすぎない。にもかかわらず、その情けなくも可笑しみのある風情が、なんとも味わい深い。「未来へ」や「GO FOR FUTURE」といった、じつにストレートで実直なメッセージを、並々ならぬ熱量によって発信してきた、これまでの活動からの明らかな方向転換である。
けれども、より重要なのは、その方向性だ。遠藤によれば、カッパ師匠とは愚直でだまされやすく、非力な妖怪であり、じっさい街を歩いていると、自らに注がれる視線には嘲笑や卑下の意味合いも含まれていることが少なくないという。遠藤は自ら、この情けない存在を引き受けたのだ。
思えば、遠藤一郎の名前が衝撃とともに脳裏に刻まれたのは、完成間もない六本木ヒルズに体当たりで突っ込む映像作品を見たときだった。「行くぞ! おい、みんな行くぞ!」と叫びながら、何度も何度も硬いコンクリート壁に激突する。当初はナンセンスな行動を笑っていられたが、次第に様子がおかしくなり、やがて真摯な悲壮感に心を打たれるようになる。自分の肉体を感電させて音を出す過激なパフォーマンスによってノイズ・バンドに参加していたように、かつての遠藤一郎は肉体の全身をフル稼働させることで、すべての神経を剥き出しにするような切迫感と緊張感にあふれていた。
だが、そのような切実な動機は、遠藤に限らず、ほとんどのアーティストにとって、それが切実であればあるほど、やがて自分自身から遠く離れていくことを余儀なくされる。そのとき、失われていく初発の動機を取り戻そうともがくのか、あるいは別の無難な動機に切り替えて乗り切るのか、アーティストのアティチュード、すなわち態度が問われるのは、おそらくこの点である。遠藤が素晴らしいのは、ある程度アーティストとして名を挙げたいまもなお、いや、いまだからこそ、見下される存在に自分自身を徹底的に貶めることを、この作品において見事に体現しているからだ。言うまでもなく、この作品が意味しているのは新たな面白キャラクターの発見などではない。それは、遠藤が、かつてとは違ったかたちではあれ、いまもなお、自分の肉体をある種の「壁」に激突させ続けているという厳然たる事実である。その、きわめて純粋な誠意に、改めて心を打たれた。
2015/05/13(水)(福住廉)
ディズニー美術
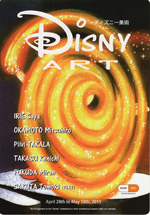
会期:2015/04/28~2015/05/10
KUNST ARZT[京都府]
ディズニーのキャラクターの引用・参照・置換といった表象の操作を行なう現代美術作品を通して、著作権と表現の自由、イメージの大量消費社会、現代社会批判としてのアートの意義を問いかける意欲的なグループ展。
企画者でもある岡本光博の作品は、ミッキーマウスのぬいぐるみの頭部を切り取り、使用可能ながま口ポーチとしてつくり替えたもの。吊るし首のように並べられたそれらは、キャラクターとしての同一性のなかに、色や目鼻立ちの多様なバリエーションを含み、それ自体がオリジナルとコピーの曖昧さを露呈させているようにも見える。また、切断した手足を縫い合わせた立体作品も展示され、マイク・ケリーへの参照ともなっている。福田美蘭の《誰ヶ袖図》は、桃山時代から江戸時代にかけて流行した、華やかな女性の衣裳を衣桁や屏風にかけて描く「誰ヶ袖図屏風」の形式を引用し、着物の代わりに様々なディズニーキャラクターのコスチュームを描き込んでいる。また、屏風には中東での日本人人質事件に関する画像が画中画として描き込まれ、「夢の国」の断片と映像越しの「現実」が混交した違和の風景をつくり上げる。両者の作品は、記号化されたキャラクターの引用のなかに美術史への参照を織り交ぜるとともに、社会に対するクリティカルな視点を提示している。
入江早耶の《ディズニーダスト》は、絵本に描かれたキャラクターを消した際の消しカスを練り上げてミニフィギュアを成形したもの。王子とドラゴン、白雪姫と魔女、ピーターパンとフック船長といった、善/悪の対立するキャラクターが、一つに合体したキメラ的な姿につくり替えられている。アメリカという国の背後にある善悪二元論の単純な世界観を浮かび上がらせるとともに、無効化が企てられている。
ピルビ・タカラの《Real Snow White》は、白雪姫のコスプレをした作家が、パリのディズニーランドに入場しようとして警備員に止められ、着替えさせられるまでの顛末を追ったパフォーマンスの記録映像。コスプレ姿の作家にサインをねだって集まる子供たちに対して、「本物」は園内にいると説明する警備員。作家と押し問答を繰り広げる様子からは、企業の著作権管理の生々しさや、架空の存在であるはずのキャラクターの「リアル」の認識をめぐる転倒したあり方が浮かび上がる。高須健市の作品は、ディズニーの登録商標をひっくり返した図像を商標登録として申請しようとする試み。特許庁の判断が下りるのは半年後とのことだが、ピルビ・タカラのパフォーマンス同様、アーティストがあえて戦略的に「敗け戦」を仕掛けることで、管理や排除の構造を露呈させることが企図されている。
知的財産の権利は守られるべきだが、「コピー商品」など商標の不正使用による著作権侵害と、アートとしての表現の自律性は明確に区別される必要がある。一方、表現者や美術関係者が過度に自主規制を行なえば、アートが本来持っている批評性は失われていくだろう。社会に対して圧倒的に弱い立場にあるアートと社会の関係を考えていく上で、本展の投げかける問いや果たす意義は大きいと思う。

会場風景 左:福田美蘭《誰ヶ袖図》 中央と右:岡本光博《Suhama / Recycling kills the copyright》 撮影:澤田華
2015/05/10(日)(高嶋慈)
フランス国立ケ・ブランリ美術館所蔵 マスク展

会期:2015/04/25~2015/06/30
東京都庭園美術館[東京都]
アール・デコの絵画や彫刻、装飾美術に用いられた主題には同時代のさまざまな社会状況、流行が影響している。東京都庭園美術館の前回展「幻想絶佳」(2015/01/17~2015/04/07)では、アール・デコと古典主義の関係が取り上げられていた。今回の「マスク展」に出品されているマスク──仮面は、フランスのケ・ブランリ美術館が所蔵するもので、もともとは世界各地から民俗資料として集められたもの。となれば、植民地として支配されたアジア・アフリカへのエキゾチシズムが西欧のアール・デコに与えた影響に焦点が当てられるのかと想像していたのだが、そうではなかった。
展示はいわばマスクをモチーフにした空間インスタレーション。庭園美術館本館のアール・デコの空間のあちらこちらに異形のマスクたちが佇んでいる。部屋の中央で堂々とした姿を見せるマスクもあれば、棚の中に小さく隠れているマスクもある。書斎ではいくつかのマスクがこちらのほうを見ながら浮遊している。一部露出展示もあり、そうでないマスクも本展のためにつくられたという台座の上に浮き上がって見える。特筆すべきは、ほとんどの展示室のカーテンが開いていて窓から光が入り、マスクの背景には緑の芝生の庭が見えることだ。「暗い室内にスポットライトで浮かび上がる異形の面」というイメージで臨むと、これもまた裏切られる。夕方、外が暗くなったらこれらのマスクがどのように見えるだろうかと考えたが、この時期、閉館時間の18時でも外は明るいのでそれも果たせない。展示品たるマスクは本来は祭祀などに用いられる民俗資料なので、そのような関心から本展を訪れる人もあろう。展示は、アフリカ、アメリカ、オセアニア、アジアと地域別になっており、それぞれの歴史、用途などについて解説が付されているが、民俗学的な関心に応えるほど詳細が書かれているわけではないので、おそらくそれは主題ではない。図録に掲載されたマスクの写真は一部分がアップにされていたり、レンズの被写界深度を浅くしてぼかしていたり、まったく図鑑的ではない。なにしろここは博物館ではなくて美術館なのだ。こうした文脈の中に日本の能面が並んでいることもまた奇異に思われる。つまるところ、こうであろうという想像、期待をことごとく外してくれているのだ。
こうした「期待」とのズレは、もちろん企画者が意図するところなのだろう。ケ・ブランリ美術館のキュレーター、イヴ・ル・フュール氏は、光の中にマスクを展示することについて、マスクが暗闇の中に展示されるのは西欧がかつてアフリカを暗黒の大陸と形容したような偏見に基づくものであり、それを変えるものとして本展示を企画したと語っている。西欧対非西欧は単に地理的な問題ではなく、先進的で洗練された文化と野蛮でプリミティブな世界という対比でもあった。2006年に開館したケ・ブランリ美術館が掲げた目標は「文明間の対話」というもの。その展示方法が文明間の優劣という文脈から相対化へと視点の転換を図るものと考えれば、この展示を「期待と違う」「ふつうとは違う」と考えてしまう私たちの「期待」と「ふつう」が、非西欧圏にありながらもひどく西欧的な価値観、西欧的なバイアスに犯されてしまっていることに改めて気づかされる。
疑問に思う点もある。新館展示室では映像アーカイブ「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカ」から世界各地のマスクを使った祭の映像が上映されており、おそらくそれは本来の文脈のなかでのマスクの役割を見せているのだろう。それはとても良いのだが、ここにヨーロッパの祭の映像があるにもかかわらず、本館には西欧のマスクはひとつも展示されてない。それはケ・ブランリが非西欧の造形だけを集めているためでもあるが、その意味はよく考えてみる必要がある。また、黒い背景にマスクを配したポスターやチラシなどの広報物、見返しにも黒い紙を使っている図録は、企画の主旨と展示の実際から考えると私たちの先入観と偏見に近いという意味でミスリーディングだと思う。[新川徳彦]



以上、すべて展示風景
関連レビュー
幻想絶佳:アール・デコと古典主義:artscapeレビュー|美術館・アート情報 artscape
2015/05/10(日)(SYNK)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)