artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
プレビュー:康本雅子『絶交わる子、ポンッ』/五反田団『宮本武蔵』/柴幸男(ままごと)『朝がある』

今月は公演が盛りだくさん。迷いますがマストは康本雅子『絶交わる子、ポンッ』(2012年6月28日〜7月1日@シアタートラム)。先日NHK『課外授業ようこそ先輩』にも出演していた彼女のじつに4年ぶりの単独公演。00年代に日本のコンテンポラリー・ダンスが意気揚々と誇示していた〈ポップで、ひねりが利いていて、リアルなダンス〉を、いまどんなかたちで展開してくれるのだろうか、期待が膨らむ。タイトルがまた康本らしい! 演劇では五反田団の『宮本武蔵』(2012年6月8日〜17日@三鷹市芸術文化ホール星のホール)が見たくてたまらない。「剣豪演劇」などと自称しているが、きっとふざけている。本番の舞台でふざけるという、よく考えるとなかなか大胆で自由で演劇批評的なことを前田司郎はやってのける。同じホールでは柴幸男(ままごと)の新作『朝がある』も行なわれる予定(2012年6月29日〜7月8日@三鷹市芸術文化ホール星のホール)。これは三鷹市の偉人「太宰治作品をモチーフにした演劇」という企画の第9回として柴が招かれて実現するもの。しかも柴が今回とりあげるのは女の子の1人語りがいま読んでも十分リアルな『女生徒』! これは、楽しみだ。
ままごと『朝がある』イメージビデオ
2012/06/01(金)(木村覚)
林千歩『You Are Beautiful──Love Primavera!』
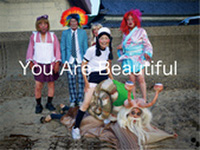
会期:2012/05/23~2012/06/03
Art Center Ongoing[東京都]
昨年末の会田誠による展覧会「美術であろうとなかろうと」に参加して話題になっていた林千歩。おもに写真と動画を用いて構成された展示では、おじさんのメイクをして街中をうろうろしたり、兎になって砂浜で小さな糞の粒を落としたりする、その過剰で脱線気味の変身願望に、並々ならぬ表現意欲を感じた。本作では在籍中の東京藝術大学大学院の研究室プロジェクトで昨年夏に小豆島に赴いた林が、現地の老人たちとともに、島の伝説に基づく変身譚を演じてゆく。インスタレーションの中心に据えられているのは動画で、そこで林はマイマイカブリ(巨大カタツムリ)に扮し、老人たちは林(マイマイカブリ)に会うことで変身するのだが、その際老人たちは林が持参した若者の衣裳を身に纏うことになる。ここで起きているのは、互いに相手の世界に入り込み、つかの間、相手の世界を生きるといった、相互に相手と自分の世界を交換してみるといったパフォーマンスだ。若者風の化粧を施し、体育着に着替えた老人たちの姿は、違和感があってむずむずする。孫ほどに年齢差のある若者のリクエストに応えてあげたいという、愛情のようなものさえ透けて見える。相手の世界に入り込むという試みは、映像作家の常套手段かも知れないが、林の作品に特徴的なのは、それを試みるに際して、変身譚を全員で演じるという仕掛けを置いていること。この仕掛けが、あるいは物語というものに潜むファンタジーの力が、相互に世界を交換する変身へと彼らをやさしく誘っている。そのマジックが、展覧会タイトルにある「美しさ」を引き出しているようだった。変身させてくれたお礼としてマイマイカブリは老人たちから「宝物」(かつら、タオル、帽子など)をもらう。この宝物はボッティチェルリ『プリマヴェーラ』の登場人物を演じる老人たちのレリーフとともに、一枚の絵画に収められていた。ここでも(『プリマヴェーラ』の)物語を演じるという仕掛けが、彼らの出会いを結晶化させるのに、上手く機能していた。
2012/05/31(木)(木村覚)
東京ELECTROCK STAIRS『最後にあう、ブルー』

会期:2012/05/10~2012/05/20
こまばアゴラ劇場[東京都]
ヒップホップのテクニックが体に染みこんだKENTARO!!主宰のダンスグループ、東京ELECTROCK STAIRSによる新作公演。いわゆる「日本のコンテンポラリーダンス」のなかでヒップホップをベースした作品というのはかなり異質。バレエ、モダンダンス、ポスト・モダンダンス、舞踏などを基礎にしつつも、たいていのダンス作家たちは独自のダンス言語を構築しようとし、観客は振付に織りこまれたその「言葉」を読みとろうとする。これに対してKENTARO!!が会話に用いるのはヒップホップというポップな言語。前者が砂から塑像をつくることに似ているとするなら、後者、つまりKENTARO!!の場合、同じことをレゴブロックで行なっているようなところがある。それぞれのパーツは、見なれた、一定のグルーヴ感をもったもので、それ自体に個性がない代わりにわかりやすい。時折、コミカルなジェスチャーや言葉が差し込まれつつ、それらが組み合わされると、「等身大の若者の肖像」がほのかに浮かび上がってくる。かわいくて、元気で、がんばっている若者だなと思う。とくにAokidのすべり続けるギャグやかっこよさとなさけなさとのあいだで固まったポーズなんてたぐいは、無邪気にいえば好きだ。けれど、そこで「人間」とか「社会」とか「歴史」が描かれることはない。一時間強の上演のあいだ、ダンスの振り、しぐさ、ポーズ、おしゃべりは観客を「くすぐり」続けるも、それらの身振りがひとつの物語あるいはメッセージへとつながることはない。「ひとつの物語あるいはメッセージ」なんてないから、観客は希望の「くすぐり」を選んで自由にくすぐられていればいい。その点、本作はとても現代的な作品構造をもっている。青春の肖像の周りに集うこのコミュニケーションが生み出すのは、外部のない、だから傷つくことのないよう構築された世界に見えた。
東京ELECTROCK STAIRS「最後にあう、ブルー」PV
2012年5月10日(木)~20日(日)@東京 こまばアゴラ劇場
2012年6月1日(金)~2日(土)@韓国
2012年6月22日(金)~24日(日)@京都 京都芸術センター(講堂)
2012/05/20(日)(木村覚)
トラジャル・ハレル『Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church(XS)』
会期:2012/05/19
森下スタジオ[東京都]
ニューヨークのダウンタウンを中心に活動するトラジャル・ハレルが本作で試みているのは、1960年代のニューヨークでともに活動し、しかし交流することのなかった2つのダンス、ひとつはダウンタウンの「ジャドソン・ダンス・シアター」、ひとつはアップタウンの「ヴォーギング」、これらを舞台上で出会わせてみるというものだ。白人のハイ・アートと黒人中心のクラブ・カルチャーのあり得なかった邂逅をコンセプトにするということも面白いが、XSからXLまでの5種類のヴァリエーションが本作にはあって、しかもタイトルの最後に「(XS)」とあるようにそれを衣服のサイズで表現しているのはとてもユニークだ。ヴォーギングがファッション雑誌『ヴォーグ』の表紙のポーズを真似ることから発展したダンスであるからという点だけではなく、そもそもファッションという第三の要素がハレルの興味のなかに含まれている証拠だろう。最初に、コンセプトを伝える資料が配られ、本人の口頭での作品説明のあと、資料をじっくり読むよう観客に伝えると、ハレルはいったん退場し、一度目は着物姿、二度目はカラフルなエプロン姿で現われ、家庭用の照明スタンドを舞台のあちこちに配置する。やや長いこうした準備の後で、ハレルは虎模様のスエット姿で登場する。照明が暗くよく見えない。舞台に置いたiPhoneからゆったりした音楽が流れると、ハレルはゆっくりと腰をくねらせるような踊りをみせた。暗くてよくわからないのは、恐らく戦略的な仕掛けであり、単にジャドソン系でも、ヴォーギングでもない、どちらかといえば腰のくねりや腕の曲がり方からゲイ的な身体動作の印象が強く残る。少し踊っては上着を一枚ずつ脱いでいくのだが、シャツの変化よりも、脱いで仕切り直したことだけが意味を持つ。準備の場面やシャツの着替えのように多数のフレームを設定し、多様な要素を示唆しながら、ひとつの理解に固定される事態をするするとかわし続ける。最初の作品説明の際、両手でTのジェスチャーをしたら終わりの合図だと言ったとおりに、ハレルがそのポーズを不意にすると真っ暗になり、終演した。そのときの尻切れトンボ感も「かわし」のひとつに思われた。
2012/05/19(土)(木村覚)
テッセンドリコ presents “Future Music”
会期:2012/05/05
東高円寺二万電圧[東京都]
「日本の近代は『幽玄』『花』『わび』『さび』のような、時代を真に表象する美的原理を何一つ生まなかった」。三島由紀夫が「文化防衛論」のなかで書き残したこの言葉は、「近代」の価値観やシステムがもはや隠しようがないほど破綻をきたしている現在、鮮やかに甦っている。いま、もっとも必要とされているのは、「近代」という呪縛から抜け出し、この時代を表象する美的原理に向かう衝動である。
全国の原子力発電所がすべて運転を停止したこの夜、切腹ピストルズのライヴは、ひとつの名状し難い美的原理に到達していた。それは、「東京を江戸に戻せ!」という彼らのメッセージからすると、前近代への回帰主義として理解できるが、だからといって必ずしも「幽玄」「わび」「さび」といった旧来の美的原理に回収されるわけではない。なぜなら、野良衣をまとった切腹たちが打ち出す太鼓、三味線、鉦の音、そして声は、私たちの心底に力強く響き、そのような静的な言葉で到底とらえられないほど、私たちの全身を打ち振るわせるからだ。平たく言えば、いてもたってもいられなくなるのである。
とはいえ、その衝動的な美は、三島が戦略的に帰着した「武士道」や「天皇」とも異なっているように思う。三島のヒロイズムが彼自身の足をすくってしまったとすれば、切腹の「江戸」はそのような逆説に陥ることがないほど、地に足をしっかりとつけているからだ。その重心があってこそ、借り物の「パンク」から出発しながらも、音楽性や楽器を徐々に変容させながら、身の丈に応じた「音」を生み出すことができているのだろう。21世紀の平民の、いやむしろ土民の思想は、ここで育まれるにちがいない。それをどのような言葉で語るべきか、いまはまだわからない。
ただし、切腹ピストルズがこの時代の最先端を切り開いていることはまちがいない。現代アートが「モダモダ」(今泉篤男「近代絵画の批評」『美術批評』1952年8月号)しているあいだに、彼らは颯爽と、美しく、そして強く、泥の中から来るべき時代を明るく照らし出しているのである。
2012/05/05(土)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)