artscapeレビュー
写真に関するレビュー/プレビュー
森村泰昌:ワタシの迷宮劇場

会期:2022/03/12~2022/06/05
京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ[京都府]
京都では24年ぶりとなる森村泰昌の大規模な個展。ただし、展示されるのは、撮影現場でのテストや「ひとり遊び」としてポラロイド写真で撮られた、ほぼ未発表のセルフポートレイト823枚。森村は、2016年のデジタルカメラ導入以前はフィルムで撮影していたため、現場での確認や調整のためにポラロイド写真を用いていた。「完成作品」に至るまでのさまざまなプロセス──ときに「引用画像」を胸に貼り付けてのポーズや表情の確認、衣装や小道具、ライティングの調整、腕や上半身に及ぶメイクのテストなど──が提示される。そこには、背景スクリーンの後ろにのぞく舞台裏、撮影機材、アシスタントの手、メイク・衣装・カツラを着ける前の森村の素顔や身体、そして私秘的な欲望など、「作品から排除されるもの」がきわめて生々しく写りこんでいる。その「メイキング過程」は同時に、森村が1985年以来歩んできた作家活動の、もうひとつの記録でもある。また、ポラロイド写真はフィルムと異なり複製不可能であり、「一回性」が刻印されている。「作品未満」である存在が「唯一性を持つ」という逆説。普段は表に出ない作家活動の履歴、排除された「作品未満」の集積という意味で、いわば「回顧展のネガ」だ。

森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M132》(2009頃)
[© Yasumasa Morimura]
展示会場には5つの入り口が用意され、決まった順路はなく、劇場の幕のようにドレープを描いて垂れ下がる重厚な布が、迷路のように配置される。その布の壁の前に浮かぶように展示された写真群は、「作品」と「資料」のあいだの宙吊り状態を暗示する。あるいは、布の壁は、「作品」の上演を待つ、開演前の舞台に降ろされた幕でもある。だが、その「幕」の向こう側をスリットからのぞくと、使用された衣装と靴、愛読書が並ぶ舞台裏のような空間(《衣装の隠れ家》)が広がっており、仮面を剥いでもその下に別の仮面が現われるようで、見る者を煙に巻く。迷路、見世物小屋、劇場のハイブリッド。また、写真群の配置にはシリーズごとのゆるやかなまとまりはあるものの、年代順や順路といった秩序の放棄は、アーカイブという迷宮を空間的に実装する。

「京都市京セラ美術館開館1周年記念展 森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」 展示風景
[撮影:三吉史高]

森村泰昌《衣装の隠れ家》(2022)
[© Yasumasa Morimura 撮影:三吉史高]
本展では、90年代の「女優シリーズ」に関連した写真が(インパクトの面でも)目につく。森村は、全裸のマリリン・モンローや緊縛シーンではあえて「つくりものの胸」を強調し、風ではためくマリリンのスカートの下に「勃起した偽のペニス」を装着するなど、「女性ではない身体」「男性の身体であること」を戦略的に露呈させていた。そこには、ヘテロセクシュアル男性の性的欲望に応えてつくられた女性像を、男性の身体で演じ直すことで、男性の性的消費の視線を無効化させ、返す刀で潜在的なトランスフォビアをあぶり出す批評性がある。さらに、「裸身や素顔のまま、女性の衣装やカツラをまとう」という「変身途中」のポラロイド写真の数々は、ジェンダーが「記号と演じられるもの」であることを示すと同時に、そうした批評の力を「作品」以上に有してもいる。

森村泰昌《ワタシの迷宮劇場 M010》(1994-95頃)
[© Yasumasa Morimura]
ここで、本展を別の角度から見るならば、「ポラロイド写真で撮影したセルフポートレイトの膨大な集積が作家自身の人生という時間の厚みを示す」例として、今井祝雄の「デイリーポートレイト」が想起される。今井が1979年5月30日からライフワークとして継続している「デイリーポートレイト」は、「前日に撮影した写真を手に持ち、1日1枚撮影する」というシンプルな行為の蓄積だ。だが、「手に持った前日の写真」には入れ子状に「その前の日に撮った写真」が写りこむため、(目視できなくとも)「撮影開始日から流れた時間」が1枚=1日ごとに加算されていくことになる。写真を列柱状に積み上げた展示では、「時間の層」が物理的に可視化されるとともに、列を追うごとに、次第に年齢を刻んでいく今井の顔の漸進的な変化がうかがえる。本展もまた、「複製不可能な一回性の蓄積により、作家の人生に流れた時間が『作品』を形成し、あるいは『作品』に飲み込まれ、不可分のものとなる」事態を指し示して圧巻だった。
関連記事
art trip vol.3 in number, new world/四海の数|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年02月15日号)
2022/05/06(金)(高嶋慈)
竹久直樹「スーサイドシート」

会期:2022/04/29~2022/05/22
デカメロン[東京都]
アーティ・ヴィアカントの《イメージ・オブジェクト》は、物理展示よりウェブサイトに掲載された作品写真の価値を高めるという転倒を起こした作品であり、ほとんどの人は記録写真しか目にすることがないなら、記録写真を作品にする方がいいという2010年代前半のイメージ論でもある。このとき、記録写真にとどまらないイメージはもうひとつのオブジェクトとして鑑賞者に提示されるのである。
展覧会「スーサイドシート」は、運転ができない作者の竹久直樹がロケでいつも車の助手席に乗るところに由来する。事故で真っ先に死ぬ席に乗るにつけてマクドナルドに寄り、帰ってはマクドナルドに寄ることが写真で、モニターではスマートフォンで写真のログを見直す様子の録画が流れる。モニターには、積み込み報告の写真、行き先のGoogleマップ、メモ用の写真。さまざまな用途の写真が流れる。たまにピンチインされる写真は、映り込んだものに対する撮影者の驚きや記憶を手繰り寄せたい様子を示す。マウスと同じサイズのミニカーは、ミニカーであると同時に「アエラスプレミアムらしきもの」であるがゆえに、あなたの背後にあるアエラスプレミアムのフロントの写真のようなものでもある。写真は死と指標性と偶発性によって語られてきたわけだが、車も竹久を死に近づける。その車の写真も実物も竹久にはいま同じに見えているのかもしれない。自作の前提となることを展示するにつけて、車を見ていたら写真は見えないし、写真をじっと見ていたらモニターも車も見えないインストール。それぞれは視界で交わることがないが、等質のものとして設置される。
 「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
 「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
《イメージ・オブジェクト》がオブジェクトよりもイメージにアウラを見出しうる時代の宣言だったなら、竹久はイメージもオブジェクトもシミュラークルも等価だ、あるいはすべては事故が起こる写真なのだと発したといえるだろう。もっと被写体と事故が選定された時代を語り得るものも今後見たい。写真の実在論としてのメメントモリ、indexの指示性と指標性、プンクトゥムとストゥディウムの往還、使用における身振り。これらとイメージ・オブジェクトを物差しにすることで、現在的な個人の写真のリアリティをさらりと示した展覧会で、面白かったです。
 「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
「スーサイドシート」展示風景[撮影:竹久直樹]
デカメロン/TOH「新宿流転芸術祭」:https://www.shinjukurutengeijutsusai.com/
2022/05/04(水・祝)(きりとりめでる)
新・今日の作家展2021 日常の輪郭/百瀬文

会期:2021/09/18~2021/10/10
横浜市民ギャラリー[神奈川県]
「わたしはあなたの個人的な魔女になる」。
百瀬文の映像作品《Flos Pavonis》(2021)で、遠く離れた地の知人に堕胎効果のある花を持って行こうとしたときに発せられたこの言葉を聞いたとき、自分自身のかつての経験について、まったく折り合いをつけられていなかったことがわかった。私と彼女が何を求めていたのか、そのとき、何に脅かされていたのかがわかっていなかったのだ。私が処置を提案した子が産まれ、祝福されるさまを見ていて、自己愛の強要でしかなかったかと思うと同時に、そのときに実は選択肢がなかったことを思い出す。「魔女になる」の一言がどれほどの具体的な救いであるか。船の上で堕胎手術を行なう団体の実際的な救済とはまた別に、この思想の伝播もまた救済である。
《Flos Pavonis》で女が強姦者の身体を反転させ馬乗りになり、自らの唾液でぬらした指を相手の口に押し込み、逃げる強姦者を目にした鑑賞者にとって、例えば「手籠め」という曖昧な言葉はどのような意味になりうるか。他者を圧倒的にあるいはうやむやに制したうえでの行為である。相手の自由を奪い、自己決定を無視することができる上で達するのだと提起される。そして、この地平から堕胎罪の存在を考えなくてはならないと。
本展で同時に展示された過去作《山羊を抱く/貧しき文法》(2016)。ヤギの空腹を待てば、百瀬は食紅で描いた絵をいつかヤギに食べさせることができるが、ヤギは顔をそむけ食べようとせず、百瀬との攻防が続く。百瀬がヤギを手籠めにせんとするときと、その紙を自分で食べると決めたとき。その二つの挙動が収められた作品の隣で、身体の自由を示そうとする百瀬。5年を経て、主題そのものでなく、その露悪性の経路が大きく変化したようだ。
公式サイト:https://ycag.yafjp.org/exhibition/new-artists-today-2021/
2022/05/01(日)(きりとりめでる)
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2022
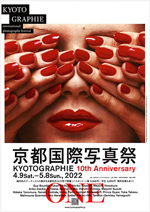
会期:2022/04/09~2022/05/08
京都府京都文化博物館 別館ほか[京都府]
このところ、コロナ禍もあって秋に会期を移していた「京都国際写真祭」が、ようやく通常通り4~5月に開催された。今回で10回目ということだが、前回からあまり間がなかったということもあり、華やかな印象はあまりなく、小さくまとまったイベントになった。
ギイ・ブルダン「The Absurd and The Sublime」(京都府文化博物館別館)、イサベル・ムニョス×田中泯×山口源兵衛「BORN-ACT-EXIST」(誉田屋源兵衛 黒蔵・奥座敷)、アーヴィング・ペン「Irving Penn: Works 1939-2007. Masterpieces from the MEP Collection」(京都市美術館別館)、奈良原一高「ジャパネスク〈禅〉」(両足院[建仁寺山内])など、それぞれしっかりと組み上げられた、クオリティの高い展示だったが、新たな展開が見えるというわけではない。
唯一、意欲的かつ刺激的なラインナップだったのは、細倉真弓、地蔵ゆかり、鈴木麻弓、岩根愛、殿村任香、𠮷田多麻希、稲岡亜里子、林典子、岡部桃、清水はるみが出品した「10/10 現代日本女性写真家達の祝祭」(HOSOO GALLERY)である。女性写真家たちを顕彰する「ウーマン・イン・モーション」プログラムの支援を受け、京都国際写真祭の共同創設者のルシール・レイボーズと仲西祐介、そして写真史家でインディペンデント・キュレーターのポリーヌ・ベルマールがキュレーションしたグループ展で、写真家たちの創作意欲を的確なインスタレーションに落とし込んだ充実した内容だった。
ただ、出品作家の表現の方向性があまりにもバラバラであり、なぜ、いま「現代日本女性写真家」という括りで写真展を企画するのかという意味づけも明確とはいえない。「複数の形態を持つ強く官能的な感情」を表出する殿村仁香「焦がれ死に die of love」と、父の死をきっかけに彼の故郷の村の祭事を撮影した地蔵ゆかり「ZAIDO」とを同居させるのは、やや無理があるのではないだろうか。とはいえ、東北の桜と伝統芸能とを撮影して震災とコロナ禍を結びつけようとする岩根愛の「A NEW RIVER」、北朝鮮に渡った日本人妻を丁寧に取材した林典子「sawasawato」の切迫感のあるインスタレーション、また、𠮷田多麻希、稲岡亜里子、清水はるみによる、これまで目にしたことがなかった新鮮なアプローチの作品を見ることができたのはとてもよかった。
「京都国際写真祭」も10回目ということで、ひとつの区切りを迎えつつある。いつも思うことだが、人選、会場、統一テーマ(今回は「ONE」)にあまり必然性が感じられないことなどを含めて、どのようなイベントにしていくのかを、もう一度再考すべき時期がきているのではないだろうか。
2022/04/29(金)(飯沢耕太郎)
平間至 写真展 すべては、音楽のおかげ

会期:2022/04/02~2022/05/08
美術館「えき」KYOTO[京都府]
タイトルがよく示すように、平間至の写真は「音楽」と強い親和性を持っている。宮城県塩竈市で写真館を営む父親は、チェロの愛好家でもあり、彼自身も子供の頃からヴァイオリンを習っていた。小学生の頃に初めて聴いたオーケストラの生演奏に衝撃を受け、10代にはパンク・ロックに夢中になる。写真家として活動するようになっても、「音楽」はまさに彼自身の表現活動のベースとして働き続けてきた。平間が撮影するミュージシャンの写真が、ほかの写真家たちとは一味違った、いきいきとした輝き、グルーヴ感を発しているのはそのためだろう。彼はミュージシャンたちと「音楽」という場を共有し、ともに巻き込み、巻き込まれていくやりとりを自在に行なうことができる写真家なのだ。
だが、初の回顧展というべき美術館「えき」KYOTOでの展示を見て思ったのは、平間の写真にはまた別の側面があるということだった。展示の中心になっていたのは、1996年からスタートしたタワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」のキャンペーンに代表される、「音楽」にどっぷりと浸かった、躍動的でエネルギッシュな作品群である。だが、平間にはもうひとつ、身の回りの事物を静かに見つめ、写しとっていく写真の系譜がある。今回の写真展でいえば、2011年の東日本大震災で実家のある東北の沿岸部が大きな被害を受けた後に、心身ともに消耗して、1年ほど自宅療養せざるを得なかった時期に撮影したという「光景」のパートがそうである。むしろ沈黙の声を聴き、それでもなお世界と自分とをカメラによってつなぎとめようと希求するようなそれらの写真群に、平間のもう一つの顔が覗いているのではないだろうか。動と静、その二つの要素が合わさったところに、写真家・平間至の写真世界の全体像が姿を現わすのではないかとも感じた。
2022/04/27(水)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)