artscapeレビュー
2016年10月01日号のレビュー/プレビュー
高倉大輔 個展 monodramatic/loose polyhedron

会期:2016/09/02~2016/09/24
TEZUKAYAMA GALLERY[大阪府]
2014年に発表し、国内外で反響を巻き起こした「monodramatic」シリーズと、新作「loose polyhedron」シリーズを出品。前者はあるシチュエーションを1人のモデルが演じるもので、モデルが分身して画面中に散らばっているのが特徴だ。後者は作家と同世代の20~30代の若者を被写体とし、彼らの喜怒哀楽、多面性、抑圧された感情を、写真と五角形のチャートで表わしている。幸い作家が在廊していたので、作品の詳細を聞くことができた。高倉はアーティストであると同時に演劇人であり、作品に登場するモデルも俳優やパフォーマーが務めている。そして高倉自身が彼らに演出をつけると同時に、一人芝居の要素を含んでいる。つまり演劇的要素の濃い写真作品なのだ。また、本展では1点だけ壁一面に拡大した作品があった。これが非常に効果的で、今後の展示スタイルに影響を与えるかもしれない。関西初個展を成功裏に終えた高倉。次回の来阪が今から楽しみだ。
2016/09/09(金)(小吹隆文)
グラフィックトライアル2016 crossing
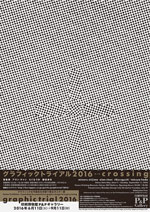
会期:2016/06/11~2016/09/11
印刷博物館P&Pギャラリー[東京都]
11回目となるグラフィックトライアルのテーマは「Crossing:横断・過渡・交差」。これまでのグラフィックトライアルではオフセット印刷における多様な表現の試みが行なわれてきたが、今回からはそれに加えてシルクスクリーンなどの特殊印刷技法も併用され、4名のクリエイターとプリンティングディレクターの協業によるユニークなトライアルが行なわれた。アラン・チャンのトライアルは陰陽五行説。森羅万象を司る木・火・土・金・水の5つの元素に宿る意味を、モチーフとなるオブジェ、5つの数字、用紙とモチーフの質感の印刷による再現によって表現している。特色金よりも特色イエローのほうが金の質感をよく表現できているところが面白い。えぐちりかのトライアルは剥離する印刷。オフセットとシルクスクリーンの組み合わせにより、触れたり擦ったりすると表面が剥離してその下の図像が現われるというテクスチャーを作っている。最終的なポスターには女性ヌードのモザイク写真がモチーフとして使われているが、表面を剥離すると何が現れてくるのか、じっさいに確かめてみることが出来なかったのが残念だ。保田卓也のトライアルは色の混ざり合い。オフセット印刷でグラデーションを表現するには網点を用いるが、今回のトライアルではあえて網点の角度を揃えたり、ベタ版の左右に異なるインキを入れて物理的に混色したり、印刷機のインキキーによって濃淡をコントロールするなど、印刷による再現というよりもオフセット印刷機を使った新たな表現の可能性を試みている。今回最も興味深いのは新島実のトライアルで、等明度な色彩空間をつくるというもの。色相は異なるが明度は同じ色。データを作ることは容易だが、印刷による再現には困難が伴うのだという。明度は同じであっても、彩度が異なると明るさが違って見える。隣どうし並んだ色の組み合わせによっても人の目には明るさが異なって見える。新島のトライアルではプリンティングディレクターの経験、知識、勘を駆使して人間の視覚に等明度と認識される色彩空間をつくりだしている。「機械と人間の感覚をどこまで『Crossing』できるかというトライアル」(新島)なのだ。[新川徳彦]
2016/09/10(土)(SYNK)
あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術

会期:2016/07/29~2016/09/11
京都国立近代美術館[京都府]
アンフォルメルとは、フランス人の美術評論家、ミシェル・タピエ(1909-1987)が構想した美的概念で、明確な輪郭を持たない形態や色面のなかで、作者自身による身体行為の痕跡や素材の生々しい物質感を前面化させた絵画や彫刻などを指している。日本には1950年代後半に導入され、岡本太郎や今井俊満が携わった「世界・今日の美術展」(日本橋高島屋、1956)を大きな契機として、爆発的に流行した。本展は、いわゆる「アンフォルメル旋風」が、油画や彫刻はもちろん、日本画、陶芸、生け花といった各種の芸術諸ジャンルに及んだ軌跡を検証したもの。九州派など一部の作品が展示されていなかったものの、それでも約100点に及ぶ作品が立ち並んだ展観は見応えがあった。
具体、九州派、そして反芸術──。戦後美術史の主脈を構成する運動や様式の出発点のひとつにアンフォルメルがあったことは、よく知られている。だが本展は、そのような主脈に位置づけられる荒川修作や工藤哲巳、高松次郎、田中敦子、中西夏之といった美術家だけでなく、麻生三郎、斎藤義重、末松正樹、鶴岡政男、難波田龍起、宮脇愛子、向井修二、村井正誠といった多様な美術家による作品も併せて展示することで、それが特定の運動体や表現形式にとどまらないほど大きな衝撃だったことを示していた。それは、まさしく日本の戦後美術全体を煽り立てた「旋風」だったのである。
本展の醍醐味は、その余波を克明に跡づけただけでなく、その前史として書との親和性を明快に打ち出した点にある。余白をあえて残した画面のなかに躍動感あふれる線の運動性を展開すること。確かに井上有一や森田子龍らの豪胆な書のあとで、白髪一雄や嶋本昭三、あるいは篠原有司男の《ボクシング・ペインティング》などを見ると、双方のあいだの強い連続性を痛感せざるをえない。線の強弱や色彩の有無は別として、いずれも激しい身体行為の痕跡を伺わせるからだ。「熱い抽象」あるいは「激情の対決」という言葉に示されているように、その荒々しいマチエールに作家の内発的な情感を見出すことも容易い。
企画者によれば、ミシェル・タピエはアンフォルメルを「あらゆる思想や形態の可能性をはらんだ混沌とした未分化な状態」として考えていたという(本展図録、p.6)。それゆえ、それは通常「非定形」ないし「不定形」と訳されることが多いが、そのようなタピエの狙いを踏まえるならば、むしろ「未定形」という言葉がふさわしい。そのような、ある種の原始性への志向性がアンフォルメルに内蔵されていることは、例えばジャン・デビュッフェが傍証となるに違いない。よく知られているように、タピエはデビュッフェをアンフォルメルの重要な美術家として評価したが、当のデビュッフェ自身はむしろアール・ブリュットを提唱し、タピエと異なるかたちで、西洋近代的な芸術概念とは「別の芸術」を構想したのだった。
しかし、その一方で改めて思い知らされたのは、「アンフォルメル」として括られたさまざまな作品の多くが、とりわけ絵画に限って言えば、明確な絵画意識によって構成されているという厳然たる事実である。ジョルジュ・マチューの《無題》(1957)は暗い背景に赤と白と黄と黒の線を勢いよくほとばしらせた絵画だが、それらの線がスピード感あふれる運動性を感じさせることは事実だとしても、画面のなかに配置された線の重層性は非常に調和されており、絵画としての美しさが保たれていることは否定できない。横山操の《塔》にしても、縦長の画面を貫く黒く太い線がきわめて暴力的な印象を与えつつも、それがかえって画面全体の統一感を担保している。その他の作品についても、作家の内発的な激情を看取できないわけではないが、それ以上に伝わってくるのは、見た目の激しさとは裏腹に、画面を精緻に構築する冷静な美意識である。つまり「別の芸術」と言えども、アンフォルメルは既存の芸術概念を根底から塗り替えたわけではなく、「別の芸術」という新たな意匠にすぎなかったのではないかという思いを禁じえない。
むろんアンフォルメルを戦後美術史を構成する重要な契機として歴史化するのであれば、それもよかろう。けれどもアンフォルメルの可能性の中心は、そのような歴史観を補強する点にではなく、むしろ根本から転覆しうる点にあったのではないか。結果的にその再生産に寄与することになったとしても、初発の動機には歴史を粉砕するほどの批評性が内蔵されていたに違いない。であれば本展に必要だったのは、例えば街中に描きつけられているグラフィティをアンフォルメルの今日的な展開として位置づけるような視点ではなかろうか。グラフィティには、かねてから線の運動性を重視する美意識が働いているし、昨今のグラフィティはスプレーやステンシルといった従来の画材や技法に加えて、粘着性の塗料や半立体の造形に挑戦しながらマチエールの前面化に取り組んでいるからだ。アンフォルメルは「あの時」に終わったわけではない。それはいまや、既存の「美術」を超えて、路上や巷にあふれ出ているのである。
2016/09/10(土)(福住廉)
星野高志郎 百過事展─記録と記憶─
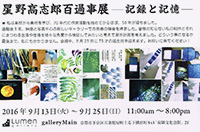
会期:2016/09/13~2016/09/25
Lumen gallery、galleryMain[京都府]
本展会期中に73歳の誕生日を迎えたベテラン作家の星野高志郎。これまでの活動を振り返る回顧展を、隣接する2つのギャラリーで開催した。作品は彼が活動を開始した1970年代から最近作までのセレクトで構成され、学生時代の石膏像なども含まれていた。そして作品以上に充実していたのが資料類で、ポスター、DM、印刷物、写真、映像、記事が載った新聞や雑誌、メモ、ドローイングなど多岐にわたる。さらに私物が加わることにより、会場は1日では見尽くせないほどの物量と混沌とした雰囲気に。美術家の回顧展であるのと同時に、一個人の年代記でもある風変わりな仕上がりであった。筆者はこれまでに星野の個展を何度も見てきたが、彼がこれほどの記録魔だとは知らなかった。資料のなかには貴重なものが含まれており、作品では1974年に富士ゼロックスのコピー機を用いて制作した《ANIMATION?》などレア物も。美術館学芸員や研究者が見たら、きっと大いにそそられたであろう。
2016/09/13(火)(小吹隆文)
キュンチョメ個展「暗闇でこんにちは」
会期:2016/08/27~2016/09/24
駒込倉庫 Komagome SOKO[東京都]
キュンチョメの新作展。2階建ての倉庫をリノベーションした会場の1階のフロアをすべて使用して展示を構成した。出品された作品の大半は、トーキョーワンダーサイト本郷で催された「リターン・トゥ」(2016年4月16日~5月29日)などですでに発表されたものだったが、それでも質の面でも量の面でも充実した展観だった。
《ここで作る新しい顔》は、《新しい顔》をバージョンアップしたもの。後者は、はるか遠い場所から逃れてきた難民と新しい場所で、福笑いのように新しい顔をつくる映像作品だが、前者は実際に東京に在住する難民を会場に常駐させ、来場者とともに目隠しをしながら新しい顔をつくるライブ・パフォーマンス作品である。来場者は、おのずと生々しいリアリティーとともに難民問題に直面することを余儀なくされるのである。
なかでもひときわ強い印象を残したのが、新作の映像作品《星達は夜明けを目指す》(2016)。暗闇のなか星座のような明かりが見えるが、それらが小さく揺れ動きながらだんだん近づいて来ると、7人の男女が二人三脚の状態で横一列になってこちらに進んでいることがわかる。彼らはロンドンで暮らす移民や難民で、口にそれぞれライトを咥えている。言葉を発することがないまま、目前の明かりを頼りに足並みをそろえて前進する姿。むろん彼らの逃避行をそのまま再現したものではないにせよ、その脱出と流浪の軌跡を象徴的に示したパフォーマンスと言えるだろう。
以上の3つの作品はいずれも移民問題を主題にしているが、ここに通底しているのは向こうからこちらにやってくるというイメージである。《星達は夜明けを目指す》は言うまでもないが、《新しい顔》にしても《ここで作る新しい顔》にしても、いずれも難民問題が決して遠い向こうの国の出来事だけではなく、まさしくこの国とも無縁ではないことを端的に示している。難民は向こうからやってくるものなのだ。
だが、このイメージは実はキュンチョメのこれまでの作品には見られない新たな局面を示しているようにも思う。なぜなら、彼らの秀逸な作品はいずれも、こちらから向こうに出かけていくイメージが強かったからだ。福島の問題にせよ富士の樹海における自殺問題にせよ、彼らは生々しいリアリティーのありかを求めて率先して各地に出かけてゆき、そこで何かしらの作品を表現してきた。むろん以上の3作品も海外へのレジデンスが基盤となっていることに違いはない。けれども、そのようにして制作された作品だとしても、そこにこれまでとは正反対のイメージが立ち現われていることの意味は決して小さくないはずだ。
それは、おそらくこちらとあちらの双方向的なコミュニケーションなどを指しているわけではない。そうではなく、むしろこちらが待ち構えることの意味を彼らが重視していることの現われではないか。待ち構えるからこそ、向こうからやってくるものに遭遇し、それらを受け入れることができる。《星達は夜明けを目指す》で彼らがカメラを通過する瞬間のぞくぞくした感覚こそ、待ち構える態度の醍醐味である。
2016/09/15(木)(福住廉)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)