artscapeレビュー
2016年10月01日号のレビュー/プレビュー
「WASHI 紙のみぞ知る用と美」展
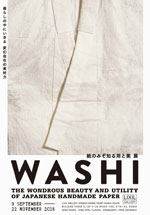
会期:2016/09/09~2016/11/22
LIXILギャラリー大阪[大阪府]
和紙の「美」についてはすぐ思いつくが、「用」の種類がこんなにあろうとは。本展は、生活の4シーン──纏う「衣」から、「食」の器、「住」空間の道具、「遊」び心ある愛玩具──に見られる、素材としての和紙の伝統的な可能性を提示している。和紙の寿命は洋紙に比べて長く、千年以上とも言われる。その耐久性に成形技術が足されれば、建具から布団、着物、お椀、傘、小物入れまで、用途は想像以上に幅広い。和紙の可変性にもびっくりしてしまう。紙をこよりにして編んでつくった丈夫な箱や傘、紙糸から織った柔らかくて気密性の高い衣類、紙の上に漆を重ねれば重さの軽い塗椀となる。展示品のなかでもロマンを感じたのは、明治期に西洋に盛んに輸出された「金唐革紙(擬革紙)」の小箱。1873年のウィーン万博で政府が出品して以来、ジャポニスムに沸く西欧で好評を得、国家主導(大蔵省印刷局)で製作されたもの。その人気は英国のバッキンガム宮殿の壁紙に使われたことでもわかるが、今は製造技術が殆ど失われて復活させるのは難しい。見た目はまさに厚みのある茶色い革、そこに浮き彫り調の凹凸で、金箔と朱色の豪華な植物文様が施されている。西欧の皮革製品を紙で代用して模倣するという技に、明治期の職人の執念を見る思いがする。私たちの暮らしを彩る変貌自在な和紙の力、ぜひ見直したい。[竹内有子]
2015/09/17(土)(SYNK)
大駱駝艦・天賦典式『パラダイス』

会期:2016/06/30~2016/07/03
世田谷パブリックシアター[東京都]
白を基調とした赤と緑の淡い色彩世界。「ゆるふわ」(信じられないかもしれないが、そんな女子向け形容詞が一番適切なのだった)の照明センスに、冒頭、驚かされる。「白」はダンサーたちの白塗り(本作のもう一つの基調は、男性のみならず女性ダンサーたちもほぼ全裸で白く塗られているところだった)とも反響する。舞踏らしからぬこの雰囲気が、大駱駝艦の今日的リアリティを強調している。20歳の観客があらかじめ情報に触れることなしに見たら、これはクレイジー・ホースと比べたくなる「奇怪なヌードショー」に映ることだろう。舞踏が積み重ねてきた歴史や伝統的側面を観客に反芻させるといった保守主義に一切与しない。だからこそのふわふわとした浮遊感。音楽になぞらえれば、その浮遊性はクラブ音楽的(テクノ音楽的)ということもできよう。短い動作をひたすら反復する。反復したら別の短い動作に変わる。起承転結のような展開は乏しく、「上げ」と「下げ」のみある。反復される短い動作は、GIFアニメのように淡々としている。そして、決してはみださない。ダンサーたちは、その鉄の掟のような「動作の反復」の奴隷である。はみださないのははみだせないからで、生物が遺伝子のプログラムに抗えないように、ダンサーたちは反復の連続というプログラム(振り付け)に抗えないようだ。タイトルの「パラダイス」とは、キリスト教的な背景を感じさせるもので、実際、知恵の実のごときリンゴをかじる場面も出てくる。パラダイスから追われても(そして自由を獲得しても)、人間の行なうことには限界があり、結局、遠く旅立ったようで、出発点に戻ってしまう。さて、大駱駝艦を見る際には、メタ的な物語から目をそらすことができないものであって、「ゆるふわ」な冒頭の色彩の下で、中心に直立する麿赤兒から放射線状に鎖が伸びてメンバーたちを縛っているさまは、このグループの師弟関係を連想させずにはいない。メンバーたちは鎖を外し、麿を置いて行く。ラストシーンでも、この「縛り」を「解く」場面が繰り返される。大駱駝艦ほど、若手と師匠が仲の良いグループは珍しい。それは単に師弟関係という以上に、世代の異なる者たちが共同で制作しているということでもあり、あらためて驚かされる。この仲の良さが、優しい「パラダイス」そのもののようでもある。
2016/07/01(金)(木村覚)
新聞家『帰る』

会期:2016/07/08~2016/07/10
NICA|Nihonbashi Institute of Contemporary Arts[東京都]
今作は「座る」作品だった。男女二人、向かい合わず、どちらも観客に顔を向けて座る。メロン(美術担当の川内理香子によって毎回異なる果物が用意されたという)が切られ、二人は食べながら話をする。対話というのではない。二人は交代で独り言のように話す。台詞は前回ほどではないけれども、耳に残りにくい。二人の言葉は、不安や、誠実さをめぐって、具体的には、傾いでしまったマンションとそこからの退去をめぐって紡がれている。言葉、その発話、食べること、座ること、また二人が横に並ぶこと。これらのどれもが等距離で並ぶ。「演劇」がしばしば演劇的身体の構築にその他のすべての要素を従属させてしまうのに比べると、新聞家の舞台はすべての要素が並立している。といいつつ、これはじゃあ「舞台」なのか。そもそも「演劇」なのかと問いたくもなってくる。観客は、ぼーっとしてくる。眠いわけではない。一般的な「演劇」のように一方向に収斂していない分、観客は集中力を求められ、いつか「苦い」ような顔になってしまう。(この状態をダンス史で形容するならば、イヴォンヌ・レイナーの「トリオA」みたいだと言ってみたくなる。レイナーはこの作品を観客に見ることの難しさに気づいてもらうために作ったという)換言すれば、いかに既存の演劇が「演劇」であることに縛られているかが新聞家を見ていると分かる。「ファッション・デザイナーではないひとが作る洋服」のように、洋服ではあるにはあるが「洋服らしさ」に縛られていない何かに身を包まれる。そんな風に、新聞家の演劇には「演劇」が引き算されている。この大胆なマイナスが、この作品を文学にも、朗唱にも、食事会にも、絵画にもする。ぼくにはこの作品は絵画的だった。果物を食べる男の肖像画と女の肖像画を二枚、50分かけて見続ける、そんな絵画的質を伴う鑑賞だった。ほとんど動かず座り続ける役者たち。目は自ずと凝視に変わり、細かい仕掛けに目を奪われる絵画鑑賞のよう。しかし、絵画が空間に質を閉じ込めたのに対してここでは質は時間のうちに閉じ込められている。要素の「並立」が生む、独自の演劇は、「演劇」よりもネット的情報需要に似ている。(この感じに似たものをあえて探すならば、core of bellsの「デトロイトテクノ人形」に似ている)多種類の情報ソースがどれもヒエラルキーなしに目や耳に飛び込んでくる状態。そこには「演劇的身体」に相当する「身体」は特にない。そんな「身体」を探そうとすると、途端に本作が「抜け殻」に思えてくる。抜け殻が初めて与える何か、それこそ新聞家が提示する演劇なのだ。アフタートークから類推するに、村社祐太朗はその「何か」に「愛」を見ているようだ。ヒエラルキーの支配を停止して初めて生じる見ること聞くこと。そこには対象への愛を生む余地がある。複雑で「モダン」な経路をくぐって実は愛へと達するのが新聞家なのだ。
2016/07/10(日)(木村覚)
鈴木ユキオほか「公共ホール現代ダンス活性化事業」
会期:2016/08/01~2016/08/03
東京芸術劇場[東京都]
上演作品だけが舞台芸術批評の対象ではないはずだ。例えば、ワークショップ(以下WS)というものがある。批評の埒外とされがちだが、作品の内在分析にとどまらず、作家の狙う芸術と社会との関係性を批評しようとする際、WSはその重要な1項目となるのではないか。WSは、アーティストの芸術観や思想が凝縮された形で、しかも、一般の参加者にも理解できるような仕方に整理された上で表現される場である。そもそも、上演作品は観客を受動的にするのに対して、WSは観客を能動的な参加者にする。その点で、WSには観客のあり方(もちろん、それに基づいた観客とアーティストの関係)を更新する可能性が秘められてはいないか。ぼくは今後、機会を見てWSを見学あるいは参加し(あるいはBONUSで企画し)、批評に試みてみようと思う。以下は、その最初の試みである。
「ダン活」の全体研修会(アーティストプレゼンテーション)を見てきた。「ダン活」とは一般財団法人地域創造による「公共ホール現代ダンス活性化事業」のことである。地域の公共ホールにダンス作家を派遣して、公演を行なったり、WSを行なったり、WSを経た後地域住民と公演を行なったりする活動である。この日は、派遣登録した6組の作家がプレゼンテーションし、客席側の公共ホールの関係者たちと実際に体を動かした。作家は、鈴木ユキオ、田畑真希、赤丸急上昇、東野祥子、田村一行、セレノグラフィカ。WSというものは「動かす/動かされる」という権力関係の発生する場である。ダンスは自由で生き生きとした表現の場と見られる一方、動きを支配する教師側と支配される生徒側とに分かれ、生徒側に自由はないということが起きる。学ぶとはそういうものだと言う者もいるだろうし、生徒とは嬉々としてそうした関係の渦中で学ぶ者だと言うこともできよう。体を動かすだけで十分に快楽がある。すると、作家の促しに答えるだけで満足は得られる。ただし、WSが単に受講者に与えるだけではなく、受講者とともに作るものとするなら、この状況は受講者を受け身にしすぎている。興味深かったのは、鈴木ユキオと田村一行という舞踏をルーツに持つ二人が、ともに「動かされる」自分を意識して欲しいと受講者に促していたことだ。受け身である(リアクションの状態)とはどういうことなのか。さらに興味深かったのは田村が、ひとを構成するのは多様なアクションに対するリアクションではないか、社会との多様な刺激への応答こそ自分であると言えるのではないかという趣旨の発言をしていたことだ。ダンスが社会へ貫通していることを示すこうした言葉こそ、ダンスの作家は発明しなければならないはずだ。
2016/08/02(火)(木村覚)
ポール・スミス展 HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH

会期:2016/07/27~2016/08/23
上野の森美術館[東京都]
2013年にロンドン、デザイン・ミュージアムで開幕した世界巡回展の東京展。日本ではすでに京都で開催され(京都国立近代美術館、2016/6/4~7/18)、このあと名古屋に巡回する(松坂屋美術館、2016/9/11~10/16)。
展示はポール・スミスの仕事そのものよりも、ポールの世界観、コレクションが生まれる場を見せる構成になっている。東京会場の最初の展示室は「アートウォール」。著名なアーティストの作品から、家族や友人、ファンから贈られたものまで、ポールが10代の頃から集めているという絵画や写真のなかから選ばれた約500点が壁を埋め尽くしている。なかには、ネットでジョーク写真として見かけたことがある画像のプリントもあり、どの作品も同種のシンプルなフレームに収められている。この展示が語るのは、作品のマーケットでの価値とは無関係に、ポールにとってのインスピレーション源としてこれらすべてがフラット、等価だということだろう。さまざまなオブジェが混沌と溢れるポールのオフィス、デザインスタジオの再現展示からも同様の印象を受ける。常にカメラを持ち歩いているというポールが撮影した写真による映像インスタレーション、他メーカーとのコラボレーション、一つひとつコンセプトが異なるというショップデザインが紹介されたあと、最後にファッション・ブランドとしてのポール・スミスの仕事、ショウの映像の部屋に至る。
この展覧会はデザイン・ミュージアムでは過去最多の入場者を記録したという。東京会場も若い人たちでいっぱいだった。会場は写真撮影自由。来場者には展覧会のイメージカラーであるピンクのイヤホンが配られ、スマートホンで無料の音声ガイドを聞くことができる。ポール・スミスという人物そしてブランドの世界観を伝える仕掛けとして、非常に成功していると思う。他方で、具体的なデザインのプロセスは曖昧だ。ポールは正規のデザイン教育を受けていない。彼はスケッチを描かない。自分は言葉でデザインするのだと語っている。ということは、誰か他のデザイナーたちがポールの世界観を共有し、彼の言葉を具体的な色や形に落とし込んでいるはずだ。再現されたスタジオの様子からその片鱗はうかがわれる。しかし他の人物の存在はほとんど語られない。世界約70の国と地域で展開するブランドに成長した現在でも、1970年にノッティンガムにオープンした最初の小さなショップと同様に、ここにはポールしかいない。ブランドとしてのポール・スミスは人物としてのポール・スミスと常にイコールなのだ。展覧会が見せているものと見せていないもの。その双方でブランドの神話はつくられている。[新川徳彦]
2016/08/10(水)(SYNK)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)