artscapeレビュー
2018年03月01日号のレビュー/プレビュー
谷川俊太郎展

会期:2018/01/13~2018/03/25
東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]
日本で最も有名な現代詩人といえば、谷川俊太郎だろう。谷川の作品のなかで好きな詩をひとつ挙げるとしたら、私は「カムチャツカの若者が きりんの夢をみているとき〜」で始まる「朝のリレー」だ。中学校の国語の教科書で初めて触れ、カムチャツカという未知の地への憧れや「ぼくらは朝をリレーするのだ」という斬新な表現に、中学生ながらお洒落な印象を抱いた覚えがある。このようにファンならずとも、多くの日本人が谷川の詩に触れた経験があるのではないか。
当初、「谷川俊太郎展」と聞いてどういう展示になるのだろうと思ったが、小山田圭吾と中村勇吾の名を見つけてニヤリとする。彼らはNHK Eテレの子供向けデザイン番組「デザインあ」で活躍する音楽家とインターフェイスデザイナーで、2013年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された同名の「デザインあ展」では展覧会ディレクターを務めた。本展のギャラリー1では言葉遊びの要素が強い「かっぱ」「いるか」と「ここ」の3作を題材に、谷川が音読する声と、小山田によるポップな電子音と、中村による弾けるような映像とがミックスされたインスタレーション作品が展開されていた。詩を体感するとはこのことだろう。
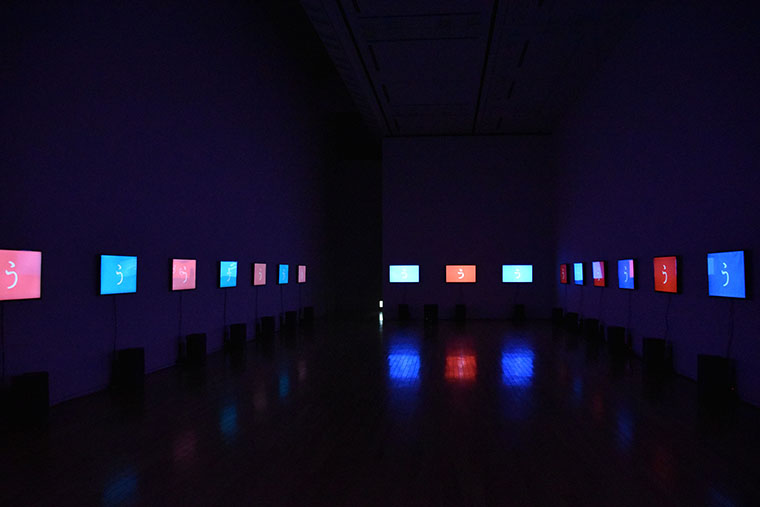 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1
展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1
詩の体感はこのあとも続く。ギャラリー2では「自己紹介」と題した20行から成る詩に沿って、20のテーマで、谷川にまつわる物が展示されていた。「私は背の低い禿頭の老人です」から始まる詩が1行ずつ柱となり、その側面が展示台に仕立てられていたのである。だから最初に目に飛び込むのは、20本の言葉の柱。それらは人の背丈より倍近く高いものがほとんどで、言葉の柱と言葉の柱の間を縫うようにして奥へ進んでいくため、ここでも詩を体感する。展示台には谷川が影響を受けた音楽や本、古いラジオ、書簡、家族写真など、個人的な物が並び、谷川が歩んできた人生や暮らしにぐっと迫る。
言葉の柱という点で、私はつい、2016〜2017年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「デザインの解剖展」を思い出してしまった。でも単なる偶然とは言えまい。なぜなら両展とも会場構成を手がけたのは同じ建築家、五十嵐瑠衣だったからだ。言葉をキャプションや解説という付属的な扱いではなく、展覧会の構成要素として重要な位置づけにすることで、言葉も展示の中心になりうるのだということを本展でますます実感した。
 展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2
展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2
公式ページ:http://www.operacity.jp/ag/exh205/
2018/01/12(杉江あこ)
村上華子展 ANTICAMERA(OF THE EYE)

会期:2017/12/11~2018/1/19
第一生命ギャラリー[東京都]
重厚な第一生命日比谷本店のビルを入ってギャラリーに向かうと、入口から金の額縁が目に飛び込んでくる。このギャラリーには似つかわしくない作品だなと思いつつ入室してみると、額縁ではなく、縁が黄金色をした大きなプリントであることがわかる。いやそれは最初からわかっていたんだけど、いちおう書き出しとして知らんぷりして書いてみました。第一生命がスポンサーを務める「VOCA展」で昨年、佳作賞を受賞した村上華子の個展。「ANTICAMERA(OF THE EYE)」と題するシリーズは、100年ほど前に生産されたものの、未使用のまま残されていた最初期のカラー写真「オートクローム」の乾板を現像したプリント作品。だからなにかが写っているわけではなく、100年のあいだにわずかながら光学的・化学的変化を起こしてシミのような偶然の模様が成長したのだ。額縁のように見えたのも、乾板の周囲にたまたま瑪瑙のような美しいパターンが現出したもの。作者もこれを見て「お、これは絵画だ!」と思ったのではないか。
2018/01/16(村田真)
Unknown Sculpture #6 末永史尚「ジェネリック・オブジェクト」
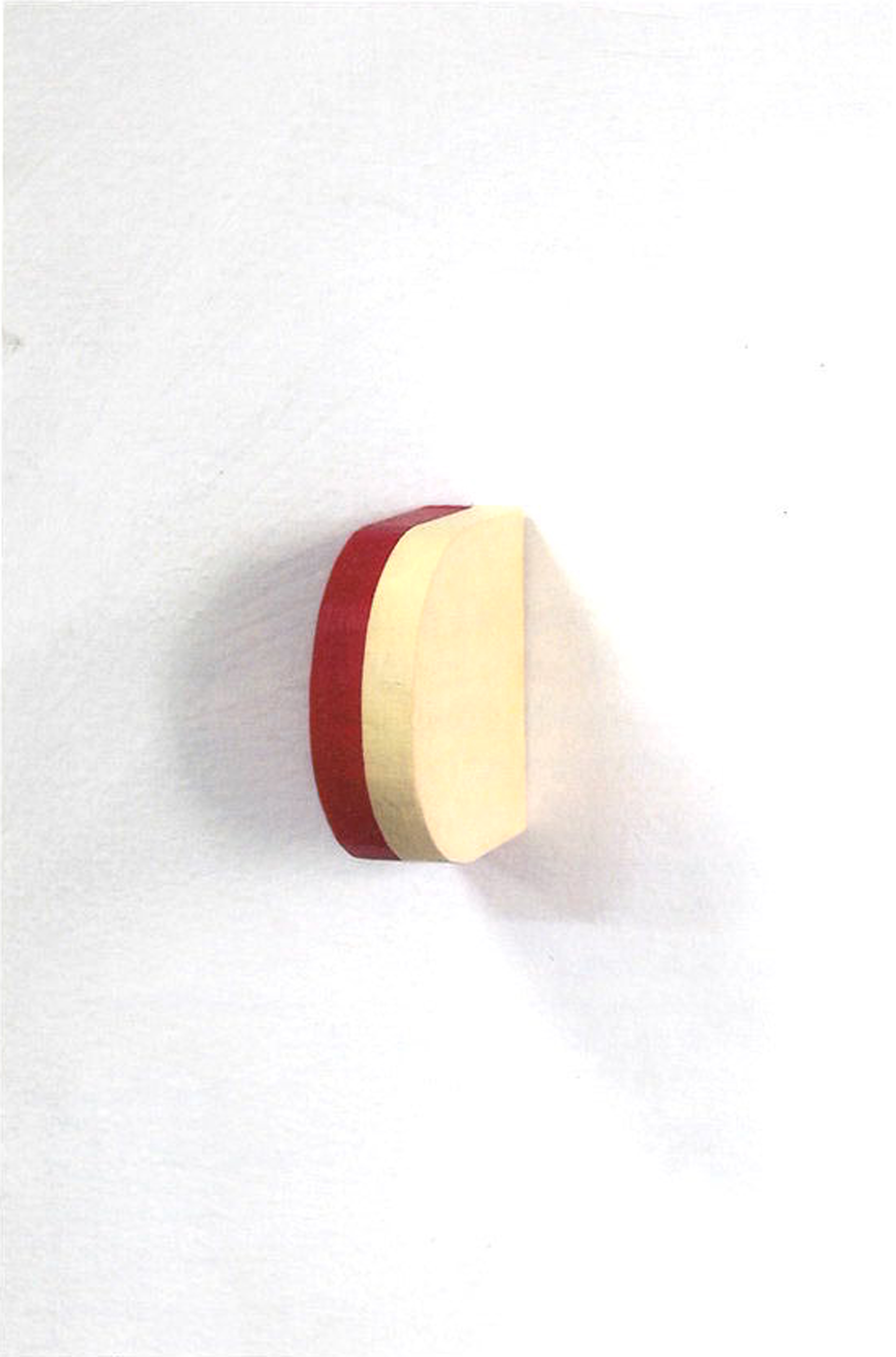
会期:2018/1/11~2018/1/28
ギャラリー21yo-j[東京都]
塀に使われるブロックが8個×2段で計16個、床に斜めに置かれている。そのいくつかにはバツ印や井桁、半円を山型に3つ重ねた青海波などの装飾が描かれている。タイトルの「ジェネリック・オブジェクト」から推測するに、これは最大公約数的なブロック塀か。四角い物体ならなんでも「絵画化」してしまう末永の新作だ(これは床置きなので「彫刻化」かもしれない)。壁には高さ5センチ、厚さ2センチほどの正方形や円形を組み合わせたような物体が突き出ている。が、展示している高さがそれぞれ異なり、色も赤や青などさまざま。これはなんだか見覚えがあるな……、この形、この大きさから察するにメジャー(巻尺)ではないか。ちょうど壁の高さを測っている状態にも見える。
ギャラリーの隅に目を転じると、ベージュと水色の四角い平らな箱がひとつずつ。これはなんだろう? ヒントは手ごろなサイズと、側面にある、折り曲げてできたような三角形にありそうだ。作品リストを見ると、正解はコピー用紙の包み。ま、正解もハズレもないが、モチーフはどれもそこらにある身近なモノばかり。それを「ジェネリック・オブジェクト」に還元して、壁、床、壁と床の境界といった絵画や彫刻の生息場所に置いている。いやーおもしろい。ギャラリーを出たら右手に青海波のブロック塀が目に入って来た。ここにあったか。
2018/01/18(村田真)
松下徹 開閉しろ都市 Part2「常磐の部屋」

会期:2018/01/12~2018/02/03
SNOW Contemporary[東京都]
白い放物線が少しずつズレながら何十本もきれいに引かれている。振り子から絵具を垂らして描いたそうだ。その曲線に沿って切り取った板を組み合わせて1枚の絵にしている。ほかにもペンキを塗った板を円や四角に切り抜いて別の板にはめ込んだり、厚さの異なる板をレリーフ状に重ねたり、余った端材を壁の下に並べたり。フランク・ステラのフォーマリズムとイミ・クネーベルの放置感とストリートアートの即興性をミクストアップした、最良のジャンクアート。
2018/01/24(村田真)
SCOOL パフォーマンス・シリーズ2017 Vol.6『高架線』

会期:2018/01/26~2018/01/29
SCOOL[東京]
私と関係したりしなかったりしながら、世界は常にそこにそれとしてある。そんな当たり前の、しかし確と実感することは少ない世界のあり方に、たしかな手応えをもって触れさせてくれるような舞台だった。
原作は芥川賞作家・滝口悠生の初の長編小説。脚本・演出は小田尚稔が手がけた。モノローグが連なって16年間の物語を紡ぐ原作は、観客に語りかけるようなモノローグを多用する小田の作風と相性がいい。原作の雰囲気をよく再現した舞台だったと言えるだろう。
西武池袋線東長崎駅徒歩5分、家賃3万のぼろアパート、かたばみ荘。そこに住む者はアパートを出るときには次の居住者を自ら連れてこなければならない。後輩・片川三郎に部屋を譲った新井田は数年後、三郎が失踪したと連絡を受ける。新井田にはじまり三郎の幼馴染の七見歩、その妻・奈緒子、三郎の後に入居した峠茶太郎、茶太郎の行きつけの店のマスター・木下目見、小説家を名乗る男・日暮純一、その妻・皆実と語り手はバトンタッチされ、話は互いに関係あったりなかったりしながら続いていく。
俳優たちは順に舞台に進み出てひとりずつ語っていく。自らの出番を終えた者は舞台奥に並べられた椅子に腰かけ、ときおり語り手に目をやったりはするもののただそこにいる。この仕掛けはシンプルだが効果絶大だ。物語は観客の目の前で紡がれる。俳優が観客と共有するSCOOLという空間に時間が堆積し、そこは「私たちの部屋」になっていく。
やがてかたばみ荘が取り壊されるそのとき、彼らはいよいよ一堂に会す。初めて彼ら全員が、いわば関係を持つ瞬間。つまり、舞台奥の椅子に控える彼らは、潜在する世界の可能性だったのだ。未来のある瞬間に、突如として私と関係を結ぶかもしれない世界の可能性。それが可能性のままだっていい。世界とはそういうものだ。だが、世界はいつも私に開かれている。
3月9日(金)からは同じSCOOLで小田尚稔の演劇『是でいいのだ』が上演される。


[撮影:前澤秀登]
2018/01/26(山﨑健太)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)