artscapeレビュー
星野太のレビュー/プレビュー
小林康夫『《人間》への過激な問いかけ──煉獄のフランス現代哲学(上)』

発行所:水声社
発行日:2020/09/30
長年にわたり、フランスの思想や文化と密接な関わりを持ちつづけてきた著者が、20世紀後半のフランス哲学を「人間」へのラディカルな問いとして総括した書物。その上巻にあたる本書では、おもにバルト、フーコー、リオタールの三者について過去に発表された時評的な文章が集められている。
本書は三部からなるが、第I部「フランス現代哲学の星雲」が、本書全体の導入にあたる。そこには、著者が80年代以降に著した数本の概説的なテクストが配されているのだが、それら「《人間》の哲学」や「《ポスト・モダン》の選択」──ともに初出は1987年──こそが、本書のトーンを決定していると言っても過言ではない。本書の表題に含まれる「人間」という言葉が重要な意味を担うのも、まずはそこにおいてである。
著者によれば、20世紀後半のフランス哲学をあえてひとつの言葉によって特徴づけるなら、それは最終的に「人間」という言葉へと帰着する。これは、いささか驚くべきテーゼだろう。というのも、ひじょうに大まかに言って、実存主義のあとに台頭した構造主義──およびポスト構造主義──には、むしろ既成の意味での「人間」を後景に追いやることによって展開してきたというイメージがあるからだ。「構造」にせよ「記号」にせよ「テクスト」にせよ、そこで探求されていたのは個々の主体に回収されることのない非人称的な次元であり、その意味で「人間」は世界の中心からの退位を余儀なくされていたとも言える。
しかし著者は、グザヴィエ・ティリエット(1921-2018)がメルロ=ポンティに捧げた「人間の尺度(la mesure de l’homme)」という表現に合図を送りつつ、そこで問われていたのは、あくまで「人間」をめぐる問いにほかならなかったと指摘する。なるほど、かつて「構造」や「記号」や「テクスト」といった合言葉のもとでなされてきた探求は、「人間」からその明証性を剥奪する営みと地続きであったと言ってよい。しかし同時にそれは、「現に生き呼吸している具体的な人間の尺度」をけっして忘れることがなかったし、超越的なものの探求においてなお「具体的な人間に注がれる眼差し」を手放すことがなかった(29頁)。本書のひとつの読みどころは、いまだフランス現代哲学が導入・紹介される途上にあった1980年代に、すでにそうしたことを指摘している著者の慧眼にある。
第I部と同じく、第II部(バルト、フーコー)、第III部(リオタール)も、著者の旧稿を新たに構成しなおしたものが大部分を占める。そのため著者の世代の仕事を追ってきた者にとって、そこにさほどの新しさは感じられないかもしれない。だが、70、78年の二度のフーコー来日に立ち会った著者の回想、さらにフランスおよび日本で行なわれたリオタールとの濃密な対話をはじめとして、ここには彼らのいまだ知られざる表情がある。そして、これまで単行本に未収録であったこれら数々のテクストから見えてくるのは、半世紀にわたりフランス哲学の「隣人」でありつづけてきた著者の「冒険」の軌跡である。あるいは本書の表現に拠るなら(8頁)、ここに読まれるのは、フランス現代哲学という星雲の「客観的なマップ」などではなく、むしろひとつの「内部観測」にほかならない。その意味で本書は、著者が言うところの「パッションに貫かれた《人間》」(29頁)が示しうる、ひとつのモデルでもあろう。
2020/12/03(木)(星野太)
許紀霖『普遍的価値を求める──中国現代思想の新潮流』

監訳:中島隆博、 王前
翻訳:及川淳子、徐行、藤井嘉章
発行所:法政大学出版局
発行日:2020/08/20
中国における「現代思想」について、日本語で知りうることはいまだ多いとは言えない。思想史的なアプローチをとったものとしては、本書の監訳者である王前の『中国が読んだ現代思想──サルトルからデリダ、シュミット、ロールズまで』(講談社、2011)という好著があるが、その地理的な範囲の広さも災いしてか、今日の中国における現代思想の勘どころを伝えてくれる学術書が、日本であまり見られないのは残念なことである。
本書は、現代中国を代表する知識人のひとりである許紀霖(1957-)がみずから選定した論文をもとに編まれた、日本語では初の単著である。巻末の出典を見てもわかるように、本書所収の論文が発表されたのはおおむねここ10年ほどのことであり、なおかつ論争的な性格をもつものが多くを占める。現代中国における思想状況を概観するための足がかりとして──とりわけ、評者のような門外漢にとっては──格好の一書である。
著者の中心的な関心事は政治思想にある。より具体的には、今日の世界的な状況のなかで、東アジアの新たな国際秩序をいかに構想するかということに、著者の関心は注がれている。東西のさまざまな思想を理論的フレームとして用いつつ、中国および東アジアの現状を見つめる著者の視線は、日本にいるわれわれのそれとも大いに重なり合うものであろう。
本書の中核をなすのは「新天下主義」という思想である。これは、古代中国における「天下」の概念をもとに、東アジアにおける「新しい普遍」を構想すべく生み出されたものである。著者によれば、この言葉にはさまざまな批判が寄せられており、「歴史上の中華を中心とするヒエラルキーの帝国が捲土重来してくる」のではないか、と懸念を抱く人もいるという(v頁)。ある意味ではそれも当然だろう。しかし、著者があえて「天下主義」という中華的な概念を持ち出してくるのは、西洋由来の「普遍主義」とは異なる、もうひとつの普遍主義を構想するためにほかならない。ここでいう「新」天下主義という表現にはむしろ、かつての天下主義の「脱中心化と脱ヒエラルキー化」を目指すという意味が賭けられているのであり、それをもとに著者は、ヨーロッパにおけるEUに相当するような共同体を東アジアにおいて構想することは可能だろうか、とわれわれに問いかける。
いわゆる普遍主義は、多元主義(多文化主義、文化相対主義)の尊重へとむかった20世紀後半の思潮のなかで、長らく旗色の悪い思想であった。しかし今日ではむしろ、狭隘なナショナリズムに対するカウンターとして機能しうるような、新たな普遍主義が必要とされている。許紀霖の議論が興味深いのは、「普遍」という概念にそもそも複数のかたちがありうるということを、ウィトゲンシュタインの「家族的類似」などに依拠しながら論じるところにある。おそらく本欄の読者にとっても、東アジアの「隣人」たる同時代の知識人が、いま何を考えているのかということは大きな関心事であるだろう。柄谷行人、汪暉、白永瑞らとの思想的対話のなかで練り上げられた本書の議論は、国家や言語の枠組みを越えた、東アジアの現代思想の一面を照らし出すものである。
2020/12/03(木)(星野太)
國盛麻衣佳『炭鉱と美術──旧産炭地における美術活動の変遷』

発行所:九州大学出版会
発行日:2020/01/31
炭鉱と美術──じつは評者にとって、このテーマは長らく気にかかるものであった。本書でも大きく取り上げられている「‘文化’資源としての〈炭鉱〉展」(目黒区美術館、2009)をひとつのメルクマールとして、炭鉱(ないし旧産炭地)に照準を定めた展覧会が、ここ十数年のあいだ目に見えて増加していることはよく知られている。さほど展覧会を網羅的に見ていない評者が実見したものに限っても、国内では前掲の「‘文化’資源としての〈炭鉱〉展」(2009)を、また国外では、元炭鉱街であるベルギーのヘンクを会場とした「マニフェスタ9」(2012)、そしてやはり元炭鉱街であるノルウェーのニーオーレスンに滞在したショナ・トレスコットの絵画作品(2012)などを挙げることができる。
本書『炭鉱と美術──旧産炭地における美術活動の変遷』は、みずから作家としても活動する著者が、2017年に九州大学に提出した博士論文を改稿したものである。大づかみに言うと、第1部は産炭地においてなされた文化活動についての歴史記述、第2部は旧産炭地を舞台とするアートプロジェクトの調査研究、そして第3部が著者本人による制作・発表・ワークショップなどの網羅的な記録と分析である。巻末には関係者のインタビューや、炭鉱を対象とした美術家たちのリストが付されるほか、本書のあとがきでは、祖父母が三井三池炭鉱の仕事に従事していたという理由もあり、なかば当事者として炭鉱をめぐる制作・研究に着手したという個人的な背景についても語られている。
ふつう「炭鉱と美術」というと、実際に当事者として炭鉱労働に従事していた山本作兵衛らの作品や、それを外部の目で描き出したルポルタージュ絵画などが第一に想起されるだろう。ゆえにその表題を一瞥するだけでは、本書がもっぱら旧産炭地における表現活動にのみ照準を合わせたものだという印象を受けるかもしれない。しかし先のように概観してみれば、本書の射程がそれよりはるかに広いものであることがわかる。たしかに本書の第1部では、おもに炭鉱・産炭地における文化活動に多くの紙幅が割かれている。だが第2部および第3部ではむしろ、閉山後に始まったアートプロジェクトに照準が合わせられることで、炭鉱という近代化の遺産をいかに継承するかという問題に関心がシフトする。著者の図(27頁)をやや改変しつつまとめるならば、本書は大きく(1)産炭地における芸術文化活動の歴史的研究、(2)炭鉱遺産の保存活用をめぐる文化資源学的研究、(3)旧産炭地におけるアートプロジェクトの研究、(4)創造都市論などを参考にした芸術文化環境の形成をめぐる研究──という4つの要素からなっていると言えるだろう。
本書を通して見られる著者の姿勢はきわめて真摯なものであり、立場の異なるさまざまな関係者に対して行なわれた巻末のインタビューも、それぞれ貴重なものである。関連資料も充実しており、日本をフィールドとした「旧産炭地における美術活動の変遷」について何かを知ろうとするとき、今後真っ先に踏まえるべき文献になることは間違いない。
その達成を踏まえたうえであえて注文をつけたいのだが、後進のためにも、巻末にはぜひとも文献表を付けてほしかった。また、これほどの情報量を含むだけに仕方のない部分もあるが、しばしば本文や註に固有名の誤りが散見されたことも、いささか残念であった。途方もない熱量をもって書かれたとおぼしき本書にそうした精確さが宿っていれば、本書は後世の人間にとって、より信頼に足る資料となったに違いない。
関連レビュー
國盛麻衣佳「be with underground」|村田真:artscapeレビュー(2011年10月15日号)
2020/09/17(木)(星野太)
井奥陽子『バウムガルテンの美学──図像と認識の修辞学』

発行所:慶應義塾大学出版会
発行日:2020/02/28
哲学の一分野としての「美学(aesthetics)」が、18世紀のドイツにおいて成立した歴史の浅い学科であることはよく知られている。また、この分野の入門書を手にとったことのある者なら、この美学という言葉がギリシア語の「アイステーシス(感性)」に由来すること、さらにそこからラテン語の「アエステティカ(aesthetica)」という言葉を鋳造したのがバウムガルテンという哲学者であることも、おそらく一度は耳にしたことがあるだろう。
アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテン(1714-62)は、美学という学問の創設者として哲学史に名を残す一方で、長らく「顔の見えない哲学者」(iii頁)であった──そのような興味をそそる導入から、本書は始まる。その先を読み進めてみるとわかるように、実はこの表現にはいくつかの含意があるのだが、たしかにバウムガルテンという人物について、従来われわれが知りえることはごくわずかであったと言ってよい。
なるほど、つい数年前にはバウムガルテンの『美学』の文庫化という画期的な出来事もあり(松尾大訳、講談社学術文庫、2016)、一見するとその思想に接近する土壌は整っているかにも見える。しかしながら、ライプニッツ(1646-1716)やヴォルフ(1679-1754)の影響を色濃く受けた、いわゆる「ライプニッツ=ヴォルフ学派」に属するこの哲学者の仕事は、今日のわれわれにとってけっして理解しやすいものではない。第一、その著書のほとんどはラテン語で書かれており、何よりも一次テクストへの接近に困難がある。また、本書の著者が言うように、今世紀に入り「バウムガルテン・ルネサンス」(vii頁)と呼びうる研究の大幅な進展が見られるようになったとはいえ、ドイツ語以外の(たとえば英語での)研究論文の数もいまだ多いとは言えない。
本書は、そのような状況において登場した、日本語としてははじめてのバウムガルテンの研究書である。博士論文が元になっているということもあり、記述は一貫して手堅く、隅々まで読んでもほとんど曖昧なところがない。ある意味では『美学』以上に重要な『形而上学』をはじめ、バウムガルテンの美学が総体として──すなわち周縁的なテクストも含めて──扱われた、モノグラフとしては理想的と言ってよい研究書である。実際に『美学』をひもといてみるとわかるように、バウムガルテンの論述は、ヴォルフ学派の特徴である過剰なまでの「体系」への欲望に貫かれている。それが読者にとっては躓きの石となりかねないところだが、本書は、各テクストの構成を示した簡便な資料を盛り込むことにより、この問題も巧みにクリアしている。
バウムガルテンの美学を総体としてとらえなおすために、本書はタイトルにもある「修辞学」との関係に注目する。もちろんこれまでにも、黎明期の美学──バウムガルテンやカント──における修辞学との関わりを論じた書物がなかったわけではない。しかし本書はそうした既往研究にも十分に目を配りつつ、バウムガルテンの『美学』を「拡張された〈一般修辞学〉」(185頁)の試みとして読むことができる、という斬新かつ説得力ある議論を開陳する。
研究書を読む醍醐味のひとつは、ふだん漠然と共有されている臆見が鮮やかに覆されることにある。この書評のはじめにも書いたように、バウムガルテンはもともと美学を「感性の学」として構想したのだ、ということが入門書などではまことしやかに言われる。とりわけ美学を「感性学」ないし「感性論」として再建しようとするここ数十年の試みのなかで、そうした言説はいっそう広まったかに見える。しかし厳密に言えば、バウムガルテンその人が「美学」に与えた定義は「感性的認識の学」にほかならなかった(71頁)。そして、この「感性的認識」とは、現在われわれが「感性」という言葉から連想するものとけっして同じものではない。本欄では、その先にある本書の核心部分を詳しく紹介するには至らなかったが、以上の消息を知るだけでも、本書を手に取る意義は十分にあるだろう。
2020/09/15(火)(星野太)
佐々木敦『これは小説ではない』
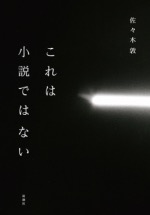
発行所:新潮社
発行日:2020/06/25
すでに広く知られているように、批評家・佐々木敦は今年に入って「批評家卒業」を宣言し、『新潮』4月号に「半睡」という初小説作品を発表した。今後も批評的なテクストは書きつづけるとのことだが、これまで著者がこだわってきた「批評家」の看板を下ろすという宣言は、わたしを含めた以前からの読者に驚きをもって受け止められた。
その理由や心境については、すでにいくつかのインタビューや著書のなかで明らかにされているため、ここで評者がわざわざ贅言を費やすにはおよばない。いずれにしても、佐々木にとって大きな節目となる今年、これまでの仕事を総決算するかのように、続々と新著が刊行されている。演劇批評集としては意外にも一冊目に当たる『小さな演劇の大きさについて』(Pヴァイン、6月)、これまで単行本未収録だったさまざまなジャンルの文章を集めた『批評王』(工作舎、8月)、雑誌『群像』での連載をまとめた『それを小説と呼ぶ』(刊行予定──『これは小説ではない』のあとがきを参照のこと)、さらに佐々木が編集長を務める文芸誌『ことばと』の創刊号(書肆侃侃房、4月)まで含めると、隔月以上のペースで何かしらの本が刊行されている。
本書『これは小説ではない』も、そうした一連の刊行ラッシュに連なるものである。しかしこの書物こそは、どうあってもこの著者にしか書けない、紛れもない主著のひとつと言って差し支えないように思う。本書のもくろみは、おおよそ次のようなところにある。すなわち、「小説とは何か」「小説に何ができるか」ということをはじめから大上段に論じるのではなく、「映画は小説ではない」「写真は小説ではない」「音/楽は小説ではない」「演劇は小説ではない」──というふうに、ほかの芸術ジャンルの可能性と限界を浮き彫りにしていくところから、来たるべき小説のポテンシャルを照射していこうという構えである。これまで「横断」ならぬ「貫通」をモットーとしてきた著者らしく、異なるジャンルを論じたどの章も、これ以外にないと思わされるような例示と分析で溢れている。
だが、おそらくこれだけでは、事の半分しか説明したことにならない。第1章「ラオコオン・エフェクト」に見られるように、本書はレッシングからグリーンバーグにいたる近代の「詩画比較論(パラゴーネ)」の基本を押さえるところから始まっている。しかし本書はそこから、各ジャンル(あるいはメディウム)の固有性とは何か、という安易な本質論にはけっして赴かない。本書の考察を導くのは、あくまでも具体的な作品である。しかも特筆すべきことに、その多くは必ずしも名作揃い(いわゆる「古典」)というわけではなく、著者が連載中に接した、あるいは過去に接してきた有名無名の作品群なのである。
かねてより、著者はたとえ大きな連載であっても、その時々に見聞した作品の「時評」を心がけているという旨のことを語っていた。それは過去の著書をひもといてみれば明らかだろう。本書もまた、紛れもなくそのような一冊である。そして、これだけ多くのジャンルにまたがるパラゴーネを遂行しつつ、それを同時に時評としても成立させることができるのは、佐々木敦を措いてほかにいまい。その意味で、本書は『新しい小説のために』(講談社、2017)や『私は小説である』(幻戯書房、2019)をはじめとするここ数年の小説論に連なる一冊であるとともに、映画から音楽へ、文学から演劇へと不断に軸を移してきた著者の、30年におよぶ批評活動の集大成でもある。
2020/07/27(月)(星野太)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)