artscapeレビュー
五十嵐太郎のレビュー/プレビュー
新しいタイプの図書館をまわる
[山口県、長崎県]
12月は《山口情報芸術センター》のほか、2つの新しいタイプの図書館建築を見学した。山口県の《周南市立徳山駅前図書館》と、長崎県大村市の《ミライon図書館》である。いずれも駅の近くに位置し、賑わいをつくる役割を担う。
前者の《徳山駅前図書館》(2014)は駅舎と並行しており、内藤廣が宮崎県の《日向市駅舎》や《福井県年縞博物館》などで得意とする120mに及ぶ細長い建築だ。プログラムとしては、1階は蔦屋書店とスターバックス・コーヒー、2・3階は図書館、そのほかキッズライブラリー、市民活動支援センター、交流室などが入る。三層の図書館の各レベルから大きく張りだすテラスが特徴であり、気持ちよい空間だ。ここから駅前広場を見渡すことができる。

駅舎と並行している《徳山駅前図書館》(2014)の外観

《徳山駅前図書館》内部。階段脇にはプリントされたフェイクの本棚が

《徳山駅前図書館》の外階段から見た細長いテラス
近年、地方都市の駅に近い公共建築が健闘しているが、これもそのひとつだろう。なるほど「賑わい交流施設」をうたうだけあって、周囲の寂れた商店街と対照的に多くの人が集まる。それにしても、佐賀県の《武雄図書館》をはじめとして、蔦屋書店とスターバックス・コーヒーの組み合わせは、2010年代における公共施設の新しい風景として完全に定着した。今後これに代わるモデルは登場するのだろうか。

徳山駅前の寂れたアーケード商店街
佐藤総合計画が手がけた《ミライon図書館》(2019)は、カタカナとアルファベットと漢字を組み合わせたキラキラネームが気になるが、JR大村駅から歩いて3分ほどの複合施設である。県庁所在地ではない地方都市としては、かなり立派な建築だった。これも部分的にリニアーな構成をもつが、ゆるやかに弧を描くヴォリュームの内部では、細い柱が並ぶ大スパンの吹き抜けにおいて、段状の図書空間がダイナミックに展開する。奥の閉架書庫に耐震性能をもたせることによって、見事に開放的な室内を実現したものだ。

ゆるやかに弧を描いた《ミライon図書館》(2019)
小さいエントラスから入ると、巨大な船底天井をもつ吹き抜けに包まれ、思わず視線は上を向く。平面の形状は、末広がりである。また象徴的な大屋根は雨水を集めて、ランドスケープに供給するという。プログラムとしては、1階(児童書やおはなしのへや)、2階(学習スペース)、3階(開架・閲覧スペース)でゾーニングを行ない、天井が高いために、個別の書棚には照明装置も付く。1階のギャラリーに沿って、奥に進むと、郷土資料を展示する歴史資料館もある。ここはカフェも併設されているが、蔦屋書店やスターバックスに頼ることなく、気持ちよい公共建築を実現していた。

吹き抜け部分の巨大な船底天井が目を引く

高い天井には県産の木材が使われ、各書棚には照明装置が付けられている
2020/12/05(土)(五十嵐太郎)
山口の美術館をまわる
[山口県]
山口市の展示施設をいくつか訪問した。鬼頭梓による《山口県立美術館》(1979)は、地味だけどよい建築である。煉瓦の外壁は、《宮城県美術館》や《東京都美術館》など、彼の師匠である前川國男の打ち込みタイルを想起させるだろう。すぐ近くの《山口県立山口図書館》(1973)も、むしろ鬼頭が得意とする図書館の作品である。

煉瓦の外壁が特徴的な《山口県立美術館》(1979)

こちらも打ち込みタイルの外壁が目を引く《山口県立山口図書館》(1973)
さて、《山口県立美術館》では、やはりコロナ禍によって、2020年度は特別展の企画が延期になったり、コレクション展示室を閉じるなど、大きな影響を受けたようだが、こうした状況を逆手にとった企画展示を開催していた。タイトルは「Distance─ディスタンス」である。すなわち、「生と死」や「男と女」など、6つのキーワードを軸にして、澄川喜一、須田一政、細江英公などの収蔵品を見せるものだ。作品の配置も、かなり疎だった(もっとも、解説のツールなしで鑑賞すると、作品選択の意図がわかりにくい)。なお同館は、香月泰男や雪舟のコレクションが目玉なのだが、後者に関しては、一部屋の三方の壁をまるごとプロジェクション映像で使った「パノラマ山水図巻」が、展示サイズも大きくて細部がよく見えた。

展覧会スケジュールには昨年春から「休室」が目立っている

《山口県立美術館》のカフェスペースもソーシャル・ディスタンスが保たれていた
温泉街の生家にたてられた《中原中也記念館》(1994)は、宮崎浩が設計したものであり、師匠の槇文彦譲りの端正なデザインによるコンクリート打ち放しの建築だった。屋外にフレームを設けることで、L字の変形敷地をまるごと建築化しつつ、奥に引き込むエントランスへのシークエンスをつくる。
展示で印象に残ったのは、これまで学校の教科書に掲載された中原の詩を調査し、時代による傾向の変化や人気作品を紹介する企画だった。文学館は美術館と違い、ビジュアルの要素が難しく、どうしても資料展示にならざるをえないが、詩人の記念館は展示の可能性があると感じられた。なぜなら、小説は文章が長すぎて無理だが、詩は全文を展示しても、その場で読めるからだ。つまり、作品の全体性を絵画や彫刻のように表現できる。実際、《アーツ前橋》や《太田市美術館・図書館》では、アートとともに詩を展示する方法をすでに試みていた。

右奥にまで引き込んでから、室内に入る《中原中也記念館》(1994)
大きな緑地に面した磯崎新による《山口情報芸術センター[YCAM]》(2003)では、映画のプログラムが開催されていた。10年以上前に訪れたときは、アートと図書館が完全に分離するわけでなく、内部に挿入された複数の細い中庭に勉強する学生がいる風景を見て、プログラムを横倒しにした《せんだいメディアテーク》のようだったことが印象に残っている。だが、コロナ禍ゆえか、今回はその中庭が活用されていなかった。クラインブルーが鮮やかな図書館の大空間は変わらず気持ちいいが、レストランが閉鎖されていたのも気になった。

《山口情報芸術センター[YCAM]》(2003)

筆者が13年前に訪問した際の《YCAM》中庭スペース
山口県立美術館 特別企画展「Distance -ディスタンス」
期間:2020/10/31〜2020/12/21(会期変更)
会場:山口県立美術館
2020/12/05(土)(五十嵐太郎)
ザ・タワー・ホテル名古屋
[愛知県]
10月にオープンしたばかりの《ザ・タワー・ホテル名古屋》を見学した。日建設計がリノベーションを担当し、エレベーター棟を脇に増築しつつ、《名古屋テレビ塔》(1954)の4階を13室・ギャラリー・レストラン、5階を屋外のバルコニーをもつスイートルーム2室に改造したものである。ベッドの脇を斜めの鉄骨が大胆に貫通し、室内にいても、ここがテレビ塔だったことがわかるデザインだ。もともと《名古屋テレビ塔》はそれほど高くはないが、久屋大通公園のど真ん中にたち、立地がよいので、見通しもよい。また杉戸洋や森北伸など、地域ゆかりの現代アートの作品が室内やフロントに飾られ、ギャラリーでは愛知県美術館の副館長、拝戸雅彦がキュレーションを担当した展示「smokes in the clouds」を楽しめる。

《ザ・タワー・ホテル名古屋》のロビー。アート作品が飾られ、斜めの鉄骨が貫通している

《ザ・タワー・ホテル名古屋》のゲストルーム。ここにも鉄骨が見える

《ザ・タワー・ホテル名古屋》関連グッズ

ギャラリーで開催されていたグループ展「smokes in the clouds」展示風景
《名古屋テレビ塔》は、電波塔の役割を終えた後、一時は解体される恐れもあったが、かくしてアートホテルとして見事に再生した。現在、コロナ禍によりインバウンドの客はいないが、名古屋のシンボル的な構築物ゆえに、泊まりたがっている地元客で賑わっているという。
このプロジェクトで思い出されるのが、あいちトリエンナーレ2010に参加した西野逹の実現されなかったアイデアである。彼は、マーライオンや駅舎の時計塔など、街でもっとも有名な場所をホテル化することで知られているが、当時、最初は名古屋城の金鯱のホテル化を提案し、それが難しいと判明すると、テレビ塔のホテル化を考えていたらしい。結局、これは実現しなかったが、それから10年後、状況が変わって、テレビ塔が本当にホテルになったという意味では、アートがテレビ塔の未来を予言したと言える。
一方、タワーの足元の久屋大通公園では、店舗群が入る《レイヤードヒサヤオオドオリパーク》が9月に誕生した。確かに人は集まっているのだが、安普請のアウトレットパークのような商業施設を都心の最重要地点につくるのは、なんとも残念である。かつて東京タワーに先駆けて、名古屋にテレビ塔を建設したときの気合いから比べると、なんとも志が低い。それが今の日本らしさかもしれないが、どうせつくるなら、テレビ塔と張り合えるような建築をめざしてほしかった。

久屋大通公園にオープンした《レイヤード ヒサヤオオドオリパーク》

左に付加された構築物は、ホテルとレストランへの専用入口となるエレベータ棟

上から見下ろした《レイヤード ヒサヤオオドオリパーク》
2020/11/15(日)(五十嵐太郎)
太田市美術館・図書館、群馬県立館林美術館をまわる
[群馬県]
おそらく4回目くらいの訪問となる《太田市美術館・図書館》(2017)にて、地域資源をいかした展示の活動についてヒアリングを行なう。図書館側の企画として、巡回展「世界のバリアフリー児童図書-IBBY選定バリアフリー児童図書2019-」が開催中だった。図書とのつながりでは、来年(2021)の頭にも「2020イタリア・ボローニャ国際絵本原画」展が予定されている。一方、開館3周年記念展として開催予定の「HOME/TOWN」展のように、地域を再発見する美術展の路線も続くようだ。ともあれ、天気がよい日に屋上をぐるぐる歩くのは、気持ちがいい建築である。

《太田市美術館・図書館》で開催されていた「世界のバリアフリー児童図書」展の展示風景

《太田市美術館・図書館》屋上の様子
その後、太田市美術館の元学芸員の小金沢智から前におすすめされていた近くの鰻屋、1914年に創業した《野沢屋本店》でランチのつもりが、思いがけず、きわめて濃厚な飲食になった。建物の外見もすごいのだが、待ち構える主人のペースで、目の前で鰻をさばく様子を見た後、どこまで盛っているかわからないディープな太田市の昔話を聞きながら一緒に飲むという展開で、約1時間半を過ごした。娘がオーストラリアに嫁いだこともあり、英語がしばしば混ざる、ルー大柴のような語り口も強烈である。これぞ生きた地域の資産だろう。太田市長も美術館の設計者である平田晃久もここに来たらしい。建築を見学した後、ぜひ訪れてほしいスポットである。

《野沢屋本店》の外観
最後は、第一工房による《群馬県立館林美術館》(2000)に足を運んだ。駅からタクシーで行きエントランスの前で降りると、せっかくのシークエンスが楽しめない。歩いていったん建物から離れ、オンサイトが手がけたランドスケープを堪能しながら、洗練された美術館に向かう(維持費がかかるため、手前には水が流れなくなっていたが)。大きな弧を描くアプローチから美術館に目を向けると、かなり幅が広く、でかい建築のように見えるが、実際は細長いプランを横から見ているためで、奥行き方向にはさほど伸びていない。

《群馬県立館林美術館》の外観

第一工房による《群馬県立館林美術館》の建築模型
さて、内部のプランは、1階レベルにおいて作品の搬出入・収蔵・展示をすべてコンパクトにまとめた機能的な計画である。2階が学芸員のエリアだ。月が欠けたようなプランの展示室1は、全面的に光が入る個性的な空間ゆえに、フランソワ・ポンポンによる動物彫刻群などが置かれていた。また別館は、コレクションの目玉であるポンポンのフランスのアトリエを外観・内観ともに再現しており(ワークショップ室も入る)、現代建築の真横に異世界が混入したかのようだ。

《群馬県立館林美術館》展示室1の様子

《群馬県立館林美術館》別館、ポンポンのフランスのアトリエを再現したつくり
2020/11/14(土) (五十嵐太郎)
群馬の美術館と建築をまわる
[群馬県]
リサーチ・プロジェクトの一環で、群馬の美術館をいくつかまわる。《群馬県立近代美術館》の「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展は、伝説の場で開催された展示の数々を写真で振り返りながら、過去の出品作をセレクトして紹介し、日本現代美術の一断面を切りとるものだった。また、同美術館の改修と、この展覧会の空間構成を担当した元磯崎新事務所の吉野弘から説明を受ける。改めて、これが1970年代としては画期的な大きなホワイト・キューブを実現したことがわかる。

《群馬県立近代美術館》展示室の模様

「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展、展示風景
美術館が良好な展示環境を維持しつつ、さらに拡張しているのに対し、隣の大高正人による《群馬県立歴史博物館》(1979)は、おそらくリニューアルによって展示物が増え、連続する船底天井がほとんど見えない。トップライトも閉鎖し、中庭へのアクセスも限られ、蔵を意識した外観もわかりにくい。空間に余裕をもって展示する美術館と比べて、どうしてもモノや説明が増えてしまう博物館の建築的な空間を維持するのが難しいことを痛感する。

《群馬県立歴史博物館》の外観
《アーツ前橋》の「場所の記憶 想起する力」展は、白川昌生ら、地元にゆかりがあるアーティストを中心に揃え、場所性を感じさせる作品が並ぶ。戦争の歴史を伝え、3月に閉館した前橋の《あたご歴史資料館》のコンテンツも組み込むのは、地域資料を掘り起こしてきた同館らしい展示だった。またコロナ禍を受けて、海外作家とのプロジェクトやアウトリーチの活動「表現の森」の状況がどうなっているかなどをうかがう。

「場所の記憶 想起する力」展、新しい祭りを構想した白川昌生の展示より
その後、すぐそばで、藤本壮介が1970年代のビルのリノベーションを手がけた《白井屋ホテル》を見学した。これは凄い建築である。部屋数を抑えることで確保した贅沢な吹き抜け空間は、東京ではまず不可能だろう。階段やレアンドロ・エルリッヒの水道管を模した作品が錯綜するさまは、まるでコンクリートのピラネージだ。また正面はポップな廃墟感を残すのに対し、反対側の馬場川面は土手をイメージしたびっくり建築を新設している。藤本、エルリッヒ、ミケーレ・デ・ルッキらがそれぞれインテリアを手がけた特別な部屋があるほか、各部屋に旧白井屋の記憶を題材にした写真家の木暮伸也など、異なるアーティストの作品が入る。

河岸の土手をイメージした《白井屋ホテル》グリーンタワーの外観

壁と床を抜いた《白井屋ホテル》ヘリテージタワーの吹き抜け
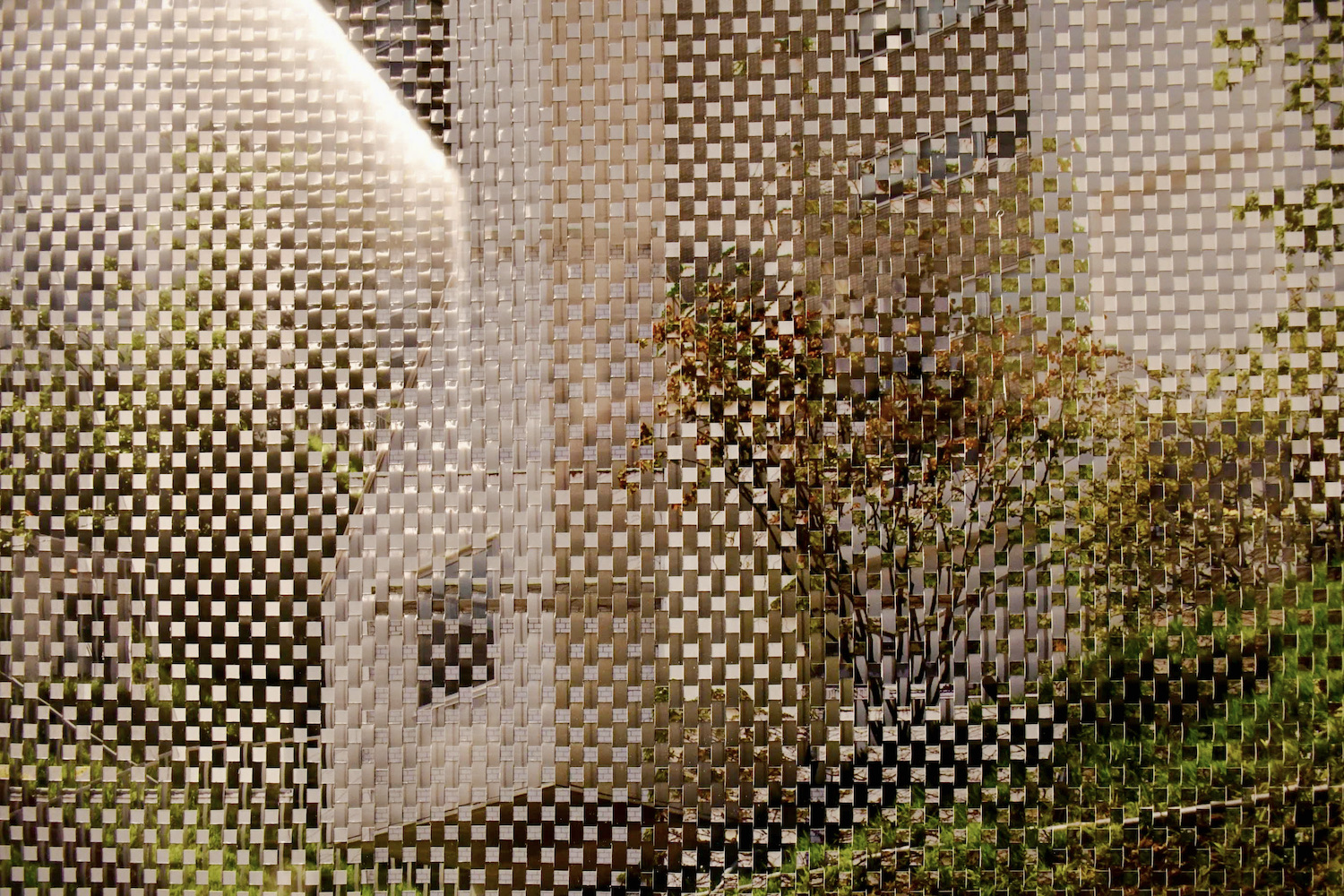
異なる時間の風景を編み込む、木暮伸也の作品
見学後、中村竜治が手がけた《Mビル(GRASSA)》(2018)で夕食をとってから、商店街の一角で行なわれていた、地元のアーティストらのネットワークであるMaebashi Worksの飲み会に合流する。昨年、筆者はこのメンバーから、ヤンキー文化論のレクチャーを依頼されたことがあった。今回、Maebashi Worksのメンバーによって、白井屋がリノベーションに着工する直前、1階ロビーにベッドを並べ、期間限定の特殊空間を出現させるパラ・ホテルのプロジェクトを展開させたことを知る。空っぽになった百貨店をリノベーションした《アーツ前橋》が開館したことによって、確かにこの街が変化し、新しい動きが起きている。
2020/11/13(金)(五十嵐太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)