artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
『植田正治作品集』
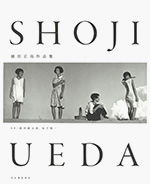
発行日:2016/12/30
植田正治のような、長い期間にわたって活動した写真家の作品を一冊の写真集にまとめるのは、簡単なようでなかなかむずかしい。ページ数の制約もあるし、どの作品を選ぶのか、年代順にするのか、テーマ別に構成するのかで、写真の見え方がまったく違ってしまうからだ。
筆者と金子隆一が監修して、5年あまりの編集作業を経てようやく完成した本書でも、そのことが大きな問題になった。そこで、植田の生涯を網羅する「決定版作品集」という目標を達成するために考えたのは、彼の作品を初出の雑誌掲載の時点から見直して決めていくことだった。そのことには大きな意味がある。これまで植田の展覧会は何度も開催され、その度にカタログが刊行されてきた。単独の写真集の発行点数もかなり多い。だが、そのほとんどは植田正治写真美術館などに収蔵されている現存のプリントを元にしたものだ。ところが、植田はプリントするたびにトリミングを平気で変えてしまうことがあり、ネガやプリント自体が残っていない場合も多い。また、1960~70年代に発表されたカラー作品は、フィルムが劣化して再プリントが不可能になっている。彼が雑誌に発表した写真のトリミングやレイアウトを基準として掲載作品を決定することによって、これまでの写真集やカタログからは漏れていた作品を、取り上げることが可能になった。特に《霧の旅》(1974)、《遠い日》(1975)、《晩夏》(1977)など、この時期精力的に発表されていたカラー作品(初出の雑誌からの複写)は、植田の写真家としての軌跡に新たな1ページを付け加えるものといえる。
ほかにも、新たな発見や見直しを迫る作品が多数収録されている。植田正治の作品世界を検証するための足がかりになる一冊が形になったことで、今後の調査・研究の進展が期待できる。また、雑誌の初出から当たるという今回の編集方針は、1970年代以前においてはカメラ雑誌での掲載が日本の写真家たちの最終的な発表の手段になっていたことを考えると、とても有効な方法だと思う。同じやり方で、植田と同世代、あるいはやや下の世代の写真家たちの作品集を編むこともできるのではないだろうか。
2017/01/07(土)(飯沢耕太郎)
林典子『ヤズディの祈り』

発行:赤々舎
発行日:2016/12/31
ヤズディはイラク北部の山岳地帯に住む少数民族。ゾロアスター教、イスラム教、ミトラ教、キリスト教などを起源とする、孔雀天使を守護神とする独特の信仰を持ち、その伝統的な慣習を守りながら暮らしてきた。ところが、近年のイスラム原理主義の台頭で、迫害を受けて故郷を追われ、難民となる者が増えてきている。林典子は2015年2月から、イラク北部クルド人自治区の難民たちの家、ヤズディの故郷であるシンガル山麓を訪ね、さらにドイツで移民として暮らす人々の丹念な取材を続けてきた。それらをまとめたのが、新作写真集『ヤズディの祈り』である。
林は写真集の後記で「世界にはさまざまな形の暴力があり、中東だけを見てもその被害者はヤズディだけではない」と書いているが、たしかにわれわれは日々流れてくるテロや迫害のニュースに慣れっこになり、不感症に陥りがちだ。だが、林はそんななかで、あえてさまざまな出来事の意味を、写真を通じて問いかけ、伝達しようとするフォト・ジャーナリストとしての初心を貫こうとしている。とはいえ、それらは「一枚ですべてを語ろうとするのではなく、そして歴史に残る出来事の全体像を写そうとしたものではなく、私の視点から見たヤズディの人々の体験の記録」として提示される。
そのために、本書に収録された写真には、その選択と配置に細やかな配慮が見られる。ヤズディの人々のポートレートが中心の構成なのだが、あえて「フレームの外にあったさりげない風景の一部」、彼らの持ち物、かつて住んでいた村で撮影された家族写真などをかなり多く取り込んでいる。また、占領下の村でダーシュ(IS、イスラム国)の戦闘員に性的な暴行を受け、顔を出すことを恐れている女性たちは、白いベール越しに撮影している。特筆すべきは、写真集の後半部の「testimony(証言)」のパートである。写真のモデルとなった人々へのインタビューが、日本語、英語、クルド語、ドイツ語(日本語以外は要約)で、かなりのページを割いておさめられている。このような丁寧な作りを心がけることで、「私の視点から見たヤズディの人々の体験」が、厚みのある記憶の集積として見事に再構成された。松本久木の手触り感にこだわった装丁・デザインも素晴らしい出来映えである。
2016/12/29(木)(飯沢耕太郎)
奥山由之「Your Choice Knows Your Right」

会期:2016/11/19~2017/04/02
RE DOKURO[東京都]
東京・千駄木の裏通りにあるギャラリースペースには、モノクロームの写真が23点並んでいた。それらをざっと見て、都市的なモノ、ヒト、風景がちりばめられたカッコいい写真だと思ったのだが、展示のコンセプトがいまひとつ呑み込めなかった。会場に置いてあった、大判の写真集とチラシを手に取ってみて、ようやくそのバックグラウンドがわかった。
写真集は、千駄木を拠点とするファッションショップのウルフズヘッドの25周年を記念した2冊組の特装本(『WOLF'S』と『HWAD』、ブックデザイン=町口覚)で、そのうち『WOLF'S』のパートの写真を奥山が担当している。今回の展示は、特製のハワイアンシャツを着た100人の関係者を撮影したその写真集の副産物だったのだ。といっても、ハワイアンシャツとモデルをフィーチャーした写真は少なめで、むしろその周辺で拾い集められた場面が中心になっている。写真を分割してグリッド状に配置したり、2枚の写真を同じフレームにおさめたり、写真の上に写真を貼ったりする小技も気が利いていて、相変わらずの映像センスのよさが発揮されていた。
とはいえ、2016年1月~2月の個展「BACON ICE CREAM」(パルコミュージアム)でも感じたのだが、奥山にはぜひファッションの引力圏から離脱した写真にチャレンジしてほしい。「いつ、何をどう選び、誰と共に握りしめ、どこへ向かうのか。選択の日々を生きる僕らは、目の前に見えるそれらが即ち自分自身でもあります。自己とは他者のあらゆる事象であることに気が付いた」。展覧会のDMに掲げられたこのメッセージは、彼が自己といまの世界との関係のあり方をきちんと認識し、思考できることを示している。繰り返しになるが、ファッションから遠く離れて、さらに先へ、写真で何ができるのかを手探りで求め続けていってほしい。
2016/12/21(水)(飯沢耕太郎)
5 Rooms 感覚を開く5つの個展

会期:2016/12/19~2017/01/21
神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]
それぞれ異なった領域で活動するアーティストたちの作品が、「感覚を開く」という基準で選出され、個展の集合として展示されていた。たしかに出和絵理(陶芸)、染谷聡(漆工芸)、小野耕石(シルクスクリーン)、齋藤陽道(写真)、丸山純子(インスタレーション)という5人の出品作家の仕事は、普段はあまり働かせることのない始原的、根源的な感覚を呼び覚まし、開放していく力を備えているように感じる。
そのなかでも特に心を揺さぶられたのは、聾唖のハンディを抱えながら活動する齋藤陽道の、写真によるインスタレーション《あわい》である。展示は2つのパートに分かれている。3枚の大きなパネルに、それぞれ29枚の写真画像を約10分かけてスライド上映する作品には、これまで齋藤が積み上げてきた写真家としての力量が充分に発揮されていた。1枚の画像が少しずつあらわれ、くっきりと形をとり、次の画像と重なり合いながら消えていく。その間隔は21秒だそうだが、息を呑むような緊張感があり、もっと長く感じる。画像の強度がただ事ではない。生まれたばかりの赤ん坊→花火→土手の上の2人の少年→正面向きの魚の顔→抱き合う2人→鹿の首を抱く少女→白いオウムと若い男→光のなかで赤ん坊を抱く女→牛の骨を抱えた少女。画像の連鎖のごく一部を抜き出してみたのだが、これだけではまったく意味不明だろう。だが、スライド上映を見ているうちに、それらの画像のフォルム、色、そして意味の連なりが、厳密な法則にしたがって、絶対的な確信を持って決定されているように思えてきた。
やはり「あわい」と名づけられたもうひとつのシリーズも面白かった。こちらは、3枚の写真を重ね合わせてフレームに入れ、透過光で照らし出している。スライド映写の途中の「重なり合い」の効果を、画像を多層化することでフリーズするという試みである。これまでは、オーソドックスな展示と写真集が中心だった齋藤の活動領域が、いまや大きく拡張しつつあるようだ。特に「スライドショー」という形式は、齋藤にとって、さらなる未知の可能性を孕んでいるのではないだろうか。よりバージョン・アップした展示を見てみたい。
2016/12/19(月)(飯沢耕太郎)
下瀬信雄「つきをゆびさすⅡ」

会期:2016/12/07~2016/12/20
銀座ニコンサロン[東京都]
山口県萩市在住の下瀬信雄は、1960年代からポートレート中心の写真館を営みながらコンスタントに写真展を開催し、写真集を刊行してきた。2005年に伊奈信男賞を受賞した「結界」シリーズもそうなのだが、身辺の光景を題材としながら、万物が呼応するような深みのあるイメージの世界を構築していく。だが、2013年に銀座ニコンサロンで開催された同名の個展の続編にあたる本展の会場には、いつもの下瀬の展示とはやや異なる眺めが広がっていた。
中判、あるいは大判のフィルムを使ったモノクローム・プリントを基調としていた作品が、B1サイズに大きく拡大されたデジタル・カラープリントになっている。「金環食の日」、「帆船が来た日」、「湧き上がる雲」など、彼の周囲に起こる出来事をスナップして提示していることに変わりはない。ただ、色鮮やかでコントラストがあるカラープリントは、視覚的なインパクトが強い分、目の前の光景にそっと触手を伸ばしていくようなデリケートさを欠いている。撮影場所も、萩を中心として山口や岩国まで広がってきていた。だが、そのことをネガティブに捉える必要はないのではないだろうか。むしろ下瀬のようなベテラン写真家が、使い慣れた機材やテクニックに安住することなく、果敢に新たな表現の可能性にチャレンジしていることを評価すべきだろう。
カラーバージョンの「つきをゆびさす」が、このまま続いていくのか、またモノクロームに回帰するのかはわからない。おそらく長期のシリーズになることが予想されるので、次の展開を注意深く見守っていきたい。なお、この展示は2017年1月19日~25日に大阪ニコンサロンに巡回する。
2016/12/18(日)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)