artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
金川晋吾『father』

発行所:青幻舎
発行日:2016年2月18日
何とも形容に困る、絶句してしまうような写真集だ。金川晋吾は、サラ金で借金を作っては「蒸発」を繰り返す父とその周辺の状況を、2008~09年にかけて撮影した。それらの写真群が写真集の前半部におさめられ、同時期に金川が執筆した「日記」をあいだにはさんで、後半部には「毎日自分の顔を一枚と、写す対象は何でもいいので何か一枚」撮るようにと父に指示して撮影してもらった「自撮り写真」1000枚以上が収録されている。
金川が、なぜ父の写真を撮り始め(撮ってもらい)、このような写真集にまとめたのか、その動機の明確な説明はない。だが、写真撮影を通じて、人間存在の不可解なありようを解きほぐし、見つめ直そうという強い意志を感じとることができる。否応なしに始まった写真撮影の行為が、次第に確信的になっていくプロセスが、ありありと浮かび上がってくるのだ。特に、父が撮影した「自撮り写真」を見ていると、それらが何とも言いようのない力を発していて、じわじわと見えない糸に絡めとられていくような気がしてくる。ほとんど無表情で、カメラを見つめる中年男の顔、顔、顔の羅列は、写真を撮るという行為にまつわりつく「怖さ」(同時に奇妙な快感)を、そのまま体現しているように思える。気になるのは現在の父との関係だが、そのあたりをフォローした新作の発表も期待したい。
なお、作者の金川晋吾は1981年京都生まれ。神戸大学発達科学部卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科(先端芸術表現専攻)で学んだ。本作が最初の本格的な写真集になる。
2016/02/23(水)(飯沢耕太郎)
田附勝『魚人』

発行所:T&M Project
発行日:2015年11月11日
田附勝は2006年頃からデビュー作の『DECOTORA』(リトルモア、2007)や、第37回木村伊兵衛写真賞を受賞した『東北』(同、2011)などの撮影で、東北地方に足を運びはじめる。『その血はまだ赤いのか』(SLANT、2012)や『KURAGARI』(SUPER BOOKS、2013)では、鹿狩りをテーマに撮影を続けた。その田附の東北地方への強い思いが形をとったのが、今回写真集として刊行された『魚人』のシリーズである。「八戸ポータルミュージアムはっち」が主催する「はっち魚ラボ」プロジェクトの一環として、2014年度から約1年かけて八戸市大久喜地区や白浜地区などの沿岸部で撮影された。
写真集は、6×9判の中判カメラでじっくりと腰を据えて撮影された写真群と、35ミリカメラによる軽やかなスナップの2部構成になっている。漁師たちの暮らしの細部を、舐めるような視線で浮かび上がらせた6×9判のパートがむろんメインなのだが、フィールド・ノートの趣のある35ミリ判の写真を、コラージュ的にレイアウトした小冊子もなかなかいい。むしろこちらのほうに、皮膚感覚や身体感覚をバネにして被写体に迫っていく田附の写真のスタイルがよくあらわれているようにも思える。
撮影中に、東日本大震災後の津波で大久喜地区から流された神社の鳥居の一部(笠木)が、アメリカオレゴン州の海岸に流れ着き、ポートランドで保管されているというニュースが飛び込んできた。田附は早速ポートランドに飛び、ガレージに保管されていた笠木を撮影するとともに、当地の漁師たちの話も聞いた。それらの写真が、写真集の後半部におさめられている。そこから「海に対する仕事の姿勢は日本もアメリカも変わらないこと」、つまり「魚人」たちの基本的なライフスタイルの共通性が、見事に浮かび上がってきた。
なお、この『魚人』は赤々舎から独立した松本知己が新たに立ち上げたT&M Projectの最初の出版物として刊行された。丁寧なデザイン・造本の、意欲あふれる写真集になったと思う(デザイナーは鈴木聖)。またひとつ、期待していい写真集の出版社が名乗りを上げたということだろう。
2016/02/22(月)(飯沢耕太郎)
石川竜一「考えたときには、もう目の前にはない」

会期:2016/01/30~2016/02/21
横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室1[神奈川県]
1984年、沖縄出身の石川竜一は、いま最も期待が大きい若手写真家の一人といえるだろう。2015年に『絶景のポリフォニー』(赤々舎、2014)、『okinawan portraits 2010-2012』(同)で第40回木村伊兵衛写真賞を受賞し、抜群の身体能力を活かしたスナップ、ポートレートで新風を吹き込んだ。今回の横浜市民ギャラリーあざみ野での個展では、二つのシリーズだけでなく、その前後の作品も合わせて展示してあり、彼の作品世界の広がりと伸びしろの大きさを確認することができた。
最初のパートに展示されていた「脳みそポートレイト」(2006~08)と「ryu-graph」(2008~09)が相当に面白い。スナップやポートレートを撮影しはじめる前に制作された実験作で、「脳みそポートレイト」では、クローズアップされた身体の一部の画像をコラージュして、ぬめぬめとした奇妙な生きものの姿を造り上げている。「ryu-graph」は「印画紙上に直接溶剤を使用しながら形態をイメージ化した」抽象作品である。彼の中にうごめいていたコントロールできない衝動を、そのまま形にしていったとおぼしき写真群で、それが『絶景のポリフォニー』や『okinawan portraits 2010-2012』で解放され、「写真」として秩序づけられていったプロセスがよく見えてきた。近作の「CAMP」(2015)にも瞠目させられた(SLANTから写真集としても刊行)。最小の装備で山の中に入り、現地で食物を確保していくサバイバル登山家とともにキャンプしながら、石川県、秋田県の山中で撮影されたシリーズで、壮絶な美しさを発する自然環境の細部が、震えつつ立ち上がってくる。都市を舞台に撮影を続けてきた石川の新境地というべき作品群で、今後の展開が大いに期待できそうだ。
なお、本展は「あざみ野フォト・アニュアル」の一環として開催されたもので、展示室2では「『自然の鉛筆』を読む」展が開催されていた。「世界最初の写真集」であるイギリスのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットの『自然の鉛筆』(The Pencil of Nature,1844-46)の収録作品に、横浜市所蔵の写真・カメラコレクション(「ネイラー・コレクション」)からの約100点を加えて、19世紀以後の写真表現を辿り直そうとしている。ちょうど『自然の鉛筆』の日本語版(赤々舎)が刊行されたばかりというタイミングでもあり、時宜を得た好企画といえるだろう。
2016/02/19(金)(飯沢耕太郎)
シャルル・フレジェ「YÔKAINOSHÏMA」/「BRETONNES」

会期:2016/02/19~2016/05/15
銀座メゾンエルメスフォーラム/MEM[東京都]
シャルル・フレジェは1975年、フランス・ブールジュ生まれの写真家。特定の民族衣装、ユニフォームなどを着用した社会的集団の構成員を撮影するポートレイトのシリーズで知られている。ヨーロッパの辺境地域の伝統的な儀礼の装束を撮影した「WILDER MANN」のシリーズは、2013年に青幻舎から写真集として刊行されて話題を集めた。それと同じアプローチで、北海道を除く日本各地の祭礼や民間儀礼を撮影したのが、今回銀座メゾンエルメスフォーラムで展示された「YÔKAINOSHÏMA」のシリーズである。
この種の民俗写真の撮影は、日本の写真家たちによっても試みられているが、フレジェの軽やかなカメラワークと弾むような色彩感覚によって、新たな視覚的表現が生まれてきているように感じる。特に日本の神々や鬼たちと、ヨーロッパの「WILDER MANN」の写真を並置した「Winter(冬)」のセクションは、インスタレーションにも工夫が凝らされ、大地に根ざした生命力をヴィヴィッドに感じさせる展示で見応えがあった。
一方、東京・恵比寿のMEMでは、ほぼ同時期に、彼のもう一つの新作である「BRETONNES」シリーズがお披露目されていた。こちらは、フランス・ブルターニュ地方の民俗衣装を身につけた女性たちを、特徴的な白いレースの頭飾り(コワフ)に着目して撮影している。背景をグレートーンでぼかして、被写体となる女性を浮かび上がらせる手法を用いることで、古典的な肖像画を思わせる画面に仕上がっていた。衣装を通じて、それぞれの地域の歴史的な記憶や文化的な背景を浮かび上がらせるフレジェの手法は、さまざまな可能性を孕んでいると思う。比較文化論な視点をもっと強調すれば、よりスケールの大きな作品世界に育っていくのではないだろうか。
「Y KAINOSH MA」2016年2月19日(金)~5月15日(火)銀座メゾンエルメスフォーラム
「BRETONNES」2月10日(水)~3月13日(日)MEM
2016/02/18(木)(飯沢耕太郎)
森永純「WAVE」
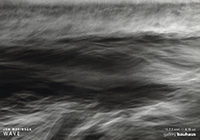
会期:2016/02/03~2016/04/16
gallery bauhaus[東京都]
寄せては返す波をずっと見ていると、次第にトリップ状態に入っていくことがある。単調なように見えて、一つひとつの波の形や変化の仕方には微妙な違いがあり、その表面で起きる出来事はひとつとして同じものはない。波の繰り返しに身を任せていると、自分がどこにいて何をしているのか、目眩とともに足下から揺らいでくるような気分になるのだ。
森永純も「ある年の5月」に、千葉の海岸に撮影行って防波堤に打ち寄せる波を見ているうちに、そんな状態に陥っていったようだ。「太陽熱と心地よい波の揺れのせいで軽い幻覚が起こり、波面が凍結したように見えた」という。この体験をきっかけとして、彼は30年以上にわたって波を撮り続けることになる。それらは2014年に写真集『WAVE~All things change~』(かぜたび舎)にまとめられ、今回はその中から44点(ほかに「河─累影」シリーズから2点)が展示された。
それら、撮影当時にプリントされたというヴィンテージ・プリントを見ると、波という現象が実に魅力的な被写体であることがわかる。撮影の条件によって千変万化するその様相は、それぞれが驚きをともなう奇跡的な瞬間として凝結しており、見飽きるということがないのだ。さらにそれらが繊細で深みのあるモノクロームの印画に置き換えられることで、視覚的な歓びはさらに強まってくる。森永が『WAVE~All things change~』に「「海の波」ほど、私たちの脳でおこる夢に似て、リアリティと幻想の交錯が激しい世界はない」と書いているのは本当だと思う。印画紙に定着された波は、われわれを夢想へと誘う強い力を秘めているのだろう。
2016/02/16(火)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)