artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間をつかまえて」

会期:2016/04/05~2016/05/22
埼玉県立近代美術館[埼玉県]
1970年代以来、「偉大なるアマチュア写真家」ジャック=アンリ・ラルティーグの写真は、展覧会や雑誌の特集などを通じてたびたび紹介されてきた。ベル・エポックの輝きを軽やかに具現化した、彼のスナップショットの魅力を知る人も多くなり、正直、今回の埼玉県立近代美術館のラルティーグ展の企画の話を聞いた時に、同工異曲の展示を見せられるのではないかと思ってしまった。ところが、実際に展示作品(約160点)を見て、われわれがこれまで享受してきたラルティーグの写真の世界は、ほんの一部であることがよくわかった。生涯に130冊以上の写真アルバムと、11万カット以上の写真原板(ネガ)を残したという彼の写真は、想像以上の広がりを備えているのだ。
今回特に興味深かったのはカラー写真である。ラルティーグは1912年から、最初期のカラー写真技法であるオートクロームの製作に取り組み、戦後の1950年代以降はリバーサル・カラーフィルムを使って撮影している。それらは全作品数のうち約3分の1を占めているという。ラルティーグのモノクローム写真は、躍動感あふれる奇抜な演出に特徴があるが、カラー写真は露光時間が長かったこともあって、ややスタティックで絵画的な印象を与える。特筆すべきは、そのみずみずしくヴィヴィッドな色彩感覚で、それは彼が画家としての経験を積んでいたことと無関係ではないはずだ。ラルティーグのカラー写真は、2015年にパリで開催された「ラルティーグ、彩られた人生」(Lartigue, La vie en couleurs)展で初めて本格的に紹介され、大きな反響を呼んだ。本展では後半部分にカラー作品が40点ほど出品されていたが、今後はそちらを中心にした展示も考えられるのではないだろうか。
ほかに、1914年にラルティーグの指揮の下に一家が勢揃いして制作された「盗賊と妖精」と題する映画が上映されるなど、アルバムや日記を含む資料展示も充実している。彼の写真がもたらす幸福感が、会場全体を包み込んでいたように感じる。
2016/04/26(火)(飯沢耕太郎)
莫毅「莫毅:1987-89」

会期:2016/04/09~2016/05/11
ZEN FOTO GALLERY[東京都]
本展は、チベット出身の中国の現代写真家、莫毅(Mo Yi)の、1980年代の軌跡を辿る連続展の「Part
II」として開催された。昨年の「Part I」では、彼の最初期のスナップショットのシリーズ「風景 父親」が紹介されたが、今回はそれに続く1987~89年の3シリーズを展示している。莫毅は中国が政治的、文化的に大きく変動していったこの時期、写真家としての試行錯誤とそこからの飛躍の時を迎えていた。「騒動」(1987)では、多重露光を積極的に用いて、視覚世界の解体をもくろんだ。「1m, 我身後的風景」(1988~89)では、カメラを頭の後ろにセットして、背後の群集に向けて5歩ごとにシャッターを切ったり、「自撮り棒」の元祖のような装置で自分自身を画面のなかに取り入れたスナップ撮影を試みたりした。「搖蕩的車廂(揺れ動くバス)」(1989)では、天安門事件直後の不安げなバスの車内の人々の姿を、自らの運命に重ねあわせて描き出している。
80点あまりの写真を壁にクリップでとめた展示は、莫毅本人の手によるものだが、この時期の作品を見ても、彼はむしろ現代美術の発想を取り込みつつ、ほかの写真家たちとは異なる、身体と表現を結びつける回路を模索し続けてきたことがわかる。その先駆的な仕事の重要性は、2000年代以降に中国国内でもようやく認められつつあるが、日本においてはまだ知名度の高い写真家とはいえないだろう。中国の現代写真を本格的に紹介する写真展が、美術館レベルでまだ一度も開催されたことがないという残念な状況ではあるが、莫毅の仕事もぜひまとまったかたちで見てみたい。
なお、展覧会にあわせて写真集『莫毅 1983-1989』(ZEN FOTO GALLERY)も刊行された。今回の展示や写真集出版が、ぜひ大規模な個展開催に向けた第一歩になるといいと思う。
2016/04/22(金)(飯沢耕太郎)
細倉真弓「CYALIUM」

会期:2016/04/02~2016/05/15
G/P gallery[東京都]
1979年、京都府生まれの細倉真弓の作品は、彼女が日本大学芸術学部写真学科在学中から見ているのだが、このところ表現力が格段に上がってきているように思える。2014年のG/P galleryでの個展「クリスタル ラブ スターライト」(TYCOON BOOKSから同名の写真集も刊行)に続いて、イギリスの出版社MACKから『Transparency is the new mystery』が出版された。深瀬昌久、ホンマタカシの写真集と同時刊行ということは、日本の若手写真家の代表格として選ばれたということで、彼女の作品の評価の高まりのあらわれといえるのではないだろうか。
今回のG/P galleryでの個展「CYALIUM」でも新たな手法にチャレンジしていた。「CYALIUM」というのは「化学発光による照明器具「cyalume(サイリューム)」に金属元素の語尾「lium」を加えた造語」だという。たしかに、カラー照明を思わせる、ハレーションを起こしそうな色味の写真が並んでいるのだが、それはカラー写真の6原色(R/G/B/Y/M/C)のどれかにブラックを加えた、7色の組み合わせによってつくられているのだという。色同士のぶつかり合いに加えて、男女のヌードと植物や岩の画像が対比され、心が浮き立つような視覚的効果が生じてくる。実物の照明器具を使ったインスタレーションも効果的だった。
ただ、作品の展示効果が洗練されていくにつれて、なぜヌードなのか、鉱物なのかという、細倉にとっての切実な動機が希薄になっていくようでもある。その点では、ヌード撮影の現場の状況をざっくりと切り取った映像作品(モニターが床に置いてある)のほうが、むしろ彼女の現実世界との向き合い方を、よりストレートに表現しているように思えた。
2016/04/22(金)(飯沢耕太郎)
「マルティン・チャンビ写真展」

会期:2016/04/19~2016/05/16
ペルー大使館 視聴覚室“マチュピチュ”[東京都]
マルティン・チャンビ(1891~1973)は南米・ペルーを代表する写真家。アンデスの先住民の出身で、鉱山技師の下働きをしながら、イギリス人から写真を学び、1918年、クスコ県シクアニ村に写真スタジオを開業する。1920年にクスコに移り、先住民を含むその地の住人たちの、堂々たる威厳を備えたポートレートや、緊密な構図の集合写真を撮影した。マチュピチュ遺跡や建築物の記録写真、スナップショット的な街の写真も多数残している。
リアルな描写に徹してはいるが、どこか「魔術的リアリズム」の伝統に根ざしているようでもある彼の写真は、近年評価が高まってきており、2015年10月~2016年2月にリマ美術館で開催された大回顧展に続いて、2017年にはサンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)での個展開催も決まっているという。カーニバル評論家としても知られる、写真家の白根全の企画で開催された今回のペルー大使館での個展は、チャンビの作品の日本での初公開である。30点余りと数は少ないが、ガラス乾板から引き伸ばされたクオリティの高いプリントが展示されていた。
今年になって、ラテンアメリカの写真家たちの写真展が相次いでいる。グアテマラの屋須弘平(あーすぷらざ)、メキシコのグラシエラ・イトゥルビデ(タカ・イシイギャラリー フォトグラフィ/フィルム)、ブラジルの大原治雄(高知県立美術館)と展示が続き、このチャンビ展に続いて2016年7月2日からはメキシコの写真家、マヌエル・アルバレス・ブラボの大規模展が世田谷美術館で開催される。こうなると、ラテンアメリカの写真家に共通する特色を抽出できそうな気もしてくる。先に述べた、リアルさと幻想性が同居する「魔術的リアリズム」も、その重要な一要素となりそうだ。
2016/04/16(土)(飯沢耕太郎)
大原治雄「ブラジルの光、家族の風景」
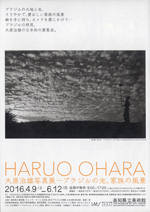
会期:2016/04/09~2016/06/12
高知県立美術館[高知県]
大原治雄(1909~1999)はユニークな経歴の持ち主である。高知県に生まれ、1927年に17歳でブラジルに渡って、パラナ州ロンドリーナで農場を経営した。その傍ら、1938年から家族との日々や農場での暮らしを撮影し始め、膨大な量の写真を残している。戦後の1950年代にはサンパウロのアマチュア写真家クラブに加わり、国内外の写真サロンに出品してアマチュア写真家として知られるようになる。死後、その評価は次第に高まり、2008年からブラジル各地を巡回した写真展は、10万人以上の観客を動員したという。その大原の代表作182点を展示した本展は、いわば故郷への里帰りの展覧会ということになる。
大原は日本で生を受けたが、写真を独学で学び、撮影したのはブラジルだった。繊細で、細やかな自然観察は日本人特有のものに思えるが、被写体の選択や構図は明らかにラテンアメリカの写真表現の伝統を踏襲している。メキシコ時代のエドワード・ウェストンを思わせる造形的、構成的な写真もある。また、のちに子供たちのために母親の生涯をアルバムとしてまとめたというエピソードからもわかるように、「写真作品」として撮影されたものではない、プライヴェートな記録写真もたくさん残している。逆に妻の幸(こう)や9人の子供たちを、のびやかに撮影したそれらの写真群こそが、彼の真骨頂であるようにも思えてくる。それらはブラジルの一家族のアルバム写真というだけでなく、誰もが自分の記憶や経験と重ね合わせて見ることができる、開かれた普遍性を備えているように思えるからだ。
なお、本展は兵庫県の伊丹市立美術館(2016年6月18日~7月18日)、山梨県の清里フォトアートミュージアム(同10月22日~12月4日)に巡回する。カタログを兼ねた写真集(サウダージ・ブックス)も刊行されている。
2016/04/15(金)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)