artscapeレビュー
飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー
MOTOKO「田園ドリーム」

会期:2012/03/28~2012/04/10
銀座ニコンサロン[東京都]
MOTOKOは2003年に刊行の『Day light』(ピエブックス)におさめた森の写真を撮影するために、初めて滋賀県を訪れた。琵琶湖の周辺の「里山の荒廃によって急速に失われていく日本の原風景」に強く魅せられた彼女は、2006年から取材・撮影し始めた。最初の頃は里山や棚田の風景、民間行事、祭りなど「ハレの日」の情景を中心に撮影していたのだが、次第に農家の暮らしに興味が移り、2008年から本格的にルポルタージュを開始する。その過程で、若手農家集団「コネファ」との協力関係ができて、展示やイベントを精力的にこなしてきた。現在は「田園ドリームプロジェクト」という名称で活動を展開している。
MOTOKOの写真は、まさに「日本の原風景」というべき琵琶湖の湖岸地域の自然、農業、祭事などを総合的にとらえており、気持ちよく目に飛び込んできて淀みがない。この地域の暮らしぶりを、明快なイメージでいきいきと浮かび上がらせているといえるだろう。ちょっと気になったのは、展示されている写真にキャプションがまったくなかったこと。むろん、写真家が被写体をどんな切り口で撮影しているのかを見せるのが眼目だから、余分なテキストを省くという選択はありえる。だが、たとえば祭りの演目、料理など生活の細部の情報は、観客にとって重要な意味をもつのではないかと思う。写真とテキストが一体化した展示を考えてもよかったのではないだろうか。
2012/03/30(金)(飯沢耕太郎)
清家冨夫「OVERLOOK」
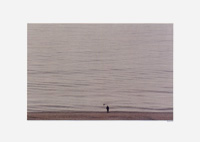
会期:2012/03/02~2012/04/28
フォト・ギャラリー・インターナショナル[東京都]
清家冨夫は日本よりはむしろ欧米諸国で高い評価を得ている写真家。1980年代に発表した女性ポートレートのシリーズ「ZOE」を皮切りに、イギリス・ロンドンのハミルトンズ・ギャラリーやアメリカ・カーメルのウェストン・ギャラリーなどで個展を何度も開催してきた。その詩情あふれる、高級感を漂わせる作品にはファンも多い。日本人には珍しく、プリントで勝負できる写真家のひとりといえるだろう。
今回の新作は、これまでモノクローム・プリントで作品を発表してきた彼のイメージをくつがえす意欲作である。デジタル、カラー、インクジェット・プリントという新たなジャンルに踏み込もうとしている。タイトルが示すように、画面はやや高い場所から海辺を「見渡す」視点で統一されている。その3分の2は海面が占め、残りは砂浜だ。海は季節や天候の変化によって、金属的な輝きを発したり、シルクの布のように柔らかくうねったりしている。その海面と砂浜とのちょうど境界のあたりに、人や犬の姿がぽつりぽつりと見える。その距離の取り方が絶妙で、突き放しているわけでも感情移入しているわけでもない、とてもきれいなシルエットとして処理されているのが目に快い。カラーといってもよくコントロールされたモノトーンの画面なので、あまりうるさい感じはなく、いかにも清家の作品らしく静謐な雰囲気を保っている。完成度の高いシリーズとして成立しているのではないだろうか。
撮影地は清家がよく滞在しているイギリスのブライトン・ビーチだという。ハミルトンズ・ギャラリーから、限定1,000部で同名の写真集も刊行されている。
2012/03/28(水)(飯沢耕太郎)
ロベール・ドアノー「Rétrospective」

会期:2012/03/24~2012/05/13
東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]
ロベール・ドアノーといえば、なんといっても《市庁舎前のキス》(1950)だ。今回の回顧展のチラシに使われ、会場となった東京都写真美術館の外壁にも、この代表作が巨大なサイズに引き伸ばされて飾られている。だが、日本ではおそらく初めての200点を超える規模の展示を見ると、ドアノーが決していわゆる「パリ写真」の範疇におさまる写真家ではないことがよくわかる。「パリ写真」というのは、比較文化の視点から写真を読み解いた今橋映子が『〈パリ写真〉の世紀』(白水社、2003)で提起した概念で、ジャーナリスティックに垂れ流しされたパリのイメージ、すなわち「パリの男女、犬や猫、子供たちを、ユーモアや優しさを込めて映し出す」写真の総称である。ドアノーの「市庁舎前のキス」は、その「パリ写真」の典型として絵葉書やポスターなどに無数に複製され、今なお流布し続けている。
にもかかわらず、写真家としてのドアノーの本質は「パリ写真」とはかけ離れたものであることが、今回の展示を見てよくわかった。彼は「ユーモアや優しさ」どころか、シニカルな批評精神の持ち主であり、被写体をクールに突き放す醒めた視線を保ち続けた写真家だったのだ。それは「市庁舎前のキス」が普通考えられているような偶然撮影されたスナップショットではなく、『ライフ』誌の特集のための完全な演出写真であることでもよくわかる。ドアノーはこれと狙った場面を撮影するために、いわゆる「やらせ」を仕組むことに対してまったく躊躇することがない。彼は決してナイーブな写真家ではなく、むしろ経験を積んだプロフェッショナルであり、その技術に誇りさえ抱いていたことが、写真から見えてくるのだ。被写体に対する批評的な距離感がドアノーの写真の最大の特徴であり、その小気味よい職人的な映像の切れ味こそ今回の写真展の見所といえるだろう。
1980年代になって、ドアノーはDATAR(国土整備庁)の依頼で、彼のメイングラウンドであったパリ郊外をカラー写真で撮影した。特別展示されていたその写真群を見て、なんともクールで素っ気ない(同時期にアメリカの写真家たちが撮影した「ニュー・カラー」の写真を思わせる)そのたたずまいにこそ、ドアノーの地金が表われているのではないかと感じた。
2012/03/24(土)(飯沢耕太郎)
宍戸清孝「Home」

会期:2012/03/20~2012/03/26
新宿ニコンサロン[東京都]
銀座ニコンサロン、新宿ニコンサロンを舞台に開催されてきた「Remembrance 3.11」の展示も最終回を迎えた。とてもよい企画だったのだが、前にも書いたように東北在住の写真家たちの写真展が少なかったのがやはり気になる。今回の宍戸清孝(仙台市在住)の展示を見て、あらためてその感を強くした。別に東京や他の地域から被災地に向かった写真家たちの仕事を軽視しているわけではない。誠実に、自分の視点で撮影に取り組んだ写真を、今回の企画でも数多く目にしてきた。だが、宍戸のような地元の写真家の仕事ぶりは、その厚みと生々しさにおいてやはり違いを感じないわけにはいかないのだ。
宍戸は仙台の事務所で被災し、4日後の3月15日に、アシスタントの菅井理恵(福島県出身)とともに初めて仙台湾岸の名取市閖上を撮影した。自衛隊員が遺体を毛布に丁寧に包んでいる様を見て、「胸がいっぱいになってしまい、カメラを持つ手が震えた」という。それからは、もう二度と被災地には行きたくないという気持ちと、「撮らなければ」という思いとの間で、ずっと長く葛藤が続いた。今回の「Home」展に展示された写真の一枚一枚に、その激しい心の揺らぎと、撮り続けていくなかで少しずつ芽生えてきた再生の兆しに託した希望とが刻みつけられている。まさに渾身の写真群であり、日系米軍兵士の戦後を追った「21世紀への帰還」など、長くドキュメンタリー写真の分野で活動してきた宍戸にとっても、この1年は覚悟を決めてひとつの壁を乗りこえていく大事な時期になったのではないだろうか。写真展にあわせて仙台市若林区の出版社から刊行された写真集『Home 美しい故郷よ』(プレスアート)も高精度の印刷、質の高いデザインの力作である。
なお、同時期に銀座ニコンサロンでは吉野正起「道路2011─岩手・宮城・福島─」(3月21日~27日)が開催された。震災後の「道路」を淡々と撮影したシリーズだが、福島県の農道を何気なく塞いでいる「立入禁止」の看板が、どうしても目に残ってしまう。
2012/03/21(水)(飯沢耕太郎)
荒木経惟 写真集展 アラーキー

会期:2011/03/11~2012/07/22
IZU PHOTO MUSEUM[静岡県]
「3.11」に「写真集展」をぬけぬけとスタートさせるところが、いかにも荒木経惟らしい。タイトルが示すように、彼がこれまで刊行した写真集を中心とする著作450冊以上を一堂に会そうという破天荒な企画である。
僕は2006年に『荒木本!』(美術出版社)という本をまとめたことがある。荒木の全著作を解説つきで紹介したのだが、そのとき、1971年の「ゼロックス写真帖」シリーズから2005年に至る時期に出版された著作の数は357冊だった。それから6年余りで100冊ほど増えているわけで、これはやはり異常事態としかいいようがない。現時点において、またこれから先も、彼を超える生産量の写真家は絶対に現われてこないだろう。
実際に会場を見て、意外にすっきりと本が並んでいるのにむしろ驚いた。一番大きな壁に1冊ごとの小さな棚をつくって本を置き、その大部分は巨大なテーブルの上に並んでいて、手に取ってページをめくり、閲覧することができる。1980~90年代の名作がずらりと並んでいるのは壮観だし、最近はヨーロッパや台湾などで展覧会のカタログや翻訳本の出版が相次いでいるのもわかる。だが全体的には、本が整然と並んでいる印象が強いのだ。おそらく、杉本博司設計の美術館のスペースでは、荒木の事務所のように仕事と生活がごっちゃになったカオス的な雰囲気が感じられないのが、その大きな理由だろう。いっそのこと、美術館のスタッフが展示室をオフィスがわりに使ったりしていると、生活感が滲み出てきていいのではないかと思った。
著作のほかにも、「さっちんとマー坊」(1963)の巨大なポートフォリオの展示や「アラキネマ」全シリーズの上映、震災を全力投球で投げ返した新作の「‘11・3・11」シリーズの展示などもあり、盛りだくさんの内容だ。覚悟を決めて、朝から夕方まで部屋に詰めていれば、「荒木世界」にどっぷりと浸ることができるだろう。なお、関連企画として、6月10日(日)14:30~16:00に荒木と飯沢耕太郎との対談「『荒木本!』のマンダラ宇宙」が開催される。
2012/03/18(日)(飯沢耕太郎)



![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)