artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
加賀美健「SPICY!!!」

会期:2013/01/25~2013/03/03
ナディッフギャラリー[東京都]
作家も作品も知らずに行ったら、ウンコチンコ系の作品がところ狭しとひしめいている。これは想定外。なんというか、ウンコやチンコに異常な興味を抱く肛門期をそのまま大人まで引きずってしまったような作品、といったらいいか。十字架にパンティをはかせたり、ぬいぐるみの動物のお尻から巨大ウンコが出ていたり、ブラピやディカプリオの顔写真つきビニール袋にウンコ(模型)を入れたり、躊躇とか深慮とかまるで感じられず、嬉々としてつくっている様子なのだ。とはいえ、作品間の距離が一定に保たれていたり、なにをどこに配置するかもそれなりに計算した形跡がうかがえ、作家としての強い意識が感じられる。
2013/02/17(日)(村田真)
アクションドローイング ヒーロー

会期:2013/01/26~2013/02/24
六本木ブルーシアター[東京都]
韓国からやって来た4人のドローイング野郎ども。歌って踊れるじゃないけど、踊って笑って絵も描く珍しいエンターテインメントショーだ。最初は日本人へのサービスなのか、坂本龍馬のポートレートに始まり(さすがに伊藤博文じゃなかった)、4人がそれぞれ描いた絵を合わせるとマイケル・ジャクソンになったり、黒い画面に黒い絵具で描いてサッと揺するとブルース・リーの顔が表われたり、積み上げたルービックキューブをいじるとスーパーマンの顔になったり、客を舞台に上げて伝言ゲームをしながらウルトラマンの姿を浮かび上がらせたり、「ヒーロー」のテーマに沿って観客を楽しませてくれる。絵もダンスも笑いも二流だけど、もの珍しさも手伝ってあっという間に1時間半がすぎてしまった。こういうアートをエンターテインメントとして見せるショーは、70~80年代にニューヨークのザ・キッチンあたりでもやっていたかもしれないが、忘れたころに韓国から飛び出してきたのが驚きだ。でも比較するのもなんだが、ローリー・アンダーソンのショーなんかに比べれば思想性も批評性もなく、あくまでエンターテインメントに徹している点がいっそ潔いというか。そういえば『誰でもピカソ』をグレードアップさせればこんな感じかも。
2013/02/17(日)(村田真)
ワンダーシード2013
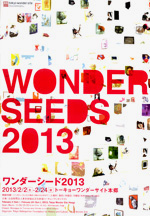
会期:2013/02/02~2013/02/24
トーキョーワンダーサイト本郷[東京都]
2003年から始まった小品の公募+展示+即売会。10号(53×45.5センチ)未満の作品が3万円以下で売られている。ザッと数えてみると、100点中79点が売約済みだから、開催2週間でおよそ8割の売れ行き。これはかなりの高確率だ。ぼくの記憶では、始めたころは半分以上売れ残っていたのに、2007~08年ころはプチバブルのせいか、開催直後に売り切れてちょっと話題になっていた。それがリーマンショック後は再び売れ残りが目立つようになったものの、最近はまた復活し始めている感じ。たった10年でこんなに浮き沈みがあったんだと再認識した。まあ今年はイラストっぽい絵が減ってレベルアップしたから売れ行きも伸びたのかな、とも思ったけど、必ずしも作品の質的レベルと売れ行きは関係あるとは限らないことがわかる。
2013/02/16(土)(村田真)
超然孤独の風流遊戯 小林猶治郎展/富田有紀子展

会期:2013/02/17~2013/04/07
練馬区立美術館[東京都]
小林猶治郎は偉大な芸術家というわけではないし、美術史にも出てこないが、ちょっとおもしろい絵を描く画家。若いころ肺を病み、25歳までしか生きられないと宣告されて慶応大学を中退し、好きな絵を描いてすごしてるうちに93歳まで長生きしてしまったという、ならば人生設計ちゃんとやってればぜんぜん違う人生を歩んだかもしれない人。画業は関東大震災後の1920年代から70年近くにおよぶが、出品は初期の20~30年代が大半を占めている。輪郭や陰影のはっきりした粘着質な描法は牧野虎雄に似ているなあと思ったら、牧野に師事したことがあるそうだ。小鳥を描いた絵の上に金網をかぶせて鳥小屋に見立てたり、ゴツゴツした木の幹を四角く組んで額縁にしたり、あれこれ工夫しているのがかわいい。戦後50年代の一時期には時流に乗ったのか抽象も試みている。晩年には簡潔な絵の余白にひとこと添える文人画のような作品にいたったが、考えてみれば絵を売らなかった彼の生き方は文人画に通じるのではないか。ひょっとしたらこういう生き方こそ画家としてもっとも幸せかもしれない。で、その孫が1階で個展を開いてる富田有紀子。富田は祖父と違っておもに花や果実を拡大描写しているが、執拗なまでの描画姿勢が少し似ているかも。
2013/02/16(土)(村田真)
アーティスト・ファイル2013──現代の作家たち

会期:2013/01/23~2013/04/01
国立新美術館 企画展示室2E[東京都]
国立新美術館の学芸員たちが、それぞれ気になるアーティストたちを選出して、個展の集合のかたちで展示する企画。多ジャンルの、あまりきちんと紹介されていない作家の作品を見ることができる貴重な機会となっている。5回目となる今回は、ダレン・アーモンド(イギリス)、ヂョン・ヨンドゥ(韓国)、ナリニ・マラニ(インド)、東亭順(以下日本)、利部志穂、國安孝昌、中澤英明、志賀理江子の8人が選ばれている。
ダレン・アーモンドの瞑想的な月光の下での風景写真、ナリニ・マラニの内蔵感覚の発現と言うべきドローイングと映像など、興味深い仕事が多かったが、やはり圧巻は志賀理江子の「螺旋海岸」のインスタレーションだろう。2012年11月~13年1月にせんだいメディアテークで開催された展覧会の縮小版と言うべきもので、点数が半分以下に減った作品は、螺旋状ではなく折り重なるように不定形に並べられ、照明もフラットなものになっている。だが、観客を否応なしに巻き込んでいく彼女の作品世界の圧倒的なパワーは、ここでも充分に伝わってきた。
この展示について、三沢典丈が『東京新聞』夕刊(2013年2月15日付)に掲載した美術展評で疑義を呈している。志賀は等身大以上に引き伸ばした写真を木製の支持体に貼り付け、斜めに立てかけるインスタレーションのかたちで作品を展示した。三沢はこのやり方だと「見る者に被災地への思いを獲得させるのと引き換えに、作品と向き合う静寂な時空は犠牲になる」と書く。さらに「被災地から近い会場なら、この形式は共感として了解され、視線の妨げにはならないだろう。だが遠い東京で見る者が、被災地の様子を漠と想起するだけなら、雑念となりかねない」と書き継いでいる。
このような一見もっともらしい、安全地帯に身を置いた見方こそ、志賀が激しく忌避し、身をもって挑発しようとしているものだろう。志賀の写真は、まさに三沢が避けるべきだと提言する「物質性」を露にして見る者に襲いかかる。被災地から遠い東京での展示だからこそ、逆にその荒ぶるノイズ(雑念)を全身で受け止める態度が求められているのではないだろうか。
2013/02/16(土)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)