artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
3331アンデパンダンスカラシップ展vol.3

会期:2013/01/26~2013/02/17
3331 Arts Chiyoda[東京都]
全国随一のアンデパンダン展として知られつつある「3331アンデパンダン」の出品作家のなかから選抜されたアーティストによるグループ展。2012年の「3331アンデパンダン」展でゲストと一般来場者によって選ばれた9名のアーティストが新作を発表した。無鑑査無賞与を原則とするアンデパンダン展本来の思想からすれば、こうした展開はいくぶん過保護のような気もするが、有象無象のなかから有望な新人を発掘することで停滞した状況を塗り替えていこうとする企画者のねらいは、理解できなくもない。
事実、今回の展覧会では、見るべき作品が比較的多かった。オーディエンス賞を受賞した駒場拓也は自然光を分解して再構成する健やかな抽象画を発表し、本展のもはや常連とも言える島本了多は肉体の形態を器の機能に転化した不気味な陶器を展示した。
なかでももっとも際立っていたのが、渡部剛である。雑誌や広告など印刷物を切り貼りしたコラージュは決して珍しくないが、渡部によるそれは量的にも質的にも徹底的に追究する執着力において他の追随を許さない。紙ものを用いる作品はえてして不必要に貧乏臭くなりがちだが、丁寧な仕事によってそれを巧みに回避しているところも好感が持てる。民芸品としてつくられている木彫りの熊の表面にカラフルな彩りを施した作品にしても、地の部分と彫りの部分を律儀に色別することで、既成の民芸品をポップにバージョンアップしてみせた。
2013/02/08(金)(福住廉)
熊谷勇樹「そめむら」
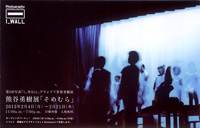
会期:2013/02/04~2013/02/21
ガーディアン・ガーデン[東京都]
志賀理江子の「螺旋海岸」を見た後、何人かの若手写真家の被写体へのアプローチにどこか共通した志向性を感じるようになった。儀式めいたパフォーマンス、過剰な光と影のコントラスト、濃密な色彩効果、画面の傾きやブレ・ボケのようなノイズの導入などだ。熊谷勇樹の作品にも、そんな傾きを感じないわけにはいかない。それを「時代の兆候」というのは先走り過ぎかもしれないが、若い写真家たちの現実世界への違和の感情が、もはやぎりぎりのテンションまで高まりつつあることの表われと言えるかもしれない。
熊谷の今回の個展は、昨年3月~4月に開催された第6回写真「1_WALL」展のグランプリ受賞作品「贅沢」を発展させたもの。大小の写真を壁に配置するインスタレーションも含めて、写真を通じて「不確かさ」を提示しようという意志がくっきりと表われていて、気持ちのいい展示だった。だが、ここから先がむずかしい。「どこの誰とも規定されずに彷徨っているような非決定的な写真を撮ることで、世の中のあらゆる手に負えないものや不合理なものの存在を証明したい」。このマニフェスト自体は間違ってはいないが、「非決定的な写真」に安住してしまうと、いたずらに断片を撒き散らすだけで終わりかねない。むしろ「手に負えないものや不合理なもの」にさらに肉迫し、それらのリアリティを引きずり出し、地図化(マッピング)していくような力業を期待したい。志賀理江子が「螺旋海岸」で成し遂げようとしたのは、まさにそういう作業の積み重ねだったのではないだろうか。
2013/02/07(木)(飯沢耕太郎)
Y・アーネスト・サトウ「Light and Shadow」

会期:2013/01/25~2013/02/28
Gallery 916[東京都]
神奈川県立近代美術館で開催された「実験工房展」カタログの巻末の座談会を読んでいたら、いきなりアーネスト・サトウの名前が出てきたので驚いた。戦後、GHQの肝いりで開始されたCIEライブラリーで、毎週のように現代音楽を含むレコード・コンサートが開催されており、その構成・解説を担当していたのがサトウだったのだ。湯浅譲二、福島和夫、武満徹、山口勝弘などはその常連だった。つまり、実験工房のメンバーの出会いのきっかけをつくったのが日米混血のサトウだったということで、これは僕にとっても驚きだった。そのサトウの写真展が、たまたま916で開催されているのも何かの縁と言えるだろう。
サトウは1951年(実験工房結成の年)に渡米し、やがて写真家の道を歩む。1962年に帰国。フォト・ジャーナリストとして活動した後、京都市立大学で教鞭をとるようになる。その彼の最大傑作と言うべき教え子が森村泰昌である。森村自身、サトウから受けた写真教育の影響をさまざまな場所で語っているが、たしかにしっかりとした技術に裏付けられた空間構築へのこだわりは、師から受け継いだものと言える。
サトウのプリントをこれだけまとめて見たのは初めてだが、やはり彼の音楽に対する造詣の深さが写真にも表われているように感じた。光と影のコントラストを活かした画面の構成力と、モノクローム・プリントのトーン・コントロールの見事さは、むしろ作曲家の仕事と共通性があるような気がする。ただ、現実世界のノイズをそぎ落とし、作品としてあまりにも完璧に仕上がっているということは諸刃の剣でもある。むしろ、レナード・バーンスタイン、オノ・ヨーコ、田中角栄などを含むポートレート作品に、モデルの強烈な個性を受け止めて投げ返した佳作が多い。帰国後の作品も含む、もう一回り大きな展示も見てみたいと思った。
2013/02/07(木)(飯沢耕太郎)
福岡現代美術クロニクル 1970-2000
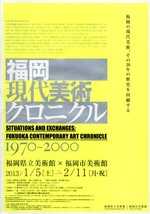
会期:2013/01/05~2013/02/11
福岡県立美術館、福岡市美術館[福岡県]
福岡の現代美術を歴史化した展覧会。九州派以後の1970年からの30年間を対象に、85人の美術家による約130点の作品を通時的に展示した。
2つの美術館にまたがるボリュームのある展示を見て気がついたのは、2つ。ひとつは、松本俊夫と川俣正の存在の大きさ。本展でも明らかにされていたように、ミニマリズムや新表現主義といった流行の表現様式が福岡のアーティストに多大な影響を及ぼしたことは事実である。ただ、それにもまして、たったひとりのアーティストがひとつの表現様式に匹敵しうるほど大きな影響力を及ぼすことがありうる。それは、福岡のような適度な地方都市だからこそ可能な条件なのかもしれないが、こうした内部と外部をつなぐ人的な交流は、地方都市の今後のアートシーンを考えるうえで、重要な示唆を与えるのではないか。
もうひとつの発見は、川原田徹の存在。トーナス・カボチャラダムスの名でも知られる画家で、ブリューゲルのような細密な油彩画やエッチングを制作している。本展では、九州派以後の70年代に位置づけられていたが、これはあくまでも通時的な展示構成の必要を満たすためであって、川原田が70年代に限って制作しているわけでは、もちろんないし、時流や美術運動とはまったく無関係に制作している。つまり、展覧会の通時性はえてして直線的な歴史観を誤認させてしまいがちだが、実際の歴史は複線的であり、無数の単独者が錯綜としているものである。通時性による歴史化は表現様式や表現集団の変遷によって遂行されやすいが、しかし川原田のように、特定の表現様式や表現集団の交代劇から離れたところで活動を持続させているアーティストの存在を抜きにして歴史を物語ることはできない。「歴史」や「批評」、ないしは「研究」といった物語からこぼれ落ちてしまいがちな歴史的真実に目を配ることこそ、歴史の記述に必要とされる態度ではないだろうか。
2013/02/06(水)(福住廉)
山内庸資 展「NEW OPEN AREA」
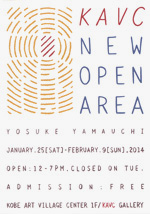
会期:2014/01/25~2014/02/09
神戸アートビレッジセンター[兵庫県]
山内庸資の、平面表現だけに収まらない、もしくは平面表現のなかでの立体的表現を追求する、イラストレーターとしての仕事とは違う側面をもって作品展開。ギャラリー空間に、ドローイングが施された積み木のような木の家を棒で高くし、1メートル程度の子どもの目線あたりに伸ばして林立させた。すると植物のような有機的に“生えている”家、“草原のような”町がゆらゆらと立ち上がってくる。
2013/02/06(木)(松永大地)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)