artscapeレビュー
美術に関するレビュー/プレビュー
篠田桃紅展

会期:2022/04/16(土)~2022/06/22(水)
東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]
前衛的な「書」における文字の解体から、MoMAの展覧会への参加を契機とした1950年代におけるアメリカ滞在を経て、現代美術の影響も受けながら、純粋なかたちによる抽象的な表現へと展開していく流れ、あるいは同じモチーフの探求など、単純にカッコ良い。当時、撮影された映像ドキュメント「日本の書」で確認できる、彼女が描く際の身のこなしも、それ自体が洗練されたパフォーマンスのようだ。個人的に特に関心をもったのは、上階のスライド・ショーで紹介されていた建築家とのコラボレーションである。20世紀の半ばは、岡本太郎、猪熊弦一郎、流政之らが、さまざまなモダニズムの空間にパブリック・アートを提供し、建築と美術の協働がうたわれていたことはよく知られているが、基本的に平面の作品によって、篠田も実に多くの建築に関わっていた。同展の年譜によれば、1954年、サンパウロ市400年祭において丹下健三が設計した日本政府館に壁書を制作したのが最初の建築関連の仕事のようである。なお、同年の銀座松屋の個展では、丹下が会場デザインを担当していた。
会場でメモしたので、以下にその事例を列挙しよう。丹下の建築では、《日南市文化センター》(1962)における緞帳やホワイエの作品、《旧電通本社ビル》(1967)のロビー、《国立代々木競技場》(1964)の貴賓室における剣持勇の家具との共同作業。そして大谷幸夫の《京都国際会館》(1966)のロビーにおける壁画やレリーフ、芦原義信の《ホテル日航》(1959)、佐藤武夫の《ホテル・ニュージャパン》(1960)、竹中工務店の《パレスホテル》(1961)、《コンラッド東京》(2005)などである。モダニズム以外では、増上寺の巨大な壁画を手がけていた。コンラッド東京をのぞくと、1960年代の重要な施設にかなり集中していることがよくわかる。なるほど、ポストモダンの時代には、建築そのものがやや装飾的になるので、モダニズムのプレーンな面に囲まれた空間に対して、具象的でもなく、過剰に装飾的でもない篠田の抽象的な作品は、相性が良かったのだろう。そして日本的なるものを現代的に再解釈した姿勢も、同時期の建築と共振している。
2022/05/18(水)(五十嵐太郎)
Kanzan Curatorial Exchange「写真の無限 」vol.1 横山大介「I hear you」

会期:2022/04/26~2022/06/12(会期延長)
kanzan gallery[東京都]
必然性と切実性が感じられ、作者の思いが伝わってくるいい展覧会だった。1982年、兵庫県生まれの横山大介は、吃音の障害をもちつつ写真家としての活動を続けている。彼にとって、「他者に声をかけ、向き合い、カメラをとおして他者を見つめ、見つめ返される」ポートレート写真を撮影するという行為は、「会話以上の他者とのコミュニケーションになる」ものだという。今回のkanzan galleryでの個展には、2011年から続けている写真シリーズ「ひとりでできない」から、11点を出品していた。
写真の多くは、まさに「見つめ、見つめ返される」あり方を、シンプルかつストレートに提示したものだ。とはいえ、距離感や構図は一定ではなく、それぞれの被写体に対応して細やかに配慮している。なかに一点だけ、和室にあぐらをかいて座っている初老の男性を写した写真があって、他の写真とやや異質な眼差しのやりとりを感じた。もしかすると、近親者なのかもしれないが、キャプションが一切ないので、観客にはモデルのバックグラウンドはよくわからない。だが逆に、この人は何者なのかと想像する余地があることで、ポートレートに深みと奥行きが備わってくる。写真の選択、プリントの大きさ、レイアウトの決定なども含めて、横山の丁寧な写真展の構築の仕方が印象深かった。ぜひ写真集にまとめてほしい仕事だ。
会場には、もう一作、三島由紀夫の『金閣寺』、重松清の『きよしこ』、金鶴泳の『凍える口』など、「吃音の描写が印象的な文学作品」をいろいろな人に初見で読んでもらうというパフォーマンスを記録したビデオ映像作品「身体から音が生まれる」も出品されていた。48分15秒という上映時間はやや長過ぎるが、見応え、聞き応えのある作品である。
2022/05/17(火)(飯沢耕太郎)
高尾俊介「Tiny Sketches」(高尾俊介を中心に考えられること[1])

会期:2022/05/13~2022/06/12
NEORT++[東京都]
高尾俊介による初個展「Tiny Sketches」は、2019年3月から高尾が始めた「デイリーコーディング」で制作された作品1500点以上のなかから200点を選出しプリントした展覧会。デイリーコーディングとは、高尾が1日ひとつ、少しでも何かコードを書いて、それをTwitterにアップロードするという修練でもあり日記のようでもある活動だ。紙に出力された作品にはプロジェクターの光が照明として投げかけられ、その輝度に眼が揺らされて、モニターを見ているような心地になる。
連動企画のトーク「NFT, コーディングの観点から考えるメディア・アート」[★]では、畠中実は高尾のオルタナティブ性を、ジェネラティブ・アートは出力物ではなくコーディングに力点があったこと、そしてNFTアートはNFTを使っているという意味ではないはずであり、NFTによってジェネラティブ・アートの成果が作品にできたのではないかと指摘した。いわば、高尾は二重の宙づりのなかでその特異性が成立したということだ。これは慧眼だと思った。続く久保田晃弘はより形式の次元での検討を進める。メディア・アートの定義のうち「作品が流通・受容・再生産される媒体過程そのものを作品の本質としてとらえるアートの呼称」(中井悠『アメリカ文化辞典』)という点に着目し、コーディングとNFTとメディア・アートの位相を考える。NFTが希少性=作家性を人工的につくり上げる一方で、その対極にあるクリエイティブ・コモンズ0(著作権フリー)とNFTは「オーナーシップ」(Braian L. Frye)でつながるというのだ。つまり、NFT(アート)は所有が目的ではなく、所有の表明によるコミュニティへの影響が重要であるため、その公開自体はフリーでも構わないという作品とのかかわり方だ。ここで久保田はNFT(アート)を著作権をなくす行動、著作権がなくても経済が回る可能性であり、メディア・アートを考えるひとつの視点なのではないかと示した。
いまは高尾の取り組みはたくさんの既存の文脈との比喩で語られることを積み重ねて、一体これが何であるのかと切り分けている最中でもあるわけだが、ここで、トークの途中で高尾がポロっと言った、NFTにおける「絶え間ない作品と作家との関係」に戻ってみたい。つまり、久保田の図式に「作家」のレイヤーを追加する必要性自体の検討であり、作家が存命であるときの時間幅での作品について考えることだ。NFTや美術作品全般は所有ではなく「影響」を買うものだとして、そのときの作品はどのようなコードをバックグラウンドに走らせているかではなく、高尾俊介のNFT上に紐づく作品だけでなく、ログ、プロジェクト、Twitterでの高尾の発言、時価を参照し続けているということだ。これもまた既存の作品の在り方との連続性のなかで語りうることでもあるだろう。しかし、NFTにおける「影響」の矛先、あるいは、高尾のデイリーコーディングのコミュニティを含めて考えるなら、それは外せないのだろう。
次回は、「継続性と高尾俊介とSNS」について考えたい。
展覧会は無料でした。作品のほとんどはウェブサイトで鑑賞可能です。
 高尾俊介《220219a_Community Statement on "NFT art"》(2022)
高尾俊介《220219a_Community Statement on "NFT art"》(2022)
★──久保田晃弘、畠中実、高尾俊介、NIINOMI「NFT, コーディングの観点から考えるメディア・アート[Tiny Sketches Shunsuke Takawo's 1st solo Exhibition]」(2022年5月21日)
https://youtu.be/S5aZ1RIUyHQ
公式サイト:https://tinysketches.neort.io/ja/dailycoding
2022/05/15(日)(きりとりめでる)
Tokyo Contemporary Art Award 2020-2022 受賞記念展:藤井光

会期:2022/03/19~2022/06/19
東京都現代美術館[東京都]
同時開催の「井上泰幸展」と「吉阪隆正展」の内覧会のときに見逃したので、あらためて見に行く。東京都とトーキョーアーツアンドスペースの主催するアワードの受賞記念展。受賞した藤井光と山城知佳子の2人展だが、ここでは藤井の作品について書く。出品作品は《日本の戦争画》と《日本の戦争美術》の2点。前者は大作ばかり153点が1セットになっているので、びっしり展示しても現代美術館の広大な1フロアの半分を埋め尽くす。《日本の戦争美術》のほうはマルチスクリーンの映像インスタレーションだが、3時間を超える長尺なので(音声のみだと12分弱)一部しか見ていない。
まず、会場入口に「日本の戦争美術展」とタイトルが掲げられ、「昭和21年8月21日-9月2日/東京都美術館/入場 占領軍関係者に限る/主催 アメリカ合衆国太平洋陸軍」と書かれている(実際は英語の下に日本語表記)。昭和21年というと、日本の敗戦後GHQが藤田嗣治らの協力の下に全国から戦争記録画を集め、東京都美術館に収蔵した時期にあたるので、その史実に基づいた架空の展覧会だろう。と思ったら、解説には「1946年に東京都美術館で、占領軍関係者に向けて開催された戦争記録画の展覧会を、アメリカ国立公文書館に現存する資料をもとに考察した映像とインスタレーションで再現します」とある。ほんとにそんな展覧会あったの? 聞いてないよ~。でも占領軍向けの非公開の展示ならありうるかも。
《日本の戦争画》は153点1セットからもわかるように、東京国立近代美術館に収蔵されている戦争記録画をすべて原寸大で再現したもの。といってもキャンバスに模写したわけではなく、ベニヤ板やカラーシート、クレート(美術品運搬用の箱)などの廃材を使って同じサイズに組み立てたものだ。1点1点すべてキャプション(これも英語が先)がついているので、ある程度知識があれば原画をイメージしやすい。例えば藤田の《サイパン島同胞臣節を全うす》は幅3.6メートルを超す横長の超大作だが、ここでは画面の9割くらいが黒い布に覆われ、上部にわずかな白い余白がのぞく構成で、崖の上で日本人たちが集団自決しようとしている原画のイメージがなんとなくオーバーラップしてくる(作者はそこまで意図してないと思うけど)。
最初の部屋はある程度余裕を持って展示しているが、通路を隔てた奥の部屋は骨組みだけの仮設壁を何枚も立て、収蔵庫のように2段がけでびっしり空間を埋め尽くしている。確か東京国立近代美術館はこれまで戦争記録画を15点以上まとめて公開したことがないが、もし153点すべて一気に見せようとすればこれだけの場所が必要だというシミュレーションとしても見ることができる。この展示のおもしろいところはそれだけではない。つぎはぎしたパネルやカラーシートを組み合わせた色面構成が並ぶさまは、まるでイミ・クネーベルかミニマルアートを思わせるため、戦争画から離れて抽象絵画として鑑賞することもできるし、また子どもが退屈したら、迷路のようなインスタレーションとして楽しむことだって可能だ。
ひとつ気になるのは、今回の展示の後これらの「作品」はどうなっちゃうんだろうってこと。「芸術作品」として153点まとめて保存されるのか、それとも再現可能なインスタレーションの素材として再び廃材に戻るのか(1点ずつバラ売りという選択肢もあり?)。これはGHQが戦争記録画を「芸術かプロパガンダか」と判断に迷ったことにもつながってくる。もし保存されるとしたら、どこがふさわしいだろう? 東京都美術館か、東京都現代美術館か、それとも東京国立近代美術館か。ま、倉庫が空いてるところだろうね。
2022/05/15(日)(村田真)
αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点
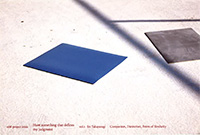
会期:2022/04/16~2022/06/10
ギャラリーαM[東京都]
私が初めて髙柳恵里の作品と出会ったのは、2003年に国立国際美術館で開催された「近作展28 髙柳恵里」であった。なかでも、《ハンカチ》(1999)は、整然と重ねられた綿と思しき布の清々しさから、洗濯物をたたむ日常の所作を想起させ、移転前の国立国際美術館の大理石の床とともにずっと記憶に残っている。
なぜ、このような語り口から始めるかというと、髙柳の作品の特徴は、普遍的なテーマを扱っていながら、鑑賞者の個人的な「出会い」の経験を蔑ろにしては記述し難いことにあるからだ。80年代半ばに作家活動を開始して以来、髙柳は一貫して身近な素材を扱いながら、その都度関心を惹かれた出来事や物事の様態と自身との関わりを探り、発表してきた。髙柳によって提示されるエフェメラルな場の背景には、先に挙げた所作や作為のような人の振る舞いだけでなく、素材や道具に対して同時代の人々が抱く共通認識や価値観のようなものがそこはかとなく漂っている。世界を知覚し、分節化する基礎的な感覚は、時の移ろいとともに変化し続け、忘れ去られていくこともあるが、髙柳の作品との出会いによって、鑑賞者は結節点を見出し、何度も出会い直していくのだ。1999年に髙柳が参加した第1回目のMOT ANNUALのタイトル「ひそやかなラディカリズム」は、このような作品の性質を言い当てているように思う。
今回の展覧会では、展示室の床の一角にタイルが敷かれている。《実例》と名づけられた本作に続き、透明のポリエチレン製のシートとベージュのカーペットを重ねた《敷く(実例)》、さらにその上にポリエチレン製のシートが敷かれており、ひび割れのある泥の水溜りが作られた作品《実例》がある。壁にテープで貼られたポリエチレン製のシートに泥水がかけられ、乾いていく痕跡も、同じく《実例》と名づけられた作品である。特定のモノや現象を扱っていながら、モノとモノの関係やそこに介在する行為を辿っていくうちに、特定の意味や背景は抽象化されていき、それぞれがさまざまなヴァリエーションのひとつとして認識される。対象を認識するプロセスが、観察から始まるにもかかわらず、概念操作でもあることに気づかされるのだ。一連の思考のプロセスと泥溜まりの形状は、図らずも、榎倉康二の《P.W.-No.50 予兆─床・水》(1974)、自宅の庭のひび割れた土を写真や映像の記録によって残した「点展」の《予兆》(1976)を想起させる。榎倉と比べると、髙柳の作品では、我々の生活に浸透している人工物との付き合いが明示されているように思えるのだ。
上記は展覧会の一部であるが、今回の展示のもう一つの見どころは、豊田市美術館の千葉真智子による企画「判断の尺度」の第1回目として位置づけられていることであろう。髙柳の展覧会を起点に、5回にわたるシリーズを通して、差異を積極的に許容する美術のありようが示されるはずだ。

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」
(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年
《実例》(2022)/床材見本/0.2×194×30cm[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」
(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年
[撮影:守屋友樹]

「αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol. 1 髙柳恵里|比較、区別、類似点」
(企画:千葉真智子)展示風景、gallery αM、2022年
《実例》(2022)/泥、ポリシート、テープ/84×123×118cm[撮影:守屋友樹]
公式サイト:https://gallery-alpham.com/exhibition/project_2022/vol1/
関連レビュー
αMプロジェクト2022 判断の尺度 vol.1 髙柳恵里|比較、区別、類似点|きりとりめでる:artscapeレビュー(2022年07月01日号)
2022/05/14(土)(伊村靖子)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)