artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
エマヌエーレ・コッチャ『メタモルフォーゼの哲学』

翻訳:松葉類、宇佐美達朗
発行所:勁草書房
発行日:2022/10/26
2016年に世に出た『植物の生の哲学──混合の形而上学』(嶋崎正樹訳、勁草書房、2019)によって、エマヌエーレ・コッチャの名前は一躍世界的なものとなった。この1976年生まれの哲学者の仕事は、いまや狭義の現代思想の枠をこえて、さまざまな文化領域に広がっている。なかでも、同時代のアーティストからの影響を公言して憚らない著者は、2019年にはカルティエ現代美術財団の「われわれという木々(Nous les arbres)」の学術顧問を務めたほか、フィンセント・ファン・ゴッホ財団の要請により、かの有名な《種まく人》についての小さな著書(『種まく人──現代の自然について』)を執筆している。現在はパリの社会科学高等研究院(EHESS)で教鞭をとるこの哲学者は、現代美術の世界でも昨今ますます存在感を増している。
その『植物の生の哲学』のいわば続篇とも言えるのが、2020年に刊行された本書『メタモルフォーゼの哲学』である。原著の翌年(2021年)にはすぐさまロビン・マッカイの手による英訳が刊行されており、そのことからも、この哲学者に対する世界的な注目度の高さがうかがえる。
本書に内包される思想は、ある意味ではきわめて単純なものである。ふだんわれわれが生命とみなしているのは、同じひとつの「生」が変容したものである。個々のあらゆる生命は、そのメタモルフォーゼの結果にすぎない。いかなる生物も単独では存在しえず、われわれはつねにほかの生物を糧として、またほかの生物の糧として存在している。その意味で、どんな生物であっても根源的にはどこかでつながっている。さらに厳密に言うなら、事態は生物の範囲内にとどまらない。コッチャによれば、生物とは無生物の延長──ないし「再受肉」──なのであり、そのかぎりにおいて「生物と無生物の間にはいかなる対立もない」(8頁)。
以上のような思想を、本書は「Ⅰ 誕生=出産」「Ⅱ 繭」「Ⅲ 再受肉」「Ⅳ 移住」「Ⅴ 連関」という5つのパートを通して詳らかにする。各章のトピックは比較的広範にわたっているが、本書全体を貫くのは、自立した個体(=わたし)というものが一種のフィクションにほかならず、その実相は大いなる「生」のメタモルフォーゼの一部である、という全体論的な世界観である。これは昨今のエコロジー思想とも親和性の高い、現代の「生の哲学」の一形態であると言えよう。
さきほど、本書はある意味で前著『植物の生の哲学』の続篇である、と言った。それは、この2冊がいずれも、生命というものを根源的に「一なるもの」として捉えている点で共通しているからだ。前著では、それを端的に言い表わす「混合の形而上学(métaphysique du mélange)」という表現が副題に用いられていたわけだが、「混合」にしろ「メタモルフォーゼ」にしろ、そもそも一なる生が根幹にあり、そのうえで個々の生物がその存在を分かち持っているという図式において、コッチャの思想はこれらのあいだで大きく異なってはない。
そのうえで言うと、わたし個人の『メタモルフォーゼの哲学』に対する評価は、いくぶん微妙なものとならざるをえない。『植物の生の哲学』においては、「混合」ないし「浸り」というキーワードを通じて、有機体のなかでも伝統的に最下位におかれてきた植物を世界の中心に据えるという大きな価値転換が見られた。対する『メタモルフォーゼの哲学』において、この地上に生きるわれわれはみな「ガイア」という大いなる存在に結びつけられる。ここには昨年亡くなったブリュノ・ラトゥール(1947-2022)からの影響も見られるとはいえ、そこでは前著にあったような価値観の大胆な転換が、いくぶん影をひそめているように見えなくもない。
さらに言おう。本書には、いまだかつてない「新しい」哲学理論が含まれているわけでは必ずしもない。勘のよい読者ならばお察しのように、ここまで紹介してきたような内容の大半は、ベルクソンやホワイトヘッドをはじめとする過去の「生の哲学」の焼きなおしにすぎない。「すべての生命はつながっている」という命題にしても、ほとんどの人にとっては、あらためて言挙げするまでもないたんなる事実の域を出ないだろう。だから注目すべきは、そんな本書がなぜこれほどまでに読まれ、注目を集めているかという問題のほうにある。
かつて本書を原著で読んだ一読者としての印象を言えば、本書には著者の第一言語でないフランス語で書かれているがゆえの、不思議な力強さがある。なるべく込み入った構文を避けて、短く断定的なセンテンスをぽつぽつと繰り出していくそのライティング・スタイルは、前著からさらなる洗練をみせている。著者であるコッチャはかつて筆者との対話のなかで、哲学(史)というのはさまざまな知の「寄せ集め」であって、そこにはいかなる共通の対象も、文体も、方法もないと述べたことがある。なるほど、プラトン、ニーチェ、ウィトゲンシュタインといった「哲学者」たちの文章には、それぞれ対話篇、アフォリズム、命題の集合といった特徴があり、ふつうに読めばそこに共通点などまったくない。コッチャの言葉を補って言えば、われわれが──事後的に──「哲学史」とみなしているのは、つねに新しい「スタイル」の発明の連続であったということだ。わたしが本書を読みながら、くりかえし思い出していたのはそのことだった。コッチャの一連の著書もまた、その哲学的な内容の新しさ云々の次元でなく、そのスタイルにおいて、ひとつの新しい形式を発明する試みであると考えるべきかもしれない──本書につづく『家の哲学(Philosophie de la maison)』(2021)も含めて、わたしがコッチャの近年の仕事から感じるのはそのような「新しいスタイル」への意志である。
関連レビュー
エマヌエーレ・コッチャ『植物の生の哲学──混合の形而上学』|星野太:artscapeレビュー(2020年06月15日号)
2023/01/05(木)(星野太)
石川竜一『zk』

発行所:赤々舎
発行日:2022/12/25
石川竜一は2014年に『絶景のポリフォニー』と題する写真集を赤々舎から刊行している。本作は、タイトルを見てもわかるようにその続編と位置づけられる。だが、やはり同年に刊行された『okinawan portraits 2010-2012』(赤々舎)とともに第40回木村伊兵衛写真賞を受賞した前作と、今回の『zk』では、かなり味わいが違ってきている。
最も目につくのは、『絶景のポリフォニー』は石川が生まれ育った沖縄の写真だけで構成されていたのに対して、『zk』では被写体の幅が大きく広がっているということだ。巻末の撮影地の一覧を見ると、埼玉、大阪、東京。神奈川、京都、広島、千葉、北海道、福岡、宮城、福島、山梨、沖縄、石川など、その撮影場所が日本各地に大きく広がってきていることがわかる。人とモノの蠢きを直裁に捉えたスナップ写真が中心なのは前作と変わりがないが、純粋な「風景」というべき作品も多く、「ノイズ」と題されたほとんど色とフォルムだけの純粋抽象写真まである。明らかに被写体をキャッチするアンテナの許容範囲が拡張しており、その精度もさらに上がってきているのだ。
石川は、いわばライフワークともいうべきこの絶景=zkシリーズで何を追い求めようとしているのだろうか。本書におさめられたテキスト「zk」で、彼はこのように記している。「記号は文化だ。文化とは集団だ。集団とは運動だ。運動とは存在だ。存在とは意志だ。意志とはすべての外側だ。すべてのものは特定の誰かや、何かのためのものではない。世界は外にあって、内にある。唯一在ることがすべてを繋げ、無いことと重なり合っている。その重なりと、揺らぎと、もつれ」。
この小気味のいい言葉の連なりから見えてくるのは、「外にあって、内にある」世界に向けて、カメラを手に全身全霊で踏み込み、もがきつつ対応していく、荒武者のような写真家の在り方である。そのような世界との向き合い方は、むろん彼自身を切り裂き、血を流しかねない、危うさを孕んだものとなるだろう。いまや、絶滅危惧種になりつつあるようにも見える、生と写真とを一体化させた撮影者のあり方を、確かに石川は選びとった。『zk』はそんな彼の、現時点での中間報告というべき写真集である。
関連レビュー
石川竜一「絶景のポリフォニー」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2015年01月15日号)
2023/01/04(水)(飯沢耕太郎)
カタログ&ブックス | 2022年12月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
SHUZO AZUCHI GULLIVER 「Breath Amorphous:消息の将来」

編集:SAGYO,Tokyo/certo Tokyo
アートディレクション:岡本佳子[ certo Tokyo ]
発行:BankART1929
発行日:2022年10月14日
サイズ:A3、256ページ
2022年10月7日(金)~11月27日(日)まで、BankART KAIKOとBankART Stationにて開催されていた、シュウゾウ・アヅチ・ガリバーの展覧会「Breath Amorphous 消息の将来」のカタログ。
「かげ」の芸術家 ゲルハルト・リヒターの生政治的アート

著:田中純
発行:ワコウ・ワークス・オブ・アート
発行日:2022年10月15日
サイズ:19x13cm、128ページ
思想史学者の田中純(東京大学大学院総合文化研究所教授)によるゲルハルト・リヒターの作品論4編を収録。リヒターの制作史で重要な3つのシリーズ《アトラス》《1977年10月18日》《ビルケナウ》をイメージ論の観点から考察しながら、リヒター作品を生政治的なアートとして紐解いていく。
吉村朗の眼 ─Eyes of Akira Yoshimura─

写真:吉村朗/編:深川雅文
発行:さいはて社
発行日:2022年10月20日
サイズ:A4変形判、240ページ
写真表現の革新を目指し、絶えざる前進を続けた吉村朗。馴化されず、媚を売らず、自らの道を突き進んだ、孤高の写真家の眼差しの軌跡と奇跡に刮目せよ!
建築家・石井修―安住への挑戦

編著:倉方俊輔+石井修生誕100年記念展実行委員会
発行:建築資料研究社
発行日:2022年11月10日
サイズ:A4判、176ページ
地形の形状を最大限生かしながら住空間と緑の共生した建築を多く手掛けた住宅作家・石井修。 経年と共に建物は疲弊し、見た目が悪くなってしまうのが一般的だが、年月を掛けることで、自然と建物が一体となることを目指した設計手法は独特である。 今でこそ当たり前の屋上緑化やエコ住宅の考え方も、石井修の自邸「回帰草庵」など初期の作品から取り入れられている。 「建物に外観はいらないのです」という一言に、その建築への考え方が集約されている。 1986年度の建築学会賞を受賞した目神山の一連の住宅作品をはじめ、代表作・天と地の家など、美建・設計事務所を創設以来追い求めてきた建築の理想像-大胆なまでの樹木との調和・合体した住宅作品を収めた「別冊住宅建築No.34」以降、平成期の作品を設計年代順に一挙に収録する。
新宗教と巨大建築 増補新版

著:五十嵐太郎
発行:青土社
発行日:2022年11月14日
サイズ:19cm、445ページ
東大寺や法隆寺だけが美しい宗教建築ではない。著名建築家の作品だけが、先進的な現代建築ではない──。新宗教の巨大で絢爛たる建築が、なぜ信仰の堕落・虚偽の教えの象徴とされるのか。近代国家イデオロギー、天皇制、さらにマスコミが増長させた偏見によって、教団と建築は徹底して弾圧を受け続けた。建築批評の気鋭が読み解く、新宗教建築に投影された「日本近代」の夢と信仰の空間。大幅に増補された決定版。
THE NEW CREATOR ECONOMY[ニュー・クリエイター・エコノミー]

編集:庄野祐輔、hasaqui、廣瀬 剛、田口典子、藤田夏海
発行:ビー・エヌ・エヌ
発行日:2022年11月16日
サイズ:B5判変型、248ページ
本書では、アーティスト、コレクター、キュレーター、リサーチャーなどさまざまな立場の視点を借りて、現在のNFTアートの状況を多面的に解説するとともに、現在へと繋がる歴史にも目を向ける。このグローバルなムーブメントは、連綿と続いてきたコンピュータアートの歴史だけでなく、既成のアートのあり方も書き換えるのか。アーティストはどのような態度で創造に臨むのか。加速するデジタルアートの可能性を追う一冊。
DOMANI・明日展 2022–23 百年まえから、百年あとへ

監修:林洋子(文化庁) 編集:内田伸一、アート・ベンチャー・オフィス ショウ
発行:文化庁
サイズ:A5判、396ページ
2022年11月19日(土)~2023年1月29日(日)まで、国立新美術館にて開催されている展覧会「DOMANI・明日展 2022–23」のカタログ。
飯沢耕太郎「完璧な小さな恋人」

著:飯沢耕太郎
作品掲載作家:野村仁衣那、磯部昭子、下瀬信雄、村上賀子、サイトウマサミツ、ときたま、小林小百合、川田喜久治、小平雅尋、尾仲浩二、飯沢耕太郎
発行:ふげん社
発行日:2022年11月22日
サイズ:B5判、116ページ
写真評論を中心に活動してきた同氏の26年ぶりの詩画集。詩と自作を含むヴィジュアル(写真、ドローイング、コラージュなど)で構成。
合田佐和子 帰る途もつもりもない

監修:高知県立美術館、三鷹市美術ギャラリー
発行:青幻舎
発行日:2022年11月26日
サイズ:A5判、280ページ
合田佐和子(1940–2016)は高知に生まれ、1965年の個展デビュー以来、オブジェや絵画、写真といったメディアを横断しながら創作を展開しました。唐十郎や寺山修司とのコラボレーション、瀧口修造など美術評論家からの高い評価、またファッションや音楽など領域を超えたものたちとの親和性により、アングラが隆盛した時代の空気を体現するに至ります。しかし一転して90年代以降はその退廃的な作風を脱ぎ捨て、まばゆい光に満たされた、より内省的な世界を深めていきます。
青春20世紀美術講座 激動の世界史が生んだ冒険をめぐる15のレッスン

著:新見隆
発行:東京美術
発行日:2022年11月28日
サイズ:19cm、240ページ
「20世紀美術」は、産業革命ののち、「近代」が定着するとともに露呈したさまざまな問題に直面する中生まれました。芸術家は、「青春」をかけて芸術と社会の問題に取り組み、苦闘の中から前例のない作品を生み出したのです。一方「近代化」の影響は、地球環境問題やコロナ禍などに直面する現代へつながり、人々を苦悩へと引き込みます。解くのが容易ではない山積みの問題を前にした現代の我々は、どうしたらよいのか? 本書では20世紀美術を生み出した芸術家達の苦闘の中にその問いへの答えを探り、現代を生き抜くためのヒントを見出します。
沖縄と琉球の建築|Timeless Landscapes 3

写真:小川重雄
解説:青井哲人
発行:millegraph
発行日:2022年11月29日
サイズ:304×230mm、88ページ
伝統的民家、およそ半世紀前につくられたリゾート建築の金字塔、そしてグスク(城)の遺構、樋川(湧水)、御嶽に見られる密やかな人為の跡、フクギの防風林など、その風土ならではの人工環境を「建築」と捉えた1冊。
潜在景色

編著:アーツ前橋
写真:石塚元太良、片山真理、下道基行、鈴木のぞみ、西野壮平、村越としや
発行:ART DIVER
発行日:2022年11月下旬
サイズ:B5判、144ページ
石塚元太良、片山真理、下道基行、鈴木のぞみ、西野壮平、村越としや これからの写真界を牽引する30歳代から40歳代の実力派作家6名による展覧会の公式カタログ。 撮り下ろし新作を含む、メディア未発表作品を多数掲載。
アートプレイスとパブリック・リレーションズ 芸術支援から何を得るのか

著:川北眞紀子(南山大学教授),薗部靖史(東洋大学教授)
発行:有斐閣
発行日:2022年12月5日
サイズ:A5判、282ページ
デジタル化とコモディティ化が進む現代,アートの「場」から得られる知見や着想,地域や文脈とのつながり,そして真正性は,企業にとって有益なものである。アートプレイスの構築から企業が得られるものとは何か。取材と分析から得られた知見をもとに伝えていく。
金サジ写真集『物語』

デザイン:佐々木暁
発行:赤々舎
発行日:2022年12月中旬(予約販売)
サイズ:B4変形
写真家 金サジの代表作「物語」シリーズの写真集。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2022/12/14(水)(artscape編集部)
ZINE『岡山芸術ごっこ』

発起人:菊村詩織
発行日:2022/11/01
コンビニエンスストアに行って、マルチコピー機のパネルで「プリントサービス」を選択した後、「ネットワークプリント」をタップ。ツイート(こちら)に書かれたユーザー番号を入力する。モノクロだと260円。2023年1月3日の18時頃までローソン、ファミマ、ポプラ系列で印刷できるようになっていたZINEが1枚ずつ印刷される★1。『岡山芸術ごっこ』である。本稿は脱線気味だがZINEを読んだ所感であり、共感と応答する気持ちから綴ったものだ。
1. ZINEを読んだ
「岡山芸術交流 2022 僕らは同じ空のもと夢をみているのだろうか」(会期:2022年9月30日〜11月27日/以下、岡山芸術交流)の総合プロデューサーである石川康晴(公益財団法人石川文化振興財団理事長)は、2018年12月のストライプインターナショナルのCEO在籍時に、同社員やスタッフへのセクシャルハラスメントに関する厳重注意を同社の臨時査問会で受けていたと、2020年3月に朝日新聞等に報道された★2。 石川は2020年3月6日付けで同社を、9日には内閣府男女共同参画会議議員も辞任したが、その理由は「自身にかかわる一連の報道を理由に」★3 「世間を騒がせているため」★4という曖昧なものだった。ZINE『岡山芸術ごっこ』は、岡山芸術交流がこの一連の報道を受けても「変更なく開催されているため、反対の意思を示すために企画」された★5。
ZINEでは、記名・無記名の15名ほどの人々が石川によるハラスメントがあった可能性が拭い去れない/あった可能性が高いという危機感のもと、「岡山芸術交流についての思い」を書いている。それは勝手ながらまとめてみると、芸術祭への関与や観賞すら、加害者かもしれない石川について言及しなければ、ハラスメント自体を「認可(license) 」★6することになり、被害者への二次加害になりうるのではないかという指摘だろう。またZINEには直接的に、時には詩を通して、石川に関するハラスメント報道への認識や関心の度合の違いが立場の違いとなり、芸術祭関係者や関心を持っている人々を分断しているという状況、あるいは、石川が報道を受けたことをどう考えるかという提起すら黙殺されるという怒りや悲痛さが切々と綴られている。
2. 報道内容を確認したくなった
私はZINEを読んで、何がどのようにいままで報道されているのかを振り返りたくなった。判断の土台となるマップが欲しいと思ったのだ。
前述の通り、2020年3月4日の朝日新聞の報道を受けた後、石川はハラスメント行為を認めていない。また、ストライプインターナショナルの広報は翌日「石川がセクハラで厳重注意を受けていた」という報道を部分的に否定した。曰く正しくは、当事者からの申し立てでないためにセクハラの事実が確認できなかったが、そこで提出された石川と社員とのLINEでのやりとりが、「トップとして社員との距離の取り方が近すぎると査問会から石川に対し厳重注意はあった」と★7。朝日新聞に掲載されているLINEのスクリーンショットは2018年12月に臨時査問会で提出されたとされるものであるが★8、CEOから夜にホテルの部屋にひとり呼び出されるLINEはどう考えても性的行為の打診にしか思えないだろう。明快に断って自意識過剰だと一蹴され職場環境が悪化したらと考えさせられる立場の非対称性を持つ時点で、これはセクシャルハラスメントだと考えられる★9。
一方で、2020年5月1日に同社の人事課長(当時)であった二宮朋子は、フィクションの漫画に実名と肩書を添えてnoteに記事を投稿している★10。そのアカウントと漫画制作は株式会社TIEWAが運営する「パレットーク」のもので、二宮が自身で語るように、「2019年からストライプインターナショナルの社内SNSで配信しているダイバーシティ/SDGsコラムのイラストを依頼」していた会社なのだが、二宮による漫画と投稿は社外からの寄稿という立ち位置だ★11。フィクションだというその漫画では、男性社長が女性社員に性的な興味を持っている場合の態度と、そういったものを見逃してきていなかったかという二宮の自己反省が描かれているが、その男性社長はどう見ても石川に似ていて、事件との関連が示唆されているようでもあり、メッセージが複雑化されている★12ことに留意したい。
3. ハラスメントへのさまざまな対処とその性質
2022年にも報道されたように、石川はストライプインターナショナルにまだ主要株主として影響を与える可能性があり★13、そのようななかで同社は、記者の林芳樹が言うように「4000人近い従業員が働く会社の存続自体が危うくなる。査問会は役員規定に基づく処分ではなく、いわば“政治決着”を選んだ」★14のだ。この漫画がハラスメントの真相を明らかにするものではないのはなぜかと質問を受けた二宮は「その説明責任を果たすべき人は他にいるはずです」と返答し、人事として採用に関わってきた責任を果たそうと漫画や記事を制作したと綴っている★15。社内の人間に向けた、それぞれの責任の範囲に応じた決断があった。ストライプインターナショナルは、二宮による記事を受け入れる土壌を示すことで社員(ひいては社会的弱者)の尊重を暗示し、ハラスメントはなかったという声明を出すことで会社の不祥事にまつわる損益を最小にしたと私は考えている。企業運営上、これ以上ない判断だったのだろう。ただしその結果、一企業のハラスメントに関する「政治決着」が、多くの人々の「岡山芸術交流」についての問題認識をバラバラにし、混乱を招き続けている。
ハラスメントは名誉毀損罪や侮辱罪として刑事訴訟、人格権の侵害から民事訴訟になる可能性もあるが、本件のように組織内での対処がほとんどであり、謝罪と被害が公表されるケースばかりではない。ハラスメントとは、(それが検証可能かは別の問題として)つねにほとんどのタイミングで、噂に留まる性質をもってしまうものなのだ。
公的に問題になる可能性が低いということは、限りなく厄介だ。外的な裁量はほとんど得られないなかで、憶測で意見を形成してもならず、自分自身の行為や判断が内的な倫理に合致するかどうかだけは見極め続けなければならない。では、内的な倫理に反した場合はどうするべきか。
4. どうしたらいいか、どうしてしまってきたか
石川のハラスメント疑惑について友人に相談したところ、パレスチナ問題に際し、親イスラエルロビーやイスラエル空軍とつながりのあるザブルドヴィチ・アート・トラストに対し何百名ものアーティストや美術関係者が採ったボイコットの手法の存在を教えてくれた。その運動団体であるBoycott Divest Zabludowicz(BDZ)が主導する方法は、作家やキュレーターはその組織のために働いたり、そのショーをレビューすることを拒否し、アーティストは作品の著作権ボイコット(イベントや展示やあらゆる記載を撤回させたり、作品を引き取り他所に寄贈するなど)を実施するというものである★16。このザブルドヴィチによるパレスチナ虐殺への関与は否定し得ない状況にあるという点が、石川問題とはまったく異なるが、そもそも、このハラスメント疑惑の事実関係が広く共有される可能性はきわめて低い。だからこそ、自身の内的な倫理に照らして、自分で責任を持てる無理のない範囲で、この文章を書くことにした。
私はBDZのアクションを読みながら、いままでのさまざまなハラスメントに関する噂とその相手への自分の対応を振り返った。私自身、自分の倫理に反する行為に対して下した決断もあるが、その行為は中途半端なために推定加害者を利してきたものもあり、被害者の損失に結果加担してしまった。私はすぐ何かアクションを起こせるような胆力がないが、まずこの自分の状態を変えていきたい。
★1──岡山芸術ごっこ(Twitter: @okayamaartgokko、2022.12.4)2023.1.7閲覧(https://twitter.com/okayamaartgokko/status/1599333151989731330?s=20&t=gcJBoI0BjrGbyZAq5pIHIQ)
★2──藤崎麻里「【独自】大手服飾社長が社員にセクハラ 政府会議の議員」(『朝日新聞』、2020.3.4)2023.1.7閲覧(https://www.asahi.com/articles/ASN346VLWN32ULFA00F.html?iref=pc_rellink_01)
★3──「代表取締役社長辞任と取締役異動に関するお知らせ」(『STRIPE INTERNATIONAL INC.』、2020.3.6)2023.1.7閲覧(https://www.stripe-intl.com/news/2020/0306-01/)
★4──「ストライプ社長が辞任、『世間を騒がせた』」(『日本経済新聞』、2020.3.6)2023.1.7閲覧(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56497930W0A300C2TJC000/)
★5──『岡山芸術ごっこ』(発起人:菊村詩織、ネットプリント、2022、p.1)
★6──池田喬「ただの言葉がなぜ傷つけるのか──ハラスメント発言の言語行為論的探究」(『哲学』69号、2018、pp.9-20)
★7──五十君花実「ストライプ石川社長にセクハラ報道 広報は『事実無根』と否定」(『WWDJAPAN』、2020.3.5)2022.12.10閲覧(https://www.wwdjapan.com/articles/1052995)
★8──藤崎麻里+松田史朗「『内緒だよ』自室に社員誘うearth社長 資料入手」(『朝日新聞』、2020.3.5)2022.1.7閲覧(https://www.asahi.com/articles/ASN356R02N35ULFA03B.html)
★9──海老澤美幸「『早朝デートする?』人気アパレル元社長のセクハラLINEが“2重で”アウトな理由──弁護士が解説」(『文春オンライン』2020.3.19)2022.12.25閲覧(https://bunshun.jp/articles/-/36659)
★10──二宮による記事は以下の通り。
二宮朋子「【漫画】会社でのセクハラに声を上げられるか - とある社員が思うこと」(『マンガでわかるLGBTQ+ / パレットーク』2020.5.1)2022.12.10閲覧(https://note.com/palette_lgbtq/n/n859e2ccbde92)
二宮朋子は2021年4月1日に人事就労コンサルタント企業である株式会社CAQNALの顧問に就任。女性活躍推進を支援する団体「WE association」のシンポジウムのファシリテーターを努めるなど活躍している。
★11──藤崎麻里「earth社セクハラ問題、実名ブログ書いた女性社員の『意表つく告白』」(『withnews』、2020.6.17)2022.12.10閲覧(https://withnews.jp/article/f0200617000qq000000000000000W02m10101qq000021231A)
★12──二宮による記事で構築されているメッセージは非常に複雑だと私は考えている。以下は私の曲解だが、メッセージの種類を記述してみたものだ。
①ハラスメントは許されるべきでないし、ハラスメントがあったら声を上げよう、②ハラスメントを間接的にほう助する環境をつくっていないかどうか考えてほしい、③石川によるハラスメントはなかったという見解を提示する(漫画はフィクションだと明言)、④しかし石川によるセクハラはあったと匂わせる(石川の似姿で漫画の登場人物が描かれている)、⑤会社全体がセクハラを無視するつもりはないという姿勢を個人で象徴的に示す、⑥この漫画が投稿されても大丈夫だという現時点での会社の透明性。
★13──「ストライプインターナショナル、セクハラ問題で辞任した前社長が主要株主に居残りか」(『Business Journal』、2022.5.18)2022.12.10閲覧(https://biz-journal.jp/2022/05/post_296178.html)
なお、新社長の立花隆央は2020年の時点で石川の経営関与を否定している。
「ストライプ立花新社長、石川氏のハラスメント疑惑に『査問会の結論を尊重』新体制で防止策を計画」(『FASHIONSNAP.COM』、2020.4.1)2023.1.7閲覧(https://www.fashionsnap.com/article/2020-04-01/stripe-tachibana/)
★14──林芳樹「『社長セクハラ査問会』の真相 連載ストライプ・ショック(1)」(『WWDJAPAN』、2020.4.6)2022.12.10閲覧(https://www.wwdjapan.com/articles/1067459)
★15──小林明子「セクハラを知った中間管理職は何をすべきか。声をあげたストライプ社員と語った『私たちの反省点』」(『BuzzFeedNews』、2020.7.22)2022.12.10閲覧(https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/diversity)
★16──「Boycott the Zabludowicz Art Trust and the Zabludowicz Collection!」(『Boycott Divest Zabludowicz』)2023.1.7閲覧(https://boycottzabludowicz.wordpress.com/boycott-zabludowicz/)
岡山芸術ごっこ(Twitter):https://twitter.com/okayamaartgokko
2022/12/06(火)(きりとりめでる)
カタログ&ブックス | 2022年12月1日号[テーマ:ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊]

言わずと知れたポップ・アートの旗手ウォーホル。1956年の初来日時の京都と彼の接点にも目を向けた大回顧展「アンディ・ウォーホル・キョウト」(京都市京セラ美術館で2022年9月17日~2023年2月12日開催)に際し、日本の作家や芸術家たちがウォーホルに向けた個人的な眼差しが時代背景とともに垣間見える5冊を選びました。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:京都市京セラ美術館
今月のテーマ:
ウォーホルをこの人はどう見ていたか? 個人の記憶と時代が交差する5冊
1冊目:見えない音、聴こえない絵(ちくま文庫)
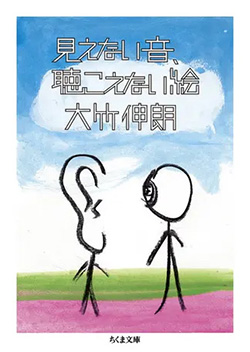
著者:大竹伸朗
発行:筑摩書房
発売日:2022年8月10日
サイズ:15cm、363ページ
Point
アーティスト・大竹伸朗によるエッセイ集。大量消費社会の合わせ鏡としてのウォーホル作品に対する著者の問題意識が綴られる「ウォーホル氏」の章だけでなく、子供時代の雑誌や漫画との衝撃的な出会い、コラージュという手法に目覚めた瞬間など、著者の現在の作家活動にもつながる記憶のディテール描写に気づけば夢中に。
2冊目:ウォーホルの芸術 ~20世紀を映した鏡~(光文社新書)

著者:宮下規久朗
発行:光文社
発売日:2010年4月
サイズ:18cm、294ページ
Point
日本でのウォーホルの回顧展にも関わった美術史家の目線から、メディアを通してセンセーショナルにつくり上げられていった国内でのウォーホルのイメージと、実は多くの人が深くは理解していないであろう美術史上での彼の作品の意義を俯瞰的に解説。ウォーホルという人物を知るうえでの最初の一冊としてもおすすめです。
3冊目:サブカルズ(角川ソフィア文庫 千夜千冊エディション)
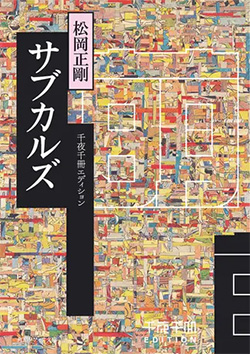
著者:松岡正剛
発行:KADOKAWA
発売日:2021年1月22日
サイズ:15cm、428ページ
Point
現代の知の大家・松岡正剛による「サブカル」に関する書評集。1世紀前のアメリカにサブカルチャーの起源を見出し、日本の漫画・ラノベに至るまで、植草甚一、都築響一、東浩紀などの著書も網羅。ウォーホル『ぼくの哲学』評では「とびきり猜疑心が強くて、ひどく嫉妬心が強い」ウォーホルの人物像を魅力的に描いています。
4冊目:CONTACT ART 原田マハの名画鑑賞術
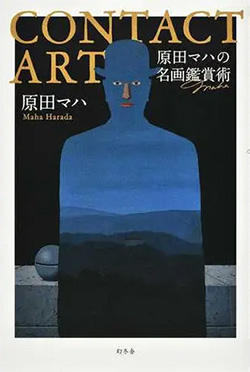
著者:原田マハ
発行:幻冬舎
発売日:2022年10月26日
サイズ:20cm、191ページ
Point
作家・原田マハが日本各地の美術館を訪ね、モネ、ルソー、東山魁夷など名だたる絵画と向き合い語られる、彼女流の作品解説。福岡市美術館で鑑賞するウォーホルのシルクスクリーン作品「エルヴィス」の章も収録。「美術館大国」として日本を少し違った角度から見つめ直すこともできる、アートファンに広く薦めたい一冊です。
5冊目:自画像のゆくえ
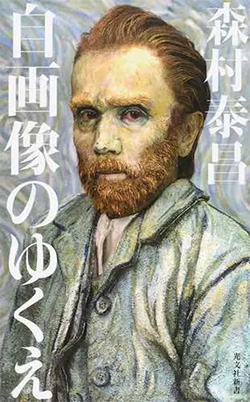
著者:森村泰昌
発行:光文社
発売日:2019年10月17日
サイズ:18cm、615ページ
Point
絵画や作家に扮したセルフポートレイト作品を通してアイデンティティとイメージの関係を問い続ける美術家・森村泰昌が「自画像」という軸で語り直す、世界と日本の美術史。ウォーホル作品を深く読み解く第8章だけでなく、ダ・ヴィンチ、ゴッホから現代日本のコスプレ文化やセルフィーに至るまでの、その射程の広さに驚嘆。
アンディ・ウォーホル・キョウト
会期:2022年9月17日(土)~2023年2月12日(日)
会場:京都市京セラ美術館 新館「東山キューブ」(京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124)
公式サイト:https://www.andywarholkyoto.jp/
[展覧会図録]
「アンディ・ウォーホル・キョウト」公式図録

編集:ソニー・ミュージックエンタテインメント、イムラアートギャラリー
発行:ソニー・ミュージックエンタテインメント ©2022-2023
発行日:2022年9月17日
サイズ:A5判型(145×210mm)、340ページ
出品作品のカラー図版と詳細な解説文、本展キュレーターのホセ・ディアズ氏(アンディ・ウォーホル美術館)の「ウォーホルと日本:1956年」と山田隆行氏(京都市京セラ美術館)の「アンディ・ウォーホル・イン・キョウト─ウォーホルの京都滞在(1956年)を振り返る─」論文を収録。1956年のウォーホル来日時の足跡をたどり、ウォーホル芸術に日本が与えた影響を考察します。ニューヨークの「ファクトリー」を二度訪問し、生前のウォーホルと交流のあった美術家・横尾忠則氏によるエッセイも必読! その他にもアンディ・ウォーホル美術館のアーカイブをまとめた『A is for Archive』からファッションをテーマとした「F is for FASHION」を本書のために翻訳。1956年と1974年の二度の日本訪問を記録した貴重な写真を多数収録した永久保存版。
◎展覧会会場にて販売中。
2022/12/01(木)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)