artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2022年11月1日号[テーマ:石と植物と──半径10メートル以内の自然の見方・愛で方が刷新される5冊]

石と植物。これら身近な存在は、芸術においても重要な素材・モチーフであり続けてきました。滋賀県立美術館の収蔵品を中心に、神山清子、松延総司、東加奈子の3名のゲストアーティストの作品を含む85点で構成された企画展「石と植物」(2022年9月23日~11月20日開催)に関連し、身近な自然を愛でる行為に新たな視点をくれる5冊を紹介します。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:滋賀県立美術館
今月のテーマ:
石と植物と──半径10メートル以内の自然の見方・愛で方が刷新される5冊
1冊目:石が書く
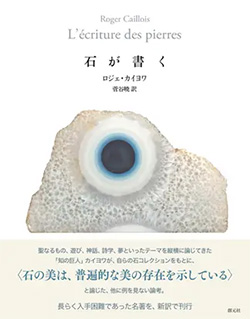
著者:ロジェ・カイヨワ
翻訳:菅谷暁
発行:創元社
発売日:2022年8月26日
サイズ:24cm、134ページ
Point
石の収集を趣味とする人は意外と数多くいますが、「知の巨人」カイヨワも実はその一人。自らの収集した石の断面の写真と、それら一つひとつに対する緻密な分析、そして時折挟まれる詩的な表現には著者の偏愛が感じられます。想像力や創作に、石たちがどのような影響をもたらしたのか。その秘密の一片に触れられる一冊。
2冊目:百花遊歴(講談社文芸文庫)

著者:塚本邦雄
発行:講談社
発売日:2018年11月11日
サイズ:16cm、329ページ
Point
反リアリズムの前衛歌人でありながら、植物愛好家の顔ももつ塚本邦雄。「石と植物」展冒頭でも塚本の随筆集『花名散策』が企画のイメージソースとして言及されていますが、本書は彼が分類・精選した、花に関する古今の詩・俳句・和歌・短歌を集めたアンソロジー。文学においても花が普遍的なテーマであることがわかります。
3冊目:植物の生の哲学 混合の形而上学

著者:エマヌエーレ・コッチャ
翻訳:嶋崎正樹
解説:山内志朗
発行:勁草書房
発売日:2019年8月31日
サイズ:20cm、215ページ
Point
「世界に在る」ということを「全体的な交感を通じて、自分をすっかりさらけだすしかない生命」である植物の視点から考察した、気鋭の哲学研究者による論考。コロナ禍以前に書かれたものでありながら、外出自粛期間や生活様式の変化を迫られた私たちにも否応なく思い当たり示唆を与える、そんな一節に本書では出会うはず。
4冊目:On the Beach 1

著者/撮影:ヨーガン レール
発行:HeHe
発売日:2015年7月18日
サイズ:21cm
Point
デザイナー・ヨーガンレールが収集した自らの石のコレクションを撮った写真集『Babaghuri』に続き、砂浜に流れ着くゴミを実用的なものに作り変える活動の一環で制作したランプシェード約90点を収録した本書。「拾う」「集める」「作り変える」、それぞれの行為の間に流れる思索が写真からも強く伝わってきます。
5冊目:草木とともに 牧野富太郎自伝(角川ソフィア文庫)
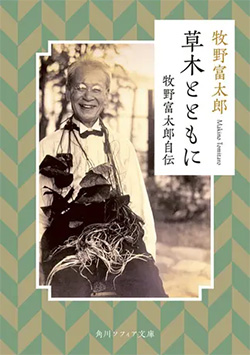
著者:牧野富太郎
発行:KADOKAWA
発売日:2022年6月10日
サイズ:15cm、276ページ
Point
日本を代表する植物研究の大家・牧野富太郎。研究成果だけでなく優れた随筆も数多く残している彼ですが、本書は94歳で亡くなる間際の病床で書かれた「はじめのことば」から始まり、短い随筆の数々を通して、一貫して植物が傍にあった彼の人生を追体験できます。新たな視点を与えてくれるいとうせいこうの解説も掲載。
石と植物
会期:2022年9月23日(金・祝)~11月20日(日)
会場:滋賀県立美術館(滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1)
公式サイト:https://www.shigamuseum.jp/exhibitions/4047/
2022/11/01(火)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年10月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
峯村敏明著作集Ⅳ 外国作家論・選

著:峯村敏明
発行:美学出版
発行日:2022年8月30日
サイズ:A5判、396ページ
日本を代表する美術評論家の一人・峯村敏明の著作集全5巻がいよいよ刊行開始。第一弾は「Ⅳ 外国作家論・選」。
関西の80年代
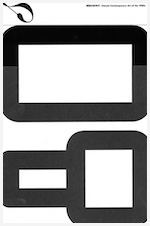
編集:兵庫県立美術館
出品作家 : 森村泰昌、辰野登美子、吉原英里など
発行:兵庫県立美術館
発行日:2022年9月
32+50ページ*「カタログ・テキスト編」と「カタログ・図版編」の2冊綴りとなっております。
本書は兵庫県立美術館で開催(会期:2022年6月18日―2022年8月21日)の展覧会「関西80年代」展の公式図録です。
芸術文化の価値とは何か──個人や社会にもたらす変化とその評価(文化とまちづくり叢書)

著:Geoffrey Crossick、Patrycja Kaszynska
訳:中村美亜
発行:水曜社
発行日:2022年9月5日
サイズ:A5版、364ページ
「なぜ芸術文化は必要なのか」「芸術文化がもたらす効果はどのように捉えられるのか」という問いに取り組んだイギリスの政府機関AHRC(芸術・人文学研究会議)〈文化的価値プロジェクト〉報告書(2018)の邦訳である。この研究は、実証的・科学的研究を扱っていながら、歴史的・哲学的に深い洞察に満ちており、国際的な反響を呼んだ。本書はブラジル、チェコ版に続く邦訳。
名画の中で働く人々──「仕事」で学ぶ西洋史

著:中野京子
発行:集英社
発行日:2022年9月26日
サイズ:四六判、224ページ
「看護師」はひと昔前なら「看護婦」。神話の時代からある仕事とは? 「リケ女」の走りは命がけ! 知っているようで知らない、仕事のルーツや歴史を、『怖い絵』シリーズの中野京子が解説。今まで見えてこなかった、もうひとつの西洋史がそこにある。
社会のなかの美術 拡張する展示空間

著:中原佑介
発行:現代企画室
発行日:2022年9月28日
サイズ:B5変形、364ページ
「芸術の行くすえを見つめる中原佑介。後期旧石器時代の洞窟壁画から2000年代の「大地の芸術祭」まで、「展示」のあり方から芸術の変遷を論じ、未知の可能性を展望する中原芸術論の白眉。2000年代になって中原が「新たな芸術の展開を示すもの」と論じた「大地の芸術祭」。中原が「大地の芸術祭」に見たものは何だったのか。1950年代までさかのぼって国際展のあり方、観客と大衆、教育と美術などを論じたテキストを概観し、都市や文明の課題と芸術の接点について、中原が積み重ねてきた思考の軌跡をたどる。
ジャン・プルーヴェ 椅子から建築まで

監修:Galerie Patrick Seguin、Tamotsu Yagi Design、東京都現代美術館
解説:ジュリエット・キンチン
寄稿:早間玲子、田村奈穂、八木保、金田充弘
発行:millegraph
発行日:2022年9月28日
サイズ:A4変型、232ページ
20世紀の建築や工業デザインに大きな影響を与えたジャン・プルーヴェ(1901–1984)を紹介する大規模な展覧会の公式カタログ。プルーヴェが手がけたオリジナルの家具や建築物を豊富な写真によって収録。解説、エッセイ、貴重な資料も多数。仏Galerie Patrick Seguinとの共同発行。
いい絵だな

著:伊野孝行、南伸坊
発行:集英社インターナショナル
発行日:2022年10月5日
サイズ:四六判、240ページ
なぜ画家たちはリアルに描くことに夢中になったのか、ヘタな絵の価値とは何か、現代美術は何を言おうとしているのか、ファインアートとイラストは違うのか……。 描き手である二人がジャンルを跨ぎ、縦横無尽に語り尽くす。絵を描くとわかることがある。勉強だけではわからないことがある。本書を読むと、料理を自分の舌で味わうように絵が鑑賞できるようになる!?
ヴァロットン ─黒と白

発行:筑摩書房
発行日:2022年10月6日
サイズ:A4変形、240ページ
19世紀末パリで活躍した画家ヴァロットン。その独特の視点と多様な表現、卓越したデザインセンス溢れる黒一色の革新的な木版画180点を中心に紹介する作品集。
切手デザイナーの仕事〜日本郵便 切手・葉書室より〜

著:間部香代
発行:グラフィック社
発行日:2022年10月11日
サイズ:A5判、192ページ
日本の切手をつくっているのは、たった8人のデザイナーたち。作家・間部香代が日本郵便のドアを叩き、丁寧な取材とともに彼らの仕事を、その姿を、紐解きます。
絵画を読む ─イコノロジー入門

著:若桑みどり
発行:筑摩書房
発行日:2022年10月11日
サイズ:文庫判、288ページ
絵画の〈解釈〉には何をしたらよいか。名画12作品の読解によって、美術の深みと無限の感受性へと扉を開ける。美術史入門書の決定版。
半建築

著:長坂常
発行:フィルムアート社
発行日:2022年10月12日
サイズ:四六判、256ページ
初期の代表作「Sayama Flat」において、引き算や誤用という考え方のリノベーションで建築界にセンセーションを巻き起こしたスキーマ建築計画。日常の中での気づき、既存のものから得られる新たな発見をきっかけに、家具から建築、都市のスケールまで1/1を基本にデザインする独自の取り組みを「半建築」というキーワードのもと書き下ろした待望の一冊。
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
2022/10/14(金)(artscape編集部)
グレゴワール・シャマユー『人間狩り──狩猟権力の歴史と哲学』

翻訳:平田周、吉澤英樹、中山俊
発行所:明石書店
発行日:2021/09/13
本書の著者グレゴワール・シャマユー(1976-)は、今日もっとも勢いのあるフランスの哲学者の一人だろう。シャマユーは、2008年の『人体実験の哲学』(加納由起子訳、明石書店、2013)、2013年の『ドローンの哲学』(渡名喜庸哲訳、明石書店、2018)、2018年の『統治不能社会』(信友建志訳、明石書店、2022)など、いずれも重要なテーマを扱った書物を次々と世に送り出してきた。なかでも、かれの2冊目の単著にあたる2010年の『人間狩り』は、思想的にも歴史的にも、きわめて広大な射程をもった書物のひとつである。
本書でシャマユーが照準を合わせるのは、「人間を狩る」という穏やかでないテーマだ。ただしこの「狩り」には、(獲物などを)「追いかける」という意味と、「暴力的に外に追いやる」という二つの含意がある(8頁)。この「追跡する狩り」と「追放する狩り」は一応は区別されるが、この二つの行為は根本ではつながっている。なぜなら、人間を動物のように追い回すことは、その人間があらかじめ公共の領域から追い立てられていることを意味するからだ。『人間狩り』は、そうした人間を人間ならざるものへと追いやる「狩猟権力」についての書である。
全12章からなる、本書の大まかなストーリーは次のようなものである。まず古代ギリシアにおいて、「狩猟権力」はポリスの市民が奴隷を力づくで調達・捕獲し、主人として彼らを支配するための権力として出現した(第1章)。次いでヘブライ=キリスト教の伝統において、「狩猟権力」はまずもって暴君が行使する「捕獲するための狩り」に相当したが(第2章)、同時にそれは、慈悲深いはずの「司牧権力」(フーコー)が行使する「追放するための狩り」でもあった(第3章)。
これら三つが「狩猟権力」の旧き形象であるが、時代とともに、この暴力的な権力は地球上のいたるところに広がる。周知のように、それはアメリカ大陸における「先住民狩り」であり(第4章)、アフリカにおける「黒人狩り」(第5章)である。また新大陸や植民地ではなく、西洋社会の内部に目を向けてみても、そこでは「貧民狩り」(第7章)や「外国人狩り」(第10章)といった暴力的営為が──警察権力の拡大とともに──連綿と続けられてきた。本書はこうして、古代から近代までの「人間狩り」をめぐる壮大な系譜学を描き出すのだ。
なかば当然のことではあるが、こうしたシャマユーの問題意識は、しばしばフーコーの権力論と比較され、それを継承するものとされてきた。その正否については本書の「訳者解題」(平田周)をはじめすでにさまざまな議論があるので、ここでは立ち入らない。だが、ここでひとつだけ触れておくことがあるとすれば、それは本書の驚くべき読みやすさにある。シャマユーの書物がきわめて「現代的」だと思わされるのは、フーコーをはじめとする先達の権力論に比べて、その論述スタイルがきわめて明晰であることだ。本書『人間狩り』や『ドローンの哲学』が英語圏で好評を得ていることからもうがかえるように、本書は簡潔にして要領を得た文体によって、歴史的にも理論的にも厚みのある「人間狩り」という主題に接近するための、格好の一冊になりえている。
2022/10/06(木)(星野太)
クリストフ・メンケ『力──美的人間学の根本概念』

翻訳:杉山卓史、中村徳仁、吉田敬介
発行所:人文書院
発行日:2022/07/30
「力(ちから)」というシンプルかつ控えめな表題に反して、本書は、きわめて複雑かつ野心に満ちた書物である。本書は、18世紀ドイツにおける「美学(Ästhetik)」という学問領域の誕生に新たな視座を導き入れるとともに、それを近代的な「主体性」の誕生をめぐるエピソードとして(再)評価する。著者によれば、美学とは、近世においてすでに生じていた「主体」の概念とは異なる「真に近代的な主体性概念が養成される場」であったという(8頁)。これが本書の第一のテーゼをなす。
以下では本書の「序言」や「訳者解説」を手がかりとしつつ、その大まかな道筋をたどっていくことにしよう。クリストフ・メンケ(1958-)は現在フランクフルト大学で教鞭をとる哲学者であり、『芸術の至高性──アドルノとデリダによる美的経験』(柿木伸之ほか訳、御茶の水書房、2010)をはじめとする数多くの著書がある。本書『力(Kraft)』(2008)はそのメンケの5冊目の単著であり、これ以後も『芸術の力(Die Kraft der Kunst)』(2013)をはじめとする比較的近いテーマの仕事を公にしている。
さて、そのメンケの見立てによれば、美学こそは「真に近代的な主体性概念」が養成される場である、ということだった。そのような「主体性」とは、具体的にはいかなるものなのか。ごく簡潔に要約してしまうと、それは(1)当の主体によって意識的に制御された次元と、(2)そこからはみ出す、無意識的で制御不能な次元の拮抗のうえに成り立つような「主体性」である。そしてこの(1)が「能力(Vermögen)」に、(2)が「力(Kraft)」に相当すると言えばわかりやすいだろう。ようするに、ここで言う「近代的主体性」とは、意識と無意識、理性と非理性といったお馴染みの対立によって構成される主体であると考えておけばよい。
ここでいったん用語の整理をしておくと、この「能力」と「力」の共通の土台となるものを、メンケは「威力(Macht)」と呼んでいる。つまり、あらゆる人間には「威力」というものがそなわっているのだが、あるときはそれが「能力」として、またあるときは「力」として発現するということである。すこしわかりにくいが、本書を読みすすめるにあたり、この三つの概念の相関を押さえておくことは有益である。
さて、そのうえで整理を続けるなら、前者の「能力(Vermögen)」とは「威力がとる特殊な形態のうち、規範的かつ社会的な実践の参加者として主体を定義するような形態」のことである(10頁)。つまり「能力」とは、人間の社会的な規範意識を醸成し、それによって社会参加を可能にするものだと言ってよいだろう。これに対する「力(Kraft)」とは、むしろ「戯れとして展開されるような作用の威力」であるという(10-11頁)。つまりそれは「能力」とは違って、ある表現を生み出しては解消し、ある表現を超克してはそれを別の表現へと変貌させる、そうした遊戯的な作用のことである。
この「能力」と「力」は、どちらか一方が──主体の「威力」として──正しく、どちらか一方が誤っているということにはならない。ある見方をすれば、この二つの威力は互いを補完しながら「弁証法的統一」へと至る、と言うことができる(=「能力の美学」)。しかしべつの見方をすれば、この二つの威力はあくまで解消不可能な「逆説」を構成していると言うことも可能である(=「力の美学」)。そして本書の最大の野心は、18世紀から19世紀にかけての美学理論の展開を、この「能力の美学」と「力の美学」の相克として語りなおすところにあるのだ。
本書は、美学の創始者バウムガルテン(1714-1762)を「能力の美学」に、そして哲学者ヘルダー(1744-1803)を「力の美学」に割り振ることで、こうした遠大な理論形成史、ないし学問伝承史を提示する。巻末の「訳者解題」(杉山卓史)が適切に示すように、第2章のバウムガルテン論が「能力の美学」の誕生、第3章のヘルダー論が「力の美学」の誕生をめぐるものだとすると、第1章、第4章はそれぞれの背景を論じたものとして、第5章(カント論)、第6章(ニーチェ論)はこの二つの美学の対決の帰趨を論じたものとして読むことができる。各章の議論はそれなりに専門的だが、本書を通読した先には、美学と近代的主体性の関係をめぐるまったく新たな認識が得られるはずである。
2022/10/06(木)(星野太)
カタログ&ブックス | 2022年10月1日号[テーマ:美術家・李禹煥を通して、世界の「余白」を見つめる人たちの5冊]

アジアを代表する美術家の一人、李禹煥(1936-)。「すべては相互関係のもとにある」という透徹した視点で「もの派」などの美術動向を牽引してきました。「国立新美術館開館15周年記念 李禹煥」(2022年8月10日〜11月7日、国立新美術館にて開催)にちなみ、李の作品や著作を紐解き、物事の間にある関係性を眺め考える5冊を紹介します。
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:国立新美術館
今月のテーマ:
美術家・李禹煥を通して、世界の「余白」を見つめる人たちの5冊
1冊目:余白の芸術
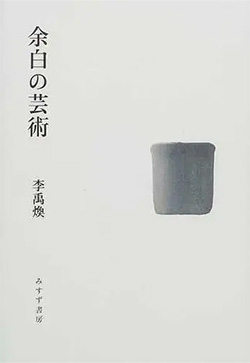
著者:李禹煥
発行:みすず書房
発売日:2000年11月
サイズ:22cm、385ページ
Point
彫刻・絵画作品で知られる一方、執筆活動も旺盛に展開してきた李。自身や「もの派」の制作活動を、同時代を生きる国内外の作家たちとともに俯瞰し、時に素朴な言葉で綴るエッセイを数多く集めた本書。古井由吉や中上健次といった作家たちに積極的に言及している点からも、言語を用いた表現に対する李の強い意識が窺えます。
2冊目:イメージかモノか 日本現代美術のアポリア

著者:高島直之
発行:武蔵野美術大学出版局
発売日:2021年11月1日
サイズ:22cm、255ページ
Point
「もの派」に限らず、ハイレッド・センターや千円札裁判といった動きが現在も鮮烈な印象を残す1960〜70年前後の日本美術シーン。当時の批評家たちはそれらにどう言及したのかを振り返り検証する本書。観念(イメージ)/物質(モノ)という二項対立を通して、「見る」行為の変遷を時代背景とともに実感できます。
3冊目:本を弾く 来るべき音楽のための読書ノート

著者:小沼純一
発行:東京大学出版会
発売日:2019年10月1日
サイズ:19cm、398ページ
Point
音楽批評家であり詩人の小沼純一がジャンルを問わず刺激を受け、折に触れて読み返す22冊の名著にまつわるエッセイ集。ことば/場/からだという三つの分類のうち、「場」で李の若年期の批評集『出会いを求めて』に言及。著者と本の間に流れる即興演奏のような読み心地は終始心地良く、読書案内としても優れた一冊です。
4冊目:展覧会の挨拶

著者:酒井忠康
発行:生活の友社
発売日:2019年4月18日
サイズ:20cm、330ページ
Point
展覧会の最初の部屋、あるいは図録の最初のページで出会う「ごあいさつ」。世田谷美術館など国内複数の美術館館長を務めてきた酒井忠康が、李のものも含む展覧会に寄せた文章は、作家との個人的なエピソードや思い入れも豊富。そのとき/その場でしか体感できない「展示」というメディアの不思議さにも思いを馳せてしまう本。
5冊目:虚像培養芸術論 アートとテレビジョンの想像力 Art Criticism and 1960s Image Culture

著者:松井茂
発行:フィルムアート社
発売日:2021年3月24日
サイズ:20cm、309ページ
Point
テレビの登場以降大きく揺れたメディアの勢力図。李も60年代以降の文献で「虚像/実体」という言葉を多用しているように、モノやリアリティの受容され方の変化を強く意識していたようです。李が作家性を確立させていった時代、メディアと芸術の相互関係が生み出した芸術家像の複雑さを、多角的に知ることのできる一冊。
国立新美術館開館15周年記念 李禹煥
会期:2022年8月10日(水)~11月7日(月)
会場:国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2)
公式サイト:https://leeufan.exhibit.jp/
[展覧会公式図録]
『李禹煥』

編集:国立新美術館、兵庫県立美術館
発行:平凡社
発行日:2022年8月16日
サイズ:28cm、303ページ
「もの派」を代表する世界的なアーティスト・李禹煥。60年代の初期作品から、彫刻の概念を変えた〈関係項〉シリーズ、最新の絵画作品を収録。国立新美術館、兵庫県立美術館での展覧会公式図録。
◎展覧会会場、全国主要書店にて販売中。
2022/10/01(土)(artscape編集部)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)