artscapeレビュー
書籍・Webサイトに関するレビュー/プレビュー
カタログ&ブックス | 2022年3月1日号[テーマ:「文字を作る」ことを通して世界を眺める/世界とつながる5冊]
注目の展覧会を訪れる前後にぜひ読みたい、鑑賞体験をより掘り下げ、新たな角度からの示唆を与えてくれる関連書籍やカタログを、artscape編集部が紹介します。
今回ピックアップするのは、書体設計士・鳥海修さんの展覧会「鳥海修 もじのうみ:水のような、空気のような活字」(京都dddギャラリーにて1月15日~3月19日開催)。「ヒラギノフォント」や「游明朝体」など、インフラのような書体の数々を手がけられてきた鳥海さん。文字を作る行為は、世界のどんな部分に波及し息づくのか。そんな想像が膨らむ5冊を選びました。
今月のテーマ:
「文字を作る」ことを通して世界を眺める/世界とつながる5冊
※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。
※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。
協力:堤拓也(鳥海修「もじのうみ:水のような、空気のような活字」キュレーター)
1冊目:文字を作る仕事

著者:鳥海修
発行:晶文社
発売日:2016年7月9日
サイズ:20cm、235ページ
Point
鳥海自ら書体設計の仕事について綴ったエッセイ。今回の展覧会タイトルにもある「水のような、空気のような」という言葉は、鳥海が書体設計士を志すきっかけとなったタイポグラファー・小塚昌彦によるもので、2016年刊行の本書にも登場します。黒子としての書体設計士の美意識をより深く知られる一冊。
2冊目:グーテンベルクの銀河系 活字人間の形成

著者:マーシャル・マクルーハン
翻訳:森常治
発行:みすず書房
発売日:1986年2月
サイズ:22cm、486+24ページ
Point
グーテンベルクの印刷文化がいかに個人主義を生んだのかを語る、マクルーハンの論説集。本展キュレーターの堤拓也さん曰く「鳥海の書体設計の仕事もこの延長にある」そう。「『水のような、空気のような活字』とはすなわち、均質かつ画一的な紙面空間を作るという西洋近代社会の要請だったのです」と両者を結びつけます。
3冊目:日本語活字ものがたり 草創期の人と書体(文字と組版ライブラリ)

著者:小宮山博史
発行:誠文堂新光社
発売日:2009年1月
サイズ:21cm、268ページ
Point
日本の近代活字の草創期、ひらがな/カタカナ/漢字といった複数種の文字が混在する日本語を活字にするゆえの格闘を伝える貴重な一冊。「極東に位置する日本においても、キリスト教と活字文化というものが切っても切れないということがわかります」(堤)。鳥海と、さらに上の世代の書体設計のあり方を比較しても興味深い。
4冊目:本をつくる 書体設計、活版印刷、手製本─職人が手でつくる谷川俊太郎詩集

著者:鳥海修、高岡昌生、美篶堂、永岡綾
発行:河出書房新社
発売日:2019年2月18日
サイズ:21cm、225ページ
Point
本づくりのプロたちが谷川俊太郎詩集『私たちの文字』を作る過程を捉えた記録集。鳥海による、谷川の詩のためのかなフォント「朝靄」の制作風景だけでなく、それが活版で組まれ、印刷、手製本されるまでの職人たちの手仕事が丹念に綴られた一冊。「朝靄」完成までの資料とともに、実際の特装本が本展でも展示されています。
5冊目:銃・病原菌・鉄 上巻
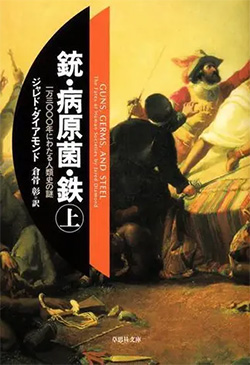
著者:ジャレド・ダイアモンド
翻訳:倉骨彰
発行:草思社
発売日:2015年11月25日
Point
かつて貧しかった欧州の国々が、いかに世界で覇権を握っていくことになるのか。生物学や言語学、宗教学など多様な視点から社会の転換を読み解くことで、人類史の見方が塗り替えられる一冊。「世界三大発明の『火薬』『羅針盤』『活版印刷術』とともに『活字』が世界史に与えた影響を間接的に想像するとより面白い」(堤)。
鳥海修「もじのうみ:水のような、空気のような活字」
会期:2022年1月15日(土)~3月19日(土)
会場:京都dddギャラリー(京都府京都市右京区太秦上刑部町10)
公式サイト:https://dnpfcp.jp/gallery/ddd/jp/00000784
2022/03/01(火)(artscape編集部)
カタログ&ブックス | 2022年2月15日号[近刊編]
展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。
※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます
◆
世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生

著者:大田暁雄
発行:オーム社
発行日:2021年12月17日
サイズ:B5判、272ページ
デザイン史を揺さぶるこのグラフィックは、なぜ、制作されたのか。「世界を描く」という不可能に挑戦した人たちの知られざる科学的グラフィズム150年の軌跡。 雑誌『アイデア』の好評連載を待望の書籍化。アレクサンダー・フォン・フンボルトからオットー・ノイラートまでの科学的グラフィズムの壮大な物語。
花裂ける、廃絵逆めぐり 福山知佐子画集

著者:福山知佐子、ジョルジョ・アガンベン、水沢勉、鵜飼哲、鈴木創士
発行:水声社
発行日:2021年12月27日
サイズ:B5判、192ページ
枯れゆくチューリップ、しなだれ、衰微するアネモネ…。枯れながら命を終えてゆく植物たち、そしてそこに潜む生命の循環を描いた、鉛筆による素描、水彩、銀箔膠絵。20年以上にわたり、花開き、枯れ、朽ちはてる草花を描き続けた画家の集大成。
都市を上映せよ ソ連映画が築いたスターリニズムの建築空間

著者:本田晃子
発行:東京大学出版会
発行日:2022年1月21日
サイズ:四六判、304ページ
ソ連時代、建築の理想や夢を映し出す一大メディアとなった映画は、社会主義都市のイメージを大衆に浸透させることに成功し、現在にいたるまで人々の「ソ連」のイメージと結びついてきた。映画は首都モスクワをいかに神話化し、解体したのか、スクリーン上の建築物が饒舌に語り始める。
僕とデザイン

著者:仲條正義
発行:アルテスパブリッシング
発行日:2022年1月25日
サイズ:四六判変型、210ページ
資生堂のPR誌『花椿』のアートディレクターを40年以上務めたほか、 同パーラーのロゴとパッケージデザイン、 銀座松屋や東京都現代美術館、カゴメなど数多くのロゴをはじめ、 斬新で粋なデザインを世に送り続けてきた仲條正義が、 キャリアを振り返りながら、デザインとはなにか? を自ら語ります。
ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて

著者:ニコラ・ブリオー
訳者:武田宙也
発行:フィルムアート社
発行日:2022年1月26日
サイズ:四六判、296ページ
1998年、『関係性の美学(原題:Esthétique relationnelle)』で美術の新たなパラダイムを切り拓いたブリオーが、21世紀の今日的状況を考察するため、旅人としてのアーティストたちの実践を通して新しい時代のしなやかな美学を描き出した、文化や想像力の標準化に抗するための挑戦的一冊。
環境が芸術になるとき 肌理の芸術論

著者:高橋憲人
発行:春秋社
発行日:2022年1月28日
サイズ:四六判、240ページ
環境と人間との関係性から芸術創造のあり方を捉えなおし、
現代建築宣言文集[1960-2020]

編者:五十嵐太郎+菊地尊也
発行:彰国社
発行日:2022年1月
サイズ:四六判、432ページ
本書は、1960年のメタボリズムから2020年まで、現代の建築概念を揺るがしてきた建築家や批評家による50の言説を再録・解読するアンソロジーである。 各言説には、五十嵐太郎、菊地尊也ほか東北大学五十嵐研究室による解説文も掲載。 約半世紀にわたる言説の蓄積を振り返ることで、現代の位置を確かめ、未来につなぐ。
サーキュラーデザイン 持続可能な社会をつくる製品・サービス・ビジネス

著者:水野大二郎・津田和俊
発行:学芸出版社
発行日:2022年2月1日
サイズ:A5判、240ページ
地球環境の持続可能性が危機にある現在、経済活動のあらゆる段階でモノやエネルギー消費を低減する「新しい物質循環」の構築が急がれる。本書は1)サーキュラーデザイン理論に至る歴史的変遷2)衣食住が抱える課題と取組み・認証・基準3)実践例4)実践の為のガイドとツールを紹介する。個人・企業・組織が行動に移るための手引書
ケアとアートの教室

編著者:東京藝術大学 Diversity on the Arts プロジェクト
発行:左右社
発行日:2022年2月4日
サイズ:四六判、256ページ
介護、障害、貧困、LGBTQ+、そしてアート。様々な分野で活躍する人々と、東京藝術大学 Diversity on the Arts プロジェクト(通称DOOR)の受講生がともに学び、考える。 そこから見えてきたのは、福祉と芸術が「人間とは何かを問う」という点でつながっているということ。 ケアとアートの境界を行く17項!
◆
※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです
https://honto.jp/
2022/02/14(月)(artscape編集部)
ジュリア・フィリップス『消失の惑星』

翻訳:井上里
発行所:早川書房
発行日:2021/02/25
2019年に全米図書賞(小説部門)の最終候補となり、商業的にも大きな成功を収めた本書『消失の惑星(Disappearing Earth)』が日本語に翻訳されたのはおよそ一年前のことである。昨今の時流にも即した本書は日本でも多くの読者を獲得し、話題を呼んだ。そのため、これから書くことはいささか時宜を逸したものであることは否めないが、あらためて同書の外郭をたどりつつ、従来の書評とはやや異なった視点から本書の紹介を試みたい。
本書は、米国ニュージャージー生まれの作家ジュリア・フィリップス(1989-)のデビュー作である。舞台はロシア東部のカムチャツカ半島であり、物語はアリョーナとソフィヤという幼い姉妹の失踪事件から始まる。しかしながら、本書の叙述は、物語が進むにつれて次第に事件の顛末が明らかになっていくミステリーのそれとは大きく異なる。姉妹が姿を消した「8月」からおよそ一ヶ月ごとに進む本書では、まるで終わりのない短編集のように、カムチャツカ半島に生きる女性たちのエピソードがかわるがわる披露される。友人との関係に悩む中学生オーリャ、新しくできたそそっかしい恋人とキャンプに出かけるカーチャ、鎖骨の下の水疱に悩む学校秘書のワレンチナ、少数民族にルーツをもつ大学生クシューシャなど、彼女たちのエピソードは──部分的に重なりつつも──ほとんど独立しており、物語の結末にむけて一点に収束していくわけではかならずしもない。それらに共通するところがあるとすれば、それは幼い姉妹の失踪事件を背景に否が応でも増幅される、同地の「女性たちの」孤独・煩悶・喪失である。
はじめにも述べたように、本書『消失の惑星』はすでに読書界で高い評価を獲得しており、その構成や文体に鑑みても、これがきわめて完成度の高い長編小説であるという評価は揺るぎようがない。かといって、終始破綻なく進むこの物語に、あらためて批評的な読みどころを見いだすこともむずかしい。そこで、ここではあえて、本書の成立の背景に注目してみたい。
英語によるいくつかの記事に目を通してみるとわかるように、著者フィリップスは、本書の執筆に20代のほぼすべてを費やしている。高校生のころからロシアに関心を抱いていたという著者は、バーナード・カレッジ卒業後にフルブライト奨学金を得て、『消失の惑星』の舞台となったカムチャツカ半島で2年間のリサーチを行なっている★1。また、そうした現地でのリサーチのかたわら、彼女がニューヨークの犯罪被害者支援センター(CVTC)で長く勤務していたという事実も注目に値する★2。本書については、前者のカムチャツカ半島でのリサーチばかりが注目されるきらいがあるが、その内容に鑑みれば、犯罪被害者に間近で接してきた後者の経験が本書の執筆に大きな影響を及ぼしていることは疑えない。
本書は、以上のような長期にわたる、粘り強い創作活動の果てに成った一冊である。その事実をここであえて強調するのは、現代美術の世界で──制度的に──しばしば横行する、ごく短い期間の「リサーチ」なるものとの、彼我の隔たりに思いをめぐらせるためである。むろん、小説とそれ以外の表現形式とでは、基本的な前提に大きな違いがあることもたしかだろう。しかしそれでも、本書のような10年単位のリサーチが、なぜ現代美術の世界において見られないのかということはやはり考えざるをえない。すくなくともこの小説は、1、2年ほどの中途半端なリサーチによっては到底不可能な、きわめて大きな達成である。実際にそうした活動に身を投じるかどうかはともかく、何らかのリサーチに基づく(research-based)作品であることを殊更に謳うからには、本書のような仕事が存在することは重々意識しておく必要があるだろう。
★1──“Barnard’s 2011 Fulbright Recipients Announced” (コロンビア大学、バーナード・カレッジ、2011年5月9日)https://barnard.edu/headlines/barnards-2011-fulbright-recipients-announced(2022年2月6日閲覧)
★2──“Julia Phillips: Debut Novelist And National Book Award Finalist” (ニューヨーク・クイーンズ公立図書館、2020年1月24日)https://www.queenslibrary.org/about-us/news-media/blog/2010(2022年2月6日閲覧)
2022/02/07(月)(星野太)
ジェニー・オデル『何もしない』

翻訳:竹内要江
発行所:早川書房
発行日:2021/10/05
アーティストのジェニー・オデルが、本書『何もしない方法(How to do Nothing)』の原型となる講演をEyeo Festivalで行なったのは2017年のことである★。その後、本書は2019年に書籍として書き下ろされ、かのバラク・オバマの目にとまることになる。その高評価とも相まって、同書は『ニューヨーク・タイムズ』をはじめ、数多くの媒体で取り上げられるベストセラーとなった。
本書が人々の関心を集めた最大の理由は、そのテーマのもつ時宜性と、語り口のユニークさにあると言えるだろう。本書の問題意識は、「われわれは注意経済(アテンション・エコノミー)からいかに距離を取ることができるか」という問いにほとんど還元されると言ってよい。事実、日本語では省略されてしまっている原書の副題は「注意経済への抵抗(Resisting the Attention Economy)」である。つまり、日々インターネットの記事・広告・SNSなどから垂れ流されてくる情報の氾濫からいかにして身を守るべきか、というのが本書の基調をなす問題意識なのだ。しかしそれと同時に、著者は「TwitterやFacebookをやめるべきだ」とか「スマートフォンを手放すべきだ」といった安易な「デジタル・デトックス」がなんの解決にもならないということを早々と指摘する。肝要なのは、そうした一見わかりやすい解決策に飛びつくことではなく、われわれの「注意」のありかたそのものを変えていくことなのだ──本書を通して、著者が一貫して唱えているのはそうしたことである。
本書『何もしない』がよくある巷の啓蒙書と異なるとしたら、それはアーティストである著者ならではの具体的な経験が広く散りばめられているからだろう。同書の論述はけっして一本道ではなく、そこでは現在と過去、理論と実践、作品と日常がいたるところで絡まりあっている。そこに登場するエピソードのなかには、オデルその人の作品や実践のみならず、彼女が教鞭をとるスタンフォード大学での学生とのやりとりや、家族やパートナーとのささやかな出来事も含まれる。また、1960年代に生じたコミューン運動への批判的なまなざし(第二章)や、彼女の論旨を補強するピルヴィ・タカラや謝徳慶といったパフォーマンス・アーティストの作品(第三章)も、それぞれ興味深いものである。かたや、全体にわたり参照される哲学・文学作品のなかには過去にさんざん使い回され、いくぶん摩耗したものも含まれるが(ジル・ドゥルーズ『記号と事件』、ハーマン・メルヴィル『代書人バートルビー』、レベッカ・ソルニット『災害ユートピア』など)、広範な読者を想定した一般書としては致し方のないことかもしれない。
いずれにせよ、本書のスタンスに注目すべき点があるとすれば、それは「注意経済」に覆い尽くされた日々の生活を惰性的に受け入れるのでも、反対にそこからの安易な離脱を説くのでもなく、そのなかで何とかやっていくためのヒントを具体的に示しているところだろう。オデルが言うように、いまのわれわれに必要なのは、みずからの注意をコントロールするための「継続的なトレーニング」である(154頁)。そのさい著者が何度も引き合いに出すのは、地元オークランドのバラ園やバードウォッチングだが、既述の通り、それはかならずしもわかりやすい「自然回帰」を志向するものではない。情報テクノロジーからの完全な離脱がもはや現実的ではない現下の状況において、本書は「第三の空間」(121頁)や「コンテクストの回復」(268頁)が、そこからの脱出口となりうることを指摘する。それを、理論/実践いずれかの一辺倒ではなく、両者を縫い合わせるかたちで──しかも、あくまでユーモラスに──示した本書の提言は、たしかに一読に値するものでる。
★──Eyeo Festivalは、コンピューター・テクノロジーに関心を寄せるアーティスト、デザイナー、コーダーらを対象とするカンファレンス。年一回、ミネアポリスのウォーカー・アート・センターで行なわれる。2017年のオデルの講演の動画は以下のURLで公開されており、講演の書き起こしもmediumのブログで読むことができる。https://vimeo.com/232544904(2022年2月6日閲覧)
2022/02/07(月)(星野太)
笠井爾示『Stuttgart』

発行所:bookshop M
発売日:2022/01/25
笠井爾示は10歳だった1980年に、舞踏家の父、笠井叡と母、久子とともにドイツ・シュトゥットガルトに渡り、18歳まで当地で過ごした。1988年に一時帰国したとき、先に帰っていた母がうつ病で危険な状態にあることを知り、そのまま日本に留まることにする。多摩美術大学卒業後、写真家として幅広く活動するようになるが、シュトゥットガルトは彼にとって特別な思いのある土地であり続けてきた。本書は、2019年7月~8月に母、久子とともにシュトゥットガルトを再訪した時に撮影した写真を、「時系列どおりに」並べた135点(すべて縦位置)によって構成されている。
思い出の土地というだけでなく、母親にカメラを向けるということには、ともすれば決意や構えが必要になるようにも思える。だが、実際に目の前に現われる景色や母の姿は、余分な感情移入がなく、どちらかといえば淡々としたものだ。被写体をコントロールしようという意思はほとんど感じられず、そこにあるものをすっと受け容れ、だが、ここしかないというタイミングでシャッターを切っている。特に印象深いのは、裸の久子を撮影した一連のカットなのだが、それらも、見る者を身構えさせるような押しつけがましさを感じさせない。老化によるからだの歪みやねじれ、窪みや皺なども、あるがままに、むしろチャーミングに写しとっている。息子と母という関係にまつわりつくことが多い陰湿さがまったくないことが、むしろ奇跡のようにすら思える。
むろん、そのような受容的な姿勢を選択するにあたっては、笠井なりの葛藤もあったのではないだろうか。よりドラマティックなスタイルで撮影することもできたはずだ。だが、あえてこの距離感、この空気感を選んだことで、『Stuttgart』は、笠井爾示と久子という母子の関係に収束することなく、「開かれた」写真集として成立した。それは、誰もが自分と母親との関係に思いを寄せてしまうような、強い共感力を備えている。町口覚の造本設計による、ブックデザインが素晴らしい。基調となる黄色は、久子がうつ病から立ち直るきっかけになったという「黄色のラッパスイセン」を意識しているのだろう。
2022/02/06(日)(飯沢耕太郎)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)