artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
プレビュー:マレビトの会『長崎を上演する』

会期:2016/03/26~2016/03/27
愛知県芸術劇場 小ホール[愛知県]
マレビトの会は、「ヒロシマ─ナガサキ」シリーズ(2009-2010年:『声紋都市──父への手紙』、『PARK CITY』、『HIROSHIMA─HAPCHEON:二つの都市をめぐる展覧会』)、『マレビト・ライブ N市民──緑下家の物語』(2011)、『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』(2012)といった近年の一連の作品において、集団制作を重視しながら、出演者自身の経験の「報告」、俳優の身体を展示するという「展覧会形式」での上演、現実の街中での上演、東京から福島へ移動を続けながらの上演、さらにはその旅の記録や上演告知をSNSなどネット上のメディアを介して発信するなど、実験的な試みを続けてきた。そこでは、都市という空間の生成、俳優の身体性、言葉の帰属、「出来事」の再現/共有不可能性、被爆地への眼差し、可視的なイメージの生成への抵抗、といったさまざまな問題が演劇的原理への問い直しとともに思考されてきた。
そして2013年からは、新たな長期的な演劇プロジェクトに取り組んでいる。長崎という都市のテーマに複数の作者が取り組み、現地取材、戯曲執筆、舞台上演を複数年にまたがって継続して行なうというプロジェクトである。2015年8月には、国内各地に住む7名の作者が執筆した戯曲20本(上演時間約7時間)が総集編として3日間にわたり上演された。今回の愛知公演では、これらから選んだいくつかの戯曲に、ドイツからの新たな参加者が長崎取材を経て書き下ろした戯曲を加え、2日間にわけて上演が行なわれる。複数の眼差しの視差の中に、さらに異化するような視点を加えることで、どのような手触りをもった都市の相貌が立ち現われるだろうか。
2016/01/31(日)(高嶋慈)
プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2016 SPRING
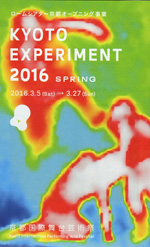
会期:2016/03/05~2016/03/27
ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール“アルティ”、京都国立近代美術館ほか[京都府]
6回目を迎える「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」。今回は、2016年1月にリニューアルオープンしたロームシアター京都をメイン会場に迎えるため、例年通りの秋ではなく、春に開催される。
公式プログラム計11演目は4つの軸に沿って構成。(1)「現代舞台芸術の源流を辿る試み」では、舞踏集団・大駱駝艦の近作『ムシノホシ』や、維新派の松本雄吉が演出する新作が予定されている。また、トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニーの初期作品群のオムニバス上演が、京都国立近代美術館で行なわれる。これら1960~70年代の実験精神の延長線上として、トリシャ・ブラウンやマース・カニングハムなど、先行世代を意識して制作している振付家・ダンサーのボリス・シャルマッツ/ミュゼ・ドゥ・ラ・ダンスによる『喰う』の上演が位置づけられている。
(2)「作家たちの共同作業による新作群」では、東日本大震災と原発事故を題材にしたエルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』で高い評価を受けた、地点と三輪眞弘が再びタッグを組み、イェリネクの『スポーツ劇』の上演に挑む。また、チェルフィッチュは、現代美術作家・久門剛史との共同作業による新作『部屋に流れる時間の旅』の上演を予定。また、ボイスパフォーマー・作曲家の足立智美は、舞台音楽を子どもたちと制作するワークショップを行なうとともに、contact Gonzoとの初顔合わせを試みる。異ジャンルのアーティスト同士のコラボレーションによる、刺激的な相互作用に期待したい。
また、KYOTO EXPERIMENTは、フェスティバルの役割のひとつとして国際的な共同製作やネットワークづくりを掲げており、特に、日本で紹介される機会の少ない南米諸国の現代演劇やダンスを継続的に紹介してきた。(3)「継続的な国際交流プロジェクト」では、チリ演劇界のホープ、マヌエラ・インファンテ率いるテアトロ・デ・チレの『動物園』が上演される。「人間の展示」という主題を通して、西欧の植民地化や軍事独裁政権といったチリの複雑な歴史、異文化の混淆や衝突、観客の眼差しのあり方への鋭い批評となるのではないか。また、シンガポール出身のチョイ・カファイは、アジア諸国のダンサーや振付家へのインタビューを通して、伝統舞踊とコンテンポラリー、現代社会とダンサー個人の身体性といった様々な問題のリサーチを行なう。さらに、フランスのダンサー・振付家のダヴィデ・ヴォンパクは、「カニバリズム」という人間の極限的な行為を切り口にしたダンス作品を上演する。
(4)「デザインと建築の視点によるリサーチプロジェクト」では、デザインと建築の領域で活躍するUMA/design farm と dot architectsが京都の街のインフラを再編集して提示するリサーチプロジェクト、「researchlight」が展開される。
以上の公式プログラムに加えて、外部キュレーター2名の視点から日本の新進作家を紹介するショーケース「Forecast」も予定。劇作家・演出家のあごうさとしが「劇場における身体のあり方」という視点から選んだ3組(岩渕貞太×八木良太、辻本佳、あごうさとし)と、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館学芸員の国枝かつらが選出した音と映像を扱う3名(小金沢健人、田村友一郎、梅田哲也)の作品が上演される。さらに、フェスティバル開催期間中に京都で発表される作品を一挙に紹介するフリンジ企画「オープンエントリー作品」では、45作品が登録されている。3月の週末は、舞台鑑賞漬けになりそうだ。
公式サイト:http://kyoto-ex.jp/
2016/01/31(日)(高嶋慈)
プレビュー:村川拓也『終わり』、手塚夏子『15年の実験履歴──私的な感謝状として』

先月は京都造形芸術大学でBONUSのイベントを行ないました。来客者の方たちからはおおむね好評だったのですが、自分のイベントを自分では批評できないというジレンマに陥っております。取り上げるのが恥ずかしいといった類のためらいではなく、批評対象のインサイダーになってしまうと批評のポジションに立てず、ゆえに物理的に批評できなくなるわけです。このことは自分に降りかかった「前衛のゾンビ」(藤田直哉)問題といっても良いかもしれません。ご覧になった方、どうかぜひあのイベントの批評を書いてくださいませ。
さて、今月は秋季に負けないくらいダンスの公演・イベントラッシュです。そして横浜ダンスコレクション、TPAM、国際交流基金(障害×パフォーミングアーツ特集)、『〈外〉の千夜一夜 VOL. 2』と横浜でのプログラムがとても多いことが特徴です。その喧騒のなかでかき消されてしまいそうですが、STスポット横浜での二つの公演が要注目なのです。
ひとつは村川拓也『終わり』(TPAMショーケース参加作品、STスポット横浜、2/12-14)。村川は2011年の『ツァイトゲーバー』で介護をテーマにした舞台をつくり話題になった作家。その彼が今回ダンスを扱った舞台作品を上演します。昨年やはりSTスポット横浜で上演された相模友士郎『ナビゲーションズ』がそうだったように、出発点がダンス分野ではなく演劇やパフォーマンスの上演を経た作家がいまダンスに注目しているということが、筆者としてはじつに興味深いのです(同じような感慨は2014年の多田淳之介『RE/PLAY (DANCE Eidt.)』からも受けとっていました)。とくに無視してはならないのは、相模も多田も「ダンス」に一定の距離を保ちながら、しかし、けっして軽んじるわけではなく、それどころか、ダンスの可能性を多くの振付家たちが思いつかないような仕方で引き出していることです。村川のこの新作にも同様の期待を抱いてしまいます。
もう一作は手塚夏子『15年の実験履歴──私的な感謝状として』(STスポット横浜、2/15-16)。昨年の山縣太一×大谷能生『海底で履く靴には紐が無い』(これもSTスポット横浜だ!)公演のアフタートークでも話題になっていたことですが、いまの日本の演劇が「チェルフィッチュ以後」と呼ばれるその光に隠れた影の歴史として「手塚夏子以後」というべき側面があることは、忘れてはなりません。いまだ「手塚夏子」に出会っていない若い皆さんにこそ、お勧めしたいです。
2016/01/31(日)(木村覚)
インバル・ピント&アヴシャロム・ポラック ダンス・カンパニー「DUST─ダスト」
会期:2016/01/28~2016/01/31
彩の国さいたま芸術劇場[埼玉県]
涙を流す目と洪水のイメージのアニメーションから始まり、明るくなると、机が並ぶ教室のような舞台が出現する。そして奥に外界への扉がひとつ。集団で連鎖しながら、流れるような踊りが繰り広げられ、クラシックの大音響が侵入する。終わりと始まりのアレゴリーを感じさせるダンスだった。
2016/01/29(金)(五十嵐太郎)
《Showing》03 映像 伊藤高志 マルチプロジェクション舞台作品『三人の女』

会期:2016/01/23~2016/01/24
京都芸術劇場 春秋座[京都府]
「『公演』における各要素の中で、複製技術を持つメディア(音、写真、映像など)を取り上げ、それぞれの視点から劇場へと向かう創作を試みる」《Showing》シリーズの第3弾。伊藤高志は、80年代以降、静止画のコマ撮りによる魔術的なアニメーション作品など、実験映画の制作を行なってきた。本公演は、「マルチプロジェクションの映画」を舞台空間において「上映」し、観客の身体と地続きの空間で起こる「出来事」を侵入させることで、映像インスタレーション/映画の文法/演劇の境界を溶解させるとともに、記憶(記録)の再生/出来事の一回性、複製可能性/「いまここ」の唯一性、複数のスクリーン間で連動・分裂した表象/生身の身体性、といったさまざまな対立項の間を行き来する磁場を立ち上げていた。
舞台上には、3枚の巨大なスクリーンが、三面鏡のように角度をつけて、間隔を隔てて設置されている。無人の舞台の中央には、一枚のワンピースが吊り下げられている。そして3面のスクリーンでは、同一のシーンが異なるアングルで分割して映し出され、時に同期しながら、3人の若い女性の物語を紡いでいく。彼女たちは大学の映像学科の学生である。
冒頭、劇中劇の撮影シーンが挿入されるように、終始無言で演じられるシーンは、劇的な予感に満ちている。カメラを通した窃視、相手を求める手、情事、そして仄めかされる死。台詞が一切なく、カット割りや視線の動き、音響効果だけで物語を進行させる方法は、映画の文法を高純度に抽出してみせている。それは、視線の動きや抑制された身振りだけで登場人物の心情を思い描く余白を与えるとともに、愛らしいバラの形の補聴器を耳に付けた女性の生きる世界を暗示する。
彼女はもう1人の女の子と付き合っていて、屋上や公園で、スキンシップのようにカメラを向けられる。3人目の女の子はそんな2人に友人として接しつつも、補聴器の女性に魅かれている。戯れる2人の傍らでひとり空にカメラを向け、地面をフロッタージュし、マイクで地面や水の音を採取し、自分の脈動を録音し続け、映画の制作に打ち込む。最後に、この世にはもういないはずの「彼女」の手が一瞬だけ優しく触れる、そんな幻覚とともに深い森の中に取り残されて映像は終わる。
しかし次の瞬間、映像内にいたこの女の子が舞台上に現れ、虚実が反転する。彼女は、物語の中で撮られていた16ミリフィルムを映写機にかけて私たち観客とともに鑑賞し、闇の中へ去っていく。映像内の世界が「現実の」舞台空間上に転移して現れ、観客の身体と地続きの空間へと侵入し、物語内で撮られていた16ミリが実際に「再生」される一方で、肉体の不在感を喚起する吊られたワンピースは、物語の中で身に付けられている。いくつもの入れ子構造の絡まり合いとともに、マルチスクリーンの映像インスタレーション、文法としての映画、演劇、といった弁別がハイブリッドに混淆していく。
カメラを手にした窃視者、見る者と見られる者、女の子同士の恋愛感情、死や自殺へ向かう願望、あてどない徘徊、亡霊の出現といった要素は、『めまい』『静かな一日・完全版』『最後の天使』といった2000年代以降の映画作品の流れを組むが、複数のスクリーンの配置による空間性や演劇の現前性を組み込むことで、より厚みを増した複雑な体感世界が構築されていた。
2016/01/23(土)(高嶋慈)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)