artscapeレビュー
パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー
中野成樹+フランケンズ2015秋・葉原「ロボットの未来・改(またつながらない星と星)」
会期:2015/11/20~2015/11/25
アキバナビスペース[東京都]
なんでここ? という感じの秋葉原のイベントスペースを借りるが、公演中に幾度もシャッターを開閉し、俳優が出入りしつつ、舞台が街と接続する趣向だった。たまに通行人も何事が起きているのかとこちらをのぞき込む。これは面白い効果である。ロボットゆえの珍妙な会話が笑えるが、同時に人とは?、自己とは?などの哲学的な問いも発せられる。
2015/11/25(水)(五十嵐太郎)
Works-M Vol.7『クオリアの庭』 progress.4 Kyoto「past_」

会期:2015/11/21~2015/11/23
京都芸術センター[京都府]
Works-M Vol.7「クオリアの庭」は、「移動をつづけながらクリエーションを行う」というコンセプトのもと、三浦宏之が作・構成・振付・美術を手がけるダンス作品。昨年11月の神戸公演progress.1「lie_」に始まり、今年8月の秋田公演、10月の岡山公演を経て、京都でのprogress.4「past_」と、各地でワーク・イン・プログレス公演を重ねてきた。来年1月には横浜にて、最終成果として「クオリアの庭」の上演が予定されている。
音・美術・ダンス、つまり非物質的な現象と物質的存在と運動が、空間内に同一のレベルで共存しつつ拮抗する。ミニマルに抑制され、計算された演出の洗練からは、そうした印象を受けた。斜めにピンと張られたいくつもの赤い糸が空間を立体的に交差する。落下し続ける白い砂や振子の運動が、時間の流れを可視化する。様々に移り変わる音響もまた、時間の持続や断絶とともに、具体的/抽象的な風景を召喚する。ハーモニックに重なり合う声、規則正しい電子音、不穏なノイズ、外国語の飛び交う街頭の喧騒、木漏れ日や小鳥のさえずり、荒野を渡る風……。その空間の中に存在する5人のダンサーたちの身体は、時に共鳴してユニゾンを描いてはふっと離れ、同期とズレを繰り返す様子は音叉の共鳴や和音を思わせ、距離を隔てた伝播や共鳴を互いに見せながら、この空間自体を少しずつ調律していくように感じられた。音、身体、美術、どこかで生じた運動が他の要素を振動させ、ふっと風景が立ち上がってはたちまち消えていく。その生成と消滅の繰り返しの中に、それぞれの意志を持って空間を生きる5つの身体があった。
2015/11/22(日)(高嶋慈)
フェスティバル/トーキョー15 岡田利規「God Bless Baseball」
会期:2015/11/19~2015/11/29
あうるすぽっと[東京都]
フェスティバルトーキョーのプログラムで、岡田利規「God Bless Baseball」@あうるすぽっとを観劇した。韓国人と日本人の男女が、野球について考えるのだが、二カ国語に加え、核の傘をつくるアメリカから発せられる英語が入り乱れる。野球という共通して人気があるスポーツを通じて、二国とアメリカの関係を考察する仕掛けだ。作品タイトルは高嶺格の作品に影響されたらしく、舞台美術でも彼に参加してもらっている。四人の非自己的運動から、水しぶきを上げる終盤へのカタルシスが爽快だった。
2015/11/19(木)(五十嵐太郎)
カンパニー マリー・シュイナール『春の祭典』『アンリ・ミショーのムーヴマン』
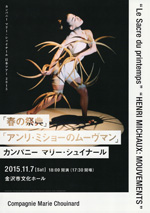
会期:2015/11/07
金沢市文化ホール[石川県]
『春の祭典』は、本来は「春の季節の復活の儀式のために、生贄となる少女」の物語をベースとしたバレエ音楽だが、シュイナール版では、上半身裸の男女10名のダンサーによって踊られるものの、むしろ男女の身体的性差が限りなく消去され、ジェンダーレスでニュートラルな身体に見えたことが新鮮だった。また、角のような突起を身体のあちこちに装着したダンサーたちは針葉樹や爪を生やした動物のように見え、性差だけでなく人間と植物、動物の境界を侵犯していく。あるいは、それらを牛の二本角や性器に見立てることで、野蛮にして洗練された官能性が際立つ。
個人的には、『アンリ・ミショーのムーヴマン』により強い興奮を覚えた。これは、ミショーの詩画集《ムーヴマン》を参照し、インクの飛沫のようなプリミティブな人間の形象のような謎めいた線の軌跡を、ダンサーの身体で立体的に表現するダンス作品。アイデアはシンプルな一本勝負だが、動きや組み合わせのバラエティと、それを可能にするダンサーの高い身体能力で魅せる。背景のスクリーンには、不定形で抽象的なかたちが「お題」のように映し出され、その前で始めはダンサーがひとりずつ、制止のポーズを決め、あるいは全身を激しく振動させ、ときに顔の表情も大きく歪ませながら、次々と「かたち」をトレースしていく。複雑なかたちになると2、3人で組んで表現し、遂には全員でユニゾン。後半では、ミショーのテクストを音読する声が流れ、激しいストロボの明滅のなか、視認できないほどの高速で切り替わる映像とともに、ダンサーの身体が激しく躍動する。もはや、「かたちを正確に表現する」という課題の遂行よりも、蓄積されたエネルギーを全身で放出しているようにしか見えない。音、光、運動が渾然となって脳髄に叩き込まれるような興奮のなかで感じたのは、「かたちの忠実なトレース」であったものがダンスそれ自体の自律した運動へと至っていること、そしてダンサーの身体を媒介することで、紙に定着された「かたち」たちがそれぞれ固有の感情を持っているという再発見だった。
2015/11/07(土)(高嶋慈)
大橋可也&ダンサーズ『テンペスト』
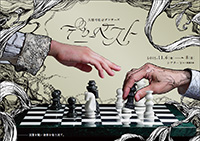
会期:2015/11/06~2015/11/08
東京・両国 シアターX(カイ)[東京都]
大谷能生が舞台上で朗読する言葉(表題通りシェイクスピアの戯曲もあり、安倍晋三の発言もあり)たちとダンサーたちの踊りが共振する。言葉は断片的で、だから物語も展開も明確には存在しない。わずかにわかるのは、描かれているのが「嵐」によって文明がゼロ状態になった世界ということ。東日本大震災を反映しているのは間違いない。ダンサーたちは風に飛ばされるように、突然何者かに意識を奪われて自分の意思が行方不明になってしまったかのような動きを繰り返す。見ながらずっと考えていたのは、舞台に社会を映し出そうとする大橋の試みに的確に反応するのは誰だろうということだ。世間の多くは、舞台に現実を見ようとはしない。言い換えれば、世間の人々は現実に向き合っていないのではなく、向き合いすぎていて(それがいかに独りよがりの世界解釈だとしても)、現実に直面することよりも逃避することを望んでいる。自分を社会という鏡に写したくないのだ。では、誰はそれを望んだか。大橋可也&ダンサーズは以前、非正規雇用が深刻な社会問題として話題になったころ、「ロスジェネ」の苦悩に応答するような舞台を意識的につくっていた。いまでも大橋作品の観客にはその層がいるはずだ。ロスジェネの怒りは社会から自分が見放されていることにあった。だから彼らは社会という鏡が自分を映すことを求めた。「ロスジェネ」世代もそこで確認された問題も消えたわけではない。とはいえ、一方で、SEALDsのような社会をつくろうとする動きが出てきている。彼らの台頭によって、社会が自分を映してくれるかどうかよりも、社会自体を変えようとする意識が高まっているなか、さて、舞台は「反映」の役割を担うべきかどうか、いまそれが問われるのではないか。発見か発明か。もちろん二者択一ではないのだが、発明の要素、すなわち「変容」へ向けた想像力のほうを、筆者などは舞台に探してしまう。
2015/11/07(土)(木村覚)


![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)